
根拠がわかる疾患別看護過程 改訂第3版
大好評参考書がオールカラーになって大改訂! 実習でよく出合う78疾患について,看護過程の展開に必要な医学的知識,病期・治療に沿ったアセスメント,看護計画とケアの「根拠」「留意点」がますます充実.好評の「関連図」では発症から病態生理学的変化,治療経過,看護問題の抽出までを図式化し,患者の経過が一目でわかる.さらに第2部以降で「治療別看護」「経過別看護」「感染症看護」「臨床検査値一覧」を収載し,患者の状況に応じたアセスメントと臨床判断ができる.看護学生や新人看護師の「なぜ・どうして」に応える,実習で役立つ頼れる味方!

≪シリーズ ケアをひらく≫
傷の声
絡まった糸をほどこうとした人の物語
現在の精神科医療に不足している視点を教えてくれる。
本書は複雑性PTSDを生きた女性が、その短き人生を綴った自叙伝である。過酷な家庭環境に育ち、複雑性PTSDを持つ著者が、ふり幅の大きな人生を描く。なぜ自分を傷つけるのか、という疑問への回答と、傷ついた人に必要なのは、権力や物理的力で抑え込むことではなく、ケアであるべきではないかという気づきとヒントを医療者に与えてくれる。

看護師のための文章ノート
読んでもらえる“仕事の文書”が書ける! 作文技術が身につく! ワークシートで自分の文書の傾向をつかめる!
しばしば「冗長」「わかりにくい」などと言われる看護師の文章。「看護」という仕事の本質が「個別性」を対象とし記述的になりがちなためですが、仕事の文書(論文や各種報告書、レポート、依頼文書、看護記録など)は読んでもらわなければなりません。本書は“読んでもらえる仕事の文書”を書くための作文技術を紹介したコンパクトな良書。思考が整理でき、添付のワークシートを使えば自分の文章の傾向がつかめます。今日から「より、読んでもらえる文章」を書いてみませんか。

学生のための医療概論[Web付録付] 第5版
各項のポイント解説映像をWeb付録とし、より学びやすくなった医療系学生必携の書
看護学生を主とした医療系学生対象に、先端科学技術だけではなく考え方や倫理の重要性を説き、患者中心のチーム医療をめざしてほしいという理念で編集されてきたロングセラー。今版もデータのアップデートはもちろん、新しいトピックもできるだけ反映している。また新たに、各項の筆者による学んでほしいポイントを述べた映像をWeb付録とし、事前課題としての活用や実際の授業で取り上げられなかった内容の補いに使用できるようにしている。
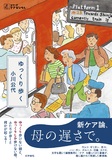
≪シリーズ ケアをひらく≫
ゆっくり歩く
新ケア論、母の遅さで。
6歳で英語の話せない母と姉とで1年半のカリフォルニア留学、12歳でケンタッキーに単身渡米、高校2年にイギリス留学、そしてケンブリッジ大学に合格──。“直立人”の道をまっすぐ歩んできた娘は、病を得た母と一緒にゆっくり歩かざるを得なくなった。そのときどんな光景が目に入り、どんな声が聞こえてきたか。ウルフ、ギリガンなど文学を通じて縦横無尽にケアを語ってきた著者が、母に導かれて到達した新境地!
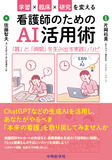
学習×臨床×研究を変える看護師のためのAI活用術 「質」と「時間」を生み出す実践レシピ
生成AIを活用し,あなたがやるべき「本来の看護」を取り戻してみませんか
資料の作成や文献の検索など,書類の作成などに時間を取られ,本来行うべき患者に向き合うための時間を確保しにくいことの多い看護師業務において,ChatGPTなどの生成AIを活用し,「もっと患者さんのそばにいたい」という思いを実現するための実践的方法をわかりやすく解説する書.

≪シリーズ ケアをひらく≫
居るのはつらいよ
ケアとセラピーについての覚書
京大出の心理学ハカセは悪戦苦闘の職探しの末、ようやく沖縄の精神科デイケア施設に職を得た。「セラピーをするんだ!」と勇躍飛び込んだそこは、あらゆる価値が反転するふしぎの国だった――。ケアとセラピーの価値について究極まで考え抜かれた本書は、同時に、人生の一時期を共に生きたメンバーさんやスタッフたちとの熱き友情物語でもあります。一言でいえば、涙あり笑いあり出血(!)ありの、大感動スペクタクル学術書!
*「ケアをひらく」は株式会社医学書院の登録商標です。

看護のためのChatGPT
初めての人も使える活用ヒント集
ChatGPTで変わる「書く・考える・教える」
臨床で働く看護職や看護教員・研究者に向け、ChatGPTの実践的・具体的な活用法を紹介する入門書。生成AIの基本から、看護業務・教育・研究への応用まで、豊富なプロンプトと出力例を交えて解説する。看護師としての視点から「看護の現場でどう使えるか」に重点を置き、初学者でも無理なく日常業務に取り入れられる工夫を随所に盛り込んだ。ChatGPTを「新しいパートナー」として育てていくヒントが詰まっている。

≪ナースのための図解シリーズ≫
ナースのための図解 検査の話
『ナースのための図解からだの話』『ナースのための図解病気の話』の続編.
検査についての「なぜ・何」がすべてわかります.

根拠がわかる症状別看護過程 改訂第4版
こころとからだの69症状・事例展開と関連図
身体症状に加え心理・社会的症状を含む69の症状について,モデル的な看護診断と,事例に基づく具体的な看護過程について関連図を交えて解説.今改訂では新たな編集体制のもと,看護計画を見やすい表形式としてより多くの根拠・留意点などを示すようにしたほか,イラスト多く用いてよりビジュアルにわかりやすい紙面とした.看護の視点から人間を捉えた「症状別看護」の決定版.

≪Nursing Todayブックレット 4≫
「聞こえにくい」をほっとかない
加齢性難聴への早期な対応は、高齢者の認知機能の低下を抑える可能性を高めると同時に、高齢者の生活の質を上げ、社会的孤立を防ぐことにつながると期待されます。「聞こえにくさを抱える高齢者」には、ぜひ早めの耳鼻咽喉科受診をすすめてください。そして、本書が紹介する最新の聴覚トレーニングや聴覚ケアの知識、聞こえにくさを抱える方とコミュニケーションを行う際の工夫、加齢性難聴に対する社会的支援に関する情報等を、看護・介護の場面でお役立てください。

現象学でよみとく
専門看護師のコンピテンシー
6領域9名の専門看護師(CNS)による事例をもとに、現象学者である村上氏が各CNSとのインタビューを実施。現象学的な質的研究により、そこから見えてくるCNSの行動や言葉を体系的に抽出。読者にCNSのコンピテンシーとして「看護師の目線で見えた世界」を示していく。CNSを目指す人へ、CNSを活用したいと考える管理者に向けての格好の参考書。また医療人のみならず看護サービスの利用者にも役立つ1冊。

≪シリーズ ケアをひらく≫
あらゆることは今起こる
私の体の中には複数の時間が流れている。
眠い、疲れる、固まる、話が飛ぶ、カビを培養する。それは脳が励ましの歌を歌ってくれないから?──ADHDと診断された小説家は、薬を飲むと「36年ぶりに目が覚めた」。私は私の身体しか体験できない。にしても自分の内側でいったい何が起こっているのか。「ある場所の過去と今。誰かの記憶と経験。出来事をめぐる複数からの視点。それは私の小説そのもの」と語る著者の日常生活やいかに。SFじゃない並行世界報告!
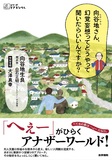
≪シリーズ ケアをひらく≫
向谷地さん、幻覚妄想ってどうやって聞いたらいいんですか?
常識は後からやってくる!
精神医療の常識を溶かし、対人支援の枠組みを更新しつづける「べてるの家」の向谷地生良氏。当事者がどんな話をしても彼は「へぇー」と興味津々だ。その「へぇー」こそがアナザーワールドの扉を叩く鍵だったのだ! そしてこの一見シンプルな話の奥には光と闇が交錯する世界が広がっていた。大澤真幸氏の特別寄稿「〈知〉はいかにして〈真実〉の地位に就くのか?」は“良心的兵役拒否者”である向谷地氏に言語論から迫った名論文!
*「ケアをひらく」は株式会社医学書院の登録商標です。

知っておきたい爪の知識と病気
すべての疑問を解決します!
ベストセラー『爪―基礎から臨床まで』の著者、東先生の簡単に手に取って読めるわかりやすい新作。日常生活においては爪そのものに原因のある病気がたくさんある。そのような爪の病気を治したり、予防するためには爪そのものについての知識をもつことが大切。身近な爪の役割や爪の切り方から爪の様々な病気まで、イラストや写真を使って原因や治療法をわかりやすく解説。爪の変化にいち早く気づき必要な対応がわかる頼れる1冊!

The 外来看護 第2版
時代のニーズに応え、専門性を発揮する
看護の役割の1つの「療養上の世話」の視点で、退院後のセルフケア支援の重要性を感じた筆者は、外来での療養指導や外来看護に関する研究などを続けてきました。
本書では、「在宅療養指導料」を皮切りに、続々と新設される外来での看護にかかわる診療報酬の詳細を中心に、外来での看護に必要な技術、仕組みづくりなどをまとめました。
第2版は、2018年から2024年までの外来看護に関わる診療報酬改定などの変更に対応して、大幅な加筆を行っています。
≪本書は第2版第1刷の電子版です≫

臨床で役立つ
看護アセスメントスケール&ツール
臨床で役立つバイタルサインや呼吸、循環、救急などの各種診断指標・尺度をまとめました。
最新のエビデンスに基づいたスケールや指標を、180項目精選。調べやすいように、系統別、状態別、疾患・領域別のパートに分類。

≪Nursing Today ブックレット 15≫
認知症高齢者とセクハラ
認知症を患うと、ケア提供者に卑猥なことを言ったり、体を触ったりといった性的逸脱行為がみられることがあります。本人は本能に基づき行動しているため、セクハラをしているという意識・自覚はなく、注意されたり拒絶されても効果がないばかりか、ケアの拒否もみられます。一方、そのような行為を受けた側は、病気が原因だとわかっていても、傷ついたり嫌な思いをすることは多いでしょう。認知症高齢者の性とハラスメントに関する問題にどう対応すればよいのか──専門家と高齢者看護・介護の現場で働く専門職が自身の経験を踏まえ考察しました。

症状を知り、病気を探る
病気とは何か、患者さんの痛みや苦しみは何に由来するのか―――病理医ヤンデル先生が、患者さんがよく訴える5つの症状の“みかた”を語る!インターネットで「病理医ヤンデル」として有名な著者が、最もポピュラーで、出合う頻度の高い5つの症状である「おなかが痛い」「胸が苦しい」「呼吸がつらい」「熱が出た」「めまいがする」の“みかた”を語ります。

≪シリーズ ケアをひらく≫
摘便とお花見
看護の語りの現象学
とるにたらない日常を、看護師はなぜ目に焼き付けようとするのか――看護という「人間の可能性の限界」を拡張する営みに吸い寄せられた気鋭の現象学者は、共感あふれるインタビューと冷徹な分析によって、不思議な時間構造に満ちたその姿をあぶり出した。巻末には圧倒的なインタビュー論「ノイズを読む、見えない流れに乗る」を付す。パトリシア・ベナーとはまた別の形で、看護行為の言語化に資する驚愕の1冊。
