
精神科の薬がわかる本 第5版
精神科全領域の薬がこの1冊で丸わかり! ざっと広くのことを知りたい方へ。
精神科全領域の薬に関する最新かつ正確な情報を、第一線で診療を行う著者が厳選して紹介。精神科を専門とする医師、研修医、精神科看護師はもちろん、精神科以外の科の医療者で「精神科の薬」を使用する機会のある方にとっても有益な1冊。第5版では、なぜその薬が効くのかを知ることで、「精神科の薬」の誤用と乱用を防ぐことに注力しています。
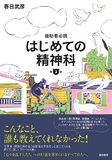
援助者必携
はじめての精神科 第3版
きれいごと一切ナシ! 口は悪いが役に立つ! 同じ精神科の最前線で働く者だけが知る共感力を全開にした「超実践的アドバイス」集は、いよいよ第3版へ。クレーマー対策、援助者としてのアイデンティティの保ち方、当事者・家族に対峙する時のちょっとしたコツなど、「こんなこと、誰も教えてくれなかった」度はますますアップ! はじめて精神科に足を踏み入れたなら誰もが感じる「不安」が、優しく解きほぐされます。

子どものための精神医学
発達障害? アスペルガー症候群? 知的障害? 自閉症? ADHD? LD? ところでスペクトラムって何?-本書を読めば、錯綜する診断名を「認識と関係の座標軸」のもとに一望できるようになる。読めば分かるように書いてある、ありそうでなかった児童精神医学の基本書。事例の機微をすくい上げる繊細な筆さばき、理論と実践の生き生きとした融合、そして無類の面白さ! マニュアルでは得られない「納得」がここに。
●新聞で紹介されました!
《463ページにも及ぶ分厚い専門書なのに、興奮しながら一気に読み切った。タイトルには精神医学とあるが、内容は「何かにつまずく全ての子ども」についての考察と助言だ。》―鈴木大介(ルポライター)
(共同通信社配信、『熊本日日新聞』2017年5月14日 書評欄、ほか)
《著者は、日本を代表する児童精神科医の一人。育つ側の難しさを語りつつ、育てる側の難しさも平等にフォローした。》
(『読売新聞』2017年4月26日より)
《〈疾患〉ではなく〈障害〉と言われる概念の理解に主眼をおき、教員・保育士・看護師・心理士向けにわかりやすく解説する。》
(『東京新聞』2017年6月18日より)
●雑誌で紹介されました!
《児童精神科医学者である著者は五十年間の研究の末、子どもの「精神発達の座標軸」を発見した。その原理と実践をつないで体系化したのが本書だ。》―本田哲也(toBe塾主宰)
(『児童心理』2017年8月号 BOOK REVIEWより)
《この書物は、児童精神医学の教科書ではない。しかし、その道へ進みつつある臨床家に向けての教導書ではある。》―清水將之(三重県立看護大学理事)
(『こころの科学』2017年7月号、BOOKS ほんとの対話より)

≪シリーズ ケアをひらく≫
傷の声
絡まった糸をほどこうとした人の物語
現在の精神科医療に不足している視点を教えてくれる。
本書は複雑性PTSDを生きた女性が、その短き人生を綴った自叙伝である。過酷な家庭環境に育ち、複雑性PTSDを持つ著者が、ふり幅の大きな人生を描く。なぜ自分を傷つけるのか、という疑問への回答と、傷ついた人に必要なのは、権力や物理的力で抑え込むことではなく、ケアであるべきではないかという気づきとヒントを医療者に与えてくれる。
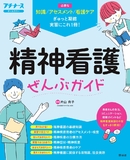
精神看護ぜんぶガイド
大人気の「ぜんぶガイドシリーズ」続刊。
精神看護学実習に必要な基礎知識、アセスメント、症状や疾患の知識、薬物療法・ケアなどを1冊にぎゅっと凝縮しました!
よくある出合う疾患の知識から、患者さんの生活、観察やコミュニケーションなど実習中の不安をすっきり解消。
図表・イラストが豊富で“わかりやすい”のもポイントです。
実習の事前学習や実習中のレポートなど全部を通して使える1冊です。

改訂2版 はじめての精神科看護
【精神科看護の知識、ワザ、マインドの決定版】今まさに新人ナースの指導を行っているスタッフが、新人ナースに必要な知識や情報をまとめた、精神科看護のスタートブックとして最適な一冊!リカバリーや行動制限最小化看護などの精神科特有の看護を加筆し、最新情報も満載。精神科病棟の3大疾患とその看護、治療、合併症、社会的な状況まで、豊富なイラストでわかりやすい!
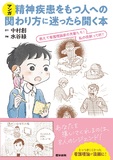
マンガ
精神疾患をもつ人への関わり方に迷ったら開く本
教えて看護理論家の先輩たち! 私の役割って何?
心の病気への対応に迷ったら……8人の看護理論家があなたを導きます!
精神科に入職した新人看護師の成長物語である。精神科は、患者さんとの関わり方や看護の方向性に迷いが大きく、何が正解なのかが見えにくい。この本では、新人看護師がピンチな場面に陥るたびに、先輩が8人の看護理論家を引きながら導いてくれる。これを読む読者も、重要な看護理論のエッセンスを漫画でつかみながら、謎深き精神科の看護を理解していくことができる。

ねじ子が精神疾患に出会ったときに考えていることをまとめてみた
●精神科治療が必要な患者さんをちゃんとみつけ、専門家にきちんと届けるために必要な基礎知識をまとめた、「精神科ではない病棟や外来」で働く医療者の皆さんにオススメの1冊。
●ねじ子先生ならではの、マニアックなイラストを「見て」、ズバッと切り込む解説を「読んで」、精神疾患の概要をざっくり理解しておけば、どんなときでも、あわてずに初期対応することができます。

日本うつ病学会診療ガイドライン 双極症2023
双極症に携わる医療者のための羅針盤。「治療」から「診療」へスコープを広げて大改訂
従来の「治療」ガイドラインの内容に、疾患情報や臨床疑問、心理社会的支援、周産期、薬物療法に関する安全性とモニタリングなどの情報が加わり、実臨床に一層役立つ「診療」のためのガイドラインとして大改訂。一部の臨床疑問ではシステマティックレビューも行い、書籍版限定の解説や資料も掲載している。当事者・治療者双方が正しい知識に基づき納得して治療を選択できる、双極症診療の羅針盤となる一冊。

精神疾患にかかわる人が最初に読む本
精神医学の必要最小限の知識を、イラストを用いながら、ひとめでわかるように解説した精神医学の入門書。
いろんな人とうまくかかわることが出来るようになるための精神症状と疾患がわかるようになる1冊。

大人の発達障害ってそういうことだったのか その後
好評書『大人の発達障害ってそういうことだったのか』の続編企画。今回も一般精神科医と児童精神科医が、大人の発達障害(自閉症スペクトラム・ADHDなど)をテーマに忌憚のない意見をぶつけ合った。過剰診断や過少診断、安易な薬物投与、支援を巡る混乱など、疾患概念が浸透してきたからこそ浮き彫りになってきた新たな問題点についても深く斬り込んだ。
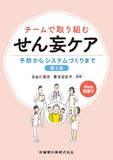
チームで取り組むせん妄ケア 第2版 予防からシステムづくりまで Web動画付
急性期病院におけるせん妄の予防とケアをわかりやすく解説した好評書が,8年ぶりに改訂!
●せん妄の基本的知識から予防・ケア実践まで,チームで取り組むノウハウをこの1冊でマスターできる!
●院内研修,自己学習に最適! 「せん妄アセスメントツールの使用法」がわあるWeb動画付
●第2版では,「せん妄ケアの質評価指標」をはじめ新たな知見・実践知等を盛り込み,再構成.また新たな項目「第5章 せん妄ケアカンファレンス」「第6章 「せん妄」の体験を理解する」を設け,チーム医療を確立し,実践につながる1冊に!

児童精神科医の臨床覚え書
●経験豊富な児童精神科医が子どものこころの問題をひも解き、実践的な対処法を解説!
診療の毎日から得た経験を、子どもたちの悩みに寄り添うものとして描き出し、医療従事者だけでなく、親御さんや教育に携わる方々にも何かしらの理解を伝えたい、そう思い続けていた――。こう語るベテランの児童精神科医が、子どものこころの問題をひも解き、病院、学校、家庭で悩む大人たちに実践的な対処法を伝えるのが本書です。
発達障害、児童虐待、子どものうつ病などへの関心が高まるなか、著者が長年の臨床で獲得した経験値と膨大な文献から得られたエビデンスを、やさしく解説します。精神科医はもちろん、小児科医や開業医、心理職、教育職の方に役立つ情報が詰まった1冊です。

認知症ケアガイドブック
認知症の病態の知識、ケアにおける倫理、症状アセスメント、日常生活のアセスメント、多様な場でのケアマネジメント、家族支援等について、わかりやすく解説しました。認知症ケアに、はじめて取り組む方、認知症ケアに悩んでいる方、院内の体制づくりをしていくリーダーの方など、すべての看護職に役立つ本です。

みんな水の中
「発達障害」自助グループの文学研究者はどんな世界に棲んでいるか
ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動症)を診断された大学教員は、彼をとりまく世界の不思議を語りはじめた。何もかもがゆらめき、ぼんやりとした水の中で《地獄行きのタイムマシン》に乗せられる。その一方で「発達障害」の先人たちの研究を渉猟し、仲間と語り合い、翻訳に没頭する。「そこまで書かなくても」と心配になる赤裸々な告白と、ちょっと乗り切れないユーモアの日々を活写した、かつてない当事者研究。
*「ケアをひらく」は株式会社医学書院の登録商標です。
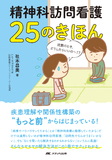
精神科訪問看護 25のきほん
【身体科との違いと、やるべきことがわかる】
精神科訪問看護の需要はますます高まってきているが、精神科未経験のスタッフも多く、実際に現場に出ると困ることが少なくない。病棟経験者も生活の場に入ってのかかわりは未経験で、病棟勤務とは別のスキルが求められる。アセスメントや看護まで行きつかない!と焦るあなたのための1冊。

エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図 改訂版
代表的な16の症状と10の疾患のケア、4の治療についてエビデンスに基づいて関連図を作成した。定義と具体的な症状、成り立ち、心理社会的反応、診断・検査、治療、経過・予後、看護の観察ポイント、治療段階に基づく看護ケアを詳解。DSM-5に対応しアップデートした。

≪からみた看護過程≫
ストレングスからみた
精神看護過程
+全体関連図,ストレングス・マッピングシート
『ストレングスモデル実践活用術』の応用として,臨床で活躍する看護師の方にもお勧め
対象者自身が望む「自分のなりたい姿」を目標に、対象者の考えや経験等をストレングスとして活かす視点から看護過程を解説する待望の書。ストレングスモデルで把握できる強みだけでなく、生物学的・心理学的・社会的情報(BPSモデル)、セルフケアに関する情報も併せたアセスメントのポイント、ストレングス・マッピングシート、取り組むことの見出し方、全体関連図、看護計画の立案と実施、評価までを指南する。
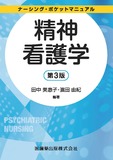
ナーシング・ポケットマニュアル 精神看護学 第3版
実習や臨床で役立つ精神看護のハンディな手引き書の改訂新版
●精神看護の実践に必要とされる知識を厳選し,コンパクトな内容でまとめました.
●第3版では最新の知見に基づいて内容を見直し,「地域移行・地域定着支援」「リカバリー・ストレングスモデル」「地域包括ケアシステム」などについても記載しました.

全人的視点にもとづく 精神看護過程 第2版
●ゴードンの機能的健康パターンに沿ってアセスメントを展開し看護につなげる精神看護実習に臨む学生の必携書
●全人的視点にもとづいて,ゴードンの機能的健康パターンを活用した看護過程を学べる好評書の改訂版.
●第1章では,精神看護の定義や概念,構造について述べたうえで,精神看護における看護過程を解説.精神障害者特有の情報収集やアセスメントのポイント,健康課題の抽出,計画,実施,評価まで示すとともに,全人的視点と精神看護とのつながりについて概説した.
●第2章では,ゴードンの機能的健康パターンについて概要を紹介し,精神看護におけるアセスメントのポイントおよびアセスメントガイドを示した.
●第3章では,事例を用いて,患者の基本情報,アセスメント項目と視点,アセスメントから結論,関連図,課題抽出,看護計画までのプロセスを展開した.事例には,統合失調症,抑うつ障害,アルコール使用障害,摂食障害に加えて,認知症,発達障害の2例を新たに追加した.
