
介護報酬の解釈 2 指定基準編 令和6年4月版
『指定基準と関係通知を6月実施分も集成した基本書』
『条例制定や事業所・施設運営で大いに活躍』
介護報酬の算定の前提となる事業者・施設の「指定基準」について、国が発出した省令・通知を網羅しています。
各サービスについて、「サービス提供の基本方針」「人員基準」「設備基準」「運営基準」を掲載。指定基準の各条文に解釈通知を配置し、他サービスからの準用規定を読み替えたうえで掲載するなど、実務本位に編集しています。
個別サービス提供についての関係告示・通知も併載しています。
自治体の条例制定に役立つよう従うべき基準や標準とする国の基準をわかりやすく示しています。
令和6年度介護報酬改定では、書面掲示規制の見直しや管理者の兼務範囲の明確化、身体的拘束等の適正化の推進のほか、協力医療機関との連携体制の構築、利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置、福祉用具貸与・販売の選択制の導入など、指定基準が多岐にわたり改正されています。
「介護報酬の解釈 2 指定基準編」では、改正点がわかるように掲載するとともに、指定基準改正のポイントをまとめた資料を掲載しました。
「介護報酬の解釈 1 単位数表編」、「介護報酬の解釈 3 QA・法令編」とあわせてご活用ください。
本書は令和6年9月発刊の第2刷を電子化したものです。

障害福祉サービス報酬の解釈 令和6年4月版
障害福祉サービス・障害児支援の報酬算定がすべてわかる決定版
単位数表と指定基準は通知と組み合わせて掲載
障害者総合支援法および児童福祉法にもとづく障害福祉サービス等の基準について、とくに報酬算定と請求にねらいをあて、必要な情報を実務上役立てることができるよう編集しています。算定のしくみを根拠とともに示しています。
第Ⅰ編「サービスのしくみ」では、障害者・障害児をささえるしくみの全体像や、電子請求受付システムによる請求といった、事業所が知っておきたいしくみを解説しています。
第Ⅱ編「費用算定基準(単位数表)」では、対応するサービスの費用算定基準(単位数表)告示・関係告示と留意事項通知を見開きで配置することにより、使いやすい構成となっています。障害福祉サービスのほか、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援、児童通所支援、児童入所支援の費用算定基準も掲載しています。
第Ⅲ編「指定基準」は、各サービスの指定基準省令とその解釈通知により構成しています。事業所を新規に立ち上げて指定を受ける際にはじまり、日々の事業所運営や指導に対応する際にも必要となる情報をまとめています。基準省令と基準通知はそれぞれひと目で区別でき、見落とすことなく指定基準が体系的に理解できるように編集しています。
第Ⅳ編「関係告示・通知」では、単位数表や指定基準を補足し、実務の根拠となる告示や通知等を、事務処理に必要な様式例・手順例も含めて掲載しています。
第Ⅴ編「疑義解釈」では、厚生労働省から発出された、請求事務の疑問に答える主なQ&A(疑義解釈)を掲載しています。
障害者・障害児の暮らしを支えるサービス事業所や施設の職員、相談支援専門員あるいは介護保険のケアマネジャー、また、社会福祉法人、医療機関、関連事業者、行政担当者・審査支払機関等、障害福祉サービスに携わる皆様に必携の一冊です。

精神疾患をもつ人への支援で、壁にぶち当たったら読む本
巻きかえしの技教えます
そんな考え方があったんだ! 地域の困難事例に「あんな手・こんな手」を提案。
どうすればよかったか──。あの達人だって、新人時代はたくさんつまずいていたのです。ベテランになっても、やっぱり難しいケースには遭遇します。大事なのは、振り返り、学ぶ勇気なのです! 本書では著者とその同僚が、自分たちがつまずき苦戦してきた事例を(恥をしのんで)公開します。そして「今ならこうやって巻きかえす」という考察・提案を記します。地域で支援・ケアを提供する人に必携の書「壁本」があなたの孤独を癒します。

介護報酬の解釈 3 QA・法令編 令和6年4月版
『厚生労働省発出のQ&Aをサービス別に整理して収載』
『関係法令も集成、さらに実務に精通するための一冊』
厚生労働省によるQ&Aをサービス種別・内容に応じてまとめ、質問の対象となった単位数表等の該当部分とともに掲載します。
テーマごとの関連告示・通知と請求書・明細書の記載要領を集大成,介護報酬・指定基準の実務・運用の細部にふみこむ一冊です。

あなたにもできる スピリチュアルケア
死を前にした人が穏やかになるために、誰もができることがあります。
「もう死んでしまいたい」「迷惑をかけてばかり」──死を前にした人の言葉に、応え続けることができますか。そこでは励ましも説明も、力を持ちません。私たちにできるのは、相手にとって「わかってくれる人」として対話を重ね、大切な「支え」を強めること。それが “スピリチュアルケア”です。スピリチュアルケアは、一部の人だけができる難しいケアではありません。わかりやすい言葉で、真似しやすい方法で、すぐに実践できるスピリチュアルケアがここにあります。

改訂第2版 救急認定ソーシャルワーカー標準テキスト
救急患者支援
救急認定ソーシャルワーカーに必要な知識と実践事例をまとめた『救急認定ソーシャルワーカー標準テキスト』の改訂版
救急認定ソーシャルワーカー認定研修を主な目的に編集されているが、救急医療に関連する医療政策担当者や病院関係者、さらに医療現場で多職種協働の担い手となる医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士・栄養士など関連職種の方々にも参考になる。
さまざまな課題を抱える救急患者にかかわる救急認定ソーシャルワーカー必携の1冊!

慢性痛のサイエンス 第2版
脳からみた痛みの機序と治療戦略
慢性痛のメカニズムを解き明かす。国際的潮流を踏まえた最新版
「痛みの定義」の改訂、Nociplastic Pain(「痛覚変調性疼痛」)の定義といった、国際的な潮流を反映して全面改訂。慢性痛のメカニズムを脳科学的視点から丁寧に解き明かす。第7章「神経変性疾患と慢性炎症」では慢性痛を訴える難病患者の脳を、また新規8章「腸の痛み、腸と脳の連関」では腸が脳に与える影響といった、慢性痛のミッシングピースを大胆に考察して大幅加筆。慢性痛患者に携わるすべての医療者必読の書。

看護・介護で使えるナーシングマッサージ[Web動画付]
「触れる」をケアにする
触れること、さすることは確かにケアになる
目の前にいる苦痛を抱えた人をなんとかしたいという思いで研究されてきたナーシングマッサージは、ケア場面で触れることがどんな意味をもつのかという原点に立ち戻り、試行錯誤を繰り返した結果、軽擦法(さする技術)を中心とする手技に進化した。本書では、触れることの意味をはじめ指圧マッサージの基本から安全に実施できる手技までを紹介。手技は35本の動画で確認できる。看護師・介護士の手はケアの道具になる!
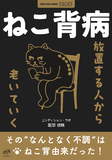
≪運動と医学の出版社実用書≫
ねこ背病 初版
放置する人から老いていく
「もう年だから…」と諦めていませんか?
1日1分から始める!【ねこ背改善メソッド】で、見た目も体も若返り、健康でイキイキとした毎日を取り戻す!
ふと鏡に映るご自身の姿勢に「背中が丸くなっているかも…」と気づいたことはありませんか? ねこ背は単なる見た目の問題ではありません。肩こりや腰痛の慢性化、股関節やひざの曲がり、転倒リスクの増加、活動範囲の縮小など、日常生活の質に直結する様々な悪影響をもたらします。歳を重ねるほど体のバランスを取る力が低下し、ねこ背が原因で身体機能全体が弱まる悪循環に陥ることもあります。また、ねこ背の人は体幹が「硬い」という特徴も持っています。
しかし、ねこ背は「歳だから仕方がない」と諦めるものではありません!
本書は、誰でも無理なく実践できる画期的なアプローチを紹介します。「ただ背中を伸ばせば治るわけではない」と提唱し、体幹・肩・股関節・ひざと全身の連動性を意識し、バランスよく整えることを重視。体全体の機能改善こそが、真のねこ背改善に繋がると説きます。
【本書で得られる効果と期待】
見た目の若返り:姿勢が改善され、若々しい印象を取り戻せます。
痛みからの解放:肩こり、腰痛、ひざの痛みの原因となる体の負担を軽減します。
転倒リスクの軽減:体幹でバランスがとれるようになり、転倒しにくい体に。
活動範囲の拡大:体が軽く動きやすくなることで、イキイキとした生活を送れるようになります。
【本書の5つの主要アプローチ】
たった1日1分、各エクササイズは30秒程度でOK! 該当ページ内のQRコードをスマートフォンで読み取ると、解説付きの映像で確認できるため、正しいフォームで無理なく続けられます。
体幹を伸ばす・筋力を改善するアプローチ:ねこ背改善の基本となる体幹の柔軟性・筋力を取り戻します。
肩周りを柔軟にするアプローチ:ねこ背と関係の深い「巻き肩」を改善し、腕の上げにくさを解消します。
股関節とひざを伸ばすアプローチ:体幹と相互に影響し合う股関節とひざの柔軟性を高めます。
下肢の筋力を改善するアプローチ:特に重要な「大殿筋」や「大腿四頭筋」など、足腰の筋肉を強化し、体の曲がりを食い止めます。
さらに、本書では「正しく立ち、正しく座る」といった基本の姿勢や、体幹をスムーズに前へ運ぶ「正しい歩き方」に加え、デスクワークやスマホ使用時など、日常生活でねこ背になりやすい場面ごとの改善ポイントも丁寧に解説しています。
「すべてを完璧に行うこと」ではなく、「自分に合ったエクササイズを1つでも見つけて続けること」が大切です。あなたの体は、きっと変わるはずです。
『もう年だから』と思う前に、ぜひ本書のメソッドを取り入れてみてください。健康でイキイキとした毎日の第一歩を、今日から一緒に踏み出しましょう!
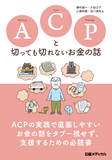
ACPと切っても切れないお金の話
ACPで患者の価値観や選好を汲み上げても、経済・法的な理由から実現できない。こんな悩みに、豊富な事例をベースに答えます。

認知症予防 第3版
読めば納得! 脳を守るライフスタイルの秘訣
読んだらすぐに実践したくなる予防法と、健康な脳と心、からだを備え、高齢期を豊かに生き生きと過ごす術を学べる、“認知症予防”の決定版。
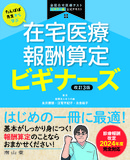
たんぽぽ先生から学ぶ
在宅医療報酬算定 ビギナーズ 第3版
はじめて在宅医療制度の報酬算定を学ぶ人にピッタリの一冊.改訂3版は『診療報酬改定2024年度』に完全対応した最新版です.本書は,毎年約3,000人以上が参加する「全国在宅医療テスト(ゆうの森主催)」ビギナー版の公式テキストとして,この本からテストが出題されます.テストに向けた予習・復習に最適な章末問題もさらにボリュームアップし,これからテストを受ける方には必読の内容です!また本書には,特別付録「たんぽぽ先生の在宅医療の5つの呪文」がついてきます! この5つの呪文は,その患者がどの在宅医療サービスを利用できるか,簡単に把握できる便利なツールです.ぜひ本書とともにご活用ください.これから在宅医療に取りかかる方,在宅クリニックや訪問看護ステーションなどの在宅医療関係の医療機関・事業所の新入職員の研修や初期学習にオススメできる本です.

≪運動と医学の出版社の臨床家シリーズ≫
寝たきりをつくらない介護予防運動 初版
~~理論と実際~~
高齢化率の上昇は、これから30年以上も止まることがありません。2055年には、なんと高齢化率が39.9%に達すると推計されています。
高齢化社会では、生涯「寝たきり」にならない身体をつくり、そして「家族の介護」を少なくすることがさらに求められていきます。
これを実現化するために、最も効果的な方法は『介護予防運動』です。
医師・療法士を含め、高齢者に関わるすべての医療人は、『介護予防運動』で効果を出すための理論と実際をしっかり学び、そして介護予防に真剣に取り組みいかなければなりません。
本書を読んで頂ければ、医療・介護が、そして社会全体が、これからしなければならいことが見えてくるはずです。

介護報酬の解釈 1 単位数表編 令和6年4月版
『算定に必要な情報を見開きで配置、一覧性に優れた定本』
本書は介護報酬の算定に関する情報を網羅しています。「算定基準告示(単位数表)」と、算定要件を定めたいわゆる「別告示」の内容、そして「留意事項通知」を原則見開き3段で掲載、算定できる単位数はもちろん、算定要件などのポイントも明快に知ることができます。
介護保険の事業者・施設での介護報酬の算定・請求やサービス計画の作成、さらには給付管理業務に必携の書として、幅広い方々にご活用いただいています。
本書は令和6年8月発刊の第2刷に、ウェブコンテンツの索引を追加したものです。

摂食嚥下訓練の基本を動画でひとつひとつやさしく学ぶ本
高品質でわかりやすい解説動画で
摂食嚥下リハビリテーション訓練の進め方がスルスルと頭に入る!
●摂食嚥下リハビリテーションの訓練法 基本28項目を網羅.
●19点,計72分の充実した訓練法解説動画がスマホやタブレット,PCからいつでもどこでも再生可能.
●第1章は動画をひとつひとつ紙面で再現.動画と本で何度も繰り返し訓練法を学習できる.
●第2章の症例解説は評価から問題点の整理,訓練法の選択へと臨床でのプロセスに沿って提示.症例ごとのまとめには,簡潔に疾病の解説もあり.
●訓練法と症例が双方向に参照できるよう,それぞれに該当ページを掲載.多くの訓練法が複数症例に適用されているので症例を通して訓練法を繰り返し復習できる.

生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン
リハビリテーション・栄養・口腔管理の一体的取り組みのための初のガイドライン!
要介護高齢者の日常生活活動および栄養状態、摂食嚥下や口腔内の問題は、相互に関連・影響するもので、単独介入ではなく、多職種による一体的な複合的介入こそ最も効果があると考えられてきた。しかし、その効果を検証した研究は少なく、ガイドラインも無かった。自立支援・重度化防止に向け、CQ11問・BQ21問を含む、リハビリテーション・栄養・口腔管理の一体的取り組みのための国内外初のガイドライン、ここに堂々刊行!
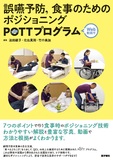
誤嚥予防,食事のためのポジショニングPOTTプログラム[Web動画付]
食事姿勢を整えるためのポイントは7つだけ! 姿勢が変わると「食べる」につながる!
食事の際の適切な姿勢を整えるポジショニングについて解説する1冊。POTTプログラム〔ポジショニングで(PO)食べるよろこびを(T)伝える(T)プログラム〕は食事の際の適切なポジショニングをとりやすくするために開発された技術。その技術は7つのポイントに分かれており、実践しやすく、それによって食事姿勢が整えやすくなり好循環を生みだします。そのコンセプト、技術をわかりやすく解説しています。
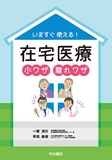
いますぐ使える!
在宅医療 小ワザ 離れワザ
在宅医療の最前線で奮闘する医師や看護師が,試行錯誤の中で培ってきた“現場の知恵”を一冊に凝縮.身近な日用品を活用するアイデアや,解決が難しいケースへのアプローチ方法まで,患者に寄り添う小ワザ離れワザを多数紹介.「そうそう,あるある!」と思わずうなずいてしまう現場の悩みを,わかりやすい解説と豊富な写真・イラストでスッキリ解決.在宅医療の奥深さと可能性を再発見できる実用書.

対話の実践力
ケアを極める聞き方・話し方
困難を抱える人の支援で有効な対話。本書では、対人援助において対話を開く際に大切なことを「3つの原則」「5つの型」に集約し、事例をもちいて超実践的に解説した。対話を展開するときのポイントや注意点など、支援現場で安全に対話を重ねていくためのエッセンスが満載。

メンタルメイクセラピスト®検定公式テキスト〈学科編〉
看護や介護の現場で活きる「メンタルメイクセラピスト®検定」。
本検定3級から1級までの資格に必要な知識に関する<学科編>公式テキストが発売です。
