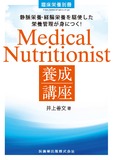
「臨床栄養」別冊 静脈栄養・経腸栄養を駆使した栄養管理が身につく!Medical Nutritionist養成講座
静脈栄養,経腸栄養を自在に使いこなす栄養管理のエキスパート“Medical Nutrition”養成のための実践的臨床講座
●静脈経腸栄養の第一人者,井上善文先生による月刊『臨床栄養』の人気誌上講座待望の書籍化.
●Part 1「栄養管理の基本」では,栄養評価法から栄養投与量の決定まで,臨床での栄養管理に必要な基本事項について,その考え方や実際を解説.
●Part 2「経腸栄養法」,Part 3「静脈栄養法」では,栄養剤の種類や適応から,投与経路やその管理方法,合併症対策までを実践に即し具体的に詳述.
●患者さんに,もっとも適正な栄養処方を実施し,もっとも有効な栄養管理を実施するための理論と実践を著者の豊富な経験からわかりやすく整理した至極の臨床講座.

月刊薬事 2026年1月臨時増刊号(Vol.68 No.2)
そうだ,認定を取ろう! 薬剤師のキャリアアップガイド
薬剤師の業務内容が高度化するなか、さまざまな学会・団体から認定・専門資格が設立されるようになり、専門性を高める機会が増えています。しかし、取得要件や取得方法などは団体によって細かく異なるため、認定資格を取得しようと思っても何から始めたらよいか迷う薬剤師も多いのではないでしょうか。
そこで、本臨時増刊号では、認定・専門資格一覧として情報をまとめたうえで、資格を取得した先人たちが取得する際に苦労した点や業務への活かし方などを紹介することで、“キャリアの道しるべ”を示します。また、実際に取得する際にネックになりがちな、症例報告や論文の書き方、学会発表のしかたなどについても触れ、キャリアアップを目指す薬剤師の背中を押す1冊とします。
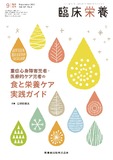
臨床栄養 147巻4号
臨時増刊号
重症心身障害児者・医療的ケア児者の食と栄養ケア実践ガイド
重症心身障害児者・医療的ケア児者の食と栄養ケア実践ガイド
重症心身障害児者・医療的ケア児者への栄養ケアアプローチを網羅的に解説
―多職種連携で実現する最適な栄養サポート
●栄養管理は重症心身障害児者の全身管理に重要であり,栄養管理方法や栄養剤の発展,各種疾患ガイドラインの充実にともない,重症心身障害児者・医療的ケア児者の栄養管理・ケアに関する研究・実践はさらに進んでいる.
●本書では基礎的なアセスメント方法から,経腸栄養の実際,合併症への対応,NST活動まで多職種の視点で解説し,事例から学ぶ特別な状態における栄養管理や,最新のトピックスも併せて網羅的に取り上げている.
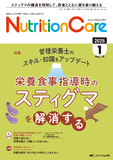
Nutrition Care(ニュートリションケア)2026年1月号
2026年1月号
特集:管理栄養士のスキル・知識をアップデート 栄養食事指導時のスティグマを解消する
特集:管理栄養士のスキル・知識をアップデート 栄養食事指導時のスティグマを解消する 患者を支える栄養の「知識」と「技術」を追究する
臨床における栄養療法の試行錯誤を取り上げ、その試みを共有し、蓄積できる専門誌です。臨床栄養学だけにとどまらず、栄養管理の実践的な知識と技術を提供します。
あらゆる栄養療法を駆使し、患者にアプローチし続ける管理栄養士・栄養士を応援します。

月刊薬事 2025年7月増刊号(Vol.67 No.10)
ハイリスク薬のリスクマネジメント インシデント・医療事故を防ぐための管理と記録
●重大インシデントを未然に防ぐ、現場ですぐに役立つ実践マニュアル!
インシデントや医療事故を防止し、安全な薬物療法を支援することは、薬剤師の基本的な業務です。特に、ハイリスク薬については、薬剤師による積極的な管理と他職種への情報提供が非常に重要です。
本増刊号では、インシデントや医療事故を防ぐための薬剤管理の基本、注意が必要な局面でのハイリスク薬の管理方法、そして他職種への情報提供や記録のポイントについて紹介します。
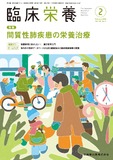
臨床栄養 148巻2号
間質性肺疾患の栄養治療
間質性肺疾患の栄養治療
●間質性肺疾患(ILD)は,肺の間質に炎症や線維化をきたす疾患群であり,特発性肺線維症(IPF)をはじめとした特発性間質性肺炎や,膠原病関連ILD,過敏性肺炎など原因や病態が多様な疾患を含む概念です.これらに共通する特徴として,疾患の進行に伴い,慢性的な呼吸機能低下,呼吸困難,食欲不振,身体活動量の低下などをきたすことがあり,低栄養やサルコペニアの併発がしばしばみられます.
●栄養障害はさまざまな呼吸器疾患において,呼吸困難の増強,QOLの低下や生命予後の悪化と関連することが明らかになりつつあります.ILD患者における栄養管理は標準化はなされておらず,医療現場では各施設の医師や管理栄養士の経験や個別対応に頼らざるを得ないのが現状です.
●本特集では,ILDにおける栄養療法の現状と課題を整理し,ILD患者の基礎病態から栄養状態の評価法,具体的な栄養療法介入の実践例,さらに多職種連携による包括的なアプローチまで,多角的な視点から各分野のエキスパートに解説をいただきました.呼吸器内科医,管理栄養士,リハ科医師など,それぞれの立場からの知見を共有することで,臨床に直結する実践的な内容をお届けします.
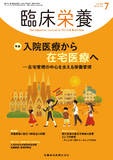
臨床栄養 137巻1号
入院医療から在宅医療へ-在宅管理の中心を支える栄養管理
入院医療から在宅医療へ-在宅管理の中心を支える栄養管理
わが国の65 歳以上,75 歳以上の高齢者人口の割合は,2025 年にはそれぞれ30%,18% を超えると予測され,5 年以内には3 人に1 人は高齢者という超高齢社会に突入することが確実となっている.この年齢分布の変化とともに,60%以上の国民が人生の終末期に自宅で療養したいと希望していることが,厚生労働省の調査により明らかになっている.さらに,要介護状態になっても自宅や子ども・親族の家での介護を希望する人が4 割を超えたことも明らかにされており,とくに高齢者では,ここ数年のうちに入院医療から在宅医療へのシフトが確実になると考えられる.この社会構造の変化に対応して厚生労働省は2012 年に在宅医療・介護推進プロジェクトチームを発足させ,入院医療から在宅医療への推進を図ってきた.2017 年の調査では,入院患者は1 日当たり131 万人に対し,在宅医療を受けた推計患者数は約18 万人となり,1996 年の7.2 万人に比較し約2.5 倍に増加している.このうち計画的かつ定期的に医療サービス・診療を提供する“ 訪問診療” の患者数は全体の60%を占めており,訪問診療の対象となった療養者数は20 年前に比較して3 倍以上に増加している.
入院医療が病院で疾患に対して主に行われる医療であるのに対し,在宅医療は個別の療養生活や社会状況を考慮に入れて行われる医療であることが特徴である.退院後,在宅医療に移行する場合には,ソーシャルワーカーやケアマネジャーを含め,入院医療よりもさらに多くの職種がかかわってはじめて成立するきわめて個別性の高いテーラーメイド医療が必要となる.とくに在宅高齢者では要支援・要介護の程度はさまざまである が,栄養状態不良によりフレイルやサルコペニアに陥り,QOL が著明に低下している場合が多い.療養者の良好なQOL を維持するためには,食支援を含めた栄養管理が不可欠である.
本特集では,現在,在宅管理を中心に行っている在宅医療機関の各職種の在宅医療のエキスパートの先生方に,在宅管理の重要性と在宅管理のなかでも必須とされる“ 在宅栄養管理” について,総論から実践的なポイントまで概説いただいた. [千葉県済生会習志野病院 外科 櫻井洋一]

月刊薬事 2025年10月臨時増刊号(Vol.67 No.14)
緩和ケア薬ケースファイル がん・非がん患者の症状緩和と薬剤選択の勘所
●各論×症例解説で患者背景に合わせた処方提案ができる!
緩和医療において、薬剤師はオピオイドの使用による効果と副作用のバランス調整や、患者一人ひとりの背景にあわせた薬剤選択など、専門的な判断が求められます。
本臨時増刊号では、緩和ケアが必要ながん患者、および非がん患者における各症状の原因や、患者背景を考慮した症状緩和のための治療方針、薬剤の使い方、モニタリングのポイントなどを解説します。

「臨床栄養」別冊 女性の食と栄養・代謝ガイドブック
女性の生涯の健康を支える指導に役立つ,日本女性栄養・代謝学会編集の実践的ガイドブック
●成長期から妊娠前,妊娠・出産,更年期,高齢期まで,女性のライフステージごとに変化する栄養ニーズと代謝特性を,最新の科学的知見に基づき体系的に解説した,日本女性栄養・代謝学会編集のガイドブック.
●女性に多い疾患別,またスポーツや災害時などの場面別の実践的な栄養管理に加え,DOHaD,周産期メンタルヘルス,免疫や機能性食品などの重要トピックスも網羅.
●女性にかかわる多職種の医療従事者にとって,女性が生涯を通じて健康な生活を楽しむための食と栄養・代謝に関する日常診療と指導に直結する一冊.

Nutrition Care(ニュートリションケア)2025年10月号
2025年10月号
特集:実践! コンビニ食を活用した栄養食事指導
特集:実践! コンビニ食を活用した栄養食事指導 患者を支える栄養の「知識」と「技術」を追究する
臨床における栄養療法の試行錯誤を取り上げ、その試みを共有し、蓄積できる専門誌です。臨床栄養学だけにとどまらず、栄養管理の実践的な知識と技術を提供します。
あらゆる栄養療法を駆使し、患者にアプローチし続ける管理栄養士・栄養士を応援します。

臨床栄養 146巻7号
働く世代の健康と栄養支援
働く世代の健康と栄養支援
●働く世代にとって,「健康」は働くことを支える重要な「資産」であるが,定期健康診断結果報告(厚生労働省)をみると,有所見率は58.9%(令和5年)と高く,脂質異常,高血圧,肝機能異常,高血糖等の所見が多い.また,働く世代ではメンタルヘルス不調による休業も多く,心の健康も同じく重要な健康課題となっている.
●働き盛りの世代では,循環器疾患等の発症率が上の世代ほど高くはなく,健康管理の優先度が低いことも多い.食事と関連する生活習慣病は多いため,日々の食事を工夫できるスキルや,自然に,健康的な食事をおいしく楽しく食べられる食環境があれば,生活習慣病対策が進むことが期待される.
●本特集は,直接的な,あるいは食環境づくりなどの間接的な栄養支援を通して,働く世代の健康づくりが進むことをめざして企画した.読者の皆様の日々の活動の参考になれば幸いである.
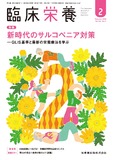
臨床栄養 146巻2号
新時代のサルコペニア対策 ―GLIS基準と最新の栄養療法を学ぶ
新時代のサルコペニア対策 ―GLIS基準と最新の栄養療法を学ぶ
●サルコペニアは,高齢者のQOLと健康寿命に大きな影響を与える重要な課題です.2024年に改定されたGLIS基準は,サルコペニアの概念を明確にし,診断基準を世界的に統一することで,より早期からの介入を可能にしました.
●本特集では,GLIS基準に基づくサルコペニアの診断と,最新の栄養介入のエビデンスについて詳しく解説します.本特集が,臨床の最前線で活躍する管理栄養士や医療従事者のサルコペニア対策の実践の一助となることを願っています.

臨床栄養 144巻6号
臨時増刊号
疾患・病態別のポイントがわかる!栄養指導オールガイド
疾患・病態別のポイントがわかる!栄養指導オールガイド
●疾患・病態別の個別栄養指導がこの一冊でブラッシュアップできる,最新の知識と指導のポイントが詰め込まれた実践的ガイドブック!
●糖尿病・腎臓病・癌など病棟でよく目にする疾患については,項目をさらに細分化して丁寧に解説.豊富な臨床経験を踏まえた栄養指導の実際の工夫がよくわかる構成.
●食事管理アプリやオンライン栄養指導,ウエアラブル機器など,これからの栄養指導に役立つ最新トピックも多数掲載.
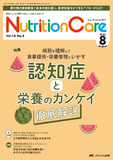
Nutrition Care(ニュートリションケア)2025年8月号
2025年8月号
特集:認知症と栄養のカンケイ徹底解説
特集:認知症と栄養のカンケイ徹底解説 患者を支える栄養の「知識」と「技術」を追究する
臨床における栄養療法の試行錯誤を取り上げ、その試みを共有し、蓄積できる専門誌です。臨床栄養学だけにとどまらず、栄養管理の実践的な知識と技術を提供します。
あらゆる栄養療法を駆使し、患者にアプローチし続ける管理栄養士・栄養士を応援します。

臨床栄養 148巻1号
これからの病院管理栄養士教育
これからの病院管理栄養士教育
●近年の診療報酬改定では,管理栄養士の専門性や配置が相次いで評価の対象となり,病院管理栄養士の臨床現場における役割が広がっています.養成校での臨床栄養教育はもとより,卒業後の現場における教育の重要性はこれまで以上に高まっています.
●外来や病棟での臨床経験を通じて実践力を育む教育,部門内での役割に応じて求められるスキルの体系的な育成,管理栄養士一人ひとりが主体的に自己研鑽に取り組むための支援体制,いずれも欠かすことのできない課題です.
●本特集では,病院管理栄養士の教育・育成において先進的な取り組みを行っている病院・組織の先生方に,現状の整理と今後の方向性についてご解説いただきます.

臨床栄養 145巻7号
食品の機能性と安全 ―正しく理解し,伝えるための最新情報
食品の機能性と安全 ―正しく理解し,伝えるための最新情報
●いわゆる「健康食品」のうち保健機能食品は,国が定めた基準に従って,食品の機能の表示が可能であり,特定保健用食品,栄養機能食品,機能性表示食品の3種類がある.このうち,特定保健用食品や機能性表示食品では,からだの調子を整えるために,また,栄養機能食品では,不足した栄養素の補給を目的として利用されることが期待される.
●昨今,食を取り巻く社会状況が刻々と変化しているため,保健機能食品を生活の中に取り入れて機能を活用したい消費者の間では,不安も広がっている可能性も否定はできない.
●そこで,本特集では,主に機能性表示食品の機能性や安全性に関する評価方法についての解説とともに,製品の品質の重要性や消費者に対する情報伝達のあり方などをまとめた.本特集により,食の機能に関する理解がさらに深まることで,消費者が安全安心に食品の選択ができる食の環境が最適化されていくことを期待する.

Nutrition Care(ニュートリションケア)2025年12月号
2025年12月号
特集:管理栄養士が取り組む タスクシフト/シェア
特集:管理栄養士が取り組む タスクシフト/シェア 患者を支える栄養の「知識」と「技術」を追究する
臨床における栄養療法の試行錯誤を取り上げ、その試みを共有し、蓄積できる専門誌です。臨床栄養学だけにとどまらず、栄養管理の実践的な知識と技術を提供します。
あらゆる栄養療法を駆使し、患者にアプローチし続ける管理栄養士・栄養士を応援します。

臨床栄養 147巻7号
栄養からみた 高血圧対策の新パラダイム
栄養からみた 高血圧対策の新パラダイム
●高血圧はいまなお国民の健康寿命に影響する最大の要因であり,その予防と管理において栄養・食生活の対策はもっとも重要です.
●2025年は,厚生労働省から「日本人の食事摂取基準(2025年版)」が発表され,高血圧に対する対策の部分が改定されました.さらに,日本高血圧学会は「高血圧管理・治療ガイドライン2025」と「デジタル技術を活用した血圧管理に関する指針」を発表しました.
●本特集では,これら最新の動きを解説するとともに,日本高血圧学会,日本循環器病予防学会,日本動脈硬化学会が進める循環器病予防療養指導士認定制度についても紹介します.
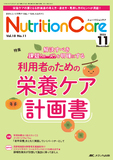
Nutrition Care(ニュートリションケア)2025年11月号
2025年11月号
特集:利用者のための栄養ケア計画書
特集:利用者のための栄養ケア計画書 患者を支える栄養の「知識」と「技術」を追究する
臨床における栄養療法の試行錯誤を取り上げ、その試みを共有し、蓄積できる専門誌です。臨床栄養学だけにとどまらず、栄養管理の実践的な知識と技術を提供します。
あらゆる栄養療法を駆使し、患者にアプローチし続ける管理栄養士・栄養士を応援します。

臨床栄養 147巻6号
これからの精神科栄養
これからの精神科栄養
●精神疾患と栄養に関する研究が進み,精神科領域でも栄養や食事への関心が高まっています.
●一定のスキルを持つ管理栄養士・栄養士を対象に,精神科認定栄養士制度が創設され,専門性を活かした支援が広がっています.
●本特集では,精神栄養学の最新情報をはじめ,急性期病院,精神科病院,社会復帰支援など多様な現場での栄養支援を紹介します.
