
眼科疾患最新の治療2025-2027
3年毎の改訂で,眼科疾患における治療指針と最新の情報を簡潔に提供.巻頭トピックスでは,話題のガイドライン,再生医療,AI診療,スマホ内斜視,萎縮型加齢黄斑変性の治療など,注目の10テーマをレビュー.各論では主要な眼疾患の治療を網羅し,コラムを豊富に掲載.日常診療のアップデートに欠かせない一冊.

≪非腫瘍性疾患病理アトラス≫
感染症
感染症の病理診断とは病原体の診断であり,そのために知っておかなければならないことも多い.本書では,総論的なこととして,感染症の病理診断の考え方や生体反応,感染防護などの基本事項を取り上げ,各論では,代表的な感染性疾患から,まれではあるが特徴的な疾患,新たに概念が確立した疾患,さらに腫瘍性病変の下地としての感染症まで,今,知っておきたい感染症を豊富な写真とともに取り上げた.まさに感染症病理の決定版アトラス.

エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図 第3版
臨床・実習でよく出会う25疾患について、誘因・原因から病態生理学的変化、看護ケアまでを図式化した看護ケア関連図ガイドの第3版。疾患のメカニズム、症状、検査・治療の知識、観察のポイント等もオールカラーで解説。看護ケアの根拠が一目でわかる!

診断+治療を完全攻略
皮膚疾患データブック
皮膚疾患をどのように鑑別診断し,治療すればよいのか。初学者でも使いやすいよう下記の工夫を施して,疾患の基本情報から,診断・治療のアドバイスまですべて詰め込んだ。
①誰もが使いやすい,見た目(水疱の有無・色)の特徴からなる診断アルゴリズムを提示
②鑑別診断に有用な所見(視診・検査・病歴)の特徴を,信頼度でランク付け
③各疾患の遭遇頻度・かゆさ・痛さ・治りにくさ・危険度を5段階評価
④疾患解説ではまず,症例写真・診断基準・治療例を紹介
⑤実践的な診断や治療は,Q&A方式でわかりやすく解説
診断・治療は,エビデンスベースで説明しつつ,コツやピットフォールは著者の経験をふまえて親切に解説。
困ったとき,疑問に直結する答えがすぐ見つかる。
根拠が明確な情報が盛りだくさんで,読むだけで知識が身につく。
これ1冊が机にあれば,皮膚疾患にも安心して臨むことができる。

ベクトル視点でやさしく読み解く
呼吸器外科手術解剖イラスト
若手呼吸器外科医が習得しなければいけない胸腔鏡手術における胸腔内の解剖をイラスト化し,「自分が今どの方向から何を見ているか」「対象臓器にどのような力が加わりどう変形しているか」という2種類のベクトル視点で解説.モニターでは視認できない奥に隠れた臓器も描かれており,解剖・手術手技の理解を深めることができる.全編にわたって目を見張るほど美しいカラーイラストが掲載されており,手術室ナースにとってもテキストとなる1冊!
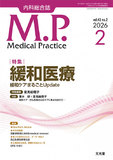
Medical Practice 2026年2月号
緩和医療─緩和ケアまるごとUpdate
緩和医療─緩和ケアまるごとUpdate 特集記事として,[対談]緩和ケア─がん患者の心のケアに焦点をあてて─,[総説]アドバンス・ケア・プランニングと療養場所の選択,アドバンス・ケア・プランニングと療養場所の選択,[セミナー]適切な緩和ケアの実践に向けたアセスメント,[治療]がん疼痛の薬物療法 等.また連載では,[One Point Advice][今月の話題][知っておきたいこと ア・ラ・カルト][心電図がよめる,得意になるシリーズ]他を掲載.

がん疼痛緩和の薬がわかる本 第4版
なぜこの薬? 副作用は? アセスメントのポイントは? 第4版ではさらにわかる!
好評書として定着した本書が、取りあげる薬剤をさらに充実させた。がん疼痛緩和の薬の効用や副作用、アセスメント、選択・使用の考え方がわかりやすく解説され、症例が豊富にあげられているので、より理解が進む。がんの痛みの理解から、非オピオイド鎮痛薬、オピオイド、鎮痛補助薬まで取りあげた、臨床のエッセンス満載の1冊。

点眼薬の選び方 3版
この5年間の変化をふまえて全面改訂。
とくに,投与中に眼科診察を定期的に行う必要がある薬剤,副作用予防のための点眼使用がプロトコールに入っている抗がん剤などの情報を充実させました。
処方薬のほか,患者さんによく聞かれる市販薬もカバー!

膠原病コンサルの手引き
その相談の根拠・原因,説明できますか?
膠原病は全身性の自己免疫疾患であり,関節症状,皮膚症状,頭頸部の症状,臓器病変,薬剤副作用,そのほかさまざまな臓器に炎症を引き起こします.しかし,これらの症状は膠原病以外の疾患でも見られることがあり,鑑別診断に苦慮することも少なくありません.本書は膠原病の解説を中心としつつ,膠原病以外に考えられる多くの原因にも目を向けました.総合内科や各専門科からよく相談をうける各種症状について,膠原病内科医が総合診療的視点でみた時にはどのように考えているのかを解説しました.

≪消化器画像診断シリーズ 1≫
消化管内視鏡診断テキスト I 食道・胃・十二指腸 第5版
消化管内視鏡の“みかた”をわかりやす解説した定番テキスト,上部消化管(食道・胃・十二指腸)編が8年ぶりに大改訂.第1版からの「シンプルな記述」「豊富な写真」のコンセプトはそのままに,解説と写真を刷新し,自己免疫性胃炎や噴門部癌など新たな疾患も追加.H. pylori 感染に基づく胃炎分類も整理され,模式図で病変を直感的に把握できる構成.研修医や若手医師,医学生が短時間で診断の要点を身につけられる最適な一冊.

〜所見を「読んで」「考える」〜
臨床医のための腎病理読解ロジック
腎臓に関わる臨床医が理想的に病理標本を読めるようになるためには,正しい用語で所見を描写し、患者の病態や
予後について考えることで「ただ見ていただけ」の読み方から脱却することが必要である.本書では臨床医として
腎病理の臨床と研究を極めた著者が,メカニズムから丁寧にわかりやすく解説した.病変の成り立ちから学び,所
見が意味するものを個々の患者ごとに考える力を身につけることができる一冊.
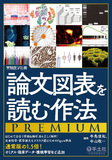
≪実験医学別冊≫
論文図表を読む作法PREMIUM
はじめて出会う実験&解析法も正しく解釈!生命科学・医学論文をスラスラ読むためのFigure事典 通常版の1.5倍!オミクス・臨床データ・機械学習など追加
論文のFigureを正しく読み解きたいあなたへ.115の実験・解析法を簡潔に解説して好評を博した前著が,58項目を新たに加えた“プレミアム版”として再登場.オミクス・臨床データ・機械学習の分野を拡充した全173項目で,生命科学の論文がもっと速く,正確に,深く読めるようになります

≪関節拘縮シリーズ≫
肩関節拘縮の評価と運動療法 改訂版
▶肩関節治療の決定版が10年ぶりにリニューアル
もっと軽く!もっと自由に!
肩関節をさらに解き放て!
▶イラストと写真を刷新。さらにわかりやすく!
▶著者の実技映像を59本追加!
本書は、10年前に出版された『肩関節拘縮の評価と運動療法』の改訂版です。
シリーズ5万部を越えている『拘縮』シリーズでも特に人気の本書に新たに実技映像を追加し、読者がより効果的に学ぶことができるようになっています。改訂版では、イラストや図が一新され、より解説がイメージしやすくなっています。
また、肩関節拘縮の評価方法から、運動療法の実施方法までを詳しく解説し、運動療法に興味がある理学療法士やスポーツトレーナー、医師、学生などに向けた内容となっています。
QRコードを読み取ることで、本書で紹介された運動療法を実際に実践している著者の解説映像を59本視聴することができます。本書を読むことで、肩関節拘縮の適切な評価と効果的な運動療法の実際を学ぶことができます。前作を読んだ読者はもちろん、新たに知見をブラッシュアップしたい方にもオススメの書籍となっています。

CT・MRI画像解剖ポケットアトラス 第4版 3巻 脊椎・四肢・関節
さらに詳しく使いやすくなった、ポケットアトラスの決定版
CTやMRIの正常解剖をコンパクトにまとめた定評あるアトラスの筋・骨格系編、10年ぶりの改訂。本書ではMRIに特化し、1・2巻と同様、身体各部位ごとに高精細MR画像写真とポイントを彩色したシェーマを見開き一頁の中で対比させており、複雑な解剖構造を容易かつ正確に認識できる。改版にともない、炎症や腫瘍などの病変理解に有用な関節近傍部位の画像やシェーマが大幅に追加され内容はさらに充実。放射線科医・技師の必携書として、研修医、整形外科医の読影の参考書として最適。

≪ジェネラリストBOOKS≫
集中講義! おなかの身体診察
フィジカル&腹診で腹部症状に立ち向かえ
フィジカル×漢方アプローチの二刀流でおなかのトラブルに立ち向かえ!
「急性腹痛の患者さんが来た! でも、CTが使えない! どうしよう…」、「慢性腹痛の患者さんか。不定愁訴の診療は苦手なんだよな…」。腹痛診療に苦手意識を持っている方は多いのではないでしょうか。でも、大丈夫、ローテクな身体診察でバッチリ対応できるんです! 急性腹痛にはフィジカル、慢性腹痛には腹診で対処しましょう。患者さんのおなかのトラブルに立ち向かうあなたのための集中講義が開講です。

症候からわかる irAE逆引きマニュアル
本書は、近年注目を集めている免疫チェックポイント阻害薬(ICI)に伴って発現する副作用、「免疫関連有害事象(irAE)」への実践的な対応法をまとめた、医療従事者向けの実用書です。ICIの登場によりがん治療は大きく進展しましたが、それに伴い、従来とは異なる副作用であるirAEへの理解と適切な対応が求められるようになっています。
著者は、経験の浅い医師や看護師をはじめとするすべての医療従事者がirAEに自信を持って対応できるよう、「連携体制の構築」「患者教育の徹底」、そして著者が独自に作成した「irAE逆引きマニュアル」の3本柱を提唱しています。
なかでも「irAE逆引きマニュアル」は、症状から疑われる疾患を迅速に確認できる構成となっており、診断・検査・治療の流れをワンストップで把握できる実用的なツールです。現場での即応力を高める一助となるでしょう。
また、irAEの治療には多様かつ専門的な対応が必要とされるため、各診療科やメディカルスタッフとの密な連携が不可欠です。さらに、患者さんやご家族への丁寧な説明の重要性にも焦点を当て、チーム医療における各職種の役割についても紹介しています。
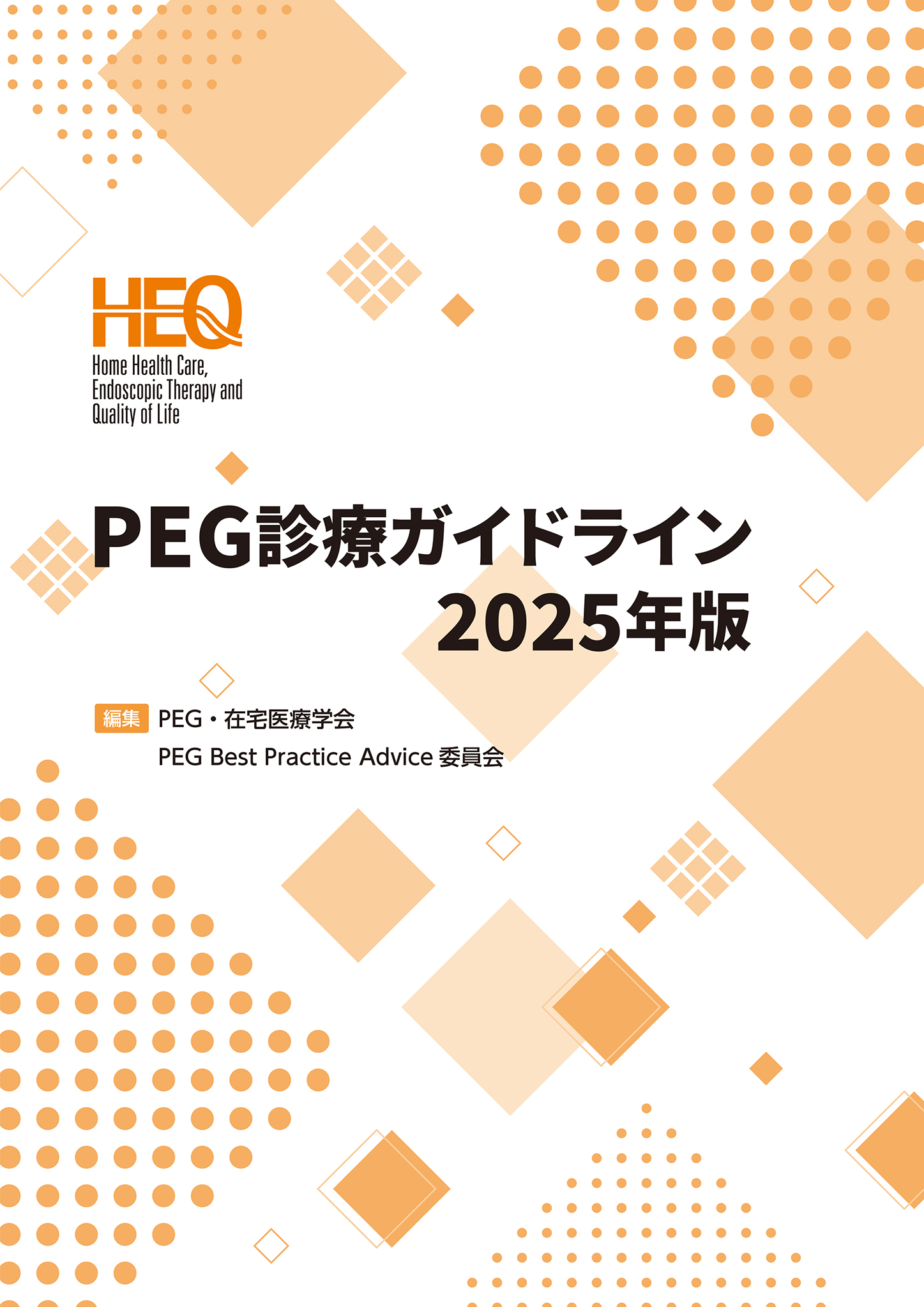
PEG診療ガイドライン 2025年版
●本書は,実臨床における真に必要なメッセージとしてPEGを冠する本学会の総力を挙げて作成されました。
<発刊に寄せてより>
今回刊行されたPEG診療ガイドラインの基本コンセプトは,実臨床において真に必要なメッセージを作成することで,そのためにエビデンスのみに縛られることなく,経験豊かな専門家の意見も柔軟に汲み入れられているはずです。海外の学会でも新定義の厳しい診療ガイドライン(PG)と区別してBest Practice Adviceという実臨床で役立つ支援ツールが開発されていますが,本ガイドラインは正にBest Practice Adviceとして,PEGに関連する診療に携わる方々を支援する有益な情報源となることを確信しています。(上野文昭)
<本書の刊行にあたってより>
胃瘻よりもCVポートの方を希望します,とか,誤嚥性肺炎の人には胃瘻がいいのでしょうか?とか,胃瘻からの栄養剤投与はどうしたらいいのですか?とか,胃瘻を造ったら口から食べられなくなるのですよね,といった声が近頃,医療従事者から私に届くようになりました。20年くらい前には想像がつかないような状況です。栄養投与には患者さんごとに最適の投与ルートがあることや,嚥下訓練には適切な栄養投与が必要なことや胃瘻の基本が理解されていないのだと痛感しました。(中略)
PEGは単なる「内視鏡を使って胃にカテーテルを留置することができ,胃内に栄養剤を注入することができる」投与ルート造設法です。胃瘻は造設することが目的ではなく,造ってからの栄養投与が目的なのです。胃瘻が出来てから医療が始まるのです。(中略)
このガイドラインはPEGと栄養に関する,現時点での標準的な扱い方が記されています。本書を読むことで,PEGを有する患者さんに真摯に向き合うようになってほしいと考えています。
多くのPEGに携わる方々に本書を読んでいただきたく思います。そして本書を手に取られた方々にとって,PEGの理解のために少しでも有用であれば望外の喜びです。(西口幸雄)

≪消化器画像診断シリーズ 2≫
消化管内視鏡診断テキスト II 小腸・大腸 第5版
消化管内視鏡の“みかた”をわかりやすく解説した定番テキスト,下部消化管(小腸・大腸)編が7年ぶりに大改訂.第1版からの「極力シンプルな記述」「厳選しかつ豊富な写真」のコンセプトのもと,解説と写真を全面刷新.症例画像の模式図は元画像を白黒加工し,矢印や線で病変の位置や範囲を明示し,ポイントが一目でわかる.多忙な研修医や若手医師,医学生が下部消化管内視鏡のエッセンスを身につけるのに最適な一冊.

レジデントノート増刊 Vol.27 No.14
【特集】基本の「型」をマスターし消化器診療に強くなる
【特集】基本の「型」をマスターし消化器診療に強くなる
研修医や非専門医が救急・病棟でよく出合う消化器疾患にフォーカス!当直・救急での初期対応から診断,治療,入院後管理に至るまで,場面ごとに「今,何をすべきか」をその根拠とともに専門医が丁寧に解説します.「急性腹症」や「消化管出血」などにも慌てず対応できる型が身につきます.また,CTや腹部エコー画像の読影のコツ,コンサルトの際に必要な情報,抗菌薬投与の考え方など,研修医が知っておくべきTipsが満載です.

サルコイドーシス診療の手引き2023
主要臓器病変として呼吸器、眼、皮膚、心臓、神経の項を設けている。多臓器に病変が及ぶことがあるので臓器病変、特殊病態などの項を設け、診断と治療を解説している。
