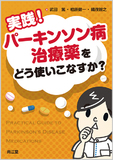
実践! パーキンソン病治療薬をどう使いこなすか?
パーキンソン病領域の第一人者である著者らが、非専門医を対象に、パーキンソン病薬物治療のHow toを伝える。治療薬の基本事項から、治療の実際(運動症状、非運動症状への対応)、さらに問題症例の解説を加えた構成。『パーキンソン病診療ガイドライン2018』の内容を反映した上でガイドラインでは触れられない実践的な部分まで、具体的な処方例を交え解説。薬剤の選択、複数薬の併用方法、減薬方法、副作用への対応など、患者一人ひとりの症状・状況に応じたきめ細やかな薬物治療について学べる一冊。

子どもの診かた、気づきかた
小さな異変もこぼさず拾える!
●ポイントがわかれば、よくある症状にあたふたしない!
●子どもの症状から診断までのロジック、必要な検査や鑑別疾患などを徹底解説
子どもは自分ではうまく症状を説明できないもの。見落としのない診断はハードルが高いと感じることはありませんか?
好評書『小児科ファーストタッチ』に続く、小児科診療を楽しく学ぶ書籍の第2弾! 症状から診断までのロジックや、見逃したくない疾患に気づくために必要な検査や鑑別疾患などを会話形式で徹底解説しました。「小児科ってこんなにシンプルなのか!」と目から鱗が落ちること間違いなしの1冊です。「実際どうなの?」と普段はなかなか聞けない疑問も丁寧に深掘りし、また、随所にあるクイズを通して理解度を確認できます。最初から読み通すもよし、不正解だったページから読み込むもよし。岡本ワールド全開の本書をぜひお楽しみください。
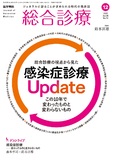
総合診療 Vol.35 No.12
2025年 12月号
特集 総合診療の視点から見た 感染症診療Update この10年で変わったものと変わらないもの
特集 総合診療の視点から見た 感染症診療Update この10年で変わったものと変わらないもの ①独自の切り口が好評の「特集」と、②第一線の執筆者による幅広いテーマの「連載」、そして③お得な年間定期購読が魅力! 実症例に基づく症候からのアプローチを中心に、診断から治療まで、ジェネラルな日常診療に真に役立つ知識とスキルを選りすぐる。 (ISSN 2188-8051)
月刊、年12冊

自信をもって正しく巻ける シーネ・ギプス固定手技
事前準備から完成・患者指示まで、専門医がいなくても迷わずに対応できる!
救急・当直で出合う整形外傷,自分でちゃんと対応できますか?手技が不安な研修医・非専門医に,正しい固定方法と症状を悪化させないコツを丁寧に教えます.お手本のWeb動画&外傷別の外固定早見表付き!

心電図のみかた,考え方 基礎編
心電図の取り方や見かたが,楽しく気軽に読み進めていくにつれて自然と身に着けられる.著者自身が心電図に苦労して克服した経験があるからこそ出来る分かりやすい解説は,読者に語りかけるような会話形式で進み,実際の講義を受けているかのように頭に入ってくるだろう.ゼロから心電図を学ぶ人,どうしても苦手意識が消えない人も,きっと心電図の判読に自信を付けることができる,強くおすすめできる一冊だ.

新 現場で役立つラクラク成長曲線
成長曲線の種類,目的などの解説から,子どもの成長・発達のなかで成長曲線をどうやってみて,どう活用していくのかを,乳幼児身体発育曲線や0~17.5歳の体重・成長曲線を用いた豊富な症例で解説しています.子どもの健康を確認し,病気や異常をみつけるためにすぐに役立つ知識が満載です!

理学療法ジャーナル Vol.56 No.10
2022年10月発行
特集 子どもの成長・発達を支える理学療法
特集 子どもの成長・発達を支える理学療法 理学療法の歴史とともに歩む本誌は、『PTジャーナル』として幅広い世代に親しまれている。特集では日々の臨床に生きるテーマを取り上げ、わかりやすく解説する。「Close-up」欄では実践的内容から最新トピックスまでをコンパクトにお届けし、その他各種連載も充実。ブラッシュアップにもステップアップにも役立つ総合誌。 (ISSN 0915-0552)
月刊,年12冊

レジデントノート Vol.27 No.6
2025年7月号
【特集】医学情報の集め方・活かし方 生成AI時代のスタンダード!
【特集】医学情報の集め方・活かし方 生成AI時代のスタンダード!
みんながいま知りたい,医学情報活用スキルが集結!臨床的疑問解決の基本を大切にしつつ,医学情報サイトやアプリの使い方,AIを利用した論文読解など各種ツールの効果的かつ実践的な活用法・Tipsを紹介します.

≪実験医学別冊≫
実験デザインからわかる シングルセル研究実践テキスト
シングルセルRNA-Seqの予備検討から解析のコツ、結果の検証まで成功に近づく道をエキスパートが指南
シングルセル研究を始めることになったら?実験計画のポイント,サンプル調製,Seurat,Scanpyなど解析ソフトの実例コードや,外注の検討事項まで.全体の流れを把握して即戦力をつけたいあなたに!

病状説明
ケースで学ぶハートとスキル
病状説明は、「説得」でも「言い切り」でもない。関係する者全員が「これまでとこれから」の価値感を共有することにある(共創)。本書は、14のケーススタディで、実際の会話や準備で重要なポイントや「技」を学ぶ(実践編)と、病状説明を漏れなくスムーズに行うためのフレームワークと、その理論的背景の解説(理論編)で構成される。病状説明を学ぶ人、教える人のために「心と技」をセオリー化した画期的な1冊。

医師のための 即効!英会話フレーズ 国際学会編
本シリーズは医師が英会話の必要性を強く感じる「外来診療」「国際学会」という2つの場面の英会話フレーズをまとめた,音声付きの英会話書籍である。
「国際学会編」である本書は,発表データの確認など受付で使う表現から,演題発表,ポスター発表,座長としての進行,質疑応答,懇親会でのソーシャルな表現まで,国際学会で必要となる英会話フレーズのほとんどをカバーしている。日英併記なので自分が必要としている英語表現がすぐに見つかり,必要なときにすぐに役立つ構成となっている。また,すべての英語音声は端末上で再生することができる。
「スライドの右斜め上をご覧ください」「前方の席が空いているのでつめてください」など,日本語では簡単に言えることでも,英語となると出てこない表現は多い。これらは学会の「決まり文句」ともいえる表現なので,英語ができるかどうかというよりも,知っていればすぐに言えるが,知らなければ出てこない表現といえる。
「抄録はすべて英語にする」「発表もできるだけ英語で」など,学会の国際化が年々進んでいる。学会参加時には必ず役立つ1冊である。

脳卒中・脳外傷者の自動車運転に関する指導指針
脳卒中・脳外傷者の運転再開の明確な基準が設けられていない中、リハビリテーション医学会専門医が運転指導にあたる医療職、行政職、教習所関連職、当事者、家族の共通の手引書となるようまとめた待望の1冊。
道路交通法などのわが国の法制度や国内外のこれまでの研究報告から、脳卒中・脳外傷者の自動車運転再開をどのように進めるか、その手続きや必要な評価について、わかりやすく解説した。

マッチングと国試対策 第2版
マッチングと国試の乗り切り方の決定版!人気病院へのマッチも夢じゃない! マッチングのテクニックと、スマートな医師国家試験対策を1冊にまとめました。マッチング対策のABCを分かりやすく、丁寧に解説。「受かる人」と「落ちる人」の差はなにかも明確に示しました。見学の準備から書類の書き方、面接での受け答えまで事細かに解説。「最強の国試乗り切り術」では対策から当日の心構えまで、受験者必須の情報が盛りだくさんです!

J. of Clinical Rehabilitation 35巻1号
経頭蓋磁気刺激とリハビリテーション
経頭蓋磁気刺激とリハビリテーション
●経頭蓋磁気刺激(TMS)は,脳の活動性を非侵襲的に調節し,運動機能や高次脳機能の回復を促す治療法として急速に発展しており,リハ医療における基礎理解と実践的知識の重要性が高まっている.
●TMSは,運動経路の評価に用いる神経生理検査としての側面と,脳皮質興奮性の調整による治療的介入としての側面をもち,脳卒中後の麻痺や高次脳機能障害,疼痛など多様な病態への応用が進み,ガイドラインでも推奨される治療として認知されるに至った.
●本特集では,TMS の基礎的な作用機序から,脳卒中後の運動障害,高次脳機能障害,多様な病態に対する最新の臨床応用,安全な実施方法・注意点に至るまで,第一線の研究者・臨床家が包括的かつ実践的に解説している.

血液検査×総合診療 非血液専門医・ジェネラリストのためのBasic&Practical血液診療
血液診療全般に通じ,かつジェネラリストである超実力派著者による「非血液専門医」「ジェネラリスト」のための血液診療指南書の決定版!「非血液専門医」「ジェネラリスト」の方に向け,症例ベースで,日常診療の現場で血液疾患をどのように考え,診断し,対応すればいいかといった思考の過程を見える化し,非専門医が対応可能な血液疾患患者に適切に対応するために必要なことのエッセンスを凝縮しました! これ一冊で,あなたも血液検査を基に診断できる!もう血液疾患は怖くない!

嗜癖、神、性愛
「中高年ひきこもり」の理解に向けて
現代社会の深刻な課題である「中高年ひきこもり」を,嗜癖(依存),神(宗教),性愛という根源的テーマから読み解く。

「Medical Technology」別冊 超音波エキスパート17 腎・泌尿器領域の超音波検査
◎腎・泌尿器領域の検査について,超音波をはじめ多角的な診かたを解説!
●大好評「超音波エキスパートシリーズ」の17冊目として待望の「腎・泌尿器領域」が登場.
●腎・泌尿器領域のスクリーニング検査から,各種疾患の鑑別,また透析腎の診かたなどについてわかりやすく解説.
●超音波像だけでなくCTやMRI検査との関連や,血液生化学と尿検査からみた腎・泌尿器疾患についても扱って,多角的な診かたを盛り込んだ充実の内容.
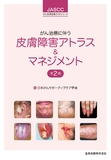
JASCCがん支持医療ガイドシリーズ
がん治療に伴う皮膚障害アトラス&マネジメント 第2版
近年のがん治療ではさまざまな作用機序の薬剤を使用するため、その副作用として生じる皮膚障害も多様化している。皮膚障害への対応の遅れは薬物療法の完遂率低下や患者さんのQOL低下につながる可能性もあり早期の対応が求められる。
本書では各治療で生じる皮膚障害を初版と同様にアトラスを用いてわかりやすくまとめるとともに、新たに放射線皮膚炎、感染症、支持療法の副作用についても記載した。
予定通りのがん治療の完遂と患者さんのQOL維持・向上のために、臨床現場で役立つ一冊。

改題改訂 喘息バイブル
成人喘息を診療するすべての人へ
◆あの「気管支喘息バイブル」が改題改訂!
◆初版からの4年のあいだに出た数々のエビデンスを踏まえ、倉原先生のわかりやすい語り口でなんと100ページを超える大幅追記!最新の臨床試験から薬剤までばっちり押さえています。
◆呼吸器診療のcommon diseaseに君臨し続ける「喘息」、重要なのは外来でしっかりマネジメントすることです。「発作を起こさせない」ためにどうすればよいのか、ぜひ本書をご参考ください。

脳神経外科 Vol.50 No.3
2022年 05月発行
一生使える 頭蓋底外科手術の”知”と”技”〔特別付録Web動画付き〕
一生使える 頭蓋底外科手術の”知”と”技”〔特別付録Web動画付き〕 雑誌『脳神経外科』は2021年1月よりリニューアルしました。「教科書の先を行く実践的知識」を切り口に、脳血管障害、脳腫瘍、脊椎脊髄、頭部外傷、機能外科、小児神経外科など各サブスペシャリティはもちろん、その枠を超えた横断テーマも広く特集します。専門分野・教育に精通し第一線で活躍する脳神経外科医を企画者・執筆者に迎え、診断・治療に不可欠な知識、手術に生きる手技や解剖を、豊富な図と写真を用いて解説します。さらに、脳神経外科領域の最新の話題を取り上げる「総説」、手術のトレンドを修得することのできる「解剖を中心とした脳神経手術手技」も掲載します。 (ISSN 0301-2603)隔月刊(奇数月),年6冊
