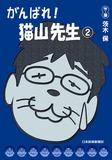
がんばれ!猫山先生②
人気漫画『Dr.コトー診療所』の監修者が描いた医療系ゆるゆるコミック。奇抜なキャラが繰り広げる「真実の(?)医療現場」の物語。好評の第1巻に続き刊行。
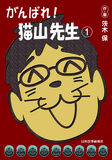
がんばれ!猫山先生①
人気漫画『Dr.コトー診療所』の監修者で,自身医師でもある茨木氏が描いた医療系ゆるゆるコミック。奇抜なキャラたちが繰り広げる,笑いとペーソスに満ちた四コマ漫画。

オーダーメイド医療をめざした 生活習慣病の遺伝子診断ガイド 第2版
動脈硬化症など,生活習慣病の発症に関連する遺伝情報が,個人の健康管理にとっていかに有益な情報になりうるか。健康管理への具体的利用はどうするかの最新情報を満載。
肥満遺伝子,酸化ストレス・体内老化関連遺伝子,動脈硬化関連遺伝子,コレステロール関連遺伝子,高血圧関連遺伝子,高血糖関連遺伝子,血栓関連遺伝子,アレルギー関連遺伝子,歯周病関連遺伝子,骨粗鬆症関連遺伝子,関節症関連遺伝子,近視関連遺伝子,アルツハイマー型認知症関連遺伝子など,各種遺伝子についてわかりやすく解説しました。

コウノメソッド流 認知症診療スピードマスター
■認知症診療30年の経験から編み出された認知症治療体系「コウノメソッド」シリーズの最新刊!
■シリーズの中で最もコンパクト。忙しい臨床の合間にも読める分量です。
■「処方はmg単位まで公開」という実践重視のコウノメソッドの生命線はそのままに,ボリュームをできるだけおさえました。
■コウノメソッドのエッセンスを手早く知りたいという方におすすめです。

論文からひもとく外科漢方
漢方に縁遠い外科領域の医師のためのエビデンス集です。メーカー協力のもと,外科領域で使用された漢方のエビデンスに新見正則先生の解説コメントを合わせ,読みやすくまとめました。また,書籍を通して散りばめられた「コラム」「一口メモ」を読めば,漢方の使い方や概略がわかるよう工夫されています。
癌,消化器外科,血管外科,小児外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,皮膚科,乳腺外科,救命救急・集中治療など,各領域の事例を紹介。漢方に興味を持っている先生にも,漢方嫌いの先生にも,“最初の一冊”としてお勧めできる書籍です。

症例を時間で切って深く知る!がん緩和医療
流れでわかる緩和ケア!
本書では架空の2症例を作成し、診断時、治療期、治療終了(治癒の場合も、死亡の場合も)と続く「縦断的(経時的)」な流れを時間で区切り、その時々で発生する複数の問題を「横断的」に解説いたしました。「立体的」な展開で人や時間が動く緩和ケアの対処方法をリアルにつかむことができます。さらに、それぞれの項目は臨床でよく遭遇する課題をテーマとしているため、より実臨床に応用したり検討したりしやすい内容となっております。
緩和ケアに携わり始めたばかりの先生から、専門的に取り組まれている先生まで、多くの先生方が参考になる点が必ずある書籍となっております!

検査と技術 Vol.45 No.6
2017年6月号
-

検査と技術 Vol.45 No.5
2017年5月号
-
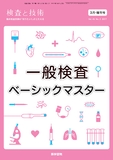
検査と技術 Vol.45 No.3
2017年3月号(増刊号)
一般検査ベーシックマスター
一般検査ベーシックマスター -

検査と技術 Vol.45 No.2
2017年2月号
-

検査と技術 Vol.45 No.1
2017年1月号
-

助産雑誌 Vol.71 No.6
2017年6月号
特集 超音波検査の今と助産師のかかわり方
特集 超音波検査の今と助産師のかかわり方 助産師は,妊婦に直接触れるフィジカルアセスメントにより経過を把握し出産へと導いていく専門職ですが,近年は胎児の状態を観察できる医療検査機器も普及しています。なかでも超音波検査は,医師による診察だけでなく助産師外来等でも用いられることが増えており,欧米と比較して日本の超音波検査の回数は突出して多いとの指摘もあります。
今回の特集では,超音波検査について押さえておきたい知識を整理し,日本における実施状況を俯瞰で見るとともに,医師の視点・助産師の視点を共有し,超音波検査について改めて考えられればと思います。

助産雑誌 Vol.71 No.5
2017年5月号
特集 がんばってます,新人助産師教育
特集 がんばってます,新人助産師教育 今年も,新人助産師が入職する時期がやってきました。新人助産師は現場に入って,何にいちばん困るのでしょうか。また,先輩助産師および管理者は,新人教育においてどのようなことに工夫をしているのでしょうか。本特集では,現場の声を明らかにし,各施設で力を入れている新人助産師教育プログラムを紹介していただきます。実際に新人助産師を迎えて,自施設の新人教育プログラムの改善点が見えてくるこの時期に,よりよい新人教育について考えます。

助産雑誌 Vol.71 No.4
2017年4月号
特集 周産期のメンタルヘルスのために助産師ができること,すべきこと
特集 周産期のメンタルヘルスのために助産師ができること,すべきこと 近年,日本の産後うつの発生率は減少傾向にあるものの依然10%を超えており,周産期のメンタルヘルス対策を充実させることの重要性は言を俟ちません。そうした状況のなか,臨床で日々妊産褥婦とかかわる助産師がメンタルヘルスケアに関して求められるものは,今後さらに大きくなっていくと思われます。本特集では,まず,周産期のメンタルヘルスケアについての動向と助産師の役割,精神医学の基礎知識について解説していただきます。そのうえで,病院,クリニック,自治体の現場で実際に行なわれている活動について具体的に紹介していただき,容易ではないメンタルヘルスの問題に現場の助産師が取り組む際の一助になることを目指します。

助産雑誌 Vol.71 No.3
2017年3月号
特集 産後ケアを成功に導くコツ
特集 産後ケアを成功に導くコツ 小誌では,2013年10月号で初めての産後ケア特集を組みました。それから3年。産後ケア事業はどのように進んでいるのでしょうか。「子育て世代包括支援センター」の全国展開に向けた準備の状況を含めて,現状の整理と課題をまとめます。最終的には全国どこでも質の高い産後ケアが受けられることを目指して,国,自治体,医療機関等が協力し事業を展開していますが,現在の各地での取り組みをご紹介いただき,反省点も含めて産後ケアをうまく軌道に乗せるためのコツを共有できればと思います。

助産雑誌 Vol.71 No.2
2017年2月号
特集 院内助産の新しい形 クリニック・病院併設助産所の取り組み
特集 院内助産の新しい形 クリニック・病院併設助産所の取り組み 厚生労働省が院内助産所・助産師外来推進の方向性を打ち出し,シンポジウムを開催したのが2008年でした。それ以降,大規模病院の開設は比較的進み,助産師による実践が積まれてきました。本特集では,最近見かけるようになったクリニック内の院内助産あるいは併設助産所での取り組みにも注目し,病院併設の院内助産も含めて自施設を紹介していただきます。そして助産師の業務内容ややり甲斐,母子・助産師・施設にとってのメリットについて解説していただき,学生の実習場所としての可能性も探ります。

助産雑誌 Vol.71 No.1
2017年1月号
特集 麻酔分娩に、どう向き合うか
特集 麻酔分娩に、どう向き合うか 近年わが国では,麻酔分娩を行なう施設数,麻酔分娩の実施件数ともに増加の一途をたどっています。先進諸外国と比べれば分娩全体における比率はまだまだ少ないものの,日常臨床で麻酔分娩を希望する妊婦と出会うことや,施設によっては実際に麻酔分娩の介助を行なうこともあると考えると,避けては通れない話題です。本特集では,麻酔分娩の場面における助産実践の実際を学ぶとともに,麻酔分娩に助産師はどう向き合えばいいのか,そのなかで何ができるのかについて,個々の助産師が臨床での体験を通して感じたこと,考えたことを中心に紹介していただきます。

臨床検査 Vol.61 No.6
2017年6月号
今月の特集1 新時代の健康課題と検査/今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
今月の特集1 新時代の健康課題と検査/今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない -

臨床検査 Vol.61 No.5
2017年5月号
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル -

臨床検査 Vol.61 No.4
2017年4月号(増刊号)
臨床検査スターターズガイド
臨床検査スターターズガイド -
