
健診医入門 身体診察の進め方(Web動画付)
健診や人間ドックの重要な役割は、疾患を早期発見し、早期治療に繋げることです。また同時に、健康状態について不安や疑問を抱える患者さんへの健康相談としての役割もあります。
そのため健診や人間ドックに携わる医師には、幅広い知識や的確な診察が求められます。健診や人間ドックには、様々な診療科を経験した医師が携わりますが、中には、これまで内科診察に携わる機会が少ない方もいらっしゃるでしょう。
本書は、診療科に問わず、健診業務に携わる医師のために、健診における診察の手順やポイントをまとめました。一般健診に加え、特殊健康診断(情報機器作業健康診断、有機溶剤健康診断・鉛健康診断、電離放射線健康診断、特定化学物質健康診断、溶接ヒューム・塩基性酸化マンガン健康診断)についても解説しています。また、本書の内容にあわせた著者による解説動画もあり、本書と動画を使って、実際の診察の流れをつかむこともできます。
推薦のことば
私がはじめて人間ドックに関わるようになったのは2013年のことです。本書の著者である後藤敏和先生にお声をかけていただき、人間ドックに携わることになりました。人間ドックは、ご存知のとおり、基本的に自覚症状のない方を診察します。この点は保険診療との大きな違いです。当初は、一般外来と同じような心持ちで内科的診察を行っていましたが、人間ドックを続けていくなか、自覚症状のない方に隠れているかもしれない疾患を的確に捉え、かつ効率的に診察を行うということは大変難しいことで、また幅広い知識を必要とすることを、強く意識するようになりました。
健康診断や人間ドックの医学書は数多くありますが、診察についてまとめられたものはほとんどありません。今回、「健診医入門」として、診察についてまとめられた本著が出版されることを、大変嬉しく思います。内容を拝見しましたところ、診察の手順やポイントが大変わかりやすく、読みやすくまとめられております。
後藤敏和先生は、高血圧・循環器内科の専門医であり、特に心臓・血管系・血圧の診察に関する項目はとてもわかりやすく、循環器系の診察を苦手と感じている先生にも非常に参考になるのではないでしょうか。神経系の診察についても、写真付きでわかりやすく・具体的に説明されており、また動画で確認することもできます。一般診療にも役立つ内容ですので、健診・人間ドックに携わらない先生にも、ぜひ参考にしていただきたい一冊と思います。
本書には特殊健康診断についても、まとめられています。特殊健康診断とは、一般健診(定期的健康診断や雇用時健康診断)に対し、情報機器作業・有機溶剤・鉛・電離放射線・特定化学物質などに関する健康診断です。それぞれ、診察の流れや検査のポイントについて、具体的に、かつ端的にまとめられています。
健診・人間ドックの役割は、疾患を早期発見し、早期治療に繋げることです。また、健康状態で不安に思っていること、疑問に思っていることへのアドバイスのような健康相談としての役目もあると思います。受診者さんの疑問や不安に答えるため、人間ドック健診医は、日頃より的確な診察を心がけ、幅広い知識の習得に努めなければなりません。本書は、より良い健診・人間ドックを行うためのヒントを与えてくれ、また自分の診察法を見直すよい機会となったのではないかと思います。
山形県立中央病院内科
深瀬幸子
序文
私は本来循環器内科医ですが、前の勤務先である山形県立中央病院では11年間人間ドックも担当しました。5年前に定年退職後は健診医として、現在の職場に勤務しております。当機構は山形県内に5つの検診センターを有し年間約18万人の健診をしている県内最大の検診機関です。常勤医のみでは手が足りず、非常勤の先生方の応援を得て業務が成り立っております。応援診療の先生方の中にはあまり聴診器を使わない診療科の先生方もおられます。本書はこれまで内科診察に携わってこられなかった先生方が新たに健診業務に就かれる場合、どのような点に注意して診察すればいいのか解説したものです。
集団検診は、決められた時間内に多くの受診者を診察しなければなりません。第1章では、内科診察法として集団検診の際の必要最低限の診察項目について所見のとり方につき解説しました。そのうえで、病院などにおける人間ドックで、診察に十分な時間を充てることができる場合に追加されうる項目を[人間ドック]として解説しました。
ドックでは神経系の診察が要求される場合もあり、神経系の所見のとり方を第2章で別に解説しました。
著者は学生時代から研修医時代にかけて基本的な内科診察法を、武内重五郎著、内科診断学、第9版、南江堂、昭和49年発行、で学びました。同著は昭和41年の第1版から現在まで改定を重ね発行され続けております。内科の診察法に関してこれほどの名著はありません。心臓の聴診は、テープで音を聞きながら同著の記載を確認しつつ学びました。神経系の診察法は、上記の内科診断学に加え、田崎義明、斎藤佳雄、著、ベッドサイドの神経の診かた、第8版、南山堂、1972年発行、で学びました。本著は主に上記2冊の詳しい内容を基に、健診、人間ドック向けに著者なりに実践的かつ簡便化、ときには追加して実施してきた診察法を紹介したものです。さらに詳しく勉強したい先生方は、上記2冊の最新版で学ばれることをお勧めします。
健診には多くの種類があります。第3章として特殊健診の種類別に内科的な診察法について紹介いたしました。
全体を通し、写真と図を多く載せて診察法が分かりやすいように工夫し、さらに解説動画も作成しました。
先生方には本書を参考にしながら、健診の種類に応じた自分なりの診察方法を確立していただきたいと思います。
近年、在宅医療が普及しています。在宅医療では検査手段が限られ、理学的所見により病態の評価をしなくてはならない場合がほとんどです。本著は在宅診療に携わられる先生方にも少なからずお役に立つと思います。さらに、実践的な理学的所見のとり方の基本を学ぶうえで、研修医や医学生、看護師の皆様にも参考になると思います。
本書が新しく健診医となられた先生方にとり、少しでもお役にたてば嬉しく存じます。
写真撮影、動画作成にご協力いただいた当機構職員の皆様に深く感謝申し上げます。
公益財団法人やまがた健康推進機構理事
山形検診センター所長
人間ドック健診専門医・指導医
後藤敏和

小児外科57巻11号
総排泄腔遺残症
総排泄腔遺残症
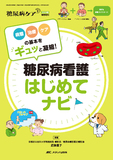
≪糖尿病ケア+(プラス)2024年春季増刊≫
糖尿病看護 はじめてナビ
【糖尿病看護のはじめの一歩をビジュアル解説】糖尿病は、発症してから長い期間つきあっていく疾患である。そのため医療者は、患者を「糖尿病をもつ人」として全人的にとらえ、長期的にかかわっていく必要がある。とくに患者とかかわる機会が多い看護師には、より専門的な看護が求められる。本書では、糖尿病の病態、治療、ケアについて看護師が知っておくべき知識を、要点を絞って解説する。単なる疾患紹介にとどまらず、患者の心理的な負担に寄り添うための考え方なども取り上げる。
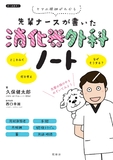
先輩ナースが書いた
消化器外科ノート
著者が、新人のころから使っている勉強ノートをもとに“消化器ナースが知っておきたいこと”をまとめました。
なぜそうするの?というケアの根拠や考え方がよくわかります。
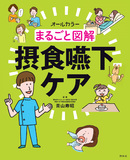
まるごと図解 摂食嚥下ケア
さまざまな診療科における摂食嚥下障害のケアを、イラストや図解でわかりやすく解説。
脳血管障害、認知症、頭頸部がんなど、疾患別のポイントも満載。

手術 Vol.80 No.2
2026年2月号
消化器外科医に求められる緩和医療の基本と緩和手術
消化器外科医に求められる緩和医療の基本と緩和手術
手術がうまくなりたい消化器・一般外科医のための専門誌。マニアックなほど深堀りした特集内容やビジュアルでわかりやすい手術手技の解説を特長とする。本号の特集テーマは緩和医療。消化器外科医として「根治が望めない患者とどう向き合うか」を考える内容である。緩和ケアに関する総説から患者の苦痛を和らげる各種対処法,根治を目的としない緩和手術の適応まで,治せない患者とともに歩むために必要な心構え・知識を詳説した。

≪画像診断の勘ドコロ≫
新 骨軟部画像診断の勘ドコロ
「ますます増加する画像診断の需要を,限られた時間でこなしていくためには,必要なことが簡潔に記載された教科書が必須である」というコンセプトから生まれた「これだけおさえれば大丈夫」シリーズ(通称「勘ドコロ」シリーズ)。
初版を2006年に刊行し,日々の診断で必要な押さえるべき事項,なおかつ技術的なことがわかりやすく簡潔に解説されている点で稀有であり,多岐にわたり多くの先生方に好評を博した人気シリーズが,時代に即した技術的最新知見をふまえ,臨床では心臓,頭頸部,脊髄などを新たに加え,より実用的に充実した内容で新たに刊行。

≪Urologic Surgery Next 9≫
外傷の手術と救急処置
近年めざましい進歩を遂げた泌尿器科手術の最前線を,第一線で活躍するエキスパートがオールカラーの豊富な写真・イラストとともにわかりやすく解説した『Urologic Surgery Next』シリーズ。
シリーズを締めくくる第9巻は,泌尿器科臨床医として憶えておきたい外傷の手術と救急処置の手技をわかりやすく解説した専門医必携の一冊。

FUJITA'S TEXT 1 腹腔鏡下幽門側胃切除
outermost layerに基づくこだわりの手術
腹腔鏡による胃癌手術のパイオニアとして積み上げてきた藤田式の技術。本書では安全で精緻な手術を行うための考え方・手技を公開。
Outermost layer(神経外側の層)に基づいた郭清の展開、高い再現性を実現するリニアステイプラーによる体腔内吻合など、術中の各場面におけるこだわりの手技を解説する。
場面ごとに作り込まれた正確なイラストが、初学者に把握しづらい構造の理解を助ける。

レジデントノート Vol.25 No.16
2024年2月号
【特集】入院時から始める退院調整
【特集】入院時から始める退院調整 退院調整・退院支援を自分で行うイメージ,できていますか? セッティングごとの考え方,状況別の医学的判断・介入の要点,多職種との協働,書類の書き方や施設の概要など,どの科に進んでも必要な内容をお届け!

呼吸器病レジデントマニュアル 第6版
研修医・専攻医に必要な呼吸器疾患の基本的知識を網羅する好評書。今回は内容を全面的に見直し、診断指針・知見をアップデート、全項目に全体像をつかむ「ポイント」欄も新設、さらにページ数を3/4にスリム化し、情報の濃さはそのまま格段に読みやすくなりました。今版から文献情報をWeb掲載し、論文データベースへのアクセスも容易です。COVID-19も新設。研修医、呼吸器専門医をめざす若手内科医におススメです。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.93 No.3
2021年3月発行
特集 カラーアトラス 基本から学ぶ病理組織の見方
特集 カラーアトラス 基本から学ぶ病理組織の見方 -

整形外科 SURGICAL TECHNIQUE(サージカルテクニック)2025年4号
2025年4号
特集:高齢者大腿骨遠位端骨折の治療
特集:高齢者大腿骨遠位端骨折の治療 整形外科領域の「手術」を徹底して取り上げる専門誌『整形外科サージカルテクニック』
教科書には載っていない手術のコツ、ピットフォール、リカバリー法が満載。各手術のエキスパートの技と知恵を凝縮した「手術が見える・わかる専門誌」です。
本誌で取り上げた手術動画を専用WEBページでチェックでき、誌面と動画でしっかり確認できます。

ポーリット & ベック 看護研究 第3版
「新訳」で生まれ変わる看護研究の羅針盤
初学者にとって、看護研究の全容を掴まんとすることは、果てしない大海原に漕ぎ出すに等しい困難がある。航海を可能とする羅針盤のように、本書は看護研究に臨む皆さんの道標となるだろう。明瞭な「新訳」により、さらに可読性が増した本書は、これまで以上に多くの読者の支えとなることは間違いない。

世界一わかりやすい
「医療政策」の教科書
高齢化社会を迎えた現在、セオリー(学問的な理論)とエビデンスの両方を兼ね備えた“綿密にデザインされた医療政策”がわが国には必要不可欠となっている。本書はハーバード大学の博士課程で学んだ著者が、医療政策・医療経済学に関するセオリーとエビデンスのうち、普遍性があり、日本の医療にも適用できるものを中心に紹介するもの。通読が容易な読みやすい記述で、医療政策学および医療経済学が一通りよく分かる。

精神療法の実践
治療がうまくいかない要因と対処法
患者さんが突然来なくなる、話が逸れていってしまう、症状がよくならない…、精神科外来で起こりうるさまざまなつまづきとそれらへの対応についてまとめた1冊。発達障害やパーソナリティ障害などへのアプローチ、行動医学への応用など、近年のトピックテーマについても議論。前作『精神療法の基本―支持から認知行動療法まで』に続き、今日の外来から実践できる精神療法のコツを徹底紹介!

あつまれ!! 飯塚漢方カンファレンス
漢方処方のプロセスがわかる
漢方薬の処方を覚えると普段の診療の幅を大きく広げることができますが,一から覚えるのはハードルが高いと思っていませんか?
本書では基本の陰陽虚実,六病位,気血水といった概念から脈診・舌診・腹診の診察法までしっかり学ぶことができます.リョウ先生,ヒロミ先生,T部長とのカンファレンスを通して,漢方医の思考を身に付けていきましょう.問診の意図がわかればどんな漢方薬を用いればいいのかわかってくるはずです.
これから漢方を勉強したい,感染症や慢性疾患の治療の選択肢を増やしたい方にぜひおすすめです.

≪スタンダード骨折手術治療≫
スタンダード骨折手術治療 下肢
インプラント(プレート,スクリュー,髄内釘など),アプローチ法(前方,後方など),骨折の状態(関節内骨折,関節外骨折,単純骨折,粉砕骨折)など,現在日本で起こりうるすべての骨折に対応できる内容を網羅した手術治療の決定版。
さらに骨折手術後の偽関節に対する手術や近年増加傾向にあるインプラント周辺骨折,創外固定治療の項目も収載し,また日本では少ないものの良好な成績が最近報告された大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術におけるセメント充填法の項目も追加。

ポケットチューター体表からわかる人体解剖学 原書第2版
体内の臓器を図示した多彩な体表写真により,体表から神経・血管,骨格などの位置を把握できるカラーアトラスのベストセラー,待望の改訂版! 最新の知見に全編をブラッシュアップしたほか,新たに加齢に伴う位置関係の変化を示した「新生児」の章を追加.体表解剖の参考となるX線像,CT,血管造影,超音波画像も多く掲載し,視診・触診や穿刺などの実臨床に役立つ実践性を備えている.すべてのメディカルスタッフのポケットに忍ばせておきたい一冊

臨床画像 Vol.41 No.5
2025年5月号
【特集】特集1:読影のお作法−連続画像スライスで追う泌尿器・産婦人科疾患の診断−/特集2:長期経過観察を要する病変の診断とマネジメント
【特集】特集1:読影のお作法−連続画像スライスで追う泌尿器・産婦人科疾患の診断−/特集2:長期経過観察を要する病変の診断とマネジメント
