
腎臓内科医のための腎移植の診かた
腎移植を受ける患者数は年々増加し,移植前の評価や移植後の長期フォローなど,その内科的管理の重要性が高まっている.よもや腎移植は泌尿器科医だけのものではなく,腎臓内科医が積極的に関わることが必要だ.本書ではそんな現状を踏まえ,腎臓内科医の視点から腎移植患者を診るために必要な知識とポイントをまとめた初めての書である.平易かつ分かりやすい解説で,医師のみならず腎移植に携わる医療スタッフ全てにお薦めしたい.

『臨床放射線』年間購読(2026年)
「画像診断」と「放射線治療」の両面から臨床に役立つ情報が充実。多数の診療例・症例を毎号掲載。特集・連載も勉強になると大好評。放射線に関わる幅広い層に愛され続ける老舗雑誌!
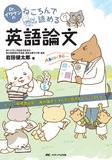
Dr.イワケンのねころんで読める英語論文
ナース・研修医必見! 海外論文がすらすら読めるようになるヒケツ
【英語論文へのニガテ意識が100分で解消!】
大好評「ねころんでシリーズ」に、あのDr.イワケンが参上! 英語論文を教科書通りに精読するのではなく、「論旨をパッとつかむ」コツをわかりやすく解説。多くの原著論文を読みこなしてきた著者だから語れる生きたノウハウが満載で、看護・医学研究や臨床で「違いを出せる」一冊

CONSENSUS 2010に基づく新生児低体温療法 実践マニュアル

看護師国家試験 解剖生理学クリアブック 第2版
看護師国家試験形式で解剖生理学の知識が身につく1冊
看護師国家試験と同じ形式の問題を解いていくことで、解剖生理学の知識が身につく1冊。解剖生理学全般を網羅し、また必ず理解しておきたい内容を必修問題として収載した。各問題には詳しい解説がついており、各問題ごとに示したキーワードとあわせることで、知識の再確認が容易にできる。『系統看護学講座 解剖生理学』と内容をそろえており、併用することでより効率的な学習が可能になる。

画像診断 Vol.44 No.6(2024年5月号)
【特集】知っておくべき核医学診断・治療のミニマルエッセンス
【特集】知っておくべき核医学診断・治療のミニマルエッセンス PET/CTの基礎知識や、合同カンファレンスで役立つ一般核医学の必須知識を解説。核医学診断・治療について、これだけは知っておくと良い【ミニマルエッセンス】をまとめ、初学者や核医学を専門としない画像診断医にとっても役立つ内容が詰まった一冊!

≪新篇眼科プラクティス 5≫
眼科救急治療
まったなし!急がば学べ
「新篇眼科プラクティス」シリーズの第5弾.本書では,「眼科手術レスキュー」「他科疾患にみる視機能障害」という従来とは異なる新たな切り口を追加.冷や汗必至の手術中の急変や,近年重要視される他科医師との連携も想定し対処法を解説した.時間的緊急性に加えて,様々な病態への対処が求められる救急疾患に対して,多数の写真やイラストを具体的な治療法と共に示した本書は,"待ったなし"の臨床現場で活躍する一冊である.

ドレーン管理はじめて BOOK
【基本・処置が写真とイラストで身につく!】ドレーン管理にかかわる解剖生理や適応、留置部位、排液の色・性状といった基礎知識にはじまり、ドレーンの固定・留置の基本手技など、知っておくべきドレーンの基本を1冊に凝縮。各科の主要な外科手術での観察や対応、患者指導の注意点も充実している。
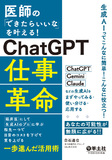
医師の「できたらいいな」を叶える!ChatGPT仕事革命
臨床医にして生成AIのプロに学ぶ指先一つで日常のコストを下げて質を上げる一歩進んだ活用術
「ChatGPTって聞いたことあるけど,医療現場でも使えるのかな?」そう思った医師のあなたのための生成AI活用バイブル.これからChatGPTを使いたい初心者から実際に医療現場で活用したい方まで,使い方の基本から応用テクニック,注意点や臨床ならではの問題解決までを網羅.臨床医にして医療用生成AIツール開発者の著者とともに,この一冊で未来の医療を先取りしよう!

臨床外科 Vol.80 No.6
2025年 06月号
特集 骨盤内臓全摘術のすべて〔特別付録Web動画付き〕
特集 骨盤内臓全摘術のすべて〔特別付録Web動画付き〕 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 (ISSN 0386-9857)
月刊、増刊号を含む年13冊

臨牀消化器内科 Vol.40 No.5
2025年5月号
膵・消化管 神経内分泌腫瘍の診療アップデート
膵・消化管 神経内分泌腫瘍の診療アップデート
神経内分泌腫瘍では的確な診断のもと治療戦略を決定しなければならない.本特集では,診断において最も重要な組織診断をはじめ,画像診断およびその病態についても詳細に解説し,内視鏡的治療,外科的治療および放射線治療を含む薬物療法の最新の情報を発信している.

股関節学 第2版
根拠にもとづく記述を基本に,基礎から臨床まで股関節に関連する専門的な知識を網羅し,詳しく解説.初版(2014年)出版後の新しい情報・エビデンスを盛り込み,さらに充実を図った.改訂のポイントはA4変形判からB5判にサイズを変更,誌面デザイン・書籍仕様を一新した.また各種ガイドラインの更新に合わせて内容をアップデートし,新たに,ロボット手術・リハビリテーション治療・データベース研究の項目を設けた.

急性腹症の診断レシピ
病歴・身体所見・CT
CTを撮ってもわからない時に手にして下さい。
急性腹症を「上腹部痛」「下腹部痛」「腹部全般痛」の3つのカテゴリーに分けて考え、それぞれで早期診断すべき重要疾患を、年齢、性別と基礎疾患からのアプローチ方法について解説。「CTの活用法」「診断がつかない場合の考え方」の章も設け、筆者のライフワークである急性腹症に正面から取り組んだ意欲作。This is the way of decision making in an acute abdomen!

改訂2版 消化器内視鏡技師・ナースのための内視鏡室の器械・器具・薬
【内視鏡室の物品情報を一挙にアップデート!】技師や看護師だけでなく、消化器内科医になったばかりの医師からも大人気の実用本、『内視鏡室の器械・器具・薬』が、約10年ぶりにリニューアル!たくさんの写真や図で情報が多いのにわかりやすい誌面はそのままに、最新情報をお届け!器械や薬はもちろん、手技の実際も一目でわかる。

運動器の計測線・計測値ハンドブック
臨床の場で必要となる体表・X線・CT・MRIによる運動器の計測線・計測値を,明快なイラストと解説で示したデータブック.主要な計測線・計測値を網羅し,定義や基準値のほか,今日的な解釈や診断との結びつけなどの臨床的意義を解説.撮像のコツや最新のエビデンスを示す文献のサマリーも提示し,多忙な現場で役立つ一歩進んだ知識を習得できる.

Dr.森の腹部超音波診断パーフェクト 改訂第2版
premium movie version
Dr. 森40年の集大成!
初版より新たに動画870点が追加され,QRコードからいつでもどこからでも再生可能.症例写真は1,100点,229疾患へ,さらに全624頁へと最新アップデートかつ大幅パワーアップ! 腹部超音波診断にかかわる方必読の,質・量ともに圧倒的な1冊です.
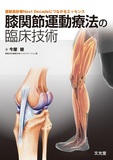
運動器診療Next Decadeにつながるエッセンス
膝関節運動療法の臨床技術
膝関節を専門とする理学療法士の著者により,運動療法の基礎から細かな治療のコツとピットフォールまでを紹介した臨床に即した一冊.前半の機能解剖と臨床的膝タイプの見極めの章では,日々の臨床の確固たる土台になる大切な知識が含まれている.後半のスペシャルテストと運動療法の章は,著者が積み重ねてきた技術・技法のエッセンスであり,臨床結果として大きな治療効果・患者満足度を導くことができる情報が凝縮されている.

プチナース Vol.35 No.2
2026年2月号
4号連続!第115回看護師国試対策号第4弾!
■必修問題でたとこまとめ
■頻出&得点源!見るだけ看護技術
4号連続!第115回看護師国試対策号第4弾!
■必修問題でたとこまとめ
■頻出&得点源!見るだけ看護技術

周術期管理ナビゲーション
周術期の患者管理に必要な知識・技術、モニターの見方、薬の解説などを1冊に凝縮。術前の患者状態把握から、緊急時の対応、術後合併症の予防と対応までが流れに沿って解説されている。術前・術中・術後管理に携わる看護師、医師、薬剤師、臨床工学技士の必携書。

ビギナーのための胸部画像診断 Q&Aアプローチ
研修医が胸部画像診断で一番教えて欲しいことを中心に、質問を設定。
その質問に答えるような形式で解説した好評の画像診断誌の特集号に新規項目を追加し、より充実させて単行本化。
日常臨床での素朴な疑問に答えられる一冊です。
