
まるごと図解 ケアにつながる脳の見かた
●豊富なイラスト図解により、複雑な脳をシンプルに、楽しく理解できる。
●解剖・機能をベースに、主要な疾患とケア、脳脊髄障害から起こる症状とケアをつなげて学ぶことで、深い知識が得られる。検査画像の解説も充実。

かんテキ 整形外科
【1分でぜったい必要なことだけ覚えられる!】「かんテキ」は、疾患・患者・看護・観察が感覚的にわかる、感動の一冊!ナースをはじめとするコメディカル向けに、領域別疾患患者対応のポイントを徹底的に見える化。リアルな臨床現場で本当に必要な知識が、この一冊でパッとつかめる。各疾患解説の前に「1分間で覚える!コレだけは覚えるコレだけシート」が入る。全身の幅広い知識が求められる整形外科において、新人でもすぐ覚えられる最低限の内容を1頁にまとめている。新人ナースから研修医レベルまで現場で必要な知識だけに絞って網羅。豊富なイラストと端的な解説で、患者対応がイメージできる。
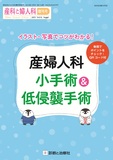
産科と婦人科 Vol.92 増刊号
2025年増刊号
【特集】イラスト・写真でコツがわかる!産婦人科小手術&低侵襲手術
【特集】イラスト・写真でコツがわかる!産婦人科小手術&低侵襲手術
糸結びやパワーソースなど基本的な知識をはじめ,子宮筋腫・子宮腺筋症・卵巣囊腫や骨盤臓器脱に対するvNOTESといった,比較的新しい低侵襲手術の手技のコツを,豊富なイラストや写真でわかりやすく解説しています.エキスパートによる動画も盛りだくさん!すぐに役立つ知識が満載です.ぜひお手に取ってご覧ください!

経鼻内視鏡検査のためのアトラス
鼻,咽・喉頭,食道の病変で困ったら
経鼻内視鏡検査で遭遇する,鼻腔?咽頭?喉頭?食道における病変の所見判読のポイントをわかりやすく解説.経鼻内視鏡発祥の地である島根大学消化器内科・耳鼻咽喉科により,貴重な症例を厳選しアトラスとして提供.正常例や解剖など,経鼻内視鏡検査に欠かせない知識も網羅.これから経鼻内視鏡を始める医師に必携の書とした.

東洋療法学校協会編教科書 医療概論【2025年1月10日 第1版第38刷】
本商品は2025年1月10日発行の「第38刷」となります.ご購入の際は刷りに間違いがないか再度ご確認いただきますようお願い申し上げます.
東西両医学・医療史および現代の医療制度,医療倫理についてわかりやすく解説したテキスト.

動作練習 臨床活用講座
動作メカニズムの再獲得と統合
ロングセラー『動作分析 臨床活用講座』の続編が登場! 『動作分析』での評価を踏まえて,基本動作である「寝返り」「起き上がり」「起立・着座」「歩行」をどのように治療するかを解説。基本動作を遂行するために必要なメカニズムを解説した後に,動作メカニズムの再獲得に向けた練習法を豊富なイラストと写真を用いて具体的に紹介する。

精神科レジデントマニュアル 第2版
レジデントにも、専門医を目指す方にも。精神科臨床のエッセンスがつまった一冊。精神科レジデントや若手精神科医が日常的に遭遇する精神症状・疾患や診療場面で直面する諸問題への対応などについて、コンパクトにまとめ、気になる事柄をすぐにその場で参照できるマニュアルの改訂第2版。
*「レジデントマニュアル」は株式会社医学書院の登録商標です。

理学療法ジャーナル Vol.59 No.6
2025年 06月号
特集 脳卒中片麻痺 理学療法の歩みと最新の取り組み
特集 脳卒中片麻痺 理学療法の歩みと最新の取り組み 理学療法の歴史とともに歩む本誌は、『PTジャーナル』として幅広い世代に親しまれている。特集では日々の臨床に生きるテーマを取り上げ、わかりやすく解説する。「Close-up」欄では実践的内容から最新トピックスまでをコンパクトにお届けし、その他各種連載も充実。ブラッシュアップにもステップアップにも役立つ総合誌。 (ISSN 0915-0552)
月刊、年12冊

研修医当直御法度 百例帖 第3版
「青本」、9年ぶりの改訂!
26症例を刷新! 最新情報へUpdate! より見やすい紙面に!
今回の改訂では見やすさを重視して1事例をおおむね見開き2ページにおさめ、さらに図や画像を大幅に増量。
また症例提示では研修医との勉強会「ER 振り返りカンファランス」で提示された、一歩誤ると医事紛争に陥りやすい事例へと一部を刷新、読み応えがあるものとなっています。
新たな追加項目としては、ニーズが高まりつつある「悪性腫瘍の救急」、「ポリファーマシー・薬剤の副作用」を掲載、高齢化社会における救急での対応にも触れています。
文献は最新かつアクセスしやすいものを厳選、使い勝手にも配慮しました。
同時刊行の姉妹本『研修医当直御法度 第7版』(通称「赤本」)ともリンクさせ、双方の関連頁を記載するなど、研修医の力強い味方としてパワーアップ!

~その麻酔管理方法にエビデンスはあるのか?~
心臓血管麻酔 Positive and Negative リスト25
日々の麻酔管理を「エビデンスに基づく」と自信を持って言えますか?
実臨床で幅広く行われている心臓血管麻酔管理の中で,意見が分かれている項目についてエビデンスがある程度確立しており実際の臨床現場で有用であると考えられる Positive list,エビデンスがない,あるいは不十分である Negative list と解説ですぐに臨床に活用できる読みやすい内容.現場で迷ったときに読んでいてよかったと思う1冊.

MGH麻酔の手引 第7版
麻酔の殿堂“MGH”発
信頼される定番、最新版
世界初のエーテル麻酔による外科手術が施行された、マサチューセッツ総合病院(MGH)に蓄積された臨床経験と知見を基に編まれた実践書。7年ぶりの改訂で全編アップデート。周術期管理、疼痛管理を含め麻酔科領域全般を幅広くカバーした定本として、日本をはじめ世界中で支持、信頼される麻酔の手引。レイアウト等の工夫により、頁数増加を抑えつつ、さらに見やすく調べやすくなった。研修医からベテランまで幅広い読者のニーズにこたえる。

運動器診療 最新ガイドライン 第2版
運動器医療に関わる、医師から柔道整復師、スポーツトレーナーまで、多くの方から定評をいただいていた書籍の待望の第2版。
●初版の発行から13年ぶりの全面改訂!
●国内・海外のガイドラインの有無がすぐわかる
●ベテラン整形外科医が実践する最新の診療体系がすぐわかる
●「がんロコモ」 「慢性腎臓病(CKD)患者への薬物使用」 「関節リウマチ」関連などが新たに充実!
●運動器疾患に関する領域を網羅した他に類を見ない1冊

運動失調のみかた,考えかた
小脳と脊髄小脳変性症
最新の知見から,臨床の現場で役立つ実践的な情報までを各領域の第一人者がまとめた決定版.
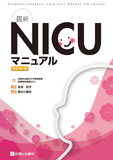
最新 NICUマニュアル 改訂第7版
1998年初版発刊より,京都府立医科大学附属病院周産期診療部NICUにて培われてきたノウハウのすべてが盛り込まれた,待望の改訂第7版発刊!「小児科医がNICUで診療するための実践的な1冊」を基本コンセプトに,実践的な内容から新生児を専門とする医療従事者にも役立つより深い内容まで含み,情報も最新にアップデート.新生児医療にかかわるすべてのスタッフに必携の1冊.

チャイルドヘルス Vol.29 No.2
2026年2月号
【特集】家で子どもを“みる”~ホームケアのすゝめ, 病気編~
【特集】家で子どもを“みる”~ホームケアのすゝめ, 病気編~
熱が出た!咳が止まらない!などなど,子どもの病気にまつわる症状や兆候に対するホームケアを徹底解説!
医療的ケアを必要とする子どものホームケアもご紹介しています。
明日からの外来にお役立てください。6月号では“けが編”を予定しています。お楽しみに!
また,来月号にわたって公開座談会の詳細をご報告します!
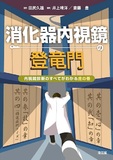
消化器内視鏡の登竜門
内視鏡診断のすべてがわかる虎の巻
消化器内視鏡の診断スキルを磨き上げたいフレッシュドクターへ贈るchallengingな一冊。上部~下部の全消化管を収載し、的確な内視鏡診断のノウハウから、その後の治療の進め方、病理診断までがこの一冊でわかる。エキスパートである先輩ドクターからの金言が散りばめられ、これ一冊を読み通せば内視鏡医としてワンランクアップできること間違いなし!選りすぐりの症例クイズがあなたを待ち構えています。さあ登竜門へ、いざ挑まれたし!
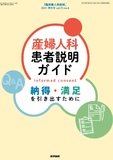
臨床婦人科産科 Vol.75 No.4
2021年4月発行(増刊号)
産婦人科患者説明ガイド——納得・満足を引き出すために
産婦人科患者説明ガイド——納得・満足を引き出すために -

医道の日本 Vol.75 No.9
2016年9月号
脈診再入門
脈診再入門 脈から患者の内部環境を探る「脈診」は、古典的な治療を行うには欠かせない診察技術であり、施術前後の変化から治療効果を確認するのにも役立つ。
今回の巻頭座談会では、3人の臨床家に各流派の脈診の特徴や共通点、臨床への活かし方などを論じてもらった。
さらに、初学者のための脈診法の解説や研究会レポートを掲載。
これらの企画に連動して疾患別特集でも、各派の脈診に対する考え方と臨床で行っている手法を紹介する。
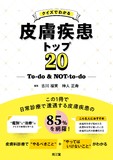
クイズでわかる皮膚疾患トップ20
To-do & NOT-to-do
皮膚科診療患者が罹患している疾患は,遭遇頻度上位20疾患で85%を占める.本書は,これら日常的に診る皮膚疾患に絞り,各疾患を「鑑別」,「治療方法」の2本立てのクイズ形式で楽しく・わかりやすく解説.実践ですぐに活かせる,皮膚科診療で“やるべきこと(To-do)”と“やってはいけないこと(NOT-to-do)”のリスト付きで非皮膚科医・非専門医にもオススメ.皮膚疾患を診る機会があるすべての医師の道標となる一冊.

≪ガイドライン≫
HTLV-1関連脊髄症(HAM)診療ガイドライン2025
HTLV-1陽性関節リウマチ&HTLV-1陽性臓器移植 診療の対応を含めて
日本神経学会によるHTLV-1関連脊髄症(HAM)のオフィシャルなガイドラインの改訂版.HAMとその関連疾患の疾患概念,疫学といった基礎的な内容から,検査・診断,治療について解説し,今後のHAM診療の指針を示す.今改訂では①ステロイドパルス療法に関する推奨文の追加,②診断・治療アルゴリズムの改訂,③「共有意思決定」をテーマとした章の新設などを行った.
