
臨床外科 Vol.79 No.4
2024年 04月号
特集 エキスパートに聞く! 膵頭十二指腸切除のすべて〔特別付録Web動画付き〕
特集 エキスパートに聞く! 膵頭十二指腸切除のすべて〔特別付録Web動画付き〕 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 (ISSN 0386-9857)
月刊、増刊号を含む年13冊

便失禁診療ガイドライン2024年版 改訂第2版
初版以降の新たなエビデンスと日本の医療状況に立脚した実践的なガイドライン改訂版.便失禁の定義や病態,診断・評価法,初期治療から専門的治療にいたるまで基本的知識をアップデートし,新たに失禁関連皮膚炎や出産後患者に関する記載を拡充.また治療法選択や専門施設との連携のタイミングなど,判断に迷うテーマについてはCQとして推奨を示した.患者像により多様な病態を示す便失禁の診療とケアに携わる,すべての医療職にとって指針となる一冊である.

本当に使える症候学の話をしよう とことんわかる病態のクリニカルロジック
●解剖・生理からひも解く病歴・身体所見の深い診かた
●患者の訴えを鵜呑みにしない「聞く」テクニック
●総合診療の目線で日々全身を診ている医師が教える新しい症候学
症状を手がかりに疾患や病態を探る症候学。しかし、実際の臨床ではシンプルに「この症状ならこの病気」とはいかないものです。そこで本書は、解剖学、生理学、組織学、免疫学などを駆使して症状をとらえ、判断に困ったときの考え方や現場で使える診かたをわかりやすくレクチャーします。
病態生理を掘り下げることで、これまでより深い病歴・身体所見の診かた、患者さんにポイントを突いた聞き方ができるようになります。
総合診療の目線で「全身を診ること」にこだわってきた医師が教える、これまでになかった病態推論。医師、薬剤師、看護師問わず、わかりやすく現場に役立つ1冊です!

心エコー 2025年10月号
非心臓手術における術前評価にどう応える?
非心臓手術における術前評価にどう応える? 特集は「非心臓手術における術前評価にどう応える?」.非心臓手術の術前評価に心エコーは必要か?/虚血性心疾患患者の術前評価/大動脈弁疾患患者の術前評価/僧帽弁疾患患者の術前評価/一次性心筋症患者の術前評価/二次性心筋症患者の術前評価/ハイリスクの高齢者の術前評価 等を取り上げる.連載として,症例問題[Web動画連動企画]心房性の三尖弁逆流?,留学のススメ,Echo Trend 2025,伊藤 浩の3分で読める!イイ話等を掲載.
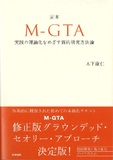
定本 M-GTA
実践の理論化をめざす質的研究方法論
質的研究方法論の1つとして広く知られるM-GTA(修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ)の決定版。M-GTAの基本的な考え方と研究方法のプロセスを具体的かつ詳細に解説し、理論面と実践面から強力にサポート。看護系大学院生や看護研究者などを中心にM-GTAのさらなる浸透を図るとともに、質的研究の未来を見据えながら、理論と実践と研究の循環の実現に向けた研究成果の産出をめざす。

ねころんで読める不眠症
【「眠れない」を解決に導く最新エビデンス】不眠症が改善すれば、合併症・併存疾患の治療もスムーズに! プライマリケア医はもちろん、看護師や心理職、リハ職も介入でき、効果を上げられる! 一般人口の約10%、プライマリケア患者の約半数が抱える不眠症に対して、国際的に第一選択となっている不眠の認知行動療法(CBT-I)を中心に解説。最新の薬物療法もエビデンスに基づき詳述。

消化器内視鏡技師試験問題解説Ⅵ
消化器内視鏡技師の必携書!!
消化器内視鏡技師試験問題解説Ⅵ
第37回(2018年)~第42回(2023年)の試験問題と解答・解説を収録
付録:第43回(2024年)の問題と解答

臨床整形超音波学
運動器超音波が切り開く新しい整形外科学の教科書
運動器超音波の登場により、整形外科が大きく変わりつつある。本書は、「臨床整形外科」誌増大特集号を全面書き直し、はじめての運動器超音波から、臨床現場での活用、新しい技術に加え、末梢神経をターゲットとする痛みへのアプローチを徹底解説。さらに、運動器超音波と解剖学を共通言語に整形外科医と理学療法士がタッグを組み、整形外科診療をアップグレードする。本書から新しい整形外科の地図がみえてくる。

プシコ
◆プシコを知る
精神疾患の国際的診断基準DSM-5-TRに論文を引用される著者が,精神疾患と器質疾患の相違点を丁寧に解説し,その核心に迫る! 本書が意味する「プシコ」は精神疾患だけではない!?
◆己を知る
豊富な脳科学研究を基に,「己」と精神疾患の連続性を見出した革新的な考察! 感覚と知覚の違い,意識と無意識の境界,情動・記憶・学習と痛みの関係,プラセボ効果・ノセボ効果のメカニズム,さらには恋愛の意義や産後の夫婦関係まで,精神疾患を理解するための「己」に関する深い内容が満載!
◆診療能力の向上
精神疾患と器質疾患が混在する30の例題でon the job training! 症例を通じて得られる具体的な思考法が実践的スキルを向上させ,「精神疾患を学ぶと器質疾患の診断能力が高まる」理由がわかる!
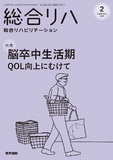
総合リハビリテーション Vol.53 No.2
2025年 02月号
特集 脳卒中生活期 QOL向上にむけて
特集 脳卒中生活期 QOL向上にむけて リハビリテーション領域をリードする総合誌。リハビリテーションに携わるあらゆる職種に向け特集形式で注目の話題を解説。充実した連載ではリハビリテーションをめぐる最新知識や技術を簡潔に紹介。投稿論文の審査、掲載にも力を入れている。雑誌電子版(MedicalFinder)は創刊号から閲覧できる。 (ISSN 0386-9822)
月刊、年12冊

レジデントノート Vol.24 No.15
2023年1月号
【特集】救急・ERを乗り切る! 整形外科診療
【特集】救急・ERを乗り切る! 整形外科診療 救急で“これだけ”は押さえたい整形外科診療のポイントをシンプル&明確に解説.よくある主訴や受傷機転での的を絞った診察の進め方や画像検査の選び方・読影のコツ,シーネ固定などの手技がやさしく身につきます.

呼吸ECMOのすべてQ&A
呼吸不全治療の最後の砦である「呼吸ECMO」.これをめぐって集中治療の現場で生じる数々の疑問にエキスパートが明快に回答します.その仕組みから,導入・管理の方法,各医療職の役割,装着下での転院搬送のノウハウに至るまで,超実践的な内容をピックアップしました.本邦における呼吸ECMO普及の中核となる「日本ECMOnet」のメンバーらがおくる,集中治療・救急医療・呼吸器診療に関わるすべての医療者必読の一冊!

リンパ浮腫診療ガイドライン 2024年版
癌治療に伴い生じる続発性リンパ浮腫の診療ガイドライン、6年ぶりの改訂版。
四肢の原発性リンパ浮腫に関するCQも含め計23のCQについて、科学的根拠をもとに診療指針を分かりやすく解説。推奨グレード表記がそぐわないCQでは、エビデンスグレード表記を使用した。
より質の高いリンパ浮腫診療・ケアを患者に提供するために、リンパ浮腫診療に携わる医療者必携の一冊。

国立成育医療研究センター
新産科実践ガイド
国立成育医療研究センターの産科実臨床66項目が簡潔にわかりやすくまとまった書籍.
「産科実践ガイド改訂2版」を全面改訂し,章の構成,項目立てのすべてを刷新.成育での症例カンファレンス,論文抄読会,蓄積されたデータをもとに,著者および複数の編集者により推敲が重ねられています.医師だけでなく助産師など産科診療に携わるすべての医療関係者に参考になる内容です.

整形×内科=大腿骨近位部骨折-ジェネラリストにならざるをえない整形外科医のための内科読本-
ジェネラリストにならざるをえない整形外科医のために
大腿骨近位部骨折は,日常診療でよく見かけるありふれた疾患でありながら,整形外科と老年内科のあいだに位置する“汽水域”のような存在です.本書では,整形外科と総合診療の両方を経験した著者が,その中間領域を両側の視点から丁寧に解説します.整形外科専門医,総合診療科専門医,整形外科専攻医,総合診療科専攻医,臨床研修医,そして学び直しを志す他科の先生方まで,それぞれの立場から頁をめくることで,大腿骨近位部骨折の診療における新たな気づきが得られるはずです.

我々の足の外科
手術手技アトラス
匠の技を継承する──奈良医大式・足の外科の真髄
奈良医大・足の外科診療班が長年にわたり築いてきた手術手技のエッセンスを余すことなく公開。前方アプローチによる前方移動骨移植術を用いた足関節固定術をはじめ、試行錯誤を重ねて磨き上げた術式について、豊富な写真とイラストで紹介。各々、手術適応や術式選択、手技のコツとピットフォールも漏れなく解説。「詳しい手術記録」のように参照しやすく、明日からの手術に活用できる、教科書を超えた、現場で本当に使える手技書。

総合診療 Vol.35 No.10
2025年 10月号
特集 攻めの安全処方術 引き算処方+多面的アプローチ
特集 攻めの安全処方術 引き算処方+多面的アプローチ ①独自の切り口が好評の「特集」と、②第一線の執筆者による幅広いテーマの「連載」、そして③お得な年間定期購読が魅力! 実症例に基づく症候からのアプローチを中心に、診断から治療まで、ジェネラルな日常診療に真に役立つ知識とスキルを選りすぐる。 (ISSN 2188-8051)
月刊、年12冊

感染症疫学ハンドブック
感染症アウトブレイク発生時のデータの集め方、解釈の仕方、伝え方を学んで、効果的な対策につなげるための実践書。国立感染症研究所実地疫学専門家養成コース(FETP-J)出身者が中心となって執筆。医療機関、自治体、保健所のスタッフが知識と経験を共有して活動していく上で必須の1冊。

≪腫瘍病理鑑別診断アトラス≫
腎癌 第2版
2021年に腎癌取扱い規約第5版,2022年にWHO分類第5版が刊行され,組織型分類は複雑さを増し,日々の病理診断に難渋することも多くなった.また分子標的治療薬などが承認され,治療選択における形態的評価の役割も増している.そうした状況を踏まえ,今改訂では,最新知見を盛り込み,精選した病理写真とともに,定義や病理診断の要点,鑑別ポイントを解説した.臨床と病理の連携を目的に,画像診断や最新の治療についても解説する.

歯科国試パーフェクトマスター 歯科放射線学 第2版
歯科医師国家試験合格にグッと近づくパーフェクトマスターシリーズ
出題基準改定(令和5年)に対応した改訂版,登場
歯科医師国家試験対策のために愛用されてきた『歯科国試パーフェクトマスター』シリーズが,国試の出題基準改定(令和5年)に対応して新しくなりました.最新の出題基準に対応した本書を活用して大切なポイントをしっかり抑え,歯科医師への道に進みましょう!
・直近の試験問題を精査して対策が記載されているので,各科目の大まかな出題傾向がつかめます!
・図や写真を多く用いているので,わかりやすく,覚えやすい!
・国試対策のほか,CBT対策や定期試験,各科目の授業の予習 ・復習にも活用できます!
