
改訂4版 胎児心拍数モニタリング講座
【CTGの生理と判読の基本がわかる決定版!】胎児心拍数モニタリング(NST・CTG)の基礎知識と基本的な波形の読み方を、問題形式でわかりやすく解説。症例にそって各波形の「定義」「臨床的意義」が示され、臨床に役立つ。日常診療で経過を大きく左右する大事なサインを、新しい知見を加えて解説する。「胎児心拍数の制御機構」の解説を加筆。

今日から使う
看護現場の基本交渉術
「患者さんにベッド移動をお願いしなければ……」「急遽、夜勤の交代要員が必要……」などよくある場面でうまく頼めず、自分が我慢したり言いやすい人にばかり頼んだりしていないだろうか? 本書を読んですぐに交渉上手とはならないものの、本書には交渉力をつけるために必要なことが具体的にわかりやすく書かれている。今日から少しずつ知識とスキルを積み重ねることで、悩んでいたあのコンフリクトも解消できるかもしれない。

よクウわかる腹膜腔・後腹膜腔の画像診断
腹部を腔・膜で理解! 解剖と連続性を理解すれば,疾患がどこに転移しうるのか/どこから波及してきたのかを判断でき,迅速かつ見落としのない鑑別が可能になる。
区分ごとに構造物や原発する疾患,転移・波及する疾患を1つずつ解説。さらに周囲の腔との位置関係でどう連続しているのかを学ぶ。また解剖は多数のシェーマでわかりやすく提示され,どの高さでスライスしたのかがわかる画像が添えられて,イラストと写真を結びつけて理解できる紙面構成となっている。
これから腹部を学びたい初学者にも,もう一度勉強しなおしたい医師にも有用な一冊。

リトルICUブック 第2版
持ち歩ける『ICUブック』
はじめての重症患者管理は世界で信頼されるこの1冊から
集中治療医学の大ベストセラー『ICUブック』の子本「リトル」が8年ぶりに改訂。親本と相互参照できる構成、最新ガイドラインへのアップデート対応、新規書き下ろし収載など、全面的に刷新。病態生理から重症患者管理を考えるMarinoスタイルはそのままで、「ダイジェスト版」の枠に収まらず、「リトル」のみでも充分に使える充実した内容。値下げしてポケットサイズに生まれ変わり、日常的に持ち歩きたい研修医にもおすすめ。

限られた時間での対応にもう悩まない!緊急PCIマニュアル
限られた時間内で患者救命が求められる「緊急PCI」について,施行のための準備から,待機的PCIとは異なる患者評価や適応判断・治療のポイント、合併症の注意点までをコンパクトにまとめた実践マニュアル.病変・病態別の緊急PCIの実践を学べるケーススタディでは,使用デバイスや治療戦略はもちろんのこと,考えられる最悪のシナリオとその回避法の解説も充実させた.夜間の当直時や休診日など,一人で術者となる可能性もある若手医師に心強い一冊.

思考プロセスと実践をミニマムにまとめました
循環器診療エッセンシャル
要領よく情報を得たいという若手読者のニーズに適った一冊!“これさえ理解していれば診療に困らない・大失敗を避けられる”……そんな,研修医が知っておきたい循環器診療の基本知識,考えかた,実践法を,日本の臨床現場に即した内容のみに絞ってポケットサイズに凝縮しました.指導医の思考プロセスが一目でわかる「ミニマム診断・治療チャート」や,おススメしたい「必読文献」,付録には「当直中に必須の循環器治療薬一覧」も収載.コンパクトながら大充実の内容.

Hospitalist Vol.12 No.3 2024
2024年3号
特集:ホスピタリストのための画像診断(3)腹骨盤部編
特集:ホスピタリストのための画像診断(3)腹骨盤部編
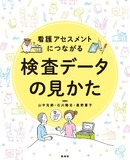
検査データの見かた
この患者さんの状態(疾患)では、どの検査項目を見るとよいか、その検査値の推移をどう読むか。検査データから、「今、患者さんの身体に起こっていること」を把握し、看護アセスメントとケアに活かす、ナースのための検査値の読み方実践書。

すぐわかる!ミッドラインカテーテル 46の疑問
本書は,国内初のミッドラインカテーテルの専門書として,基礎から適応,挿入手技,管理方法までを体系的に解説しました.エコーガイド下での挿入手技や挿入時のトラブルシューティングについても,豊富なイラストを用いてわかりやすく説明しています.実際の挿入,固定,採血手技が学べる「Web動画」も収録.ミッドラインカテーテルを安全かつ適正に使用するためには,カテーテル管理に関わる医療従事者が,十分な知識と技術を習得することが求められます.ミッドラインカテーテルについて初めて学ぶ方はもちろん,臨床でさらに活用していきたい方まで,すべての医療従事者におすすめの1冊です.

脳卒中の下肢装具 第4版
病態に対応した装具の選択法
下肢装具のベスト・フィッティングを学ぶ一冊、待望の動画付きで改訂!
脳卒中の下肢装具療法は種類が多く(短下肢装具:約30種類、長下肢装具、股装具、膝装具など)、患者の病態もさまざまなため、フィッティングは容易でない。本書は装具の機能分類だけでなく、片麻痺患者の身体機能を加味し、個々の状態に適した装具の機能および選定方法を紹介する。今版では、装具の特徴や症例の歩行訓練の様子を動画で示し、より実践的に充実した内容に改訂されている。

運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖学 第2版
徒手療法がわかるWeb動画付
「なぜ?」シリーズの元祖本にWeb動画がついてパワーアップ!
臨床あるあるの疑問や理由が解剖学ですっきり解決! 実際の徒手療法がWeb動画で見てわかる! 頸椎症由来の頭痛はなぜ起こるのか? 投球動作を解剖すると? くり返す足関節捻挫後の不安定感にはどう対応すればよいか? 遭遇頻度の高い運動器疾患のメカニズムや痛みの原因、運動療法の選択を症例にそって解説。筋・神経の構造や動きを把握することで、痛みの原因や治療法が解明されます。実践的解剖学、待望の改訂です。

看護教育のためのパフォーマンス評価
ルーブリック作成からカリキュラム設計へ
やってみたら「逆向き設計」だった! 現場で求められる看護実践力とは何か。そもそも教育とは、学びとは、評価とは何かという根源的問いからカリキュラム再構築を追求してきた看護教員が、気鋭の教育学者と協働し、同じゴールを目指したその背景を初解説。なぜパフォーマンス評価が看護基礎教育に必要で、ルーブリックが看護師養成の場で有効なのかがこの1冊でわかる実践的ガイドブック。領域別実習例やQ&Aも充実。
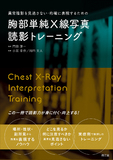
異常陰影を見逃さない・的確に表現するための
胸部単純X線写真読影トレーニング
胸部X線読影の初学者や一般内科医を対象に,異常所見を“見逃さず,的確に表現する”ための胸部X線読影・スクリーニングの要点についてやさしく解説.①異常陰影を的確に表現するための基本,②“見逃し”を防ぐための読影手順と要点,③難易度順に読影のトレーニングができる実症例の3部構成で,“異常所見を見逃さないための読影ポイント”や“鑑別に導く考え方”を簡潔に学ぶことができ,明日からの診療に自信がもてる一冊.
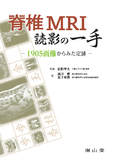
脊椎MRI読影の一手
1905画像からみた定跡
17万件以上の国内トップクラスを誇るMRI検査数であらゆる整形外科疾患を撮像してきた著者らが,26年間の集大成として培った情報と経験を披露する.病変部と正常像を比較できる構成やスカウトビューで三次元的に画像を把握でき,診断につなげる読影法と1900枚の頚椎・胸椎・腰椎の圧倒的なMRI画像数により読者の経験値を補完する. 「下肢MRI読影の一手」に続く第2弾.
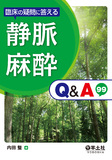
臨床の疑問に答える 静脈麻酔Q&A99
TIVAの適応と禁忌は?術中覚醒の防止策は?高齢者のTIVAの注意点は?薬物動態モデルはすべての患者に使える?など,臨床の疑問にやさしく答える!静脈麻酔の入門に最適!
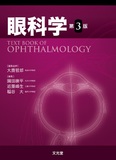
眼科学 第3版
“一冊で眼科専門医に必要十分な知識を学べる”教科書,『眼科学』の9年ぶりとなる改訂第3版.眼科研修医ガイドライン,眼科専門医認定試験出題基準に準拠し,疾患・診療から法律・歴史にいたるまで眼科のあらゆる領域を,最新知見を盛り込みつつ,当代一流の執筆陣272名が明瞭に解説.約3,000点の豊富な図版掲載で,臨床の現場でも活躍する一冊.

画像で究める認知症
年間1万例以上に及ぶ65歳以上高齢者の脳画像をみる神経放射線読影トップランナーが,汎用なCT・MRIから認知症の背景疾患の診断に迫る最前線のストラテジーを詳解。自験例を中心に認知症の背景疾患,注意すべき重畳的所見のなかでも特に優先すべき回復可能な疾患の鑑別から病期診断まで余すことなく徹底解説。新規治療薬で欠かせないARIAやピットフォールも豊富に示唆し,フォローアップ症例の病理画像やSPECT,解析データを交え,局所的診断と評価,根拠,放射線科医がチームとして共有すべき考え方を示す。認知症マネジメントに欠かせない日常診療の検査,高齢者診療にかかわるすべての人に伝える,放射線科医の視点からみた唯一無二のハイパーリファランス。

日本認知症予防学会監修
軽度認知障害(MCI)診療マニュアル
プライマリケア医,高齢者をみるすべての医療スタッフに役立つ認知症を予防するための1冊
EBMに基づく非薬物的アプローチでMCIを適切にマネジメント! MCIの診断・治療・管理の必須知識を基礎から解説し,臨床現場で実際に出るCQについてエキスパートの対応を伝授.MCI の診断後支援に役立つ患者・家族へのアドバイス付き.早期発見と的確な対応で認知症予防に役立つ実践的知識が学べる1冊.注目の新薬レカネマブについても解説!

臨床泌尿器科 Vol.79 No.5
2025年 04月号
特集 シン・泌尿器科当直医マニュアル〈外来編〉
特集 シン・泌尿器科当直医マニュアル〈外来編〉 泌尿器科診療にすぐに使えるヒントを集めた「特集」、話題のテーマを掘り下げる「綜説」、そして、全国から寄せられた投稿論文を厳選して紹介する。春に発行する書籍規模の増刊号は、「外来」「処方」「検査」「手術」などを網羅的に解説しており、好評を博している。 (ISSN 0385-2393)
月刊、増刊号を含む年13冊

重症筋無力症/ランバート・イートン筋無力症候群診療ガイドライン2022
日本神経学会監修による,エビデンスに基づいたオフィシャルな診療ガイドライン.今版では初版「重症筋無力症診療ガイドライン2014」を基に,分子標的治療薬の情報等も追加して内容をアップデート.また,これまでガイドラインが存在しなかったランバート・イートン筋無力症候群も取り上げ,両疾患について疾患概念や診断基準,疫学,予後等の基礎的な内容から,治療指針や具体的な治療法等の実診療に関する情報までを網羅している.
