
ニッチなディジーズ
あなたがみたことのない病気を診断するための講義録
「ニッチなディジーズ」とは頻度的にレアな疾患、またスキマ領域にあってどの科にも属さない認知上の死角にある疾患の総称である。「診たことのない病気でも、その備えと考え方のスキルがあれば診断できる!」をテーマに10講のレクチャーを講義形式で掲載。授業を聴いているような臨場感で楽しく学べる。真の臨床医は“ひづめの音が聞こえたら、馬も探すし、シマウマも探す”。今日、出会うかもしれないレア疾患をつかまえろ!
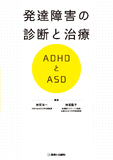
発達障害の診断と治療 ADHDとASD
小児科医×児童精神科医のコラボ!発達障害(ADHDとASD)の診断と治療,疫学や併存症,ライフコースに沿った経過や生物学的病態,障害概念の歴史的経緯などを,最新のエビデンスに基づいてわかりやすく解説.さらには,著者らの熱い思いが詰まったコラムも必見!発達障害研究・臨床の最前線をいく著者らによる,渾身の一作です!

Advanced Myofascial Techniques Volume 1
ビジュアルで学ぶ 筋膜リリーステクニック Vol.1 肩、骨盤、下肢・足部
今、注目が高まる「筋膜!」
その理論と施術が身につくビジュアル本
身体で最も大量にある組織は何だろうか?
その答えは「骨」でもなければ、「筋肉」でもない。
「筋膜」である。筋膜は筋肉、腱、骨、血管、臓器、神経を覆い、つなげ、包んでいる線維性結合組織のことで、身体に何百または何千も存在している。身体の複雑な三次元ネットワークを形成しながら、その伸縮性によって運動を促進させ、皮膚の感受性を高めるという役割を持つ。臨床家は、筋肉や骨と同様に、筋膜についても理解しておく必要があるといえそうだ。
そんな筋膜への知識を深めながら、多彩なリリーステクニックが身につけられるのが、本書である。筋膜リリーステクニックは、身体の弾力性や知覚感覚を回復させ、さまざまな疾患を改善させる。CGイラストと施術写真が豊富な本書で、ぜひそのテクニックを身につけてほしい。

手 その機能と解剖
今迄に出版した各版をもう一度見直し、内容を統括し、その上で最近の知見を加えて第6版が作製された。
基本的な知識から治療の実践上知っておくべき手の機能と解剖の要点がまとめられている。この本を熟読して頂ければ、正常な手の進化の過程やその機能と解剖の知識を得られるばかりでなく、手の先天異常、損傷、病気などについてもある程度は学べるように配慮され、生きた手の機能と解剖が克明に説き明かされている。
また、多数の色刷りシェーマとカラー写真やX線写真で、明快に展開されているので、整形外科医、形成外科医はもちろん、ハンドセラピスト、理学療法士、作業療法士など幅広い読者層に対応する充実した内容を完備した。

発生状況からみた
急性中毒初期対応のポイント 農薬・工業用品(TICs)編/化学剤編
公益財団法人日本中毒情報センター(JPIC)の実績とデータがここに結実
「発生状況からみた急性中毒初期対応のポイント」シリーズは,JPIC設立30周年を記念して企画され,JPICが運営する「中毒110番」における経験と蓄積されたデータをもとに,プレホスピタルや医療機関での初期対応とその解説をまとめたものである。本書は既刊「家庭用品編」(2016年9月発行)に続く,シリーズ第3巻である。
「農薬・工業用品(TICs)編」は,農薬や工業用品などの有毒な産業化学物質(Toxic Industrial Chemicals;TICs)について,農薬は用途別の製品群もしくは物質(成分)ごと,工業用品は物質ごとにまとめた。「化学剤編」は,戦争やテロ活動において人々を殺傷することを目的とした化学物質である化学剤(Chemical Agents;Cas)について,作用グループと化学物質ごとにまとめた。
「農薬・工業用品(TICs)編」では製品群・物質(成分)全30項目,「化学剤編」では化学剤7類型25物質について,実際に事故が発生した際に患者対応にあたる医師や看護師,薬剤師,また事故発生現場において対応するファーストレスポンダー,消防や警察などの関係者が,「自らの身を守りつつ」「状況を客観的に把握」し「起こり得る危険を想定」したうえで「的確に判断して対応」するための情報をまとめている。
その他,TICsによる事故の発生状況や中毒の発現機序と症状(トキシドローム)についてや,化学テロ対応の基本的な考え方など,それぞれ総論的な解説も施した。
続編として「医薬品・自然毒編」(シリーズ第2巻)の出版を予定している。
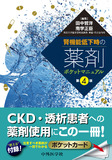
腎機能低下時の薬剤ポケットマニュアル 第4版
腎機能の低下した患者に至適な薬剤処方を行うための必要知識を解説したポケットブック改訂第4版が表紙を刷新
して登場.患者に応じた使用法・注意点を薬剤ごとにまとめたコンパクトでわかりやすい構成・体裁はそのまま
に,次々に出てくる新薬に関する記載に加え,既存項目の加筆・修正・増補を行った.特に注意すべき薬剤をまと
めた付録「携帯用ポケットカード」付き.

≪ジェネラリストBOOKS≫
よくみる子どもの皮膚疾患
診療のポイント&保護者へのアドバイス
エキスパート直伝! 豊富な症例写真と解説で、的確な診断・治療・紹介へ。小児科・内科を訪れる子どもの多様な皮膚症状を、豊富な症例写真とともにエキスパートがわかりやすく解説。外来でみることが多い子どもの皮膚疾患の「原因」「症状」「鑑別」「治療」のほか、感染症では「登校(園)の目安」、あざ・色素異常では「治療や紹介の目安」もわかる。保護者への情報提供にも重点を置いており、最新のエビデンスに基づくスキンケアの指導法から、的確なホームケアへつなげることができる。

Hospitalist Vol.6 No.3 2018
2018年3号
特集:肝胆膵
特集:肝胆膵
クロノロジスト宣言:
肝胆膵の臨床マネジメントにおいては「クロノロジー(時間軸)」が最も重要である!
本特集は,2014年刊行の「消化管疾患」特集で取り組んだ「問診と身体診察から鑑別診断を考え絞り込んでいく内科的アプローチにのっとった消化器病学」を,肝胆膵疾患でも試みるものです。
肝臓は「沈黙の臓器」といわれるとおり,黄疸を除けば,臓器特異的な症状に乏しい臓器です。胆道,膵臓疾患でも,主要症候である腹痛の鑑別が多岐にわたることに異論はありません。まず,肝胆膵疾患であるか,またどのような肝胆膵疾患であるかを考え,さらに病態を切り分けていくうえで,肝酵素,膵酵素,腹水検査を含めた検体検査,各種モダリティによる画像検査が重要な役割をもってくることもまた真実です。
「時間軸を意識したアプローチ」で,肝胆膵疾患の病態生理と時系列を意識することにより,個々の患者から得られた,症候のみならず検査結果も含めた診断の手がかりを,「あり/なし」だけではなく「濃淡のある」データとして包括的にとらえ,有機的に診断に結びつけていくことができます。「クロノロジスト」に,我々は,疾患や病態の経過の部分,すなわち経時的な観点を重視し,臨床病態や診断治療アプローチをとらえなおせる存在という意味を付与し,今回は特集全体の縦糸として「クロノロジー(時間軸)」に注目しました。

叢状神経線維腫-悪性末梢神経鞘腫瘍診療ガイドライン
本邦初!!
NF1患者におけるPNとMPNSTの診療に特化した診療ガイドラインです。
2022年11月より保険適用となったNF1に対する初の治療薬となるMEK阻害剤であるSelumetinibの適切な使用のための確かな情報もお届けします。
関連する医療従事者、患者・ご家族の方々は是非、ご参考にしてください。

松島流 肛門疾患手術
なぜそうするのか?
世界有数の診療実績を誇る大腸・肛門疾患の専門病院である松島病院の,100年にわたる肛門疾患手術のエッセンスを言語化した手術書.肛門部の代表的な疾患に対し,手術写真とその要点を表した手術イラストを用いて「なぜそうするのか?」という治療コンセプトとともに手術手順をわかりやすく解説.確信をもって手術に臨み,判断が分かれる難しい症例にも的確に対応する力を身につけられる一冊.

誰も教えてくれなかった
血算の読み方・考え方
最低限の病歴と血算から、可能性の高い疾患を「一発診断する」力を身につけるための本。血算は、すべての臨床検査の中で最も基本的で頻用される検査。臨床現場では簡単な病歴と血算を中心とした情報だけで、診断を推定しなければならない場面は多く、また実際かなりの疾患の推定ができる。誰も教えてくれなかった血算の読み方・考え方が学べる本書は、研修医、若手血液内科医はもちろん、すべての臨床医、検査技師にも役立つはず。

だけでいい! フィジカルアセスメント
【55本の動画で身体所見がばっちり見える!】フィジカルアセスメントの方法は習ったけれど、実際の所見の診かたが分からない、なんて人、いませんか? そもそも異常所見はタイミングよく現れてくれないし、異常を異常として認識することは難しいもの。外来や病棟でよく遭遇する“ホンモノ”の所見動画・写真が満載の本書が、「学びにくい」「教えにくい」を解消。日々の経過を追う力、異常を見極める力を磨く“見える・わかる”が詰まった一冊。研修医にもおすすめ。

作業療法ジャーナル Vol.60 No.2
2026年2月号
■特集
ルックスケアと作業療法―外見支援から広がる生活と社会参加

講義から実習へ 高齢者と成人の周術期看護 術前編 第4版
周術期看護の定番テキストが6年ぶりに大幅改訂!
より使いやすい構成へと抜本的に見直し,最新情報を完備!
●豊富な写真・資料と付録動画で視覚的に周術期看護の実際をとらえる定番テキスト.
●成人看護学実習の予習や手術室ナース向け臨床書に最適.
●<術前編><術中・術後編>の2冊で学ぶべき全容を押さえる構成.
●術式の変遷から各種ガイドライン・周術期管理プロトコルの改訂まで,最新トレンドに対応.

看護師のための文章ノート
読んでもらえる“仕事の文書”が書ける! 作文技術が身につく! ワークシートで自分の文書の傾向をつかめる!
しばしば「冗長」「わかりにくい」などと言われる看護師の文章。「看護」という仕事の本質が「個別性」を対象とし記述的になりがちなためですが、仕事の文書(論文や各種報告書、レポート、依頼文書、看護記録など)は読んでもらわなければなりません。本書は“読んでもらえる仕事の文書”を書くための作文技術を紹介したコンパクトな良書。思考が整理でき、添付のワークシートを使えば自分の文章の傾向がつかめます。今日から「より、読んでもらえる文章」を書いてみませんか。

≪グリーンノート≫
CCUグリーンノート 第2版
日本有数の実績と経験を有し、医師の研修,教育にも注力する国立循環器病研究センタースタッフが初版刊行以来
の最新の知見を反映させて改訂したCCUグリーンノート第2版。循環器医療を学ぶうえで欠かすことのできない
CCUでの基礎知識、診断、治療、手技などのポイントを簡明に解説し、臨床で役立つ実践的な内容を目指して作成
されている。

産科と婦人科 Vol.89 No.2
2022年2月号
【特集】早産と妊娠高血圧腎症:病因・病態生理−私はこうみる
【特集】早産と妊娠高血圧腎症:病因・病態生理−私はこうみる 産科学の2大研究テーマである早産と妊娠高血圧症候群について進化,遺伝,細菌叢,炎症,酸化ストレスや免疫など多角的に解説しました.

「感染症が苦手」な研修医へ 感染症診療の極意を伝授
診断のポイント,抗菌薬の処方,患者やスタッフと信頼関係を築くための秘訣などをエキスパートが伝授します!
診断できる,処方がわかる,手技・対応もわかる・・・
感染症診療に携わるスタッフへ贈る,すべてが詰まった1冊です!

分子腫瘍マーカー診療ガイドライン 第2版
遺伝子・蛋白解析技術の飛躍的進歩により、癌診療に有用と思われる分子が多数報告されている一方で、評価の定まっていない検査が無規制で施行されていることが問題となっている。本ガイドラインでは、実際の診療現場における分子腫瘍マーカーの臨床的有用性と、それに基づいた診療について解説。「感度・特異度」の基本的概念から各癌種における腫瘍マーカーの役割・癌関連遺伝子検査まで、診療に活せる情報が満載。

心電図のみかた,考え方 応用編
「才能はいらない!」心電図の読み解く力が必ず身に着く,頼れるガイドブック.
心電図のみかたを軽妙な語り口と明確な判読方法で解説し,好評を博した書の「応用編」.主に波形異常を扱うカタチ編を中心に,前回の基礎編からより実践的な内容となっている.現場でよく見られる具体例を交え,心電図が丁寧に読み解かれていき,着目すべきポイントや考えかたを無理なく身に着けることができるだろう.「心電図には才能はいらない」と言う著者の言葉通り,必ず心電図を使いこなせる自信が持てる,頼りがいのある一冊だ.
