
小児看護2025年11月号
重症心身障害児の「生きる」を支える
重症心身障害児の「生きる」を支える 医学の発展により、重い障害のあるこどもが在宅で暮らせるようになっている。いのちを保つために質の高い医療処置や看護ケアが提供されているが、彼らが「生きる」ためには本人・家族のQOLや、本人の意思決定が尊重されることも重要である。本特集では重症心身障害児の「平常時」、またレスパイトなどの「準緊急時」、災害時などの「非常時」に焦点をあてて、彼らが「生きる」ために行われている支援を紹介する。

新訂 NBI内視鏡アトラス
NBI(narrow band imaging)内視鏡診断における貴重な写真を満載したアトラスの新訂版.持ち歩いていつでも参照できるハンディサイズながら,通常光,拡大内視鏡,病理像も盛り込み,咽頭・喉頭~大腸・直腸を一冊で網羅.新訂版では経鼻の画像や超拡大内視鏡のアトラスも追加.NBIの開発時から先駆的に取り組んできた編者らによる,消化器科医,内視鏡医,内視鏡診療に携わる実地医家必携の一冊.
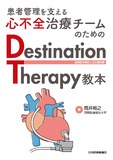
患者管理を支える心不全治療チームのためのDestination Therapy教本
重症心不全の治療のひとつの選択肢として発展してきたDestination therapy(DT)が2021年に保険収載されました。保険収載から約4年。症例を重ね、蓄積された知見をまとめたのが本書です。
本書では心不全治療チームとしてDTを知るための基礎知識、DTの適応と実施体制、植え込み手術および周術期管理、遠隔期管理と合併症対策、在宅管理に関する最新情報を網羅しています。
心不全パンデミックの現代では、いつDT患者さんを診ることになってもおかしくありません。本書を手に取り、DT患者さんへの対応に備えてみませんか?

≪診断と治療社 内分泌シリーズ≫
内分泌代謝疾患クリニカルクエスチョン100 改訂第2版
内分泌代謝専門医をめざす若手医師らにアンケートをとり,特にここが知りたい,わかりにくいという点を100選出し,ChapterごとにCQ形式でまとめ,エキスパートの執筆陣がわかりやすく簡潔に解説.改訂第2版では18のCQを入れ替え,すべての項目で最新のガイドラインや診療指針の最新版の反映.内分泌の専門医をめざす医師のみならず,内分泌疾患の診療にたずさわっている医師がつねに手元において,日常診療に活用できる!

極論で語る神経内科 第2版
神経内科の定番書の、7年ぶりの大改訂!「頭痛」「末梢神経障害」「めまい」の新章を追加。日本と米国で指導医として活躍する著者が海外のトレンドを踏まえて、神経内科医師の極意を伝授します。

脳神経外科速報2025年2号
2025年2号
特集:アプローチから学ぶ脳神経外科の歴史
特集:アプローチから学ぶ脳神経外科の歴史 臨床医の人生に伴走するLifetime Journal
『脳神経外科速報』は2021年、「臨床医の人生に伴走するLifetime Journal」として、リニューアルしました。
裾野が広い脳神経外科領域のテーマを幅広く取り上げ、また、知識の更新につながるように、最新情報やトピックスを提供し、生涯学習を支えます。
手術の知識・スキル・テクニック・思考・ビジョン、診療のワザやコツ、現代の臨床医に求められる教養など、脳神経外科医の「人生」に寄り添う情報を紹介します。

やってみたくなるアディクション診療・支援ガイド
アルコール・薬物・ギャンブルからゲーム依存まで
近年,アルコールや薬物の依存症,ギャンブルやゲームといった嗜癖行動は社会的関心を集めており,アディクション問題に関する専門職への期待は高まっている.本書は,アルコール依存・薬物依存・ギャンブル依存・ゲーム依存の4章から構成.総論・診断から,医療機関での治療,多職種連携・地域多機関連携による回復支援,各依存症に特有の問題点とその対応,関連法規,さらに当事者の治療・支援への期待と要望まで網羅した.

研究の育て方
ゴールとプロセスの「見える化」
はじめて「研究」に取り組む人のために「総合リハビリテーション」集中講座「研究入門」(2016年1月~2017年3月掲載:全15回)の書籍化。20年にわたる大学院での研究指導の経験から得た、研究のノウハウと指導のポイントをもとに、研究に関する考え方、進め方、論文の書き方など研究に必要な全体像を1冊にまとめた。初心者でもイメージしやすいように、基礎的な用語解説や具体例を含む「コラム」を用いることで、「研究」の全体像を掴めるようにした。

臨床雑誌内科 Vol.136 No.4
2025年10月号
クリニック・在宅で診る血液疾 できること,できないことを見直そう
クリニック・在宅で診る血液疾 できること,できないことを見直そう 1958年創刊。日常診療に直結したテーマを、毎号"特集"として掲載。特集の内容は、実地医家にすぐに役立つように構成。座談会では、特集で話題になっているものを取り上げ、かつわかりやすく解説。

≪グリーンノート≫
皮膚科外来グリーンノート
皮膚科の各分野のエキスパートが集結し、外来で遭遇するcommon diseasesについて明快に解説した。皮膚疾患
の病態・診断・治療などについて、ポケットサイズで簡潔にまとめられており、皮膚科の研修医や一般医が気軽に
知識を身につけることができる。また、最新の知識が整理されているため、専門医にとっても、広範である皮膚科
学の最新の進歩を効率よく取り入れるのに有用である。皮膚科学にかかわる全ての医師に必携の一冊。

INTENSIVIST Vol.10 No.3 2018
2018年3号
特集:人工呼吸器
特集:人工呼吸器
人工呼吸は集中治療の基本です。人工呼吸器の性能の進化により,かつては患者にとって苦でしかなかった“道具”は,患者の呼吸に合わせて患者を補助する“患者の良きサポーター”になりました。しかし,その機能や及ぼす影響などを理解して使用しなければ,患者とグラフィックモニターをしっかり観察しなければ,かつてのような単なる道具の域を超えることはありません。それどころか,性能の進化とともに,患者に及ぼす害も大きくなる可能性があります。われわれ人工呼吸を患者に施行する者は,人工呼吸器と人工呼吸の患者に及ぼす影響に対する深い知識をもつ義務があると思います。本特集では,人工呼吸器やモードが患者に及ぼす影響・効果を考えるときに,常に考慮しなければならない重要な要素として,酸素化,ガス交換以外に「肺傷害を最小限にできるか」「同調性は良いか」「呼吸仕事は適正に保たれているか」「循環への影響」の4つの要素を提案します。

うんこのつまらない話 Ver.2
好評に応えて全面改訂.AIで患者との医療面接が練習できる!
便通異常症診療ガイドラインの刊行に合わせ,便秘をテーマにして大好評だった初版を全面的に改訂.便秘だけでなく,下痢についても盛り込み,便通異常に悩むすべての人に寄り添うために必要な知識を収載.さらにAIを活用して医療面接の練習できるページを追加.誰も避けては通れない人類共通の“便通”問題に取り組む,超マジメな“うんこ”の本が大幅にボリュームアップして登場!_x000d_

現場の悩みをスッキリ解消 慢性便秘症診療プラクティス
「便秘」がにわかに注目を集めている.慢性的な便秘は長期生存率を低下させ,冠動脈疾患やパーキンソン病との関連も示唆されている.2023年には日本消化管学会編集『便通異常症診療ガイドライン』も発刊された.すでに便秘薬の処方も変わりつつある.
しかし,ガイドラインは難解との声も多い.主な読者として消化器内科専門医が想定されているためであろう.一方,便秘はありふれた病態で,医療従事者であれば誰もが身近に感じていたものだ.それゆえにこれまで漫然と行ってきた対応と,ガイドラインの記載との乖離に戸惑うのかもしれない.
本書では,「プライマリ・ケアの現場」で使えることを意識し,慢性便秘症の基礎知識をわかりやすく整理,解説した.

新訂版 実践に生かす看護理論19 第2版
19人の看護理論家の看護理論と看護過程のつながりと、中範囲理論を事例を用いた看護展開で解説している。

消化器内視鏡34巻5号
【特集】大腸鋸歯状病変のすべて
【特集】大腸鋸歯状病変のすべて

骨折の機能解剖学的運動療法 その基礎から臨床まで 総論・上肢 第2版
2015年の初版から7年ぶりの改訂となる第2版.総論では骨折の運動療法を行うために必要な知識,各論では骨折後に必ずおこる組織の修復過程を基礎に、上肢,体幹,下肢ごとに疫学、整形外科的な治療の考え方、評価と治療について解説.主な改訂内容として、総論では近年話題のfascia、慢性疼痛のfear-avoidancemodelを加筆.また肩関節と手関節周辺骨折の運動療法について可能な限り詳細に修正と加筆を加えた待望の第2版の刊行.
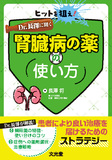
ヒットを狙え! Dr. 長澤に聞く腎臓病の薬の使い方
CKDヒートマップを野球のストライクゾーンになぞらえた,革新的な腎臓病の薬の使い方の書籍が爆誕!! 第1章では,腎臓病の頻用薬(降圧薬,利尿薬,血糖降下薬など)の特徴や使い方,さらに具体的な治療目標を解説.第2章では,さまざまな腎臓病患者に対する薬剤選択・治療戦略を思考過程も含めて解説.実臨床で患者を目の前にして,どの薬を選ぶか,どのように処方すればよいか迷うときに手に取ってほしい.

実験医学増刊 Vol.43 No.20
【特集】オミクスデータを探す!使いこなす!公共データベース厳選53
【特集】オミクスデータを探す!使いこなす!公共データベース厳選53
「どうすれば欲しいデータを効率よく探せるだろう?」「このオミクス解析結果,どう解釈しよう?」生命医科学分野の公共データベースの数は2,000を超えるといわれており,研究の目的に合ったものを見つけ出すのは困難です.本書は,ゲノム,タンパク質,代謝物などあらゆるレイヤーについて,データの入手と解釈に有用なデータベースを厳選して特徴と使い方を紹介します!
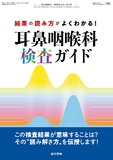
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.94 No.5
2022年 04月発行(増刊号)
結果の読み方がよくわかる! 耳鼻咽喉科検査ガイド
結果の読み方がよくわかる! 耳鼻咽喉科検査ガイド 目のつけ処が一味違う耳鼻咽喉科・頭頸部外科専門誌。「こんなときどうする!?」などの臨床的なコツの紹介から、最新の疾患概念を解説した本格特集まで、硬軟とり混ぜた多彩な企画をお届けする。特集2本立ての号も。「Review Article」欄では研究の最前線の話題をわかりやすく解説。読み応えのある原著論文も多数掲載。 (ISSN 0914-3491)

臨床整形外科 Vol.61 No.1
2026年 01月号
特集 下垂足を極める 病態理解から治療戦略まで
特集 下垂足を極める 病態理解から治療戦略まで よりよい臨床・研究を目指す整形外科医の「うまくなりたい」「学びたい」に応える月刊誌。知らないままでいられないタイムリーなテーマに、トップランナーによる企画と多角的な解説で迫る「特集」。一流査読者による厳正審査を経た原著論文は「論述」「臨床経験」「症例報告」など、充実のラインナップ。2020年からスタートした大好評の増大号は選り抜いたテーマを通常号よりさらに深く掘り下げてお届け。毎号、整形外科医に “響く” 情報を多彩に発信する。 (ISSN 0557-0433)
月刊、増大号を含む年12冊
