
レジデントノート増刊 Vol.26 No.5
【特集】臨床医なら必修!外科・手術のキホン
【特集】臨床医なら必修!外科・手術のキホン 専門家でなくても必要な手術療法の知識・考え方・スキルがわかる!術前評価・術後管理ですべきこと,手術室で行われることなど,手術療法の一連の流れで押さえたい重要点が掴めます.術野が見えるWeb動画付!

発達性トラウマ症の臨床
簡易型トラウマ処理TSプロトコールを用いて、発達性トラウマ症・複雑性PTSDなどの困難事例に向き合うための、最新の実践論集!

消化器内視鏡37巻1号
基礎から学ぶ 咽頭・食道内視鏡診断
基礎から学ぶ 咽頭・食道内視鏡診断

目からウロコの疣贅診療ハンドブック 困った時のこの一冊
疣贅は皮膚科に限らずプライマリケアの対象疾患として多様な診療科が扱う疾患であるが、その病態はさまざまである。疣贅の特性を把握し、正確な診断・治療にあたるために、基礎知識から多様な治療の実際とエビデンス、保険請求の実情までを包括的に解説した。よく目にするが、あまり知らなかった疣贅への理解を深め、診療の羅針盤となる一冊。

今日の診断指針 ポケット判 第9版
臨床の場で必要な情報に「いま」「すぐに」アクセスできる診断マニュアル 第9版
本邦最大級の診断マニュアルの全面改訂第9版。症候編172項目と疾患編691項目を相互リンクで構成し、臨床医が遭遇しうる疾患の診断に必要な情報をコンパクトに提示。専門外の領域でも臨床医として知っておきたい全身の症候、各診療科の疾患を1冊に網羅。第9版では、診断に関するエビデンス情報も随所に追加。新見出しとして「専門医へのコンサルト」を収載。
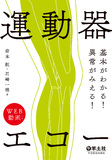
基本がわかる!異常がみえる!運動器エコー
「走査と正常像」「疾患」の二部構成で全身の各部位を解説.運動器エコーの基本がコンパクトにわかる初めてでも安心の入門書.運動器の日常診療でエコーを使用するなら読んでおきたい一冊!Web動画つき.

≪画像診断別冊 KEY BOOKシリーズ≫
婦人科MRIアトラス 改訂第2版
婦人科MR画像診断の決定版が待望の改訂! 日常でよく遭遇する疾患をカバー.
改訂第2版ではMR画像の全面刷新をはじめ,掲載疾患・症例もさらに充実
また,正常解剖の章を新設.見開き構成で,病態や画像所見,鑑別ポイントの理解を深め診療に活かせる.

SHDインターベンションコンプリートガイド 第2版
成熟と革新を遂げるSHD治療。ハートチームのためのマイルストーンとなる一冊。
大動脈弁狭窄の治療法として確立されたTAVI、さらに円熟味を増したTEER、心室/心房中隔欠損、PFO閉鎖術、心房細動による脳塞栓症予防ための左心耳カテーテル閉鎖デバイスなど、進化するSHD治療の最新知見を網羅して改訂。病態生理から、心エコー、ガイドライン、臨床試験、外科治療、そして具体的なデバイス留置術まで、各領域のエキスパートが詳述する、ハートチームのためのマイルストーンとなるガイドブック。
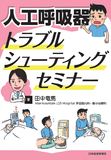
人工呼吸器トラブルシューティングセミナー
これさえ読めば、アラームが鳴っても怖くない!
当直中に人工呼吸器のアラームが鳴って困ったこと、ありませんか?
本書はあの田中竜馬先生が人工呼吸器トラブル原因検索・解決術を伝授!
各モードの仕組み、トラブルの種類・原因・対処法などについて、平易な文章で懇切丁寧に解説します。
どんなトラブルも一人でたちどころに解決できる考え方を身につけられます。

上部消化管内視鏡検査パーフェクトブック
~早期病変を見逃さないための基本テクニック・経年発見症例から学ぶ~
1~3年目の若手消化器内科医がおさえておくべき上部内視鏡検査の観察法を,見逃しやすい症例を元に,丁寧に解説した.
豊富な術中写真から観察時のポイントや,内視鏡像と病理組織を対比した解説で内視鏡診断のコツがわかる.

INTENSIVIST Vol.17 No.2 2025
2025年2号
特集:ICUにおける抗菌薬 new era strategy
特集:ICUにおける抗菌薬 new era strategy

婦人科MRIの読み方
婦人科における診断は、MRIを丹念に凝視することにより、臓器を手に取って眺めているごとく実像に肉迫できるようになった。これからMRI診断をはじめるひとへの最適な入門書として読み継がれてきた名著の電子版登場。

LiSA Vol.30 No.12 2023
2023年12月号
徹底分析シリーズ:身近なのに距離がある 医療機器/症例ライブラリー:周術期の低体温/エコー解剖のひろば:患者さんにプローブを当てる/小児心臓麻酔 事始め:単心室とGlenn手術とFontan手術/ぶらり研究室探訪記:山口大学大学院医学系研究科医学専攻 麻酔・蘇生学講座/こどものことをもっと知ろう:低身長
徹底分析シリーズ:身近なのに距離がある 医療機器/症例ライブラリー:周術期の低体温/エコー解剖のひろば:患者さんにプローブを当てる/小児心臓麻酔 事始め:単心室とGlenn手術とFontan手術/ぶらり研究室探訪記:山口大学大学院医学系研究科医学専攻 麻酔・蘇生学講座/こどものことをもっと知ろう:低身長

整形外科専門医へのminimal requirements
整形外科専門医を目指す医師が習得しておくべき知識をぎゅっと凝縮! 正誤問題と自己評価欄により得意不得意が把握でき,効率的に勉強を進められる。若手医師だけでなくすべての整形外科医の知識の整理書としても役立つ1冊。

小児救命救急・ICUピックアップ(2)呼吸管理
小児急性期診療の現場で頼れるシリーズ、第2弾
小児の救命救急・ICU領域における標準的な治療、最新の知見・エビデンスに基づく治療の選択肢を提示するシリーズ、「ショック」に続く第2弾。小児は成人とは異なることは踏まえつつも、成人領域の知見や経験を小児に当てはめて解説。人工呼吸器に馴染みのない小児科医のみならず、小児を診る機会の少ない集中治療医や救急医、メディカルスタッフにも配慮した記述。小児の呼吸管理に携わるすべての人に向けた、呼吸管理エキスパートによる指南書。
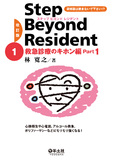
改訂版 ステップビヨンドレジデント1 救急診療のキホン編 Part1
心肺蘇生や心電図、アルコール救急、ポリファーマシーなどにモリモリ強くなる!
救急の神髄はLOVE&RESPECT! 大人気シリーズ第1巻を全面改稿した待望の改訂版!救急診療でまず身につけたい技と知識を,おなじみの“ハヤシ節”と最新の世界標準のエビデンスでやさしく伝授します!

小児心電図のみかた,考えかた
小児科診療に心電図をもっと活用してみませんか? 豊富な実症例を用いた解説で,様々な年齢の心電図の読みかたが身につく.基本的な心電図のみかたから先天性心疾患,不整脈,後天性心疾患の典型例や,運動負荷や長時間記録まで,診断に必要な知識がすっきりわかる.心電図を日常診療でますます活用できるようになる小児科医必携書.

研修医のための腎臓内科病棟マニュアル

非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドライン 改訂第3版
7年ぶりの改訂となる第3版は,患者への副作用を最低限に留め,QOLの改善薬としてオピオイド鎮痛薬を効果的に活用するための情報が充実.処方期間や用量,副作用とその対策,減量や中止のタイミングなどが詳述されている.また,非がん性慢性疼痛に対し使用可能なオピオイド鎮痛薬の剤型・種類が増えているため,知識の整理にも役立つ各薬剤の薬理学的な解説も豊富に記載.疼痛治療に関わる方々に必携の最新指針となっている.
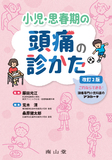
小児・思春期の頭痛の診かた 第2版
これならできる!頭痛専門小児科医のアプローチ
小児・思春期の頭痛診療を「難しい」と感じている医師に向けて,問診,診断,治療,患児や保護者への指導,経過観察などにおいて,頭痛専門小児科医が日々実践しているさまざまな工夫やアプローチ方法をわかりやすく紹介.「これなら自分にもできる!」と頭痛診療に対するハードルをなくして一定レベル以上の診療が実践できるようになる1冊.改訂2版では,頭痛の診療ガイドライン2021に準拠した内容にアップデート,さらに「不登校・不規則登校を伴う頭痛」など,とくに苦慮する頭痛への対応のしかたも新たに詳しく解説した.
