
日本リウマチ学会 シェーグレン症候群診療ガイドライン 2025年版
わが国初の「シェーグレン症候群診療ガイドライン」の刊行から8年.日本リウマチ学会の編集による改訂.
38個のCQからなり,関連論文を見直し,推奨提示・エビデンスの強さなどを改訂.また,実地臨床において有用と考えられる9個のコラムを追加し,『シェーグレン白書2020』の調査内容を記載し,患者の声をガイドラインに反映させています.
本症候群にかかわるすべての医療者にとってスタンダード診療のための必携の書.

カンデル神経科学 第2版
・8年ぶりの改訂にして,約30%の改訂量。
・全面的にアップデート。全9パート,64章からなる新構成。「ブレイン・マシン・インターフェース」など3章を新たに追加。
・より完成度を高めた大好評の概論に始まり,神経系の分子メカニズム,発生,末梢・中枢神経系,高次機能,精神・神経疾患の基礎を詳述。
・情報工学系項目を特に強化。また,光遺伝学やイメージング技術などの最新研究データを各章で紹介。
・「脳科学」を包括的に解説する最も信頼できる教科書。
・読みやすい日本語訳と、美しく見やすい907点のフルカラー図版。
・医学,薬学,リハビリテーション,理学,工学,情報工学,心理学,経済学,哲学などさまざまな学問領域の基礎として「人間を知るための科学的基盤」を与えてくれる本。
・初学者から専門研究者・医師,さらにはAIエンジニアまで、幅広く知識を共有できる一冊。
・幅広い読者に手に取っていただくべく,旧版に続き廉価を実現。

救急現場における精神科的問題の初期対応
PEECガイドブック 改訂第2版
多職種で切れ目のない標準的ケアを目指して
PEECガイドブック、6年ぶり待望の改訂版!
多職種チームで救急現場の精神科的問題に挑む
【本書の概要】
・自殺未遂者の多くが救急医療機関に搬送されている現状を受け、日本臨床救急医学会では、2007年に「自殺企図者のケアに関する検討委員会」を立ち上げ、テキストの作成と講習会を開催してきました。こうした活動のなかで、その必要性から、アルコールや薬物依存患者、混迷状態の患者やトラブルを起こす患者への対応などにも範囲を広げ作成されたものが本書です。
・本書は、救急現場で精神科医のいない状況でも、精神科的症状を呈する患者へ、安全で患者にとっても安心な“標準的”初期対応ができるためのガイドブックであり、「PEEC(ピーク)」とよばれる同教育コースのテキストにあたります。
【対象】
・救急医(研修医を含む)、看護師、精神科医、ソーシャルワーカー、臨床心理士、救急救命士、PEECコースに参加するあらゆる対象職種
【特徴/ポイント】
・初版発行から6年の間に読者よりいただいたご意見を参考に、最新の知見も取り入れて100ページを超える増補改訂を行いました。
・多職種によるチーム医療の推進を重視し、各職種にとっての「PEEC」を解説しました。
・救急隊員や救急救命士が直面する精神症状の評価とトリアージについても取り上げました。
・災害時のメンタルヘルスケアとDPAT(災害派遣精神医療チーム)についても、新たなケースシナリオを加えるなどして言及しました。

レジデントのための小児感染症診療マニュアル
小児の特徴をふまえた感染症診療の原則、考え方、具体的なプラクティス
小児の特徴(Children are not just miniature adults)をふまえた感染症診療の原則、考え方、プラクティスを示し、「感染臓器とそこに感染した微生物を考える」診療を実践していくための最適な一冊。発熱へのアプローチ、感染臓器、検査、原因微生物、治療薬、予防接種の各章で、エビデンスに基づいた記載とともに臨床現場で実際に使えるマニュアルの簡明さも備えた新しいスタンダード!

〜至適透析を理解する〜
血液透析処方ロジック
尿毒素物質の解説や透析の原理といった基礎知識から、混乱しやすい透析の各種モードを図説で平易にレクチャーした一冊。
透析処方現場で欠かせない各種ガイドライン等に示された各種設定目標や指針も網羅し、患者一人一人に最適な透析を「処方」するための考え方、臨床上のノウハウを惜しげもなく披歴した。
医師、看護師、各種医療者すべてのニーズに応えた、筆者の豊富な臨床経験がにじみでる「真のスターターブック」。

最新! 心臓デバイス攻略本
【最新の高度なデバイス技術が身につく入門書】ペースメーカ・ICD治療の最前線について、適応、機能・特徴の要点を押さえて、わかりやすく解説する。適応のエビデンス、主要メーカー製のデバイスの機能・特徴比較一覧も付いているから、さっと学べて、ぐっと納得できる。初学者に必携の頼もしい一冊!

頭頸部画像解剖ナビゲーション
基本的な解剖構造や正常画像をきちんと理解して読影するために―地図のように広域アトラスから詳細解剖へアプローチできる,新しい画像解剖書が完成!
各論では,臨床的に異常や病変の進展をきたしやすい解剖構造を,正常・変異・異常を比較して解説します.

結核診療ガイドライン2024
日本結核・非結核性抗酸菌症学会編集による,本邦初のエビデンスに基づく結核診療のガイドライン.総論では結核の診断・結核菌検査・結核患者の管理・治療・潜在性結核感染症について基礎から実践までまとめた.また臨床上問題となる「IGRA検査の解釈」,「薬剤耐性遺伝子検査の適応」,「高齢者結核の治療」,「免疫抑制宿主に対する治療」といった12のCQに推奨を明記し,対応の指針を示している.呼吸器科医、感染症医はもちろん,結核診療に関わる全医療スタッフ,行政担当者必携の一冊.

入門腫瘍内科学 改訂第4版
日本臨床腫瘍学会編集による,医学部生を主対象とした臨床腫瘍学の入門書の改訂第4版.各項の冒頭には要旨がわかる「summary」,末尾には「この項のキーポイント」を掲載し,理解しやすい構成が特徴.腫瘍学における基礎医学から診断・治療の総論,疾患各論までを網羅し,医学部生に必要な知識をわかりやすくまとめた.今改訂では同学会のテキスト『新臨床腫瘍学』の改訂内容を反映し,最新の内容を解説した.
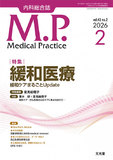
Medical Practice 2026年2月号
緩和医療─緩和ケアまるごとUpdate
緩和医療─緩和ケアまるごとUpdate 特集記事として,[対談]緩和ケア─がん患者の心のケアに焦点をあてて─,[総説]アドバンス・ケア・プランニングと療養場所の選択,アドバンス・ケア・プランニングと療養場所の選択,[セミナー]適切な緩和ケアの実践に向けたアセスメント,[治療]がん疼痛の薬物療法 等.また連載では,[One Point Advice][今月の話題][知っておきたいこと ア・ラ・カルト][心電図がよめる,得意になるシリーズ]他を掲載.

抗菌薬ドリル
感染症診療に強くなる問題集
感染症の診断や抗菌薬の選び方・やめ方,アレルギー,感染対策など,感染症診療の基盤になる考え方が問題を解きながら楽しく身につく!やる気をなくすほど難しくはなく,笑い飛ばせるほど簡単じゃない,珠玉の73問に挑戦しよう!

かんテキ 肺保護にこだわる人工呼吸
【患者の肺を守る医師・ナース全ての医療者に】「かんテキ」は、疾患・患者・看護・観察が感覚的にわかる、感動の一冊!医師・ナースをはじめとする医療従事者向けに、患者の肺にやさしい換気のしくみを徹底的に見える化。リアルな臨床現場で本当に必要な知識が、この一冊でパッとつかめる。筆者独自のユニークな切り口・語り口で、「人工呼吸のコアの知識」をどこまでも丁寧に、とことん根拠にもとづいて解説。どこから読んでもわかりやすく、つまずいたときに何度でも振り返ることができる。

もう困らない 救急・当直<新装改訂版>当直をスイスイ乗り切る必殺虎の巻! 新装改訂版
jmedmookシリーズで圧倒的人気を誇る林 寛之先生の「もう困らない救急・当直」が遂に書籍化!
従来の32項目のアップデートに加え,「ERでのcrisis communication」の項目が新たに追加されました。
■「鑑別診断のキモ」「決め手となる思考回路はこれだ! 」など,実臨床で大いに役立つ内容はそのまま,皆さんの期待に沿えるよう最新の知識を加えています。
■豊富な図表・イラストと優しく楽しく語りかける文体で,症候ごとの系統立ったアプローチがすっかり頭に入ります。救急・当直の診療の流れを構築するための導入として,また知識の整理整頓にお役立てください。
■執筆陣が数十年かけて磨きあげてきた勘所を余すことなく掲載。本書を何度も読むことで,それらをぜひ我が物にしましょう!

はじめての講義
リハビリテーション概論のいろは
リハビリテーション”そのものを掘り下げて解説したテキスト.国家試験合格レベルを念頭に,とくに1年生向けに平易な表現となるよう,文章はやさしく,図表は豊富に掲載した.理学療法士・作業療法士国家試験出題基準の該当分野の用語を網羅したリハビリテーション入門に最適なテキスト.

肺がん薬物療法 副作用マネジメント プロのコツ 改訂第2版
抗がん薬治療の効果を最大限に得るには,治療をできるだけ長く・患者負担なく継続することが重要である。そのためには副作用に対して適切な支持療法を行い,必要に応じて抗がん薬を減量・休止するといった「副作用マネジメント」が重要な鍵となる。
本書は,現時点で最新の肺がん薬物療法レジメンを解説。治療開始前の前投薬・前処方の工夫,副作用の発現時期や対処法,減量・休薬・再開の判断まで,治療の流れに沿ってプロのコツを徹底解説。アピアランスケアや心のケアのコツ,また,よりよいOSを得るための治療戦略のコツや,転移性腫瘍におけるQOL維持のコツまで,複雑化する肺がん薬物療法をフルサポート。
「臨床ですぐに・本当に使える」この1冊で,副作用マネジメントにはもう悩まない!

≪jmedmook 100≫
jmedmook100 フレーミングでとらえる臨床推論
◆ 既存の臨床推論における「フレームワーク」や診断をテーマとした書籍の内容は症候学の解説や難症例の解説であることが多く、「何を問題と定義するか」(フレーミング)の部分を論理的・具体的・平易に解説した書物は少ないのが現状です。
◆ 本書では臨床推論、中でも分析的診断推論の手法を一般化してわかりやすく解説。臨床推論の一般化された「型」をあえて示し、有効で効率的な情報取得の戦術,陥りがちな誤謬を紹介します。
◆ 臨床推論の「型」あるいは「理論」を知ることで、自身の推論を言語化できるようになり、ひいては診断が早く上達することが期待できます。
◆ 診断・推論に自信が持てない先生や研修医などに特にお勧めの、自身の推論スタイルを身につけるための1冊です!

じんべえ先生のステップアップ! 心臓麻酔
心臓麻酔の経験知、本っ気で伝えます
エキスパートのノウハウを学べるMS(麻酔に差がつく)ブックスシリーズの第2弾。心臓麻酔の基本的な流れから標準的な術中管理方法、そして困難症例まで、段階を踏んで理解できる5Stepで構成。エビデンスにもとづく麻酔の理論と著者の経験にもとづく臨床のコツを交えた明瞭な解説は統一感があり読み進めやすい。心臓麻酔デビューを終え、さらに踏み込みたい麻酔科医必読の書。「じんべえ先生」の呼び名の由来となったコラムも収載。
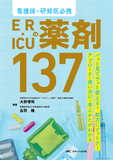
看護師・研修医必携 ER・ICUの薬剤137
【必須知識×実践知メガ盛りの“超”網羅本!】
各薬剤ごとの「1分でわかる必須ポイント」、アプローチ・使い分け・考えかたを解説した「もっとわかるパワーアップポイント」、投与前・中・後で時系列かつ一目でわかる「ナースの注意点」、使い方が実践的にわかる「ER・ICUでの典型的なケース」、パッとわかる各薬剤のまとめ表など、かゆいところに届く&実践を徹底的に追求。ビジュアル満載の誌面で、見たら絶対にほしくなる、渾身の1冊!

知らないと危ない!
新版 病棟でよく使われるくすり
ロングセラーにはわけがある!くすりの本なら信頼と安心のこの1冊
・ナースが病棟で出合う機会が多い基本薬に絞って紹介
・降圧薬・昇圧薬、抗不整脈薬・抗血小板薬、鎮痛薬、睡眠薬・抗不安薬、血糖降下薬、インスリン製剤、下剤、排尿障害治療薬、抗菌薬など17領域の最新薬を網羅
・「なぜこの薬が処方されるのか」「くすりの機序と特徴」「投与時の観察とケアのポイント」をわかりやすくイラストで解説
投与時、投与後の観察ポイント、ナースが行うべきケアが具体的にわかり、薬剤別に、一般名、商品名、剤形、用法・用量、重大な副作用、最高血中濃度到達時間、半減期を一覧表にまとめています

十二指腸癌診療ガイドライン 2025年版
十二指腸癌診療における本邦初のガイドラインとして作成された初版を4年ぶりに改訂した。腹腔鏡・内視鏡合同手術のCQなどを新たに追加した他、治療手技や薬物療法の進歩に伴い集積された最新のエビデンスを取り入れて、全面的にCQをアップデートしている。
十二指腸癌は希少癌に属するが、近年の診断モダリティの進歩により、発見される機会の増加が予想される。初版に引き続き、専門医のみならず十二指腸癌診療に携わるすべての臨床医に対し、広く十二指腸癌診療の指標を示した。
