
Medical Practice 2024年臨時増刊号
Q&Aでとことん答えます!予防医療の羅針盤~エビデンスと臨床をつなぐ渾身の88問答
Q&Aでとことん答えます!予防医療の羅針盤~エビデンスと臨床をつなぐ渾身の88問答 予防医療の『気になるけどよく分からない…』にQ&A方式で目の前の疑問にぱっと答え,エビデンスに基づき推奨される・されない(あるいは推奨が存在しない)予防医療とその根拠を丁寧に解説.興味のあるQ&Aをピンポイントで読んで学ぶのもよし,最初から読めば知識を総ざらいもできる.健診や検診,予防医療を「ある程度知っているし,実践もしている.でもよく分からないこともある」,そんな実地医家に届けたい珠玉の一冊!

医学のあゆみ295巻5号
第1土曜特集
エピゲノム編集の進歩と医療応用への道
エピゲノム編集の進歩と医療応用への道
企画:中村卓郎(東京医科大学医学総合研究所未来医療研究センター実験病理学部門)
・解析技術の進歩により,疾患病態におけるゲノム変異の役割が明らかになる一方で,ゲノム変異に依存しない病因としてエピゲノム異常の重要性が浮かび上がってきている.
・エピゲノム異常を主要な病因とする疾患は,先天性代謝異常,神経筋細胞の機能異常,がん,老化関連疾患など多岐にわたり,各分野の専門家が病態解明と治療法開発に取り組んでいる.
・本特集では,エピゲノム編集の基本技術の開発に携わっている研究者が最新のプラットフォームを説明するとともに,医療応用の基礎となるエピゲノム病態の概念に関する研究成果についても紹介する.

≪目で見る実験ノートシリーズ 5≫
バイオ実験イラストレイテッド⑤
タンパクなんてこわくない
好評の「バイオ実験イラストレイテッド」シリーズ!
SDS-PAGE,ゲルの染色と解析,ウェスタンブロッティング・免疫染色・ウェストウェスタンブロッティング,免疫沈降,抗体の取扱い方まで,いままで敷居の高かったタンパク質の解析を豊富なイラストで習得できます。
分子生物学実験にはじめて携わるすべての人のバイブルです。
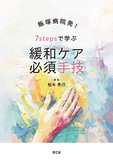
飯塚病院発!7stepsで学ぶ 緩和ケア必須手技
緩和ケアや在宅医療の現場で「手を動かす」機会は多く,苦痛緩和や症状コントロールのために避けては通れない手技がある.本書ではそのような手技の実際とコツを,飯塚病院で研鑽を積んだ経験豊富な執筆陣が伝授.「7steps」(適応と禁忌, 処置説明,準備,手技,成否判断,合併症,記録)の手順に沿った解説のほか,緩和ケアならではの配慮や工夫,経験談までを紹介し,手技が苦手な読者でも読めば自信をもって実践できる一冊である.

ここが知りたかった緩和ケア 改訂第3版
緩和ケアの定番書が改訂!意外に知られていない薬剤の使い方やケアのコツを,各項目冒頭の「概念図」でつかみ,その場で教えてもらっているようなわかりやすい解説が大好評.今版では新しい便秘治療薬,睡眠薬,鎮痛補助薬や悪液質の新薬のほか,前版からの臨床上の進歩を盛り込んだ.臨床家が日々直面する問題・疑問に答えた内容で,“今”の緩和ケアの現場で“本当に使える”実際書.

ジェネラリストのための
がん診療ポケットブック
がん診療は専門医だけでなく、ジェネラリストと連携しながら行っていく時代に
2人に1人ががんになる。今やがんは国民病である。世界的にも、がん診療は専門医だけでなく、ジェネラリストと連携しながら行っていく時代になってきた。本書は、がんに強い総合診療医・総合内科医、そして総合診療に通じたがん専門医・腫瘍内科医を目指す医療者に向けて編集。がん専門医・治療医、総合医とが手に手をとって、一緒になってがん患者を支えていくことができるような医療が実現することを期待して。

もっとよくわかる!エピジェネティクス
環境に応じて細胞の個性を生むプログラム
生物にとってエピジェネティクスはなぜ必要なのか,その本質を丁寧に解説した入門テキスト.分子メカニズムから関連する生命現象や疾患までを収載し,基本原理と分子・現象をつなぎ合わせて理解できる一冊.

増補版 周産期初期診療アルゴリズム
【妊産婦救命のカギは産科と救急の共通戦略!】Perinatal Critical Care Course(PC3:ピーシーキューブ)のコースガイド。情報を更新した増補版。周産期医療に携わる医療スタッフであれば誰でも直面する可能性のある妊産婦の急変対応に必要なスキルをトレーニングするとともに、シナリオを通して母児の救命を目指した治療戦略を学習する。

標準頸動脈エコー
テクニックと意義
◾動脈硬化性疾患の指標となる頸動脈の機能・形態の診断を、無侵襲かつリアルタイムに行える超音波エコー。その重要性は近年、ますます高まっています。
◾本書は頸動脈エコー測定の意義、頸動脈の病理、実際の手技、主要メーカーの最新機種など、必要な情報を網羅し、徹底解説。さらに臨床に即した練習問題も掲載しています。頸動脈エコー測定を行う先生の座右の書として親しまれてきたロングセラーが、待望の新装改訂です。
◾日本超音波医学会/日本脳神経超音波学会「超音波による頸動脈病変の標準的評価法2017」に準拠。

皮膚疾患超音波アトラス
皮膚疾患の超音波検査は,腫瘤の存在診断や,皮膚がんの切除範囲の決定,血管腫診断における血流の有無など,診断や治療方針の決定において非常に有用である.本書では,「腫瘤性病変」,「炎症性疾患」,「循環障害」など,超音波検査が有用な皮膚疾患を取り上げている.豊富な画像とともに著者ならではの診断のコツが随所に盛り込まれている.超音波画像と,臨床像,病理組織像の対応についても解説された,充実した内容の一冊.

リハビリテーションのための臨床神経生理学
臨床神経生理学は難しいわりに,リハビリテーションに直接使えない…と思っている人は多いのではないだろうか.本書は,臨床神経生理が疾病や障害の理解をより深め,実際のリハビリにとても役立つツールであることを示している.初学者や,苦手な人にも理解しやすいよう,少しでも耳慣れないワードには注釈を付け,平易に解説した.一読すればきっと,「これなら自分でもできる」と自信が付く.明日からのリハビリが変わる一冊だ.

日本肝臓学会肝臓専門医認定試験問題・解答と解説 第7集
日本肝臓学会の監修により,肝臓専門医認定試験の過去問題とその解答・解説をまとめた第7集.問題は日本肝臓学会誌『肝臓』に2022~2024年掲載のものから106題を収載した.第6集と同様に,疾患ごとに関連した知識が学びやすいような章立てとしており,専門医認定試験対策だけではなく,肝臓診療に必須の知識を再確認できる一冊.

ベッドサイドの臨床神経生理学
脳波検査や筋電図検査の原理や検査のコツといった基礎的事項から実際の疾患への臨床応用まで,臨床に役立つ臨床神経生理学のエッセンスを平易に解説したハンドブック.

スキンケアの科学
科学的なデータを示しながら,美容から疾患に関わるスキンケアまでを解説した!
豊富な図やわかりやすい解説により,皮膚の構造からスキンケアの必要性まで,すんなり学べる実用書!!
本書を読めば,スキンケアの大切さがわかるようになる.

≪産業保健と看護2025年春季増刊≫
保健指導ブラッシュアップBOOK
【行動変容につなぐコツをつかもう】面談の場で「水を飲んでも太るんです」と言われたらどう返しますか? この方の健診結果から何が読み取れる? ここから行動変容へと導くには? ケースを通して検査値の読み方とアセスメントのポイント、保健指導の流れと健康に関する最新情報を学びましょう。

医師と薬剤師が考える処方箋のつくり方
医師には処方権があり、薬剤師には調剤権があり、処方箋に疑しい点がある場合は疑義照会もできる。全ては患者のため。しかし現実にはこうした意思確認の方法は確立されていない。処方箋から見えてくる医師と薬剤師の思惑が「対話」を通じて明らかになる時、患者にとってより望ましい処方提案ができるはずだ。11の処方箋が導きだす本当の「解」
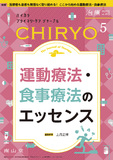
治療 Vol.105 No.5
2023年5月号
運動療法・食事療法のエッセンス
運動療法・食事療法のエッセンス さまざまな患者さんが訪れる外来診療において,限られた時間内で運動・食事について細やかな指導をするのは容易ではありません.また,理想論や一般論による指導では生活習慣の改善に取り組めない患者さんも多いです.本特集では,医師が忙しい外来診療のなかでも実践でき,患者さんも日常生活に無理なく取り入れられる,運動療法・食事療法のエッセンスをまとめました.評価や治療の進め方はもちろんのこと,患者さんをやる気にさせる秘訣も多数紹介しており,明日からの診療で実践したくなること請け合いです!

診断と治療 Vol.114 No.1
2026年1月号
【特集】脂質代謝異常最前線 治療の進化を追いかける!
【特集】脂質代謝異常最前線 治療の進化を追いかける!
脂質代謝異常の治療は今、革新の時代へ!
新薬が続々登場し、スタチンだけに頼らない選択肢が広がっています。
そして治療の目標は“数値改善”から“包括的な心血管イベント抑制”へ――
本特集では、最新の治療選択肢と実臨床での活用ポイントをわかりやすく解説いただきました。

重度四肢外傷の標準的治療
Japan Strategy
運動器(上肢・下肢)の重度外傷においては、確実に救命したうえで後遺障害を防ぎ、クォリティの高い治療を達成するためには「外傷再建外科医」による技術と治療戦略が求められる。本書は重度四肢外傷の初期治療に直面する可能性のある一般整形外科医・救急医ら“非専門家”を対象とした「非専門家編」と、エキスパートの判断を掘り下げた「専門家編」の構成に分け、非専門家・専門家双方にとって必読の“日本における重度四肢外傷の標準的治療戦略”を解説している。

麻酔科で使う薬の疑問58
研修医,若手麻酔科医が麻酔を学び,用いる上でつきあたる薬の疑問を集めたQ&A形式のガイドブック.「揮発性吸入麻酔薬はどうして効くか?」「プロポフォールが持続投与で使われる理由は?」といった作用機序にまつわる質問から,「揮発性麻酔薬と静脈麻酔薬はどのように使い分けるか?」「高齢者での薬物使用の注意点は?」といった臨床上の問いに至るまで幅広く解説した.各項目の末尾には「まとめ」としてポイントを要約.
