
がん治療副作用対策マニュアル 改訂第3版
化学療法,放射線療法などがん治療における副作用を詳細かつ実際的にまとめた好評マニュアル.今改訂では,新たな分子標的治療薬に特有の副作用,oncology emergency,肝炎ウイルスの再活性化など最新情報にアップデートし,支持・緩和療法も盛り込んだ.今版より2色刷りとなり,さらに見やすくデザインを一新.医師だけでなく,がん治療に携わる全てのスタッフにもおすすめの一冊.
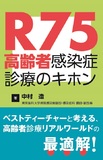
R75高齢者感染症診療のキホン
●超高齢社会の現在、R75(75歳以上の高齢者)を診ない日はないとおもいます。
●感染症診療の理想解が必ずしもゴールではない、高齢者の感染症診療。教科書通りに行かないときにどうするか?を考えた1冊です。
●コモンディジーズの模擬ケースシートを掲載。検査所見にまどわされない診療の流れがわかります。
●巻末綴じ込み付録「抗菌薬投与量一覧」「抗菌薬スペクトラム一覧」ほか

高齢者のための感染症診療
『類化性能』 と 『別化性能』、高齢者を前にしたとき、あなたなら、どちらを選ぶか。本書は、岩田健太郎氏・シリーズ総監修による超高齢者時代における新たな臨床指南書(【高齢者のための】シリーズ)の第1弾「感染症診療」編。高齢者ならではの「Difference Point」(フレイル、免疫低下、水分量、腎機能など)を提示し、外来、在宅、施設等における感染症診療の「リアルパール」を解説している。また、第4部「座談会」では、著者3名に集まってもらい、「2025年問題」や「HIV感染者の施設受入拒否」など、高齢社会を踏まえた本音トークが披瀝される。シリーズ第2弾は『高齢者のため漢方診療』。

トライアングルモデルで身につける
感染症診療の考え「型」
“患者背景からPitfall、今後のマネジメントまで”デキる医師の思考プロセス完全版
「トライアングルモデル」を使えば感染症診療の基本が身につく!患者背景からPitfall,治療後のマネジメントまでを見やすく,丸ごと解説.診療に自信がつく1冊.

小児内科2023年55巻増刊号
エキスパートが教える小児の薬物治療
エキスパートが教える小児の薬物治療

泌尿器科医,小児外科医,小児科医も使える
小児泌尿器疾患診療ガイドブック
泌尿器科医,小児外科医のみならず小児科医,新生児科医も対応するケースが多い小児泌尿器疾患を,腎・尿路の発達の理解から検査の落とし穴,診断のコツ,保護者とのコミュニケーション,そして手術手技に至るまでフルスペックで詳述した,類書のない教科書!
貴重な症例写真満載のカラー口絵8ページを設けたほか,本文にも写真・シェーマをふんだんに掲載し、初学者にもわかりやすくグラフィックに詳述した決定版テキストである.

胸部画像診断と呼吸器外科手術
画像診断を究めて手術力を向上させる
外科医と放射線科医が解説する,呼吸器外科手術に役立つ胸部画像診断のノウハウがつまった一冊.
診療経過に沿うべく術前と術後に分け,疾患ごとに画像診断を両科の医師が解説.
動画でも画像診断を解説した必携の書.

呼吸器外科ロボット支援手術〜達人への道〜[Web動画付]
入門書『呼吸器外科 ロボット支援手術実践マニュアル』(日本呼吸器外科学会・編)に続くロボット支援手術の実践書。
全国トップクラスの実績を誇る執筆者が,ワンランク上の手術手技とそのノウハウを余すところなく解説。また,豊富な囲み記事(“Advanced Techniques” “Essential Techniques” “DO NOT”)により,基本から高度な手技,してはいけない手技までをポイントを押さえて紹介する。
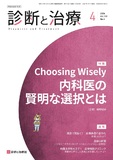
診断と治療 Vol.112 No.4
2024年4月号
【特集】Choosing Wisely 内科医の賢明な選択とは
【特集】Choosing Wisely 内科医の賢明な選択とは
患者との対話のなかで最適な診断と治療を選択するために,「Choosing Wisely」という国際的なキャンペーンが注目を集めています.Choosing Wiselyの概念から,内科領域における重要なトピック,臨床現場での問いについて紹介します.

動画で身につく!おさえておきたい皮膚科エコー50
皮膚疾患におけるエコーの“読み方”を、豊富な写真とシェーマで解説。皮膚腫瘍はもちろん、血管から関節病変まで網羅した充実の症例数! 病理・CT・MRIもふんだんに収載。“レーダーチャート”を用いた解説は、パッと見てもわかりやすい。「どうしてエコーを施行するのか?」といった、エコーで知りたいポイントも明確に記載しているので、実際の現場で役立つ。あなたの読影力を養う一冊。
【Web動画配信サービス】
●本書では、動画を計59本収載しています。
●各項目内のQRコードを読み込むことにより、お手持ちの端末(スマートフォン、タブレット)で視聴できます。
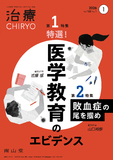
治療 Vol.108 No.1
2026年1月号
【第1特集】医学教育のエビデンス
【第2特集】敗血症の尾を掴め 難しい敗血症診療を解きほぐすためのエッセンス
【第1特集】医学教育のエビデンス
【第2特集】敗血症の尾を掴め 難しい敗血症診療を解きほぐすためのエッセンス 【第1特集】
医療現場では「教える」ことも重要な業務です.でも最適な教え方ってどんなものなのでしょうか? 医学教育学のエビデンスをもとに,働き方改革やAIなどの最新トピックもふまえて,一度,自分の場に合ったベストな教え方を学んでみましょう.
【第2特集】
敗血症はいつ出会うともわからない疾患で、常に対応を備えておく必要があります.どういうときに疑うのか,治療の方針の立て方はどうするか,全身管理を要点はどこか.大事な点をコンパクトにまとめた永久保存版ともいえる解説です.

助産師と研修医のための産科超音波検査 改訂第3版
産科超音波検査について,習得すべき優先順位の高い知識をわかりやすく解説.助産師と研修医を対象とした,産科超音波検査の実用的な知識を提供する必読の1冊.妊婦さんとのコミュニケーションツールとしても活用できるよう説明方法を紹介し,目次には,読者対象である,研修医,助産師向けのマークも示した.今版では新しいガイドラインを踏まえ,全般的によりわかりやすいよう画像と解説を見直すとともに,新しい検査法である経会陰超音波検査の項目を追加した.

臨床画像 Vol.38 No.10
2022年10月号
【特集】特集1:地力が伸ばせる 乳房MRI診断/特集2:免疫チェックポイント阻害薬の画像診断
【特集】特集1:地力が伸ばせる 乳房MRI診断/特集2:免疫チェックポイント阻害薬の画像診断

完全版 医師・薬剤師のための漢方のエッセンス
厳選した漢方処方103の基礎知識や処方の特徴から、実際にどのような訴えの患者に適するのか、症例を挙げて解説する。[病名から][症状から][処方から][生薬名][中医学用語]の索引を充実させ、様々な視点から検索ができるのも特長である。
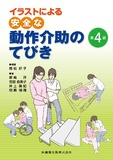
イラストによる 安全な動作介助のてびき 第4版
豊富なイラストで安全・快適な移動介助がよくわかる!
定評あるマニュアルが最新の知見により全面改訂!
●移動の際の介助に重点を置き,対象者の身体能力に留意し,安全を考慮した方法を多数のわかりやすいイラストを用いて具体的に解説.
●現代にマッチした道具,介助用具を最大限利用し,日常ですぐ役立つ技術や介助法を中心に紹介した実践的な内容.
●改訂第4版では,旧版までの記載を踏襲しつつ補充すべき内容を追加した.

いい顔ひろがる
医療的ケア児 ケアポケットブック
医療的ケアにかかわるすべての人たちへ
看護職,保育士,学校関係者,学生などの皆さんに届ける! 重症心身障害児のケアにも役立つ
「この子ってどんな子なのだろう?」
「どんなことに気をつけてケアすればいいのだろう?」
困ったときや疑問がわいたとき,パッとひらいて理解!
医療的ケア児や重症心身障害児のこどもたちは,在宅(地域)や医療機関,療育施設などで生活し,教育を受けたり,遊んだり,休息したりして過ごしています。
それぞれの場所で暮らすこどもたちにかかわるうえで必要な知識,ケアのポイント,コミュニケーションや遊びのバリエーションを学び,こどもたちの声を聞くことで,支援の輪がもっとひろがる一冊です。

医療的ケア児等コーディネーター実践テキスト
【医ケア児と家族に伴走するための実践書!】医療の発展により重症心身障害児とは支援内容が異なる多様な医療的ケア児たち。従来の福祉制度が使えない、成長に伴って適切な生活の場が見つからないなどといった多くの課題がある。それらに対しコーディネーターがまず知っておきたい基本の知識、そして、医ケア児本人と家族の抱える課題にどうアセスメントし、支援していくか事例やプラン例を用いて解説する。

神経難病の病態・ケア・支援がトータルにわかる
神経難病にはさまざまな種類があり、疾患ごとに経過や起こりうる症状が異なります。
そのため、看護においては、「疾患別」の視点、「症状別」の視点、そして「療養行程」の視点をあわせもつことが重要です。
長い経過のなかで変化していく療養生活課題(困りごと)にどう対応し、個々の生活歴や価値観などをふまえた「その患者さんにとって最善のケア」をどう提供するか、実践に基づいて具体的にわかりやすくまとめました。

イラストでわかる 生活支援のためのリハビリ・プログラム2
視界を広げよう
朝日新聞社説で「訪ねてみると、驚きの連続」と紹介された夢のみずうみ村デイサービスセンターのリハビリ・プログラムを豊富なイラストとともに一挙満載。
ICF(国際生活機能分類)に沿って、だれでも、どこでも生活の中で楽しくリハビリできる。第1巻「自分を広げよう」編では61、第2巻「視界を広げよう」編では60のプログラムを紹介する。
内容は活動を捉えやすいように、〈ねらい〉〈手順〉〈ちょっとしたヒント〉〈特にお勧めしたい方〉に分けて解説されている。また、活動の評価が一目で理解できる〈活動MILK成分表〉をそれぞれのプログラムに付した。
病院・施設で働くセラピスト・福祉関係者、生活の中でリハビリを楽しみたい本人にお勧めのイラスト解説集。

学習課題とクイズで学ぶ看護マネジメント入門 第2版
医療チームの一員として効果的な看護サービスを提供するためには,看護マネジメント(看護管理)の基礎概念を理解しておくことが大切です。厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン改訂版」では,看護実践における管理的側面についての到達目標(「安全管理」「情報管理」「業務管理」「薬剤等の管理」「災害・防災管理」「物品管理」「コスト管理」)が示されています。
本書は,看護マネジメントの基盤となる考え方から,上記の7領域はもとより,「医療の質評価」「地域包括ケアシステム」「身体拘束ゼロの推進」など注目度の高いキーワードまでを学べる初学者のための入門書です。豊富なイラストや事例がポイントをわかりやすく示し,クイズやミニテストも盛り込まれているので楽しみながら学べます。
