
ケアの基本がわかる
重症心身障害児の看護計画
ライフステージにそった乳幼児期から成人期まで
看護計画の立案に困まりごとはつきものです。
重症心身障害児に対してはどうでしょうか?
疾患ばかりに注意が向いて、生活に目がいかなくなっていませんか。
子どもたちは日常生活のなかで何に不便を感じ、苦痛を感じているのでしょう?
本書を参考に、重症心身障害児の看護計画を立ててみましょう!

作業療法ジャーナル Vol.59 No.8
2025年増刊号
■特集
就学・就労支援
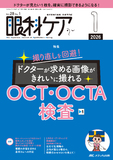
眼科ケア2026年1月号
2026年1月号
特集:撮り直しを回避!ドクターが求める画像がきれいに撮れるOCT・OCTA検査
特集:撮り直しを回避!ドクターが求める画像がきれいに撮れるOCT・OCTA検査 眼科に勤務するすべてのスタッフのレベルアップをサポート
『眼科ケア』は、眼科ナースや視能訓練士、眼科コメディカルなど、眼科に勤務するすべてのスタッフのレベルアップをサポートする専門誌です。
眼科ならではの診療と検査、ケアの最新知識や、明日からすぐに始められる工夫など、臨床で実際に役立つ情報が満載です。

臨床眼科 Vol.79 No.13
2025年 12月号
特集 みんな大好き! 涙道クリニックっ。
特集 みんな大好き! 涙道クリニックっ。 読者からの厚い信頼に支えられた原著系眼科専門誌。厳選された投稿論文のほか、眼科領域では最大規模の日本臨床眼科学会の学会原著論文を掲載。「今月の話題」では、気鋭の学究や臨床家、斯界のエキスパートに、話題性の高いテーマをじっくり掘り下げていただく。最新知識が網羅された好評の増刊号も例年通り秋に発行。 (ISSN 0370-5579)
月刊、増刊号を含む年13冊

眼科 Vol.67 No.12
2025年11月号
アイペイン:研究の最前線と日常診療
アイペイン:研究の最前線と日常診療
今号の特集は「アイペイン:研究の最前線と日常診療」です。アイペイン、すなわち「目が痛い」というよくある、そして原因が多岐にわたる訴え・症状について、研究の最前線やドライアイとの関係、ペインクリニック的視点からの解説、そして鑑別疾患まで、それぞれのポイントを解説いただきました。眼振の基本的知識や細菌性眼内炎に対するポビドンヨードを用いた治療に関する綜説も臨床にすぐさま役立つ内容です。ご一読ください。

眼科ケア2025年11月号
2025年11月号
特集:迷わず対応できる白内障検査・治療・ケア完全ガイド 手術の流れと手術介助も徹底解説!
特集:迷わず対応できる白内障検査・治療・ケア完全ガイド 手術の流れと手術介助も徹底解説! 眼科に勤務するすべてのスタッフのレベルアップをサポート
『眼科ケア』は、眼科ナースや視能訓練士、眼科コメディカルなど、眼科に勤務するすべてのスタッフのレベルアップをサポートする専門誌です。
眼科ならではの診療と検査、ケアの最新知識や、明日からすぐに始められる工夫など、臨床で実際に役立つ情報が満載です。

臨床眼科 Vol.79 No.12
2025年 11月号
特集 見てわかる!眼の感染症 最近のトレンド
特集 見てわかる!眼の感染症 最近のトレンド 読者からの厚い信頼に支えられた原著系眼科専門誌。厳選された投稿論文のほか、眼科領域では最大規模の日本臨床眼科学会の学会原著論文を掲載。「今月の話題」では、気鋭の学究や臨床家、斯界のエキスパートに、話題性の高いテーマをじっくり掘り下げていただく。最新知識が網羅された好評の増刊号も例年通り秋に発行。 (ISSN 0370-5579)
月刊、増刊号を含む年13冊

眼科グラフィック2025年5号
2025年5号
特集:近視進行抑制の最前線~子どもの眼を守れ!~
特集:近視進行抑制の最前線~子どもの眼を守れ!~ 「視る」からはじまる眼科臨床専門誌
高齢化に伴い、眼科の手術件数は増加し、患者さんの「見え方」の質への要求もますます高まっています。
検査機器も日々進化し、眼科医にはつねに知識のアップデートが求められています。
本誌は、なかでも眼科医の多くを占める開業医や、専門医を目指す若手医師を対象に、臨床で役立つ知識・技術を大きな写真やイラストでグラフィカルに解説。さらに、専用WEBサイトでは、手術や治療、検査などの動画を随時アップし、自身の知識習得、技術向上をさせたい眼科医のニーズに応えます。

イラストでまなぶ生理学[Web講義動画付] 第4版
生理学をまなぶなら、まずはこの1冊! 重要なポイントを解説した動画つき
看護学生・看護職のみならず、その他の医療系学生にも評判の高い生理学の入門書。たくさんのイラストを掲載しているため、気軽に楽しくまなべる。また、本文は重要度を3段階で示し、キーワードを色文字にして強調していることで学習の手助けとなる。第4版では押さえておきたい重要なポイントを著者みずからが解説した動画を収載。生理学の基本的事項を網羅的かつわかりやすく解説した、必携の1冊!
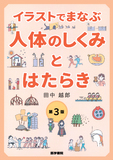
イラストでまなぶ 人体のしくみとはたらき 第3版
人体のしくみとはたらきを学びたいけれど、一体どこから手をつけていいかわからない…という人のための、気軽に楽しく学べる入門書。イラスト・漫画で比喩やデフォルメをしながら、臨床につながる知識もしっかり理解できるように解説しています。第3版はフルカラー化+理解を深める解説動画の付加で、さらにパワーアップしました。看護学生や医学生のみならず臨床で働く医療職からも「わかる!」と大好評の1冊です。

令和スタイル 鏡視下 胃手術のすべて
胃の腹腔鏡手術について,いま関心の高まっているリンパ節郭清・再建法の手技を取り上げ,次代の胃外科領域を牽引していくであろう全国のエキスパートに各手技のコツをイラストに投影して丁寧に解説していただいた。また,他書には載っていないロボット手術や腹腔鏡・内視鏡合同手術などの実践的テクニックまで紹介している。新時代に求められるスキルをコンプリートした必読の手術書。

看護 Vol.74 No.14
2022年11月臨時増刊号
総特集 看護職が健康的に働き続けるために 今こそ進めよう夜勤・交代制勤務の負担軽減
総特集 看護職が健康的に働き続けるために 今こそ進めよう夜勤・交代制勤務の負担軽減 特集1:看護職が健康的に働き続けるために今こそ進めよう夜勤・交代制勤務の負担軽減
看護職の就業場所があらゆる場へと拡大を続ける一方、超少子高齢化による生産年齢の減少、労働力の高齢化が進んでいます。このような中、安心・安全な看護を提供するための体制を維持していく上で、看護職が健康で働き続けられる持続可能な働き方の実現と職場環境の整備が喫緊の課題となっています。
看護職の多くは、365日24時間、患者の命をまもるために、夜勤・交代制勤務を担っています。夜勤は、サーカディアンリズムに反した働き方であり、その乱れが心身に不調をもたらします。また、昼間働く人との活動時間のズレにより、仕事と家庭生活で求められる役割葛藤が生じます。看護職ができるだけ長く健康で働き続けるためには、これらの不調や葛藤を最小限にするよう、夜勤・交代制勤務の負担軽減に取り組むことが求められます。本特集では、日本看護協会の夜勤・交代制勤務の負担軽減の取り組みや研究者による現状と課題の分析結果を示し、現場の活動や海外・他職種における実状を報告します。

≪消化器ナーシング 2023年秋季増刊≫
決定版! まるごと知りたい消化管
【この1冊で消化管のすべてがわかる!】解剖生理から病態生理、検査・治療、患者ケアまで、消化管にまつわる知識を網羅。消化管の治療や疾患に関わる機能障害、またリハビリテーションについての知識も取り入れ、「消化管」についての理解を深める1冊に。

小児外科57巻3号
Hirschsprung病
Hirschsprung病

INFECTION CONTROL(インフェクションコントロール)2025年5月号
2025年5月号
特集:清潔・不潔を交差させない!ベッドサイドにおける感染対策テキスト
特集:清潔・不潔を交差させない!ベッドサイドにおける感染対策テキスト
医療関連感染対策の総合専門誌『INFECTION CONTROL』は、すべての感染対策活動を全力で応援します。
「整理された最新情報が欲しい」というあなたのために、ピンチを乗り切る最新情報&指導ツールとともに、現場ですぐに生かせるトピックや領域で話題のテーマを分かりやすく解説します。
現場で活躍する執筆陣による、専門誌ならではの解説はICT・ASTメンバー必読!そのまま使えるイラストやパワーポイントなど、豊富なダウンロードサービスも充実です。
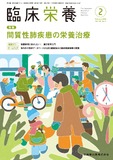
臨床栄養 148巻2号
間質性肺疾患の栄養治療
間質性肺疾患の栄養治療
●間質性肺疾患(ILD)は,肺の間質に炎症や線維化をきたす疾患群であり,特発性肺線維症(IPF)をはじめとした特発性間質性肺炎や,膠原病関連ILD,過敏性肺炎など原因や病態が多様な疾患を含む概念です.これらに共通する特徴として,疾患の進行に伴い,慢性的な呼吸機能低下,呼吸困難,食欲不振,身体活動量の低下などをきたすことがあり,低栄養やサルコペニアの併発がしばしばみられます.
●栄養障害はさまざまな呼吸器疾患において,呼吸困難の増強,QOLの低下や生命予後の悪化と関連することが明らかになりつつあります.ILD患者における栄養管理は標準化はなされておらず,医療現場では各施設の医師や管理栄養士の経験や個別対応に頼らざるを得ないのが現状です.
●本特集では,ILDにおける栄養療法の現状と課題を整理し,ILD患者の基礎病態から栄養状態の評価法,具体的な栄養療法介入の実践例,さらに多職種連携による包括的なアプローチまで,多角的な視点から各分野のエキスパートに解説をいただきました.呼吸器内科医,管理栄養士,リハ科医師など,それぞれの立場からの知見を共有することで,臨床に直結する実践的な内容をお届けします.
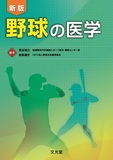
新版 野球の医学
月刊誌『臨床スポーツ医学』2015年(Vol.32)臨時増刊号として刊行し,大好評をいただいた「野球の医学」が書籍化.書籍化にあたって項目の追加ならびに大幅な加筆を行い,より実践的な書となった.標準的な治療はもちろんのこと,野球選手に特化したリハビリテーション・エクササイズの解説を豊富に掲載し,受傷者の競技復帰支援と障害の再発予防に必ず役立つ一冊である.

投球障害 予防&治療プラクティカルガイド
メディカル・スキル・コンディショニングの架け橋に
医療者(メディカルスタッフ)は野球現場の実際にそれほど詳しくなく,野球指導者(スキルコーチ,コンディショニングコーチ)は医学的知識が十分ではない。このギャップの橋渡しを目的に,投球障害にかかわる職種それぞれの知識・技術を,シンプルにかつポイントを押さえ,わかりやすい図や言い回しで解説。
後副題に示すように,Medical(医学的知識),Skill(投球動作の技術),Conditioning(体のケア,トレーニング,栄養学まで含めたコンディショニング全般)の三本柱で構成。

≪新 執刀医のためのサージカルテクニック≫
上肢
基本的な手技を学べる現場に即した手術書として好評を得た『執刀医ためのサージカルテクニック』シリーズの刊行から10年以上が経過し,手術手技・使用器具の進歩により大きく変更されている術式や,新たな術式も取り上げ,今の時代に即した手術内容で新シリーズとして刊行。
本書『上肢』では,上肢手術の基本的な手技について,手術の流れとペース配分が理解しやすいように,手術を「起承転結」の4段階に分けて解説している。特に執刀医になりたての整形外科医が経験することが多い疾患について,観血的整復固定術(ORIF),鏡視下手術,骨折の固定術,縫合術など,豊富なイラストでわかりやすく紹介。また,場面ごとに,是非とも継承したいテクニックや思わぬアクシデントを招きそうな注意点,覚えておくべき解剖学的ポイントなど,最前線で活躍する医師が実際に経験して得た知識を「アドバイス」として随所に掲載。
執刀医となったその日から即役立つ,手術で実力を出し切るために必携の一冊!

学習指導案ガイダンス 第2版
看護教育を深める授業づくりの基本伝授
授業設計に悩む看護教員のための教授法の定本、待望の改訂!
授業設計に悩む看護教員のための好評ガイドブック、待望の改訂! 教育現場で用いる学習指導案とワークシート(カラー付録)の意義と作成方法、授業での実際の運用まで詳らかに解説。第一線の教育学研究者の知見からその内容を補強している。コロナ禍以降に発展したICTを用いた授業づくりにも対応。学習者を中心とする「主体的・対話的で深い学び」を基盤とする、看護を教える人必携の書。
