
整形外科 SURGICAL TECHNIQUE(サージカルテクニック) 2016年4号
2016年4号
特集: ここが知りたい! 手指ピンニング手術 コツとポイント
特集: ここが知りたい! 手指ピンニング手術 コツとポイント 整形外科領域の「手術」を徹底して取り上げる専門誌『整形外科サージカルテクニック』
教科書には載っていない手術のコツ、ピットフォール、リカバリー法が満載。各手術のエキスパートの技と知恵を凝縮した「手術が見える・わかる専門誌」です。
本誌で取り上げた手術動画を専用WEBページでチェックでき、誌面と動画でしっかり確認できます。

救急・集中治療領域における緩和ケア
救命ができても死が避けられなくても、がんだけではなく心不全でも外傷でも、緩和ケアニーズは存在する。救急外来やICUにおける緩和ケアニーズのアセスメント、患者・家族とのコミュニケーション、苦痛症状に対するケア──時間が限定された救急外来やICUだからこそ、提供できる緩和ケアがある。「救命か、緩和か」ではなく、「救命も、緩和も」かなえるために、領域を越えて編まれたはじめての書。

心臓の機能と力学
苦手意識を持つ人が多い心機能.そんな“心機能アレルギー”の方々へ送る,アレルギー克服のための入門書.ひとつひとつ,喩えも使ってわかりやすく解説することで,心機能・心力学が正しく分かる構成となっている.心エコー,MRI,CTなどの画像診断または心カテで心機能を評価したい人,血行動態や心機能を理論的に理解して心不全の診断・治療を行いたい人など,心機能をこれから学ぶ人や自信がない人はまず手に取ってほしい1冊.

2年目からのICU看護 気道・呼吸・鎮静ケア
いつもの看護の根拠がわかる!
もっとケアを深めたいICUナースのために,絶対必須の意識・気道・呼吸・リハの看護の根拠や考え方をやさしく解説.よりよい看護ケアに役立つ,患者さんの評価や実践のポイントがわかる.後輩指導の参考にも.

眼疾患アトラスシリーズ 第2巻
後眼部アトラス
「眼科専門医認定試験出題基準」および「日本眼科学会専門医制度眼科研修医ガイドライン」で扱われている「網膜」「脈絡膜」「硝子体」「視神経」「緑内障」領域の疾患の眼底写真・造影写真・OCT・電気生理等、必要な画像情報を網羅。
眼科専門医認定試験の臨床問題対策としても最適です。
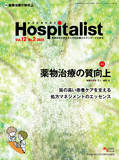
Hospitalist Vol.12 No.2 2024
2024年2号
特集:薬物治療の質向上
特集:薬物治療の質向上

CT縦横無尽
各部位のスキャンテクニックはもちろん,アーチファクト低減技術,高精細CT,デュアルエナジーCT,フォトカウンティングCT,画像再構成アルゴリズム,三次元画像処理,ワークステーションの特徴,各メーカーのフラグシップモデルなどを紹介。
撮像現場と読影現場のどちらでも役立つ記載をカラー写真とともに満載した,圧倒的なボリュームで贈るCTの新たな手引書。

解剖学的視点で解き明かす 女性骨盤手術
婦人科領域の腹腔鏡下骨盤臓器手術を安全におこなうための指南書。腹腔鏡下手術の進歩によって得られた詳細な解剖構造を踏まえ、胎生解剖の視点から複雑な膜・層構造や臓器の相互関係を正しく捉えた「外科解剖学」に立脚し、骨盤臓器手術の理論と技術を、豊富な写真・シェーマと卓越した技術を有する著者ならではの分かりやすい語り口でまとめた。

周産期医学49巻2号
【特集】新生児黄疸を再び考える
【特集】新生児黄疸を再び考える
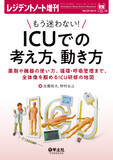
レジデントノート増刊 Vol.25 No.11
【特集】もう迷わない! ICUでの考え方、動き方
【特集】もう迷わない! ICUでの考え方、動き方 「ICUとはまずどんなところか」という最初の疑問から,薬剤や機器の使い方,循環・呼吸管理まで,集中治療の勘所をわかりやすく!研修を有意義に過ごすために押さえておきたい必須の知識が満載の1冊です.

呼吸器ジャーナル Vol.72 No.4
2024年 11月号
特集 今こそ知りたい! 過敏性肺炎の“勘どころ”
特集 今こそ知りたい! 過敏性肺炎の“勘どころ” 呼吸器専門医を目指す若手の呼吸器内科医・研修医を主な対象とした季刊誌。 臨床に役立つ最新の知見を、第一線で活躍する経験豊かな執筆陣が解説する。 (ISSN 2432-3268)
年4冊刊(2月・5月・8月・11月)

シンプルでわかりやすい 薬歴・指導記録の書き方 第2版
薬歴・指導記録で重要なことは「人に伝わる」記録であることです.さらに「簡潔で」「わかりやすく」書く必要もあります.書き方の理論やルールにこだわり,悩んだり振り回されてはいけません.POSやSOAPはツールとして使いやすいようにアレンジしましょう.本書はその秘訣を盛り込んだ,新人からベテランまでお役立ていただける一冊です.改訂2版では,「施設間情報連絡書」などの新規項目を追加し,初版と基本的なコンセプトや内容は変えずに症例を中心に変更して違う切り口で薬歴・指導記録を記載するコツを紹介しています.

腎と透析99巻5号
内因性調節因子と治療薬による体液量コントロール
内因性調節因子と治療薬による体液量コントロール

臨牀透析 Vol.41 No.13
2025年12月号
■ 特集:透析患者の口腔合併症と口腔ケア
■ 特集:透析患者の口腔合併症と口腔ケア
透析患者特有の合併症や病態が,口腔環境に及ぼす影響や病態については,知られていないことが多い.透析患者の口腔環境悪化は,摂食障害や低栄養に直結するほか,細菌や真菌感染症の元凶となることから,患者の口腔観察や口腔ケア,歯科との連携が重要となる.本特集では,透析に関わる歯科関係者の諸氏に執筆依頼し,多くの透析医療スタッフが,基本的なことから,できるだけ理解しやすいようにご配慮いただいた.

シンプル理学療法学シリーズ
小児理学療法学テキスト 改訂第4版
理学療法士がかかわる小児疾患について,概要とその理学療法についてわかりやすく解説したテキスト.小児理学療法に欠かせない定型発達と姿勢反射などの基本知識から,脳性麻痺と二分脊椎症・進行性筋ジストロフィーなど運動機能発達障害を呈する代表的な疾患を収載.ケーススタディを豊富に掲載し,基礎から臨床の概要までを学習するのに最適な構成.

≪ペリネイタルケア2024年夏季増刊≫
New 乳房ケア・母乳育児支援のすべて
【母乳育児支援の必携書がパワーアップ!】大好評を博した2017年夏季増刊から、最新のエビデンスやニーズに沿ってアップデート。母乳育児支援に関わる助産師必携の保存版!第1章では乳房の生理やトラブル対応を、第2章では妊娠期・産褥期・卒乳期のケアや、母子に沿った支援方法を、第3章では7団体の支援の特徴を紹介する。

内科初診外来 ただいま診断中!
本書では、内科の初診外来におけるコモンな症候や症状で診断が想起できない場合、どのような戦略的アプローチを行うべきかについて、Semantic Qualifier, 解剖学的アプローチ、Pivot and Cluster Strategyなど、具体的な診断戦略を挙げながら分析的かつ、わかりやすく解説。他の成書ではあまり扱わないテーマや手法による診断推論も展開され、研修医のみならず、専攻医〜指導医レベルの医師にとっても実践的に役立つ書となっている。

産業医はじめの一歩
「働く人・企業」のニーズをつかむ!基本実務の考え方と現場で困らない対応
産業医ビギナーのためのわかりやすい入門&実践書.ベースの産業医術とその応用を伝授.「面談での対応に自信がない」「衛生委員会をうまくサポートするには」「職場に合った提案をしたい」など業務の困ったを解決!

「Rp+レシピプラス」年間購読(2026年)
南山堂発行の季刊誌「Rp.+レシピプラス」の2026年の年間購読(電子版)になります. 毎号,保険薬局薬剤師の臨床現場で注目されている薬や疾患を取り上げ,「やさしく・くわしく・強くなる!」をコンセプトに解説.基礎的な疾患・検査の知識を確認しながら,患者背景を理解し,「なぜ?」を解消することで臨床力を磨けます.オールカラーでみやすい人気の季刊誌.

≪入門・診療報酬の請求≫
入門・診療報酬の請求 2024-25年版
点数表の全要点解説と算定事例82
診療報酬請求の初級から上級まで確実にステップアップできる実践的入門書
★2024年診療報酬改定に完全準拠。初級から実践応用までのすべてのノウハウを,わかりやすく丁寧に解説した算定・請求の完全入門書。具体的な算定事例,レセプト記載例に沿って解説しているため,実務や試験に役立つ実践知識が確実に身につきます。
★2色刷の見やすいレイアウトに,図表・算定要件一覧表・算定事例・レセプト記載例も豊富で,わかりやすさ抜群!! 「練習問題」も多数収載しているので,確実に実力がアップします!!
★2024年診療報酬改定に準拠し,改定による新設項目と変更部分についても解説しています。
★診療報酬点数表の構成に沿って,①点数表の基礎知識,②診療報酬算定のポイント,③実際の算定例(82事例),④レセプトの記載例,⑤特に注意すべきチェックポイント――を,実例に即して具体的にわかりやすく解説しています。また,算定要件も一覧表にまとめてあるので簡単に理解できます。
★これから診療報酬請求を学ぼうとする初級者に最適です。また,診療報酬の難解ポイントにまで踏み込み,要点を凝縮し,実践的に解説してあるので,初級者から中級者,上級者へのステップアップの書としても有効です。『診療点数早見表』の該当ページも明記してあるので,併せて利用すれば便利です。
