
四訂 精神保健福祉法の最新知識
歴史と臨床実務
精神保健福祉法のほか、総合支援法、医療観察法といった関連法を含む精神科医の実務に必要な諸制度、指定医のケースレポートの書き方に至るまで広く解説。医療保護入院の見直し、入院者訪問支援制度創設、精神科病院における虐待防止など、令和6年度施行の改正法に対応。

≪新戦略に基づく麻酔・周術期医学≫
麻酔科医のための周術期危機管理と合併症への対応
周術期における安全対策・危機管理は,麻酔科医が日常臨床で常に直面する問題であり,現在の医療現場では最も基本となる重要事項として熟知していなければならない.本書では,災害時での対応にも言及して,安全を確保するための基本を簡潔にまとめ,さらに,危機的状態が予想される重篤な合併症・偶発症について,実臨床での対応を具体的に解説した.麻酔科医必携の一冊.
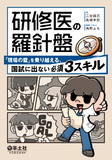
研修医の羅針盤 「現場の壁」を乗り越える、国試に出ない必須3スキル
臨床研修で誰もが必ず経験する悩み・失敗をコミュニケーション,臨床推論,意思決定の3つのスキルを身に付けて解決!国試と実臨床のギャップを埋めて,スキル取得のポイントや考え方,スキルの活用法がわかります!

LOH症候群(加齢男性・性腺機能低下症)診療の手引き
現代社会において、LOH症候群(加齢男性・性腺機能低下症)の適切な診断と的確な治療の重要性が高まっています。
LOH症候群の診療に関わる医療従事者のみならず男性の更年期症状に関心のあるすべての方々へ。
是非、ご活用ください。

精神医学 Vol.62 No.5
2020年05月発行(増大号)
特集 精神科診療のエビデンス 国内外の重要ガイドライン解説
特集 精神科診療のエビデンス 国内外の重要ガイドライン解説 -

新版 看護に役立つ検査事典
主要な生体機能検査、検体検査について、検査の意味・方法から、看護に活かす見かたまで、わかりやすく解説した検査の事典。

≪ハートナーシング2024年冬季増刊≫
ナースのためにみんなで教える補助循環
【多職種の実践的な解説で疑問・不安が解決!】管理中の患者さんのケアに自信をもちたい、機械が苦手で近寄るのも怖い、モニターのどこを見たらいいかわからない……など、「補助循環」について基礎から解説します。臨床に即したQ&Aや症例解説も豊富で、補助循環に関わる全てのナースにおススメの1冊!

Clinical Engineering Vol.34 No.4(2023年4月号)
臨床工学ジャーナル[クリニカルエンジニアリング]
【特集】新しい補助循環
【特集】新しい補助循環 新たな補助循環として臨床使用され始めている,補助循環用ポンプカテーテル・体外設置型VAD・植込み型VADについて,原理構造・適応や装着手術手技,装置の操作・管理方法を解説。本号で臨床の新スタンダードを押さえよう!
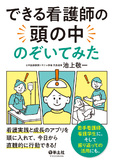
できる看護師の頭の中のぞいてみた
看護実践と成長のアプリを頭に入れて、今日から直観的に行動できる!
「できる看護師はどう考えて,どう行動しているのか?」をとことん見える化しました!本書のフレームどおりに実践するだけで,できる看護師の頭(臨床判断能力や対応力)と心が身につきます.若手看護師,看護学生におすすめ! 〔付録の特典PDF(教育理論の追加解説)は看護教育にもご活用ください〕

臨床外科 Vol.80 No.8
2025年 08月号
特集 痔核治療のすべて〔特別付録Web動画付き〕
特集 痔核治療のすべて〔特別付録Web動画付き〕 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 (ISSN 0386-9857)
月刊、増刊号を含む年13冊
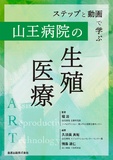
ステップと動画で学ぶ 山王病院の生殖医療 第2版
山王病院リプロで実際に行われている一般不妊治療、生殖補助医療(ART)をステップ形式で具体的に紹介。注意点やコツも併せて解説しているため、手技のポイントが一目でわかる。
PGT-AやTh1/Th2、ERA、EMMA、ALICEなどの新たな検査方法や、PRP療法、社会的卵子凍結といった最新のトピックも取り扱う。
不妊診療に携わる医師、看護師、胚培養士はぜひマスターしたい一冊。
書籍内のQRコードから手技の動画を視聴できる。
初版「山王病院 不妊診療メソッド」からタイトルを変更した。

消化器外科2025年10月号
オペレコ・手術イラストの作成法教えます!
オペレコ・手術イラストの作成法教えます! 外科医にとって必須の作業である手術記録・オペレコ作成。より効率的に、効果的で、教育的で、魅力的なオペレコを作成するために、その具体的方法とこだわりを伝授。オペレコには、外科医の技術と情熱が詰まってる。

臨床外科 Vol.78 No.10
2023年 10月号
特集 肝胆膵外科 高度技能専門医をめざせ!〔特別付録Web動画付き〕
特集 肝胆膵外科 高度技能専門医をめざせ!〔特別付録Web動画付き〕 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 (ISSN 0386-9857)
月刊、増刊号を含む年13冊

こだわる! 神経ブロック 下肢
下肢神経ブロックについてエキスパートの実践テクニックをあなたのものに!
神経ブロック麻酔は骨盤や下肢の手術において不可欠な技術であり,その効果的な実施は術後の患者の快適性や回復速度に直結します.
歴史を理解し,多面的に適応を判断し,自分の得意な手技だけに固執することなく,より良い方法を探求する指導医の目線と手技を詳しく学べる1冊.
整形外科医による執刀医の視点での下肢手術術式の解説により,現場でよりよい麻酔の実践につながる!
解剖学的構造や超音波画像の詳細な解説と症例に基づく実践的なアプローチが,下肢神経ブロックの初心者からベテランまで臨床現場で即座に活用できる内容.
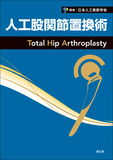
人工股関節置換術
日本人工関節学会による,本邦の人工股関節の臨床,研究成果を集大成したものである.人工股関節の歴史から,解剖,バイオメカニクス,手術手技,術後成績,難症例への対処,合併症対策まで,本邦で積み上げられた研究内容を俯瞰し総括した内容となっている.若手,非専門医なども含む全整形外科医必読の実践書

Hospitalist Vol.11 No.4 2023
2023年4号
特集:STI/HIV
特集:STI/HIV

ポケット呼吸器診療2024
【2024年版のポイント】
・特別付録→電子書籍版(PDF版)の無料ダウンロード権が付いています。
※1冊につき1ライセンスです。ライセンス使用済みの中古書では利用できません。
・「2024年版になってどこが変わったの?」がわかります→改訂部分を色付け
・各種ガイドラインの改訂に対応など→最新情報にアップデート
【本書のポイント】・臨床で使える小さなマニュアル(新書版)
・呼吸器疾患の診療手順/処方例/診療指針
・ガイドラインを掲載
・患者さんへの病状説明のポイント、よくある質問の解答例も
◆著者より
このマニュアルは「できるだけコンパクトかつ有用な安い書籍」を目標にしていますが、限りなく最新の文献に基づいた疾患情報を提供できるよう心がけています。実臨床で使用することを最優先に、不要な贅肉を極限までこそぎ落としているつもりです。

左心耳閉鎖のすべて
本邦初の経皮的左心耳閉鎖術に関する参考書です。
SHD、不整脈のエキスパートによる執筆でWATCHMANの最新情報も網羅!
是非、ご一読ください。
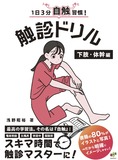
触診ドリル 下肢・体幹編
1日3分自触習慣!
触診ドリル。
それはペンもノートもいらない、究極の学習法。
■触診は大事!...だけど...
時間がない...
練習相手がいない...
場所がない....
■そんな人におすすめな学習法が“自触(じしょく)”
自触とは、『 “自”分の身体を“触”診する学習法』です。
自触は触れる感触・触れられる感触を同時に体感できるため、他人に対して触診するよりも効果的に学習できます。 ・
■自触の3つのメリット
いつでもどこでも気軽にできる。
触れる・触れられる感触を同時体感できる。
必要なのは自分の身体と手だけ。
➡1日3分の自触習慣で触診マスターに! ・
【本書の3つの特徴】
いつでもどこでも効率よく練習できる
自触は1人でどこででも行うことができます。また、他人を触れるより、自分自身を触れるほうが、対象が良く分かる為、効率的に練習できます。自分自身を触れるのに遠慮は要りません。どんどん触れていきましょう。
専門用語を使わない分かりやすい文章構成
本書では、可能な限り解剖学用語や運動学用語を知らないでも肢位や運動が理解できるような文章構成にしています。そのため、初学者でもイメージしやすく、楽しく読めるように工夫しています。
臨床応用につながる知識も多数掲載
本書では各部位の初めに、対象部位の機能解剖学と臨床との接点についての解説があります。そのため、習得した触診技術をどのように臨床に応用するのかをイメージしながら練習できるので、効果的に学習できます。

Hospitalist Vol.10 No.3 2022
2022年3号
特集:ホスピタリストのための画像診断(2)脳脊髄編
特集:ホスピタリストのための画像診断(2)脳脊髄編
