
行動経済学で学ぶ感染症
あなたの行動はあなたが決めたの? 医療現場の“あるある”が満載。その解決策は!?
あなたのその行動は、本当にあなたが決めているの? 医療現場の“あるある”を紹介しながら、「自分」だけでなく、「あの人」に行動を変えてもらうためのコツ&ヒントを教えます! 人が無意識にどう動くのか、気持ちよく行動してもらうにはどうするか、自分の無意識の行動をどう自覚すればよいのか。本書では行動経済学の考え方を利用しながら、医療職に必須の感染症の知識を楽しく学ぶことができます。

VisualDermatology Vol.23 No.6(2024年6月号)
【特集】太陽光線と皮膚
【特集】太陽光線と皮膚 光皮膚科学について、最新の話題から各論までをお示しし、光皮膚科学関する最新の知見を得ていただける、若手皮膚科医から第一線で活躍する医師にもおススメの特集!

Visual Dermatology 2020年臨時増刊号
皮膚疾患の診断に至るプロセスに必要な検査の内,皮膚科医が熟知しておくべき生体検査を取り上げ,その有用性と限界を症例をあげながら,どのように用いると有用かを解説.
患者さんへの検査説明にも使える便利な1冊.

爪 【改訂第2版】
基礎から臨床まで
爪の基礎的な知見、ならびに現在の爪疾患に関する臨床的知見・治療法をまとめたロングセラーテキストの改訂版ついに刊行!50年にわたり爪疾患の原因や治療法に関する研究を行う爪のスペシャリストの決定版。陥入爪・巻き爪に対する多くの治療法の登場,治療可能となった厚硬爪や爪甲鉤彎症についても追加し、本邦美容業界のジェルネイルの普及もふまえて解説・文献の追加を行った。QOLの改善に役立つ、関係者必携の書。

臨床泌尿器科 Vol.78 No.6
2024年 05月号
特集 泌尿器科医のための核医学 正しく理解して潮流に乗れ!
特集 泌尿器科医のための核医学 正しく理解して潮流に乗れ! 泌尿器科診療にすぐに使えるヒントを集めた「特集」、話題のテーマを掘り下げる「綜説」、そして、全国から寄せられた投稿論文を厳選して紹介する。春に発行する書籍規模の増刊号は、「外来」「処方」「検査」「手術」などを網羅的に解説しており、好評を博している。 (ISSN 0385-2393)
月刊、増刊号を含む年13冊

明日からの診療を変える プライマリ・ケア/総合診療の最新論文70
著者が厳選した論文を日々の診療に役立てるための実践的な手引書
プライマリ・ケアや総合診療の分野で,診断に難渋するさまざまな症状や,社会的背景のことなる患者に相対するとき,既知の知識やスキルでは対応ができず困ることがある.それを解決する手段としては,世界中で同じように困っている医療者が発信し続けている論文を読むことだ.本書は,そのような考えをもつ著者が自ら選んだ最新の論文について,背景や結果などを踏まえて,要点をわかりやすく解説した実践的な書となっている.

新耳鼻咽喉科学 第12版
1967年に初版を発行して以来,わが国の耳鼻咽喉科領域のバイブル的役目を果たしてきた本書は,時代に即して改訂を重ねてきた.今回の改訂では,図表の見直しを行い,最新の知見を加え大幅な改訂を行った.総論では解剖や生理,検査法などが丁寧に書かれており,各論では各疾患の診断や治療などについて多くの図表を用いて簡潔にわかりやすくまとめられている.医学生や研修医のみならず,専門医にも手にしていただきたい書である.

≪プラクティス耳鼻咽喉科の臨床 4≫
めまい診療ハンドブック
最新の検査・鑑別診断と治療
めまいは様々な疾患により生じる空間識の異常で発症する.医師はその多彩な原因疾患と病態を把握し,最新の診断基準とエビデンス,科学的知見に基づき診療にあたらなくてはならない.本書では,めまい診療の最近の進歩を第一人者の執筆により網羅し,臨床の最前線で活躍する耳鼻咽喉科専門医だけでなく、専門医を目指す専攻医にも手元に置いてすぐに参考になるハンドブックとなっている.

帰してはいけない外来患者 第2版
やっぱり帰さなくてよかった! 第2版では外来診療に求められる「臨床決断」「診断エラー」「28症候」の知識をブラッシュアップ。「帰宅して様子を…」と言いたくなる47症例はすべて書き下ろし。「緊急性、重篤性、有病率、治療可能性から決断する!」「秒単位、突発で持続する症状は危ない!」「増悪傾向の症状はピークアウトするまで目を離さない!」など、外来で使えるgeneral ruleが満載。外来研修にも最適。

対話でリカバリーを支える
ストレングスモデル実践活用術[Web動画付] 第2版
対話を通じて、リカバリーに向かうストレングスをともに見出すための1冊
ストレングスモデルは個人がもつ強み・希望や、その人を取り巻く環境の強みに着目し、ケアの資源として活かす支援方法。当事者中心のこのモデルを真に実践し活用するためには、わかりやすい強みに着目して弱点から目をそらすのではなく、当事者と対話するなかで、本人の言葉を通じてストレングスを理解する必要がある。著者オリジナルのストレングス・マッピングシートを使った対話の様子を、付録動画として収載した。

はじめてのヘンダーソンモデルにもとづく精神科看護過程 第3版
ヘンダーソンモデルにもとづいて精神科の看護過程をわかりやすく解説した好評書第3版
●ヘンダーソンの14の基本的欲求項目に3項目を加えた17項目によるアセスメントによる「患者主体型看護計画」の立案を具体例を用いて詳細に解説.
●第3版では,POS(SOAPIE)を用いた看護記録の実例を記載するとともに,第5章「学生のための看護計画立案モデル」に「うつ病患者の看護展開」を追加した.

放射線治療学 第7版
最新の放射線治療の知見・知識を体系的に整理できる好評書籍.改訂7版では全国各地から当該分野の新進気鋭が執筆陣として参画,新章「標的核医学治療」「臨床小線源治療」を新設し,最新情報をアップデートする.

脳神経外科 Vol.52 No.5
2024年 09月号
特集 くも膜下出血のニューフロンティア 病態の再考と治療の進化〔特別付録Web動画〕
特集 くも膜下出血のニューフロンティア 病態の再考と治療の進化〔特別付録Web動画〕 「教科書の先を行く実践的知識」を切り口に、脳血管障害、脳腫瘍、脊椎脊髄、頭部外傷、機能外科、小児神経外科など各サブスペシャリティはもちろん、その枠を超えた横断テーマも広く特集します。専門分野・教育に精通し第一線で活躍する脳神経外科医を企画者・執筆者に迎え、診断・治療に不可欠な知識、手術に生きる手技や解剖を、豊富な図と写真を用いて解説します。さらに、脳神経外科領域の最新の話題を取り上げる「総説」、手術のトレンドを修得できる「解剖を中心とした脳神経手術手技」も掲載します。 (ISSN 0301-2603)
隔月刊(奇数月)、年6冊
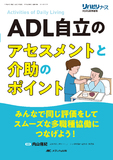
≪リハビリナース2025年秋季増刊≫
ADL自立のアセスメントと介助のポイント
【ADLの評価と介助を実践できる!】
回復期リハビリテーション病棟では多職種が協働して患者さんとかかわるため、ADLのアセスメントは看護師にとって必須のスキルである。本増刊では、多職種が同じ基準でADLの評価ができることを目標に、ADLごとの評価・アセスメントと実際の看護のポイントまで解説する。

図解 誤嚥を防ぐポジショニングと食事ケア―食事のはじめからおわりまで 【第2版】
摂食嚥下障害への決め手
医療現場、介護現場で適切な食事ケアができる見てわかる誤嚥を防ぐポジショニング
少子高齢化が進行し、誤嚥性肺炎や窒息、低栄養、フレイルなど“食”に関する健康問題が山積するなか、健康寿命をいかに延ばすのかが大命題になっている。
本書では健康回復やQOLの向上に寄与する適切なポジショニング、口腔ケア、呼吸ケア、食事介助、リスク管理など、“ケアされる人”の食べるよろこびにつながる食事ケアの深化した技術を、理論的根拠や事例とともにわかりやすく紹介。病院や施設の看護師をはじめとする医療スタッフ、在宅での介護者などすべての“ケアする人”に向けて改訂された第2版。

今日からできる!
改訂版 摂食嚥下・口腔ケア
●急性期~リハビリテーション期まで、患者状態を維持・向上させるために、ナースが留意したいことを、くまなく解説。
●患者さんや家族の「食べたい」「食べてもらいたい」を支え、対応できるようになるための1冊。
●患者さんの状態に応じた摂食嚥下ケアや、効果的に取り入れられる口腔ケアについて、最新の知見を加えた改訂版。
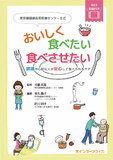
東京都健康長寿医療センター方式
おいしく食べたい食べさせたい
誤嚥が心配な人が安心して食べられるケア
口から食べることは、高齢者の生活の質(QOL)を高める、免疫機能を高める、健康維持に重要な役割を果たしている腸管細菌叢を健全に保つなど効果があります。
本書は、東京都健康長寿医療センターで長年培ってきた誤嚥のリハビリテーションに関する経験と工夫を、わかりやすい文章と動画15分で解説。
病気や加齢により嚥下機能の低下した高齢者が、安心して口から食べられるポイントやコツが満載です。
栄養指導を行う看護師、介護スタッフ、誤嚥が心配な高齢者のご家族の方にお薦めです。

がんサポーティブケアのための漢方活用ガイド
がん診療において出現するさまざまな症状に対して漢方を活用するために,漢方やがんサポーティブケアに関する基礎知識をふまえながら,それらの症状に対する漢方の使用法や主要な漢方製剤について,症例・エビデンスを交えながら解説.がんサポーティブケアに漢方を取り入れたいと考える医療者必携の一冊.

LiSA Vol.27 No.11 2020
2020年11月号
徹底分析シリーズ:出血治療戦術 適応外の製剤も駆使して止血を図る/症例カンファレンス:心機能が極度に低下した透析患者に対する大腿切断術/ 快人快説:麻酔メカニズム研究シリーズ(4)先生,全身麻酔中は眠っているだけなんですか?
徹底分析シリーズ:出血治療戦術 適応外の製剤も駆使して止血を図る/症例カンファレンス:心機能が極度に低下した透析患者に対する大腿切断術/ 快人快説:麻酔メカニズム研究シリーズ(4)先生,全身麻酔中は眠っているだけなんですか? 徹底分析シリーズ:出血治療戦術 適応外の製剤も駆使して止血を図る
症例カンファレンス:心機能が極度に低下した透析患者に対する大腿切断術
快人快説:麻酔メカニズム研究シリーズ(4)先生,全身麻酔中は眠っているだけなんですか?

臨床画像 Vol.41 No.8
2025年8月号
【特集】基本的なIVRの手技のおさらい−故きを温ね新しきを知る−
【特集】基本的なIVRの手技のおさらい−故きを温ね新しきを知る−
