
医学のあゆみ271巻6号
ゲーム依存
ゲーム依存
企画:樋口 進(国立病院機構久里浜医療センター院長)
・国際疾病分類の最新版であるICD-11にゲーム障害(gaming disorder)が新たに加わった.既存の医学的エビデンスから,ギャンブルとともにゲームがはじめて依存の一疾患として認められたわけである.
・ゲーム障害に関しては包括的対策が必要である.そのためには,まずゲーム障害の理解が進む必要がある.まだ歴史の短い疾病のため,医学的エビデンスの蓄積は十分とはいえない.
・本特集では,現時点で把握されているエビデンス等をそれぞれの専門家に執筆いただく.今後,実態解明,予防教育の広範な施行,相談システムの充実,医療体制の整備などが期待される.

形成外科 Vol.67 No.11
2024年11月号
臍と形成外科
臍と形成外科 日常生活において露出する部位ではないものの,恥ずかしがらずに自信をもって出せるようでありたいと誰もが思っているであろう「臍」。臍の美しさに焦点を当てた本特集では,10年間での変化や新たな取り組みに加え,美しい臍を保つための術式や考慮,工夫を紹介する。

小児外科50巻4号
2018年4月号
【特集】臍ヘルニア:手術と圧迫
【特集】臍ヘルニア:手術と圧迫

J. of Clinical Rehabilitation 31巻8号
小児発達障害のリハビリテーション-運動機能発達に着目して
小児発達障害のリハビリテーション-運動機能発達に着目して
小児を含む発達障害(神経発達症)は2004年に制定された発達障害者支援法を契機に社会的にも広く認知されるようになり,最近では,各地の小児のリハビリテーション医療・療育機関を受診・利用する児のかなりの程度を占める状況になっている.子どもを取り巻く育児・保育・教育の領域では,「気になる子」が多く見出されるようになっており,早期発見・早期対応につながっているところであるが,必ずしも十分であるとは言い難い現状がある.発達障害(神経発達症)は,協調運動,感覚受容,コミュニケーション,対人関係等,小児の発達全体にかかわり,多領域・多職種での対応が求められている.
リハビリテーション診療の領域では,運動の不器用さや日常生活動作スキルの獲得遅延等,運動発達面からのサポートを求めての受診が多いと考えられる.また肢体不自由を主病像とする疾患においても,発達障害の要素が認められる例も少なくない.
しかし,現場では,「発達障害(神経発達症)はわかりにくい」という声もしばしば聞かれるところである.また,養育者が発達障害(神経発達症)のある子どもへの対応に困難さを自覚し,極端な場合には疲弊していることもあり,リハビリテーション診療を進めるうえでの課題となっている場合もある.
発達障害(神経発達症)のある子どもを成人後はどのようにフォローしていくのか,移行期医療の問題も今後重要視されていくものと思われる.
本特集では,発達障害の中でも特に運動機能に着目して,専門的に診療研究されている執筆者の方々に,それぞれのご専門・ご経験を踏まえて多面的な視点から解説をお願いした.すなわち,小枝達也先生には発達障害全体の概要について,橋本圭司先生には早期発見の手がかりとなるツールを中心に,小池純子先生には総合療育施設における発達障害児へのリハビリテーション診療の基本的な考え方について,岩永竜一郎先生には発達性協調運動障害に焦点を当てた具体的な介入方法の詳細を,井上雅彦先生には養育者へのサポートともなり得るペアレントトレーニングの紹介とリハビリテーション実地診療における応用の考え方を,丹治和世先生には成人と小児における発達障害診療の比較と小児から成人へのトランジションにかかる問題についてそれぞれご執筆いただいた.
本特集が読者各位の,発達障害児への多職種・多施設連携の下でのリハビリテーション診療を進めて行くうえで一助となれば幸いである.(編集委員会)

発達障害支援の実際
診療の基本から多様な困難事例への対応まで
自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの発達特性を有する人をどのように診断し、どう支援していくべきか――。本書は、昨今の精神医療・福祉の現場で最も関心の高いテーマの一つである発達障害の診療・支援に真正面から向き合い、具体的な対応策を提示するもの。検査ツールの使い方や薬物療法、困難事例への対応など、発達障害にまつわるさまざまなトピックを第一人者らが具体的・実践的に解説。

臨床画像 Vol.38 No.8
2022年8月号
【特集】特集1:絶対苦手分野にしない 冠動脈の画像診断/特集2:直腸癌のMRIにレポートを付ける前に知っておくべきこと
【特集】特集1:絶対苦手分野にしない 冠動脈の画像診断/特集2:直腸癌のMRIにレポートを付ける前に知っておくべきこと

BeyondER Vol.2 No.2 2023
2023年2号
特集1:救急医ルートの多様性と現実解[前編]/特集2:心不全 「っぽい」の核心をとらえて,しっかり対応する!
特集1:救急医ルートの多様性と現実解[前編]/特集2:心不全 「っぽい」の核心をとらえて,しっかり対応する!

medicina Vol.62 No.7
025年 06月号
特集 精神科×内科 患者と家族を支えるために知っておきたい見えない“こころ”のこと
特集 精神科×内科 患者と家族を支えるために知っておきたい見えない“こころ”のこと 内科診療に不可欠な情報をわかりやすくお届けする総合臨床誌。通常号では内科領域のさまざまなテーマを特集形式で取り上げるとともに、連載では注目のトピックスを掘り下げる。また、領域横断的なテーマの増刊号、増大号も発行。知識のアップデートと、技術のブラッシュアップに! (ISSN 0025-7699)
月刊、増刊号と増大号を含む年13冊

脳神経外科 Vol.51 No.6
2023年 11月号
特集 神経救急 初期診療から集中治療までエキスパートの暗黙知に迫る
特集 神経救急 初期診療から集中治療までエキスパートの暗黙知に迫る 雑誌『脳神経外科』は2021年1月よりリニューアルしました。「教科書の先を行く実践的知識」を切り口に、脳血管障害、脳腫瘍、脊椎脊髄、頭部外傷、機能外科、小児神経外科など各サブスペシャリティはもちろん、その枠を超えた横断テーマも広く特集します。専門分野・教育に精通し第一線で活躍する脳神経外科医を企画者・執筆者に迎え、診断・治療に不可欠な知識、手術に生きる手技や解剖を、豊富な図と写真を用いて解説します。さらに、脳神経外科領域の最新の話題を取り上げる「総説」、手術のトレンドを修得することのできる「解剖を中心とした脳神経手術手技」も掲載します。 (ISSN 0301-2603)
隔月刊(奇数月)、年6冊

腎盂・尿管癌診療ガイドライン 2023年版
9年ぶりの大幅改訂!
その間、新規治療薬、ロボット支援手術の腎尿管全摘徐術、それぞれの保険収載がありました。
特に本邦での新規薬物療法の保険収載はここ5年間に集中しております。
初版からさらにアップデートされた新規ガイドライン!
是非、ご覧ください。

OCTアンギオグラフィコアアトラス
ケースで学ぶ読影のポイント
OCTアンギオグラフィ(OCTA)は、非侵襲的に眼底の血管像が得られることから注目されている。本書では、OCTAの原理・正常眼底について概説し、疾患各論では症例を通して読影ポイントを示した。各症例では、カラー眼底、蛍光眼底造影、OCTなど他の検査との対比により、OCTAで何が分かるかを詳説。また、特有のアーチファクトについても随所で解説し、注意を喚起した。OCTAについて知りたい眼科医の必携書。
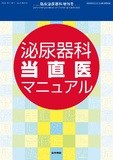
臨床泌尿器科 Vol.75 No.4
4月発売(増刊号)
特集 泌尿器科当直医マニュアル
特集 泌尿器科当直医マニュアル -

≪泌尿器Care & Cure Uro-Lo別冊≫
疾患別 泌尿器科の薬物療法と患者管理
【薬物の治療戦略と患者管理の要点がわかる】
泌尿器科の薬物療法では、治療とケアの多様化とともに新しい薬剤が次々と開発され、各種ガイドラインが見直されている。本書は、薬剤の特性を生かした治療戦略と患者管理、副作用への対応について、医師・看護師・薬剤師が最新の情報をまじえて解説する。
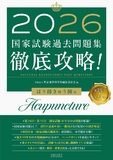
2026 第24回~第33回 徹底攻略!国家試験過去問題集 はり師きゅう師用
この10年間に国家試験問題として実際に出題された全問題について、解答の解説をこの1冊に収載!答えを羅列するだけでなく、設問の意義や狙い、鑑別点などもわかりやすく解説掲載しています。明治東洋医学院編集委員会による執筆。各科目の担当執筆者が、「国家試験出題基準」の小項目順に並べかえているので*、過去10年間に多く出題された問題もすぐわかり、同じ項目の問題を連続して解いていくことで、分野ごとに確実に理解を深められる体裁になっています。
*複数の項目に該当する問題等は担当執筆者の判断により分類。
冊子タイプの付録には、過去3年の試験当日と同じ通し問題と正式解答を掲載しており、本書内の解説ページもすぐに参照できるので、解答の根拠をしっかり理解して身に付けることができます。
最新の出題基準に対応したこの1冊を、試験対策として、ぜひご活用ください。
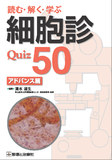
読む・解く・学ぶ 細胞診Quiz50 アドバンス篇
細胞診の知識と実際が,クイズを解き進めることにより自然と身につく2ページ単位のコンパクトな構成.アドバンス篇では,資格認定試験の合格ラインを確実に超えるための内容という点に照準を絞り,50問を各領域(乳腺・婦人科・呼吸器・甲状腺・唾液腺・肝胆膵・体腔液・泌尿器など)から厳選した.また,陥りがちなピットフォールを各項目にコラムとして掲載した.自主学習にも,試験対策本としても利用できる1冊.

完全版 脳血管内治療学
病態・治療法の本質的理解と臨床・研究発展のために
【血管内治療の学問体系を完全網羅した教科書】
脳血管内治療を単なる手技・テクニックとしてではなく、体系的な学問として、周辺を含む全容を完全網羅した領域初の教科書。血管内治療の安全な遂行と発展のために必要な基礎および介在的研究の現在までの成果と今後の展開を、分野の「サムライ」が結集してまとめた金字塔的1冊。
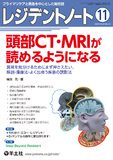
レジデントノート Vol.22 No.12
【特集】頭部CT・MRIが読めるようになる
【特集】頭部CT・MRIが読めるようになる 頭部画像の読影に苦手意識のある方,必見!画像オーダーの基本や解剖,よく出会う疾患でのCT・MRIそれぞれの特性をふまえた読影など,異常所見を見分けるために知っておきたい,専門家の読み方を教えます!

名古屋第二日赤流!臨床倫理コンサルテーション 実例に学ぶ、本当に動けるチームの作り方
臨床倫理活動はいかにして始め,運営・維持していけばよいか.本邦で早くからこの活動に取り組み定着させてきた,名古屋第二日赤・倫理コンサルテーションチームのノウハウを公開.倫理研修会のテキストにもお勧め.

サルコペニアを防ぐ!
看護師によるリハビリテーション栄養
サルコペニアに対し有用なリハビリテーション栄養の基本的知識、実践を解説する1冊。臨床では“とりあえず安静・禁食”という指示により、医原性サルコペニアが生じている実態がある。そういったサルコペニアにはリハビリテーション栄養が有用であるとされ、アセスメント・診断推論、診断、ゴール設定、介入、モニタリング等のリハ栄養ケアプロセスが大切であり、看護師の果たす役割は大きい。リハ栄養を実践するための必携書!

1年目ナースがそのまま使えるすごい「声かけ」フレーズ 1版1刷
患者さん、ご家族、先輩、スタッフに「こう言えばよかったのか!」
SNSで大人気! 現役看護師・よんさん待望の最新刊!
あいさつ、環境整備、清拭、検査、与薬、クレーム対応、電話対応、報・連・相……等の基本&対応例から、「採血を失敗してしまった」「内服薬を拒否された」「ベッド上安静の患者さんにトイレに行きたいと言われた」「院外へのお使いを頼まれた」「インシデントの報告をしたい」……等、看護師が困りがちな場面での声かけ例まで、ギュギュッと詰まった1冊!
ほっこり癒されるイラスト満載で楽しみながら“コミュニケーション能力”がグンとUPする!
これから現場に出る看護学生も、1年目の看護師も「できるナース」に一瞬で変わる!
