
看護・介護で使えるナーシングマッサージ[Web動画付]
「触れる」をケアにする
触れること、さすることは確かにケアになる
目の前にいる苦痛を抱えた人をなんとかしたいという思いで研究されてきたナーシングマッサージは、ケア場面で触れることがどんな意味をもつのかという原点に立ち戻り、試行錯誤を繰り返した結果、軽擦法(さする技術)を中心とする手技に進化した。本書では、触れることの意味をはじめ指圧マッサージの基本から安全に実施できる手技までを紹介。手技は35本の動画で確認できる。看護師・介護士の手はケアの道具になる!

≪シリーズ ケアをひらく≫
あらゆることは今起こる
私の体の中には複数の時間が流れている。
眠い、疲れる、固まる、話が飛ぶ、カビを培養する。それは脳が励ましの歌を歌ってくれないから?──ADHDと診断された小説家は、薬を飲むと「36年ぶりに目が覚めた」。私は私の身体しか体験できない。にしても自分の内側でいったい何が起こっているのか。「ある場所の過去と今。誰かの記憶と経験。出来事をめぐる複数からの視点。それは私の小説そのもの」と語る著者の日常生活やいかに。SFじゃない並行世界報告!

≪シンプル≫
シンプル薬理学 改訂第6版
簡潔でわかりやすく通読性に優れた記述と、豊富な図表が特徴の薬理学の教科書。看護、リハビリテーション、臨床検査、栄養などの医療系学部学生から好評を得ている。今改訂では新知見の追加と医薬品情報を更新。読者からの指摘も盛り込み、さらに理解しやすい内容となった。

疾患・病態を理解する尿沈渣レファレンスブック
尿沈渣成分と疾患の関連性がわかる!
『臨床検査』誌 Vol.62 No.4(2018年4月・増刊号)「疾患・病態を理解する 尿沈渣レファレンスブック」待望の書籍化。検査編(解剖、尿路の検査・処置・手術、尿沈渣成分の解説)、疾患編(尿沈渣成分と疾患との関連性を解説)の二部構成。尿沈渣成分略語一覧表を追加、尿検査や尿沈渣成分の解説を拡充。尿沈渣検査の強拡大像の追加により弱拡大像との比較が可能となり、鏡検力のレベルアップが期待できます。

新解剖学 第7版
信頼のロングセラー 待望の改訂版!
20年以上にわたって医学生に支持されてきたロングセラー、待望の改訂第7版。
解剖学の要点を、カラー図版360点とともにコンパクトにまとめました。
各項目1~2ページの読み切り構成。短時間で概要を把握できるので、初学者におすすめです。

Heart View Vol.24 No.11
2020年11月号
【特集】アミロイドーシス
【特集】アミロイドーシス
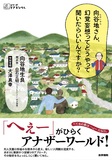
≪シリーズ ケアをひらく≫
向谷地さん、幻覚妄想ってどうやって聞いたらいいんですか?
常識は後からやってくる!
精神医療の常識を溶かし、対人支援の枠組みを更新しつづける「べてるの家」の向谷地生良氏。当事者がどんな話をしても彼は「へぇー」と興味津々だ。その「へぇー」こそがアナザーワールドの扉を叩く鍵だったのだ! そしてこの一見シンプルな話の奥には光と闇が交錯する世界が広がっていた。大澤真幸氏の特別寄稿「〈知〉はいかにして〈真実〉の地位に就くのか?」は“良心的兵役拒否者”である向谷地氏に言語論から迫った名論文!
*「ケアをひらく」は株式会社医学書院の登録商標です。

みんなで実践する小児緩和ケア
医師や多職種チーム,家族や地域でこどもを支える
小児医療の進歩にともない医療的ケア児や重症児も増加しています。成人患者の緩和ケアやACPは認知されつつあるものの、こどもや家族に対する支援はこれからなのかもしれません。「症状緩和」「意思決定支援」Well-beingを支える」「こどもホスピス」「メンタルヘルスケア」など、本書には小児緩和ケアを考える臨床家の気づきが述べられています。

みき先生の皮膚病理診断ABC ①表皮系病変
系統的な病理標本の見方がわかるシリーズ刊行開始!
◎国試・専門医試験対策から,エキスパートの皮膚科医まで,必要な知識を満載しています.
◎項目ごとに2ページ見開き単位で記載し,皮膚病理の世界に気軽に入っていくことができます.
◎疾患概念や定義をはっきりさせたうえで,診断に役立つ所見を多数の組織写真を用いてわかりやすく紹介します.
◎症例の経時的なバリエーションや亜型どうしの違いなども多数提示しています.
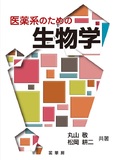
医薬系のための 生物学
本書は,医学系,薬学系,看護系など医療系に必須な生物学の基礎知識と応用力の習得を目的とし,豊富な図表とともに具体的な薬の名称や働きを織り交ぜながら,平易に解説.また学生の意欲を喚起するために最先端の「薬学ノート」「コラム」「トピックス」など適宜織り込み,さらに章の最後に演習問題と,巻末にその解答を掲載した.
本書の知識があれば,さらに巨大な生物学教科書や専門論文原著も容易に理解するための応用力が身につくであろう.
姉妹書に『医療・看護系のための 生物学(改訂版)』『理工系のための 生物学(改訂版)』がある.

保健師ジャーナル Vol.73 No.3
2017年3月号
特集 「見える化」時代の地域診断 データとツールを上手に活用しよう
特集 「見える化」時代の地域診断 データとツールを上手に活用しよう 保健・医療・福祉・介護の「見える化」が進められている時代の中,保健師がデータヘルスや地域包括ケア等を進めるにあたって,各種の統計データや分析ツールを駆使した地域診断がますます重要になっている。本特集では,データ分析による「見える化」の意義を知るとともに,どのように統計データや分析ツールを活用して戦略的に地域診断に取り組んでいくべきか,事例を交えながら考える。

違いを生み出す消化器内視鏡
静岡がんセンターの奥義、すべて教えます
消化器内視鏡分野は近年、目覚ましい進歩を遂げ、高度に専門分化した知識と技術が求められるようになっています。本書の編集にあたった静岡がんセンター内視鏡科は、2002年に開設され、現在までに多数のレジデントが卒業し、日本全国で活躍しています。そのなかで、代々引き継がれてきた “静がんの奥義” をここに余すところなく公開します。
本書は消化器内視鏡に共通する「学ぶ心得」から、「上部消化管」「下部消化管」「胆膵」のそれぞれの領域の各論、そして「学術活動」の項目で構成されています。特に「学術活動」の項目は、カンファレンス、抄読会から学会発表、さらに臨床研究の発案から計画書作成、症例報告執筆、原著論文執筆などを取り上げており、類書にはない本書の「ウリ」になっています。
これから消化器内視鏡を学びたい若手医師にとっては絶好の指南書であり、若手医師の教育に困っている指導医にも是非読んでいただきたい一冊です。

小児てんかん重積状態・けいれん重積状態治療ガイドライン2023
6年ぶりの改訂版である2023年版では,小児救急医療で高頻度に遭遇するけいれん重積状態の病院前治療・初期治療から難治性病態への対応まで日本における治療選択肢等の医療事情を考慮しつつ.システマティックレビュー5項目を加え,実臨床に即してアップデート.適応外使用となる薬剤はその適切な使用を注意喚起のうえ解説し,発作時の患者に対して最善の治療が施せるよう,よりわかりやすく解説した1冊に.
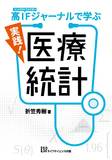
高インパクトファクタージャーナルで学ぶ 実践!医療統計
インパクトファクターの高い世界のトップジャーナルで最先端の研究に触れ,学習ポイントを確認しながら効率よく医療統計が学べます。
本書はこんな方にお勧めします
□ 統計担当者
□ 臨床論文を読むことの多い医療従事者
□ 医薬品・食品の臨床研究担当者
□ 医療系の大学院生

膝の鏡視下手術 テクニカルガイド[Web動画付]
代表的な膝関節手術に的を絞り,“テクニック”にこだわった手術書。
疾患数は少ないが,その代わりに手術手順の細部まで細かく解説。さらに,特にポイントとなる点は「テクニカルポイント(TP)」として詳述し,また助手の動きが重要な局面についても記載。また取り上げられることの少ない再再建手術についても解説。
本書を読めば確実に手術を再現できる“こだわり”の一冊!

医学のあゆみ296巻7号
がん患者への栄養療法と栄養指導
がん患者への栄養療法と栄養指導
企画:志賀太郎(がん研究会有明病院総合診療部,同腫瘍循環器・循環器内科)
・がん医療の進歩により,多くの患者が社会生活を維持しながら治療を続けられるようになってきたが,化学療法や放射線療法,外科的治療に伴う副作用や代謝性変化,後遺症,さらに高齢化や心血管疾患などの併存疾患の影響により,低栄養や栄養状態の低下を呈する患者も少なくない.
・摂取不足や代謝異常など体組成や身体機能を低下させ,結果的にがん治療の継続や回復を妨げる要因となるため,これに対する栄養療法・指導は,がん医療の根幹を支える重要な支持療法としての役割を担う.
・本特集では,がん薬物療法,手術的治療,高齢がん患者,摂食嚥下障害,がんサバイバーなどに関連した栄養管理の要点をはじめ,臨床現場で直面する課題を包括的に取り上げる.

臨床整形外科 Vol.59 No.2
2024年 02月号
特集 ここまで来た! 胸郭出口症候群の診断と治療
特集 ここまで来た! 胸郭出口症候群の診断と治療 よりよい臨床・研究を目指す整形外科医の「うまくなりたい」「学びたい」に応える月刊誌。知らないままでいられないタイムリーなテーマに、トップランナーによる企画と多角的な解説で迫る「特集」。一流査読者による厳正審査を経た原著論文は「論述」「臨床経験」「症例報告」など、充実のラインナップ。2020年からスタートした大好評の増大号は選り抜いたテーマを通常号よりさらに深く掘り下げてお届け。毎号、整形外科医に “響く” 情報を多彩に発信する。 (ISSN 0557-0433)
月刊、増大号を含む年12冊
2024年通常号定価:2,970円 (税込) 2024年増大号定価:6,490円 (税込)

INFECTION CONTROL(インフェクションコントロール)2024年2月号
2024年2月号
特集:薬剤耐性菌対策の基本知識と日常のケア 10
特集:薬剤耐性菌対策の基本知識と日常のケア 10
医療関連感染対策の総合専門誌『INFECTION CONTROL』は、すべての感染対策活動を全力で応援します。
「整理された最新情報が欲しい」というあなたのために、ピンチを乗り切る最新情報&指導ツールとともに、現場ですぐに生かせるトピックや領域で話題のテーマを分かりやすく解説します。
現場で活躍する執筆陣による、専門誌ならではの解説はICT・ASTメンバー必読!そのまま使えるイラストやパワーポイントなど、豊富なダウンロードサービスも充実です。

独習! フローチャート式デジタル脳波判読法
著者らは「脳波は脳の心電図。気軽に臨床を知っている医師が判読するようにしよう」をモットーに、フローチャートに沿って脳波を捉えることにより、ステップバイステップで脳波を判読できる指導法を行っています。
本書は、脳波判読の「総論編」、「各論編」、「応用編」、「Q&A」の4章から構成されており、「背景活動」、「非突発性異常脳波」、「突発性異常・鋭波、棘徐波複合などの判定」などのフローチャートを参考にしながら初学者が脳波判読できる仕組みになっています。
特に、第3章「応用(実際の脳波の判読)」では、「正常脳波」「軽度異常脳波」「中等度異常脳波」「高度異常脳波」の症例を8本の動画から確認できたり、第4章「良い爺〔いいじい(EEG)〕さんのQ&A」では、学生や研修医の先生方からのよくある質問~回答が紹介されていたり、脳波判読の苦手意識を少しでも払拭できる工夫がされています。
脳波判読のエキスパートの実際の脳波の読み解き方、ポイントをフローチャート式で捉えることで、初学者や脳波を読み解くことに苦手意識をもつ方も、独学で脳波を勉強でき、脳波判読への理解も深まり、実臨床に活かせるようになります。

周産期医学55巻10号
おさえておきたい! 胎児・新生児の超音波検査
おさえておきたい! 胎児・新生児の超音波検査
