
臨床外科 Vol.80 No.13
2025年 12月号
特集 Advanced LECSを安全に導入するためのバイブル〔特別付録Web動画付き〕
特集 Advanced LECSを安全に導入するためのバイブル〔特別付録Web動画付き〕 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 2026年より全面リニューアルし、隔月刊化と同時に1冊のページ数を大幅にボリュームアップ。さらに充実した特集と連載をお届けします。 (ISSN 0386-9857)
2025年:月刊、増刊号を含む年13冊 2026年:隔月刊(偶数月)、年6冊

消化器内視鏡35巻11号
内科と外科のコラボレーション手術の今
内科と外科のコラボレーション手術の今

医道の日本 Vol.77 No.7
2018年7月号
「妊鍼」治療の最前線 ―不妊症への鍼灸マッサージ―
「妊鍼」治療の最前線 ―不妊症への鍼灸マッサージ― 無資格者の参入も増えて、開拓から競争の段階に入った「不妊専門治療院」。改めて、鍼灸マッサージ師だからこそできる不妊治療が問われている。
体外受精など高度生殖医療の成功率を上げるための鍼灸治療や、医療機関との連携の仕方、鍼灸院での生活指導などについて紹介する。
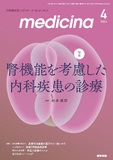
medicina Vol.61 No.5
2024年 04月号
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療 内科診療に不可欠な情報をわかりやすくお届けする総合臨床誌。通常号では内科領域のさまざまなテーマを特集形式で取り上げるとともに、連載では注目のトピックスを掘り下げる。また、領域横断的なテーマの増刊号、増大号も発行。知識のアップデートと、技術のブラッシュアップに! (ISSN 0025-7699)
月刊、増刊号と増大号を含む年13冊

診療放射線技師 イエロー・ノート 臨床編 5th edition
「学生さんが各自の学習に合わせて「+α」の知識を書き込み,独自の講義ノートを作成できる」という基本コンセプトで,日々の学習を積み重ねながら自ずと国家試験に十分対応できる知識が身に付く書籍。本書『イエロー・ノート]は診療放射線技師(RT)養成校の学生が共通して学ぶ「臨床分野」を網羅し,各項目ごとに平易にかつポイントのみを記述し,図表を多用している。
改訂にあたっては,①新カリキュラムおよび令和7年版国家試験出題基準に準拠し,②タスク・シフト/シェア関連項目を反映(主に医療安全管理学の項目の新設),③旧出題基準の内容で新基準からは削除された項目を削除。
講義用のサブテキストから,学内試験,国試まで対応するRT養成校学生必携の一冊として,『ブルー・ノート』とセットで活用できる,国試対策の強い味方!

手術 Vol.78 No.13
2024年12月号
一般外科医として押さえておくべき外来処置と小手術
一般外科医として押さえておくべき外来処置と小手術
手術がうまくなりたい消化器・一般外科医のための専門誌。マニアックなほど深堀りした特集内容やビジュアルでわかりやすい手術手技の解説を特長とする。今回の特集は外来処置と小手術。外科診療の細分化が進む昨今であるが,“外科ジェネラリスト”を目指す一般外科医として,押さえておくべき基本事項は数多い。体表の傷(創)や熱傷・凍傷,爪・皮膚疾患,気管切開などの外科処置まで,各領域の専門家が基本的な点を解説した。

がん看護 Vol.30 No.4
2025年7月号
エビデンスに基づく 看取り期のケア
エビデンスに基づく 看取り期のケア 高齢者機能評価(GA・CGA)を活かした高齢がん患者のケア がんの医学・医療的知識から経過別看護、症状別看護、検査・治療・処置別看護、さらにはサイコオンコロジーにいたるまで、臨床に役立つさまざまなテーマをわかりやすく解説し、最新の知見を提供。施設内看護から訪問・在宅・地域看護まで、看護の場と領域に特有な問題をとりあげ、検討・解説。告知、インフォームド・コンセント、生命倫理、グリーフワークといった、患者・家族をとりまく今日の諸課題についても積極的にアプローチし、問題の深化をはかるべく、意見交流の場としての役割も果たす。

臨床雑誌外科 Vol.87 No.9
2025年8月号
高リスク患者に対する周術期管理の要点
高リスク患者に対する周術期管理の要点 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

≪教科書にはない敏腕PTのテクニック≫
臨床実践 足部・足関節の理学療法
好評シリーズの第2弾.足部・足関節に対する敏腕理学療法士の技術とコツを12テーマに分けて解説.前半では,触察技術が有効である足部・足関節の機能解剖,力学的な負荷による障害のメカニズム,テープやインソール療法などを紹介.後半では,扁平足障害・痛みを有する外反母趾・後脛骨筋腱,腓骨筋腱の障害・アキレス腱炎,足底腱膜炎・足関節捻挫を取り上げ,機能的特徴を踏まえた理学療法手技をレクチャーする.
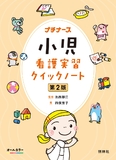
小児看護実習クイックノート 第2版
看護学生が小児看護実習の際に持って行きたい知識をコンパクトサイズに見やすくまとめました。
アセスメントに必要な基礎知識から実習でよく出合う症状・疾患・ケアまですぐに引けるのはもちろん、
指導ナースによく聞かれることや、注意しておきたいポイントなどもまとまっており、みなさんの実習をサポートします。
実習中に実習着のポケットに入れて持ち歩くのにも、事前準備にも最適の1冊です!

エコーは心眼
消化器領域の超音波検査20症例から学ぶTips
超音波検査の教科書では伝えきれない,臨床現場で比較的遭遇しやすい消化器疾患20症例について,技師と医師の会話を通して各症例のエコー画像を読み解く.意外と知られていないエコー画像の見方と特徴を提示し,他の画像(CT画像・X線画像)と比較することにより,エコー検査の有用性と利便性が理解できる一冊です.Webで見られるエコー動画付!
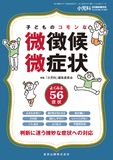
小児科 Vol.62 No.10
2021年9月臨時増刊号
子どものコモンな微徴候・微症状
子どものコモンな微徴候・微症状
毎年役に立つテーマでお届けしている臨時増刊号、本年は「子どものコモンな微徴候・微症状」です。日々の診察で目にしたり、育児相談や乳幼児健診の際に保護者から相談されたりする微徴候・微症状と向き合えるのは、小児科医の醍醐味といえましょう。そんな「ちょっとした」事柄を56項目ピックアップし、それぞれの専門家に解説していただいたことで、本号は知識を更新し日々活用できる座右の書となりました。是非ご一読ください。

図解 よくわかる経絡治療講義
図をふんだんに使った講義で経絡治療をマスターしよう!
『素問』『霊枢』『難経』など古典を基礎として理論体系化した「経絡治療」。多くの鍼灸師が一度は学ぶ古典医学の流派ですが、「『陰陽』『五行』など言葉が独特で理解できない......」「なぜ脈で病気が分かるの?」「どこから勉強していいのかわからない」などなど、さまざまな壁にぶつかり、断念した人も少なくないのではないでしょうか。
本書は、夏期大学講師の大上勝行氏による実際の講義をわかりやすく編集した一冊。図もふんだんに用いているため、黒板で実際の講義を受けているような感覚で、経絡治療を初学者でも簡単に、かつ実用的に学べる! 自分の治療スタイルを固めていくきっかけの一つに、本書を活かしてもらえれば幸いです。

精神医学 Vol.67 No.12
2025年 12月号
特集 成人の知的発達症 精神医学の視点からできる支援
特集 成人の知的発達症 精神医学の視点からできる支援 精神医学・医療の現在地を確認し、針路を示すナビゲーションとして、多彩なテーマを毎月の特集で取り上げ、第一線の執筆陣による解説をお届けする。5月号は増大号として多角的にテーマを掘り下げる充実の内容。日々の臨床から生まれた「研究と報告」「短報」など原著論文も掲載している。 (ISSN 0488-1281)
月刊、増大号を含む年12冊

歯科国試パーフェクトマスター 口腔組織・発生学 第2版
歯科医師国家試験合格にグッと近づくパーフェクトマスターシリーズ
出題基準改定(令和5年)に対応した改訂版,登場
歯科医師国家試験対策のために愛用されてきた『歯科国試パーフェクトマスター』シリーズが,国試の出題基準改定(令和5年)に対応して新しくなりました.最新の出題基準に対応した本書を活用して大切なポイントをしっかり抑え,歯科医師への道に進みましょう!
・直近の試験問題を精査して対策が記載されているので,各科目の大まかな出題傾向がつかめます!
・カラーの組織写真や模式図を多く用いているので,わかりやすく,覚えやすい!
・国試対策のほか,CBT対策や定期試験,各科目の授業の予習・復習にも活用できます!

医学部で留年しない・繰り返さないために読む本〜自己調整学習力の磨き方
「留年になるのではないか」「留年を繰り返すのではないか」「課題が多すぎてパニック」「学習管理ができていない」…という不安を抱えた方のために、これまで数百人に及ぶ医学生をメンタリングしてきた著者がアドバイスをまとめました。
医学生は、およそ5人に1人は留年経験があると言われますが、「自己調整学習力」を磨いていけば、必ず乗り越えられます。本コンテンツは、日々の学習に悩む医学生の皆さんに,大きな推進力を与えるものとなることでしょう。
「医学部に入学することができた皆さんが基礎的な能力が不足しているということはありません。ただ、多様な学修形態が必要な医学部の学修への自己調整力が一時的に低下しているのだと思います。少し教員目線から書くと、「医学部における学修不良の原因の多くは『自己調整学習力』の一時的低下である」ということです。自己調整学習力は、能動的に学ぶために自分で学修方法を調整していくスキルのことです。今、学修に困難や不安を抱えていても、少しずつ自己調整学習力を回復していけば必ず目標達成はできます。」

実験医学増刊 Vol.40 No.5
【特集】シン・マクロファージ あらゆる疾患を制御する機能的多様性
【特集】シン・マクロファージ あらゆる疾患を制御する機能的多様性 マクロファージは疾患ごとに多様なサブタイプの存在が明らかになるなど,疾患との深い関わりが注目されています.本書はこのような最新の知見を中心に,マクロファージ研究の総集編といえる内容となっています.

≪新OS NEXUS No.12≫
上肢の関節鏡視下手術[Web動画付]
「専攻医が経験すべき手術」を全20巻でほぼ網羅。メインの特集項目に加えて,手技の理解を深める解剖学的知識を示した「Anatomy Key Point」や,知っておくと有用な基本的手術・治療手技の紹介も毎号掲載し,専攻医として必要なスキルを漏れなくカバーできるシリーズ構成となっている。さらに前シリーズからの特徴である豊富な画像と精密なイラストに加えて今シーズンではストリーミング動画も配信し,静止画では伝わりづらい部分もよくわかる!
No.12では上肢の鏡視下手術を網羅し,肩関節/肘関節/手関節の主な手術を取り上げ,手技について解説する。最終章の「基本手術手技」では,de Quervain病と手関節ガングリオン病に対する基本的な手術手技を取り上げた。

≪BEAM(Bunkodo Essential & Advanced Mook)≫
消化器の基本薬を使いこなす
本書は一般医も使いこなしたい消化器薬を厳選,研修医が消化器科ローテート時に必要になる薬を加え,実践的に解説する.各剤について,①どんなときに使用するか,②薬理作用,③実践的処方例,④処方前にチェックすること,⑤処方時患者に説明すること,⑥処方後にチェックすることを基本構成とし,薬理の説明は最小限,処方例と使い方のヒントに重点をおいた.

理学療法ジャーナル Vol.51 No.4
2017年4月号
特集 理学療法と下肢装具
特集 理学療法と下肢装具 下肢装具は,理学療法のためのひとつのツールである.固定・制御・矯正の基本機能をもつ装具は,「補装具」として身体機能障害や姿勢保持・運動能力低下を補う.その一方,装具個々の制御機能特性に応じ「正常とは異なる動き」が生じ得る点も理解する必要がある.装具はさまざまな動作練習に役立つ反面,生活領域では面倒なものという印象も拭えない.さらに理学療法士は下肢装具を動作練習に利用すると,装着関節以外の範囲にまでその影響が及ぶことにも注意を払い,利用することが重要である.
