
臨床で役立つ
看護アセスメントスケール&ツール
臨床で役立つバイタルサインや呼吸、循環、救急などの各種診断指標・尺度をまとめました。
最新のエビデンスに基づいたスケールや指標を、180項目精選。調べやすいように、系統別、状態別、疾患・領域別のパートに分類。

名古屋えきさい会病院式
ロボット支援鼠径部ヘルニア修復術[Web動画付]
腹腔鏡手術とは異なる,ロボット手術ならではの鼠径部ヘルニア修復術(TAPP)のアプローチ法を,第一線で活躍する著者が言語化。
まずは鼠径部の複雑な膜構造を,著者解釈も交えて解説。解剖構造を最初に頭に入れることで,手術理解が圧倒的に早まる。
術式解説では,メジャーな外鼠径ヘルニア修復術を,細かく順序立てて徹底的に深掘り。術野で何が見えていて,何に注意しながらどこを剥離すべきかをビジュアライズに解説。
手術動画も約60本付録されており,動画と本を行き来しながら理解を深めることができる。
本術式でロボット手術の修練を始める読者にも,腹腔鏡を経てロボット支援TAPPをスタートする読者にとっても有用な情報が満載の1冊。
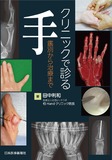
クリニックで診る手
手の訴えの8割近くは“手術無し”で改善します!手術不要・クリニックで鑑別・治療可能な手の疾患を解説!
日常診療で出会う頻度の高い「手」の疾患について、指、手関節の痛みや外傷の有無など、部位・症状から鑑別すべき疾患が分かるようまとめました。
多くの現場で使いやすいよう、単純X線と超音波エコーというありふれた画像だけで診断ができるように図を多く掲載。
本書を通読しておけば、日々の診療の幅が大きく広がります!

膨大な医学論文から最適な情報に最短でたどり着くテクニック
全ての医療職の皆さんへ!
めざす医学論文に最速ヒット!
おなじみの検索エンジンPubMed、Google Scholar。
そして文献管理ソフトEnd Noteなどなど。
使いこなしている気になってませんか?
医療ビッグデータ研究チーム直伝の文献さばきで
めざす論文に最速でヒットしよう。
効率にグッと差がつく必携アイテム!
書籍『膨大な医学論文から最適な情報に最短でたどり着くテクニック』の刊行を記念し、著者の重見大介先生、岩上将夫先生がご解説!
著者らが実際に行っている一歩踏み込んだ検索をレクチャーします。
本書を読んで、この動画をチェックしたら、ぜひご自分の検索にトライしてみてください!
新興医学出版社のYouTubeチャンネル https://youtu.be/HYHDrij9vdc

脳神経内科グリーンノート
2010年に刊行された「神経内科ポケットリファレンス」を大幅改訂・改題.
臨床現場で本当に必要な情報を凝縮したグリーンノートシリーズの脳神経内科編として満を持して登場.
図表,実際の画像・波形,フローチャートを随所に盛り込み,多忙な臨床医であっても視覚的に,そして短時間に臨床神経学を理解できる内容となっている.
ベッドサイドや外来診察室などの臨床現場における必携の一冊である.

脳神経外科グリーンノート
最高水準の診療を目指し,脳神経外科の知識をミニマムかつ網羅的に解説.エキスパートが膨大な情報から知識を選択してまとめあげたレジデント必携の1冊.

エキスパートナース Vol.40 No.8
2024年7月号
◆身体的拘束をどうとらえ、チームでどう取り組むか
◆患者さんが行動変容したくなる生活指導
◆身体的拘束をどうとらえ、チームでどう取り組むか
◆患者さんが行動変容したくなる生活指導

≪健康・栄養科学≫
健康・栄養科学シリーズ
基礎栄養学 改訂第7版
栄養の基本的概念,ならびに各栄養素の代謝とその生理的意義についてわかりやすく解説した好評テキスト.今改訂では管理栄養士国家試験出題基準(2023年改定)および日本人の食事摂取基準(2025年版)へ対応したほか,フルカラー化を実施.豊富なイラストとビジュアルな紙面で情報を視覚的に提示し,さらなる理解を助ける.

≪みんなの呼吸器Respica別冊≫
呼吸療法認定士 要点整理&まるおぼえノート
【覚えておくべき要点をコンパクトに整理!】みんながニガテな呼吸生理、人工呼吸、血ガス、薬剤、肺機能検査、新生児・小児領域まで、講習会テキストの幅広い出題分野から重要なポイントをすっきり整理。『呼吸療法認定士“合格チャレンジ”100日ドリル』とのセット使いで勉強効率UP!

臨床整形外科 Vol.58 No.11
2023年 11月号
特集 外傷性頚部症候群 診療の最前線
特集 外傷性頚部症候群 診療の最前線 よりよい臨床・研究を目指す整形外科医の「うまくなりたい」「学びたい」に応える月刊誌。知らないままでいられないタイムリーなテーマに、トップランナーによる企画と多角的な解説で迫る「特集」。一流査読者による厳正審査を経た原著論文は「論述」「臨床経験」「症例報告」など、充実のラインナップ。2020年からスタートした大好評の増大号は選り抜いたテーマを通常号よりさらに深く掘り下げてお届け。毎号、整形外科医に “響く” 情報を多彩に発信する。 (ISSN 0557-0433)
月刊、増大号を含む年12冊

薬剤師のための栄養療法管理マニュアル
患者の症状や疾患に応じた最適な栄養療法を進める時の心強い相棒!
薬剤師が知っておきたい栄養療法の知識をコンパクトにまとめたマニュアル。総論は経腸栄養、末梢栄養、中心静脈栄養について「投与法」「薬剤との相互作用・配合変化」「アセスメント」のポイントを解説。各論は下痢、便秘、肝疾患、腎疾患、悪性腫瘍など主要な22の症状・疾患について、「栄養管理」「食事療法」「薬物療法」の各ステップの介入ポイントを提示。患者の症状や疾患に応じた最適な栄養療法を進める時の心強い相棒!
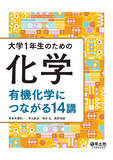
大学1年生のための化学 有機化学につながる14講
大学の化学を学ぶうえで必要な知識を厳選!高校化学や有機化学とのつながりを意識した解説で「どこがポイントか」がわかります.豊富な例題に取り組み,化学的な考え方に慣れることが,専門科目につながる第一歩!

QUICK生理学・解剖学
人体の構造と機能・病態生理
効率的に学習できる,最初に読むべき生理学・解剖学の統合型教科書!要点整理と明快な図表で長期記憶に結びつきやすく,国試練習問題で到達目標がわかりやすい.将来の医療職に役立つ質の高い情報をギュッと凝縮!
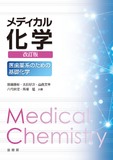
メディカル化学 改訂版
医歯薬系のための基礎化学
医師・歯科医師、薬剤師等を目指す大学一年生を対象とした通年用の基礎化学教科書として2012年に刊行され、定評を得た教科書の改訂版。
初学者に向けた化学全般のきわめて平明な解説に加え、専門課程で学習する有機化学・生化学につなぐための有機化学反応や有機化合物およびさまざまな生体分子の解説、医療現場で役立つ知識も満載されている。
改訂版では、刊行以来読者から寄せられたご意見を参考に、近年の化学のトピックスもふまえて各章の内容をアップデートした。また、補遺として「活性酸素・活性窒素と生体反応」「生体補完材料」を加え、医歯薬系の項目をより充実させた。および、旧版ではいくつかの章に分かれていたビタミン、ホルモンを第8章にまとめ、教科書としての使い勝手をよりよくした。

医学のあゆみ265巻2号
内分泌緊急症
内分泌緊急症
企画:伊藤 裕,栗原 勲(慶應義塾大学)

≪ナーシングビジネス2022年春季増刊≫
タスクシフト・シェア実践ガイド
【看護現場の「働き方改革」も待ったなし!】
医療現場のタスクシフト・シェアを取り巻く最新の動向とともに、管理者が担う役割、先鋭的な施設の取り組み例を紹介。真の目的である「患者のアウトカム向上」を目指し、現場が働きやすい体制構築を実現するためのヒントが満載で、実践に即活かせる一冊。
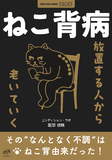
≪運動と医学の出版社実用書≫
ねこ背病 初版
放置する人から老いていく
「もう年だから…」と諦めていませんか?
1日1分から始める!【ねこ背改善メソッド】で、見た目も体も若返り、健康でイキイキとした毎日を取り戻す!
ふと鏡に映るご自身の姿勢に「背中が丸くなっているかも…」と気づいたことはありませんか? ねこ背は単なる見た目の問題ではありません。肩こりや腰痛の慢性化、股関節やひざの曲がり、転倒リスクの増加、活動範囲の縮小など、日常生活の質に直結する様々な悪影響をもたらします。歳を重ねるほど体のバランスを取る力が低下し、ねこ背が原因で身体機能全体が弱まる悪循環に陥ることもあります。また、ねこ背の人は体幹が「硬い」という特徴も持っています。
しかし、ねこ背は「歳だから仕方がない」と諦めるものではありません!
本書は、誰でも無理なく実践できる画期的なアプローチを紹介します。「ただ背中を伸ばせば治るわけではない」と提唱し、体幹・肩・股関節・ひざと全身の連動性を意識し、バランスよく整えることを重視。体全体の機能改善こそが、真のねこ背改善に繋がると説きます。
【本書で得られる効果と期待】
見た目の若返り:姿勢が改善され、若々しい印象を取り戻せます。
痛みからの解放:肩こり、腰痛、ひざの痛みの原因となる体の負担を軽減します。
転倒リスクの軽減:体幹でバランスがとれるようになり、転倒しにくい体に。
活動範囲の拡大:体が軽く動きやすくなることで、イキイキとした生活を送れるようになります。
【本書の5つの主要アプローチ】
たった1日1分、各エクササイズは30秒程度でOK! 該当ページ内のQRコードをスマートフォンで読み取ると、解説付きの映像で確認できるため、正しいフォームで無理なく続けられます。
体幹を伸ばす・筋力を改善するアプローチ:ねこ背改善の基本となる体幹の柔軟性・筋力を取り戻します。
肩周りを柔軟にするアプローチ:ねこ背と関係の深い「巻き肩」を改善し、腕の上げにくさを解消します。
股関節とひざを伸ばすアプローチ:体幹と相互に影響し合う股関節とひざの柔軟性を高めます。
下肢の筋力を改善するアプローチ:特に重要な「大殿筋」や「大腿四頭筋」など、足腰の筋肉を強化し、体の曲がりを食い止めます。
さらに、本書では「正しく立ち、正しく座る」といった基本の姿勢や、体幹をスムーズに前へ運ぶ「正しい歩き方」に加え、デスクワークやスマホ使用時など、日常生活でねこ背になりやすい場面ごとの改善ポイントも丁寧に解説しています。
「すべてを完璧に行うこと」ではなく、「自分に合ったエクササイズを1つでも見つけて続けること」が大切です。あなたの体は、きっと変わるはずです。
『もう年だから』と思う前に、ぜひ本書のメソッドを取り入れてみてください。健康でイキイキとした毎日の第一歩を、今日から一緒に踏み出しましょう!
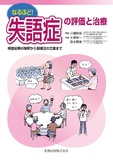
検査結果の解釈から訓練方法の立案まで
なるほど!失語症の評価と治療 第1版
本書は、「基礎編」「検査編」「訓練編」「症例編」の4編で構成され、各章には理解を深めるための「チェックポイント」を設けた。教科書としても使えるように巻末付録に「学習確認テスト」「訓練教材のサンプル」を収載。
検査編では、聴覚的理解、読解、発話、書字の4つの言語モダリティーの情報処理の流れをイラストやチャート図を多用して解説。
訓練編では、認知神経心理学的視点から情報処理過程の障害メカニズムとタイプ分類を提示し、それぞれの訓練法とノウハウを示した。

形と模様を極める大腸腫瘍内視鏡診断学
「命を奪う形と模様」を極めることが大腸癌死を減らす!
23年間に及ぶ著者単独の18,921症例の解析による渾身の診断学!
「本書では形と模様を敢えて分離し、別々に考察してから統合するという形式をとった。
まず肉眼型別の臨床病理を考察した上で、肉眼型と組織、ピットと組織、そして、肉眼型とピットの統合という構成にした。1 例毎のマクロとミクロの対比だけでなく、同じ組織型のマクロとマクロ、ミクロとミクロの横断的な対比ができるように、マクロ画像集、ミクロ画像集も用意した。
また、全体の見え方としても、すっきりとしたできる限りシンプルなページ構成を心がけ、ビジーにならないように努めた。シェーマなどによる図解も取り入れ、読者の理解の一助とした。
そして、1 章ではなぜ診断学が必要かということを解説し、what、how だけでなく、why にもこだわった。
その結果、本書の主旨を一言で言うならば、「命を奪う形と模様を極めることが、大腸癌死を減らす」ということである。」(本書「はじめに」より)

臨床雑誌内科 Vol.134 No.6
2024年12月号
エキスパートはこう読む! 検査値の臨床的解釈 日常臨床での疑問にお答えします
エキスパートはこう読む! 検査値の臨床的解釈 日常臨床での疑問にお答えします 1958年創刊。日常診療に直結したテーマを、毎号"特集"として掲載。特集の内容は、実地医家にすぐに役立つように構成。座談会では、特集で話題になっているものを取り上げ、かつわかりやすく解説。
