
ESDのための食道癌術前診断
目の前の食道病変に対してESDの施行は可能なのか?深達度は?側方伸展は?ESDの第一人者による食道癌術前診断の指南書がついに完成!豊富な内視鏡像、病理像の中から代表例を供覧し、診断に至るプロセスや考え方を懇切丁寧に解説。総論で基本を学び、各論ではクイズ形式で正確な術前診断に必要なノウハウが学べる。『ESDのための胃癌術前診断』とセットで揃えたい待望の一冊!

ぼっちでもできる医学研究
初心者にちょうどいいデータ(食材)で論文執筆(料理)してみる
論文の書き方や統計手法のその前に,どんなデータを使って論文を書いたらいいかわからない……
そんな論文執筆初心者に向けて,「いかに論文執筆に使えるデータを確保するか」に重点をおいた入門書が登場!
前半ではデータ入手から投稿・掲載までの一連のプロセスを,料理になぞらえて解説(食材/データの入手→営業許可/倫理審査委員会の承認→下処理/データクリーニング→調理/解析→盛り付け/論文執筆→提供/投稿→接客/Revision対応)。購入したり,無料で手に入るデータの選び方はもちろんのこと,投稿先の選定やRevision対応まで,著者の体験談や知っておくと役立つTipsが盛り込まれている。
後半では実際の論文を例に,どのようにデータを活用して論文化するかを,難易度やデータ種類別に紹介。
そのほか,初心者が抱きやすい疑問に答えるQ&Aページも充実。
漠然とした不安も解消できる,論文執筆の前に読んでおきたい1冊!

抗アミロイドβ抗体療法導入マニュアル
認知症治療薬レカネマブ・ドナネマブについてこの1冊で導入から診療実践までよくわかる!
アルツハイマー病の新規治療薬「抗アミロイドβ抗体薬」を導入し,実臨床で効果的に使うために必要な知識をコンパクトにまとめました.適切に使用するための適応判断から,各種検査,実際の治療フロー,副作用のモニタリングと対応,併用注意薬剤まで具体的に解説.アミロイドPET検査,MRIは実際の画像をふんだんに用いて所見を視覚的に学べます.付録「抗アミロイドβ抗体療法を希望する患者さんへの説明文書」はダウンロードして各自の施設基準に合うようにアレンジやそのまま患者・家族へ渡して使うことが可能です.認知症診療に携わる方に必携の1冊!

子宮内膜症取扱い規約 第2部 診療編 第3版
第2版が刊行された2010年以後、腹腔鏡下手術の技術向上や薬物療法の新たなエビデンス確立により子宮内膜症の治療は大きく変化した。その現状を3部構成で解説する。第1章では子宮内膜症の診断・治療について最新の考え方を、第2章ではフローチャートを用いて治療方針を示した。そして第3章の治療ガイドラインでは、癌化や産科合併症、妊孕性温存、QOL、代替療法など様々な視点から24のCQを設け、検討している。
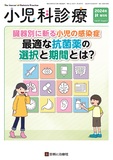
小児科診療 Vol.87 秋増刊号
2024年秋増刊号
【特集】臓器別に斬る小児の感染症 最適な抗菌薬の選択と期間とは?
【特集】臓器別に斬る小児の感染症 最適な抗菌薬の選択と期間とは?
診療現場で使いやすいように臓器別に感染性疾患を分類し,感染臓器,想定される微生物,提出すべき検査,経験的に使用される抗菌薬を簡潔にまとめました.
さらに起因菌判定後の抗菌薬,効果判定,経口抗菌薬への変更,治療期間,参考となる成書やガイドラインも紹介.サマリーで必要な情報が一目でわかり,解説もじっくり読んで知識を深められます.
日常の感染症診療に今日から役立つ1冊です.

NICU看護 myポケットマニュアル
【ポケットにサッと新生児看護のエッセンスを】
重いテキストをあれこれ持ち運ぶ必要は、もうない。NICU看護の核となる臨床知識・技術をコンパクトにまとめた頼れる1冊が登場。困ったときにすぐに確認、さらに要所に設置されたメモ欄を活用してオリジナルの注意点を書き込み、自分だけのmyマニュアルにできる。“現場で役立つ”にこだわり抜いて厳選したラインナップを、要点を押さえた親切なカラー図解を交えて解説。NICUナースの必携書。

The 外来看護 第2版
時代のニーズに応え、専門性を発揮する
看護の役割の1つの「療養上の世話」の視点で、退院後のセルフケア支援の重要性を感じた筆者は、外来での療養指導や外来看護に関する研究などを続けてきました。
本書では、「在宅療養指導料」を皮切りに、続々と新設される外来での看護にかかわる診療報酬の詳細を中心に、外来での看護に必要な技術、仕組みづくりなどをまとめました。
第2版は、2018年から2024年までの外来看護に関わる診療報酬改定などの変更に対応して、大幅な加筆を行っています。
≪本書は第2版第1刷の電子版です≫

眼科検査ガイド 第3版
眼科医・視能訓練士の皆様に広く活用されてきた『眼科検査ガイド』の改訂第3版.今回5年ぶりの改訂にあたって,OCT・OCTAなど昨今保険適用になり広まりつつある検査機器に関する記述を増やすなど,近年の検査技術の進歩に応じた構成となった.現時点での眼科検査の標準的な実践知識を示した,スタンダードテキスト.

臨床画像 Vol.39 No.11
2023年11月号
【特集】特集1:放射線科医がもっているべき 超音波検査の知識/特集2:放射線科医が触れる死後画像(突然死)
【特集】特集1:放射線科医がもっているべき 超音波検査の知識/特集2:放射線科医が触れる死後画像(突然死)

基礎運動学 第7版
理学療法士・作業療法士の必携書である「基礎運動学」が21年ぶりの大改訂!
●運動学のエッセンスを簡潔にまとめて定評を博しているテキストの改訂第7版.
●第7版では,前版までの重要部分を継承しながら,新たに定着してきた知見を加え,各章の内容を全面的に整理した.
●本文頁をを2色化し,初学者でも見やすい・分かりやすいテキストとしてリニューアル.

形成外科 Vol.65 No.5
2022年5月号
人工物露出に対する形成外科的対応
人工物露出に対する形成外科的対応 近年では,さまざまな人工物が人体に用いられている。これらは自己組織ではないために,生異物除去反応により露出することがあり,除去や温存の対応など,難しい選択を迫られてきた。本特集では,人工血管,整形外科領域の人工物,人工尿道括約筋,頭蓋顎顔面領域の異物を対象とし,さらに頭蓋骨に関しては脳神経外科医の視点も取り入れた。

だれも教えてくれなかった
本当のレーザー治療・美容皮膚科治療
国内初のQスイッチルビーレーザー開発に携わった著者が,基本から疾患別の治療法まで,レーザー医学と美容皮膚科の全てを紹介.病態からみた治療のメカニズムと,治療が効いた症例と効かなかった症例の根拠など,他にない切り口も示し,また美容ビジネスの利益相反など,様々な問題にも触れている.日本の全ての美容皮膚科医が根拠に基づいた適切な治療を行えるように,本当に患者の為となる治療とは何かを記した著者渾身の一冊.

≪看護管理まなびラボBOOKS≫
組織の力学
パワーを掌(つかさど)る
成功し続けるための組織行動論
組織に渦巻くパワーの正体を掴み、影響力を発揮し続けるリーダーになるために
「なぜ、人は動かされるのか?」「成功し続けるリーダーと〈脱線〉するリーダーは何が違うのか?」「人や組織は本当に変えられるのか?」「リーダーたちはなぜパワーを手放せないのか?」──リーダーとして自身のパワーを増強し、組織の中で影響力を発揮し続けるために、何を考え、どう行動すべきか。コンサルティングファームに長年従事し経営大学院で教鞭を執る筆者がすべてのリーダーたちに贈る、パワーと影響力の要諦書。
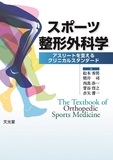
スポーツ整形外科学
アスリートを支えるクリニカルスタンダード
スポーツ医学の第一線で競技復帰をサポートする執筆陣による,スポーツ整形外科の役割と強みを前面に押し出し解説した教科書.アスリートが求める「競技レベルを維持しながらの外傷・障害の予防」,「早期の高いパフォーマンスでの競技復帰」を支援するための基礎知識と診断・治療を中心に構成.また,競技現場ならではの治療・判断・テクニック,競技復帰・再発予防に向けた手術・リハの工夫など臨場感溢れる内容も紹介している.

脳卒中の栄養療法
急性期・回復期・維持期の栄養管理がこの一冊で実践できる!
超急性期の栄養管理や製剤選択から回復期・維持期のリハビリテーションまで,脳卒中治療に必要な栄養療法についての解説を1冊に集約.脳卒中治療に関わる医師・メディカルスタッフ必携のこれまでなかった実践書!

Medical Technology 54巻1号
一般検査のpotential pitfallに備えよう
一般検査のpotential pitfallに備えよう
●一般検査は日常診療における最初の判断材料として,患者の状態を迅速かつ正確に把握する重要な役割を担っていますが,検査原理や検体特性の理解不足,採取条件や前処理の違い,観察・判定の技術差などにより思わぬ“pitfall”が生じることがあります.
●本特集では,尿定性・尿沈渣,髄液・体腔穿刺液,寄生虫検査について,現場で生じる代表的なpitfallとその回避策を整理します.

最新臨床検査学講座 遺伝子関連・染色体検査学 第3版
急速に発展する「遺伝子関連検査・染色体検査学」の基礎から,
最新知見までを広く理解できる定本テキスト!
●「令和7年版臨床検査技師国家試験出題基準」対応.
●「臨床検査技師学校養成所指定規則改定」対応.
●急速に発展し続ける遺伝子関連検査・染色体検査の領域について,確実に理解が進むよう基礎から丁寧に解説し,さらに新しい知見についても紹介している定本テキスト!
●改定された倫理ガイドラインの更新をはじめとした内容のアップデートに加えて,より理解しやすいテキストとなるよう解説の見直しを実施.また,遺伝子関連検査および染色体検査の基本と実践について,それぞれ続けて学べるように構成の変更も行った.

臨床外科 Vol.80 No.13
2025年 12月号
特集 Advanced LECSを安全に導入するためのバイブル〔特別付録Web動画付き〕
特集 Advanced LECSを安全に導入するためのバイブル〔特別付録Web動画付き〕 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 2026年より全面リニューアルし、隔月刊化と同時に1冊のページ数を大幅にボリュームアップ。さらに充実した特集と連載をお届けします。 (ISSN 0386-9857)
2025年:月刊、増刊号を含む年13冊 2026年:隔月刊(偶数月)、年6冊

消化器内視鏡35巻11号
内科と外科のコラボレーション手術の今
内科と外科のコラボレーション手術の今

医道の日本 Vol.77 No.7
2018年7月号
「妊鍼」治療の最前線 ―不妊症への鍼灸マッサージ―
「妊鍼」治療の最前線 ―不妊症への鍼灸マッサージ― 無資格者の参入も増えて、開拓から競争の段階に入った「不妊専門治療院」。改めて、鍼灸マッサージ師だからこそできる不妊治療が問われている。
体外受精など高度生殖医療の成功率を上げるための鍼灸治療や、医療機関との連携の仕方、鍼灸院での生活指導などについて紹介する。
