
レジデントノート Vol.21 No.9
2019年9月号
【特集】人工呼吸管理・NPPVの基本、ばっちり教えます
【特集】人工呼吸管理・NPPVの基本、ばっちり教えます 初期設定,鎮痛・鎮静,離脱など….若手医師だったら最低限知っておきたい人工呼吸管理のキホンをじっくり丁寧に解説!ICUに欠かせない機器の使いかた,エキスパートと一緒に1から学んでみませんか?

動画で学ぶ! 婦人科腹腔鏡手術トレーニング
〜手術経験数より大事なトレーニング法を知る〜
身近にTLHを学ぶ機会が無いとあきらめていませんか?ボックストレーニング・SNSを使った遠隔トレーニングなど,off the jobで腹腔鏡手術手技をスキルアップするための実際のメソッドを動画付きでわかりやすく伝授!環境整備,解剖など術前の準備や指導のポイントも解説.レベル別トレーニングでこれから始める人・より上を目指す人・指導医の全員に役立つ新時代の婦人科腹腔鏡手術書!

エキスパートの手元がみえる!血管エコー
解剖・正常像で身につく走査テクニックと検査手順、報告書作成まで
「正常像+走査の手元の写真+解剖像」をセットで示し,検査手順や走査方法をコンパクトに解説.実際に検査室で教えてもらっている感覚で読め,検査技術が身につく!プローブ走査とエコー像が連動した動画つき!

Medical Practice 2025年8月号
関節リウマチ~ガイドラインとその先のリウマチ診療
関節リウマチ~ガイドラインとその先のリウマチ診療 特集テーマは「関節リウマチ~ガイドラインとその先のリウマチ診療」.記事として,[座談会]実地診療における関節リウマチの診断と治療,[総説]関節リウマチ診療ガイドラインJCR2024,[セミナー]関節エコーを活用した関節リウマチ診療,[トピックス]関節リウマチに対する精密医療,[治療]関節リウマチ治療のfirst line 等.連載では,[One Point Advice] [今月の話題][知っておきたいこと ア・ラ・カルト]他を掲載.

臨床外科 Vol.79 No.3
2024年 03月号
特集 外科医必携 患者さんとのトラブルを防ぐためのハンドブック
特集 外科医必携 患者さんとのトラブルを防ぐためのハンドブック 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 (ISSN 0386-9857)
月刊、増刊号を含む年13冊

≪「看護管理」実践Guide≫
看護管理者のための医療経営学 第3版
働き方改革と医療機関の健康経営
本書は、看護管理者のために、医療制度と経営理論の基礎知識をわかりやすく解説するものです。さらに、ケーススタディの解説を通して、具体的な病院経営戦略の立て方・組織マネジメントに関するヒントを示します。
第3版では、近年の医療制度改革の動向、特に医療従事者の働き方改革や看護業務の効率化、医療機関における健康経営といった事項を中心に、大幅な加筆がなされています。
自学自習を助ける「試験問題」「参考資料・文献解題」「Glossary(基本用語集)」も収載した充実の一冊です。

胆と膵 Vol.43臨時増刊特大号
Vol.43臨時増刊特大号
特集:IgG4関連疾患大全―自己免疫性膵炎とIgG4関連硬化性胆管炎を中心に―
特集:IgG4関連疾患大全―自己免疫性膵炎とIgG4関連硬化性胆管炎を中心に―

胆と膵 2020年10月号
特集:自己免疫性膵炎の最前線 企画:神澤 輝実
特集:自己免疫性膵炎の最前線 企画:神澤 輝実

あたらしい人体解剖学アトラス 第2版
定価・ボリューム・内容 「ちょうどよい」アトラス、待望の改訂
立体的な構造がよくわかる、深部を透かして見せる表現技法「ゴースト」を採用するなど、解剖に初めて接する学生読者にとっての使いやすさを徹底的に追究したアトラス、11年ぶりの改訂。改訂にともない、CGによる美麗かつ精緻な人体解剖図は適宜追加・新図への入れ替えを行い、起始・停止、作用、神経支配、主要動脈が理解できる筋肉の表を新たに収載。増頁ながら学生の購入に配慮し定価据え置き。医学部のみならず、歯、看護、リハ系学部の解剖学講義・実習に最適。

ステロイド治療戦略<新装改訂版> 新装改訂
好評巻『jmedmook63 ステロイド治療戦略』が書籍化!
◆「最小限の副作用で,最大限の効果を得る」というコンセプトはそのまま,最新のエビデンスや知見を反映し,内容をアップデート。新たに6つの疾患を項目に加え,より充実した1冊となりました。
◆「エビデンス」の有無を意識しつつ,「医療者の臨床的経験」をもとに各領域のエキスパートがステロイドの使用法について解説しています。
◆ステロイドの使い方(開始基準や初期用量など)だけでなく,やめ方(減量の指標や減量速度、中止はできるか?)という「出口戦略」に重きを置いている点も特徴です
◆ステロイド診療に携わるすべての医療者に必携の1冊。本書の内容をヒントに,目の前の患者さんごとの考察を加えつつ,ベストな治療方針を探っていきましょう。
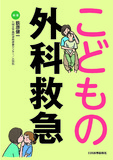
こどもの外科救急
小児のケガ、ヤケド、薬物中毒、異物誤飲…自信を持って診られますか?
こどもを診る機会のあるすべての医療従事者に役立つこと間違いなし!
こどもの外因系診療の要点とピットフォールをわかりやすく解説。保護者への説明の仕方もわかります。
専門外でもできること、専門家へのコンサルトのタイミングを明示しました。
小児救急の最前線で奮闘中のアツイ執筆陣がコツを伝授!

関節外科 基礎と臨床 Vol.38 No.4
2019年4月号
【特集】足関節果部骨折の診断と治療の最新アップデート
【特集】足関節果部骨折の診断と治療の最新アップデート

精神看護 Vol.26 No.3
2023年 05月号
特集 [保存版]「頓服」の迷い解決! 現場の問題を整理しよう
特集 [保存版]「頓服」の迷い解決! 現場の問題を整理しよう 「地域」へ向けて、本格的な変革期に入る精神科領域。大きな時代の流れも見据えつつ、自分の仕事も楽しんでいきましょう。この雑誌にはワクワク情報がいっぱいです。 (ISSN 1343-2761)
隔月刊(奇数月)、年6冊
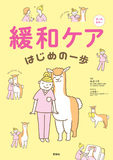
緩和ケア はじめの一歩
●エビデンスが確立されたスタンダードなケアはもちろんのこと、エキスパートならではの臨床知や最新知見を豊富に取り入れ、今日からすぐに使える知識をわかりやすく解説
●がんでも非がんでも、治療期でも終末期でも、一般病棟でも在宅でも、あらゆる場面で役立つ知識を簡潔にまとめました

腎と透析94巻1号
急性腎障害(AKI)
急性腎障害(AKI)

理学療法ジャーナル Vol.52 No.5
2018年5月号
特集 視床出血と理学療法
特集 視床出血と理学療法 視床出血のなかの約40%は四肢体幹の体性感覚の中継核である後外側腹側核を中心に発生する.しかし,その血腫は同核を越えてさらに広範囲に及ぶ.また,残りの60%の出血は他の視床核で発生する.視床核は脊髄,小脳,脳幹,大脳基底核,大脳皮質を中心として極めて機能的な線維連絡をなしている.さらに視床の周囲には内包や視床下部などが存在していることから,視床出血という診断には多種多様の病態が内在していることを知る必要がある.

皮膚病理用語辞典ベストアトラス
皮膚科医・病理医に必須の項目,皮膚病理組織学.病理標本を読み解くためには,皮膚病理独特の用語を習得する必要がある.
本書ではこの初心者の障壁となる用語について精緻な写真を用いて定義と使い方を示し,写真で読める用語辞典とした.
若手だけでなく,ベテランにもおすすめ.
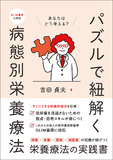
パズルで紐解く病態別栄養療法
●病態・栄養・薬剤・検査値の知識が結びつく栄養療法の実践書!
●すぐにできる栄養評価のコツや低栄養を見逃さないための視点・思考スキルを伝授!
●これからの成人の低栄養診断基準:GLIM基準に対応!
患者の栄養状態は、疾患の治療、回復、悪化防止と密接に関わっているため、その評価は適切な栄養療法を実施するうえで重要です。栄養療法を適切に行うためには、基本的な知識に加え、患者のさまざまな所見から問題点を抽出し、それぞれに対するアプローチを考えるトレーニングが求められます。
本書は、病棟で遭遇する栄養療法がカギを握る悩ましい疾患・病態について、質の高い実践的な症例を用いて問題点を抽出したのち、エキスパートとともにパズル形式で解決策を導きだす構成で、栄養評価や問題解決のための思考プロセスを惜しみなく解説します。さらに、非専門医・薬剤師もすぐに実践できるようGLIM基準を用いた栄養評価のコツも伝授。栄養療法を一通り学んだけれど、いま一つうまくいかない、いつもの栄養療法を見直したい医療者に手に取っていただきたい栄養療法の実践書です。
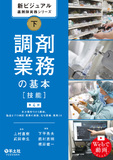
新ビジュアル薬剤師実務シリーズ 下 調剤業務の基本[技能]第4版
処方箋受付から調剤、監査までの病院・薬局の実務、在宅医療、薬局DX
写真が豊富でわかりやすいと大好評の教科書シリーズを改訂!改訂薬学教育モデル・コア・カリキュラムに対応,CBT対策に役立つ演習問題つき!OSCE対策に役立つ動画がWebで見られます

改訂第2版 胆膵EUS教本
コンベックスEUSを極める 描出の基本から穿刺の秘技まで動画で学ぶ
胆・膵疾患を専門とする消化器内視鏡医へ
【本書の概要】
胆道・膵臓疾患の診断ならびに治療において必要不可欠な内視鏡手技である“EUS”
本書では,コンベックスEUSで確実な胆膵スクリーニング観察,腹腔内血管や脾臓などの関連臓器の観察,そして最終的には縦隔の観察や術後腸管症例の観察をマスターできるよう,豊富な写真で図解しています。
また,折々の観察における臓器描出困難時のトラブルシューティング方法や,一歩進んだスコープ操作手技さらには観察画像の理解法など,初学者だけでなく,ある程度経験を積んだ先生方にも目からウロコで,十二分に役立つ“プロの技” も盛りだくさんです。
改訂第2版では,EUS-FNA の基本から極意をマスターするために新章を設けています。EUS-FNA における確実な病変の描出と穿刺について,豊富な動画によりマスターいただけます。
73の動画がQRコードからすぐに閲覧でき,膵臓,胆管など腹腔内臓器を描出するコツとワザがわかり,解剖の理解が進みます。
