
臨床画像 Vol.32 No.14
2016年10月増刊号
【特集】放射線科医必携 単純X線写真サイン集
【特集】放射線科医必携 単純X線写真サイン集

非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)診療ガイド2023

これからはじめる周産期メンタルヘルス 第2版
すべての妊婦さんが妊娠していることがわかって,うれしく幸せな気持ちでいるとは限りません.また,出産後すべてのお母さんが赤ちゃんをかわいく思えたり,元気に楽しく子育てができるものでもありません. そのような妊婦さん,お母さんに関わる助産師や看護師,また精神科や小児科の医師,地域の保健師,病院などで働く臨床心理士の方へ向けた周産期メンタルヘルスの入門書.

医師がチームリーダーになったら読む本
Dr.いすのチームリーダー養成塾
医師同士をまとめられず苦労していませんか?本書は,チーム医療・多職種連携の重要性も盛り込んでいるが,特に現場での苦労が多い「医師が医師同士をまとめること」にフォーカスしており,チームリーダーを目指すあなたへ,著者自身が長年試行錯誤しながら築き上げたリーダーシップ論&マネジメント論を自身の経験も振り返りながら解説した医師のための指南本.

小児骨折における自家矯正の実際
骨折部位と程度からわかる治療選択
小児骨折の治療にあたっては、成人との最大の違いである“成長軟骨板”の特性や特徴をよく理解したうえで、“自家矯正”が生じうることを常に頭に置いて保存治療あるいは手術治療の選択を行う必要がある。本書は、こどもの骨折に特有の自家矯正力にスポットを当て、自家矯正の傾向や程度が実感できる138ものバリエーション豊かな症例をもとに、部位ごとに、骨折後の変形がどの程度矯正されうるか明確に示している。

整形・災害外科 Vol.67 No.9
2024年8月号
広範囲腱板断裂に対する鏡視下手術
広範囲腱板断裂に対する鏡視下手術
腱板断裂に対する鏡視下修復術では,できるだけ再断裂を避けるための手術手技が望まれている。本特集では広範囲腱板断裂診療のエキスパートが開発した様々な術式や独自の工夫に加え,最新の解剖学的知見やリハビリテーションも紹介。広範囲腱板断裂に対する鏡視下修復術の最前線について理解できる。

誰も教えてくれなかった スピリチュアルケア
「スピリチュアルケアって何?」 本書は、臨床で働く医師、ナース、そしてすべての医療者のために、何よりも臨床に役立つ形で、わかりやすく、スピリチュアルケアについて解説した本です。スピリチュアルケアは、決して特殊なケアではなく、すべてのケアの基盤になるといえるほど、大切な考え方であり、役に立つ方法です。スピリチュアルケアを理解することによって、日々のケアのあり方が変わってきます。

染色法のすべて
●検査室で行われる染色法を網羅した,定評ある染色手技マニュアルの改訂新版!
●『MedicalTechnology別冊 最新染色法のすべて』を改訂・改題のうえ,新版として書籍化.
●現在,検査室レベルで行われている染色法について,項目を再検討して内容を大きくアップデート!
●各染色法について,目的,原理,準備,試薬,手技,染色態度,注意点を具体的に記載.検査室ですぐに染色できるよう,実利的にまとめられた,定評ある染色手技マニュアルの改訂新版!

PCIのための虚血評価
非侵襲的虚血評価スタンダードマニュアル
PCIの適応が考えられる病変(慢性冠動脈疾患)に対する非侵襲的虚血評価法を1冊にまとめた書籍。各々の検査法を解説するだけでなく,モダリティごとのさまざまな違いをPCIによる治療にどう活かし使い分けをするか(虚血評価をマルチモダリティでどう行うか)を実践的に解説。また,2019年3月に改訂された慢性冠動脈疾患診断ガイドラインの概説も掲載。
「基礎編」では,各モダリティの概要と特徴,ポイント,エビデンスを解説。「実践編」では各モダリティの実践的な使い分けを主要な症例を挙げて解説。さらに「症例解説」では,臨床の場で遭遇する知っておきたい稀な症例を取り上げ,より実践で役立つ内容としている。

かかりつけ医のための甲状腺疾患治療ガイド
ガイドラインに沿った甲状腺診療の普及に向けて
専門外なので,どのような検査をすればよいかわからない・・.そんな声におこたえし,甲状腺疾患の診断から治療,管理までをわかりやすく解説した“かかりつけ医”のための書籍です.
日常臨床で甲状腺疾患を疑い,必要な検査をして治療につなげられるよう,甲状腺機能検査や抗体検査など診断に必要な検査の理解,治療法の選択肢,選択基準,治療の終了の中止時期と方法,経過観察の対象,治療中での検査法とその時期,投与薬剤の相互作用や副作用,適正投与のための投与量の決定,抗甲状腺薬の副作用対処法などが書かれ,コンパクトながら盛りだくさんの内容です.

脳神経外科レジデントマニュアル
定評あるレジデントマニュアルシリーズ、待望の脳神経外科版。脳神経外科診療の現場においてレジデントレベルで必要とされる全般的事項を、実践的かつコンパクトにまとめた。実際の診療手順や処方例、患者管理、救急対応など具体的な記載にあふれ、本書を開けばすぐに知りたいことを確認できる。脳神経外科研修医はもちろん、脳神経外科疾患に携わる機会のあるすべての医師にお勧めしたい、ポケットサイズの頼りになる1冊。

胆と膵 2021年6月号
特集:胆道・膵管上皮内腫瘍の総整理:診断と治療の現状 企画:廣岡 芳樹
特集:胆道・膵管上皮内腫瘍の総整理:診断と治療の現状 企画:廣岡 芳樹

ST CHECK!
言語聴覚士国家試験必修チェック2026
分野別要点マスター
20年以上にわたり養成校で国試後に改訂を重ねながら使われてきたチェックリストをベースに,内容を整理しコンパクトで覚えやすい構成にリニューアル.言語聴覚士を目指す全ての受験者に推薦したい一冊.■2026年版の特長 ・過去5年分(第23回~第27回)の頻出キーワードをマークで表示 ・「出題基準」の大項目に準じた項目立て ・養成校の教員による効果的な学習方法の紹介
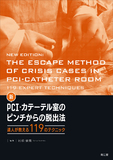
新 PCI・カテーテル室のピンチからの脱出法
達人が教える119のテクニック
PCI困難例やカテーテル室のトラブル解決策をエキスパートが解説した好評書『達人が教える!PCI・カテーテル室のピンチからの脱出法119』の改訂新版.今版ではマイクロカテーテル,ダイアモンドバック,3Dワイヤリング法などの新デバイス・手技についても盛り込み,「どうしてもうまくいかないときの奥の手」などのTipsも充実させた.ピンチに立ち向かうPCI医へ贈る一冊.
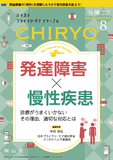
治療 Vol.105 No.8
2023年8月号
発達障害×慢性疾患
発達障害×慢性疾患 プライマリ・ケア医が慢性疾患の診療にあたる際,患者が発達の問題を抱えているために診療が上手くいかないケースも珍しくないのではないでしょうか.本特集では「発達障害×慢性疾患」のさまざまな組み合わせごとに,具体的な治療計画の立て方・説明のコツ・患者とのつきあい方を実践的にまとめました.また,当事者×医療者の対談記事もあり,発達障害の特性についてさまざまな角度から理解を深めることができます.若手医師に留まらず,患者を紹介できる施設が近くになく,試行錯誤しながら診療にあたっているすべての医療者を後押しする1冊!
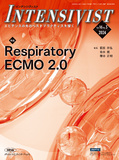
INTENSIVIST Vol.16 No.3 2024
2024年3号
特集:Respiratory ECMO2.0
特集:Respiratory ECMO2.0

機能性消化管疾患の診断と治療
神経消化器病学への招待
過敏性腸症候群,機能性ディスペプシアなど器質的異常に乏しく診療に苦慮することも多い機能性消化管疾患(脳腸相関病)の基礎から臨床までをカバー.基礎編と実践編からなる臓器別の第1~4章,診療の実際に役立つ第5章,専門医試験に挑む力がつく第6章(問題・解答・解説)で,消化器科・内科・総合診療科,開業医に必携の1冊

整形外科Knack & Pitfalls
整形外科手術の要点と盲点
手術に初めて参加する研修医から執刀を任され始めた若い整形外科医を対象に,整形外科手術の全体像を概説.今までの成書ではあまり扱われてこなかった器具の扱い方や,術前準備にも多くのページを割いており,整形外科手術全体を通した,「コツ」と「落とし穴」を学ぶことができる.美しい器具写真や手技のシェーマも,一層の理解を助ける.手術に臨む前,まずはじめに手にとって欲しい一冊.

クリニカルスタディ Vol.46 No.13
2025年11月臨時増刊号
苦手な方の多い「栄養生化学」「病理学」「薬理学」「微生物学」の4科目を、ポイントを押さえながらしっかり強化できる国試対策入門ドリルです!
「穴埋めドリル」と「国試過去問題」で、各科目の基礎知識から国試に必要な力まで無理なく身につけることができます。
●11月増刊号のおすすめポイント!
重要知識をおさえる! 穴埋めドリル
まずは、各科目の重要知識を書き込み式の穴埋めドリルでおさらい!
効率よく学ぶことができます。
実践で腕試し! 国試過去問題
穴埋めドリルが終わったら、実際の過去問題にチャレンジ!
各科目をしっかりマスターできます。

Dr.Bonoの生命科学データ解析 第2版
大好評!すらすら読めるバイオインフォマティクスの教科書、全面改訂
バイオインフォマティクスの第一人者、坊農秀雅先生書き下ろしによる、ゲノム配列データの解析を中心に概観したコンパクトな教科書、3年半ぶりの改訂。改訂に際し変化の著しいデータベース、ツール、アプリなど全編にわたりアップデートを行い、macOS以外の環境にも配慮し加筆。生命科学分野等で、次世代シークエンサー(NGS)やゲノムの解析などに携わるときの土台を身につけることができる、入門者の力強い味方。
