
最新臨床検査学講座 医動物学 第2版
●使いやすく学びやすいコンパクトな構成は維持しながらも,最新の情報を盛り込みつつつ内容を見直し,カラー写真の掲載も増やすなど,さらに充実した内容へアップデートした改訂版.
●寄生虫疾患についてわかりやすく解説されており,教科書としてのみならず,本領域の専門家にも役立つ内容.

軟部腫瘍のMRI
あらゆる部位に発生し組織型も数多くあるため診断が難しい軟部腫瘍。第一線で活躍する執筆陣が、軟部腫瘍で主流となりつつあるMRIにおいて“どのような所見に注目するか”“どのような手順で診断を進めるか”“どのように鑑別診断を絞り込むか”などを実践的かつ詳細に解説した、これまでになかった一冊。レベルアップしたい放射線科医、整形外科医必読。
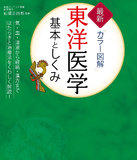
最新カラー図解 東洋医学 基本としくみ
基礎理論から東洋医学の診察・診断法、漢方薬、鍼灸・気功の治療の最前線、東洋医学の食養生、東洋医学による現代病の治療まで、わかりやすく東洋医学を学びたい人は必携の一冊!
※本書の著者情報は2018年の初刷刊行時の情報を基にしています。

分娩の生理・病態に基づいた
頸管熟化と分娩誘発法
経腟分娩に必須である頸管の熟化について産科医,助産師向けに平易に解説。
頸管熟化のメカニズムとその指標であるBishopスコアから,器械的な頸管熟化の方法・手技,および頸管熟化薬の使用法までを,エビデンスに基づき豊富な図表やイラストでビジュアル解説。

がんサポーティブケアのための漢方活用ガイド
がん診療において出現するさまざまな症状に対して漢方を活用するために,漢方やがんサポーティブケアに関する基礎知識をふまえながら,それらの症状に対する漢方の使用法や主要な漢方製剤について,症例・エビデンスを交えながら解説.がんサポーティブケアに漢方を取り入れたいと考える医療者必携の一冊.

臨牀消化器内科 Vol.39 No.10
2024年9月号
自己免疫性肝疾患とICI(免疫チェックポイント阻害薬)による肝障害
自己免疫性肝疾患とICI(免疫チェックポイント阻害薬)による肝障害
自己免疫性肝疾患の有病率は増加傾向にあり,かつ依然として難治の疾患であることから,肝硬変や肝移植における成因としてきわめて重要である.
ICIによる肝障害については本特集でも触れられているとおり,現在肝臓専門医による「ICIによる肝障害の診断指針」が作成され,今後は治療指針も作成される運びとなっている.

医学のあゆみ283巻11・12号
自己免疫性肝疾患――いま何が問題となっているのか?
自己免疫性肝疾患――いま何が問題となっているのか?
企画:田中 篤(帝京大学医学部内科学講座)
・本特集では,臨床において重要であり,かつ日本から優れた仕事がでている自己免疫性肝疾患のテーマを選び,それぞれのエキスパートに執筆をお願いする.
・自己免疫性肝炎(AIH)は中年以降の女性に好発する肝炎である.原発性胆汁性胆管炎(PBC)は,中年以降の女性に好発する慢性進行性の胆汁うっ滞性肝疾患である.
・原発性硬化性胆管炎(PSC)は肝内外の胆管に多発性・びまん性の狭窄が生じ,胆汁うっ滞をきたす慢性肝疾患である.

術後アセスメント・ケア ポケットBOOK
POINT1 経過ごとに必要な知識がわかる
患者さんの状態が大きく変化する術後は、「術直後」「術後急性期「術後合併症」と3パートに分けて、見逃せない観察ポイントやケアの知識をしっかり解説。術前から術後まで通して1冊でコンパクトにまとめています。
POINT2 覚えきれない知識をカバーできる
見逃してはいけない観察ポイントやケアの根拠、覚えきれない評価スケール、さまざまな数値も、本書を持ち歩くことで、ベッドサイドなどでいつでも確認できます。
POINT3 さまざまな診療科の患者さんに対応
7領域(消化器・呼吸器・循環器・脳神経外科・婦人科・泌尿器・整形外科)の主な手術と観察・ケアもあわせて掲載。最低限おさえておきたいポイントがわかって安心です。
POINT4 いますぐ知りたいことをすばやく検索
すぐに知りたい情報や知識が調べやすいように、文章は少なめ、図表スタイルが中心。“いま必要なこと”だけをスピーディに調べて、すぐ実践できるような構成です。
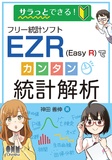
サラっとできる! フリー統計ソフトEZR(Easy R)でカンタン統計解析
統計解析の定番ソフト「R」が、EZR(Easy R)で手軽に使いこなせる!
本書は、統計解析の定番ソフト「R」がGUIで使いこなせる「EZR(Easy R)」を活用して、初心者でも手軽に統計解析ができる方法を解説する入門書です。
EZRを使えば、コンソール入力を行わなくても、マウスでサクサク解析を進めることができます。しかも、EZRの開発者である著者が専門とする医療分野を中心に、統計解析の現場で活用されている本格的なパッケージなので、安心して使うことができます。
本書では、多くの方に親しみやすいテーマを扱いながら、日常生活から実務まで役立つ統計解析の基本的な考え方をやさしく解説するとともに、サンプルデータを用いたわかりやすい事例をとおして、EZRを操作しながら統計解析手法の基本を押さえることができます。
EZRと本書で、サラっとカンタンに、統計解析を始めましょう!

消化器内視鏡36巻4号増大号
十二指腸・小腸疾患アトラス
十二指腸・小腸疾患アトラス

作業遂行6因子分析ツール ―クライエントの思いと主体的な作業の実行状況を支援する―
私たちが作業療法で対象としている人々は,なぜ生活行為をうまくできていないのだろう?
作業遂行6因子分析ツール(Occupational Performance Analysis Tool with 6 Factors:OPAT6)とは、クライエントの作業遂行を「主体的な作業の実行状況」として捉え、その作業遂行にどのような要因が関連しているか多角的に分析し、介入方針やアプローチの立案を導く臨床ツールです。
作業遂行へ関連する因子を、「健康状態」「心身機能」「活動」「環境」「認識」「情緒」という6つの因子とし、特に「認識」「情緒」という2つの因子はクライエントの“思い”が表出されている因子としています。
特に回復期リハビリテーションでは、クライエントの生活行為における課題が幅広いため、それら多くの課題を並行しながらも、優先度を見定めつつ、作業療法は展開されています。本ツールを活用することで、大局的な思考が求められる作業療法士ならではの思考過程が視覚化され、かつ、クライエントの主体性や内的動機付けを具体的に整理でき、さらに、個別性を尊重しつつも偏りのない作業療法介入が実践できるようになります。
作業療法は、作業を介在させることで、内界と外界をつなげることができる、唯一無二の療法です。さあ、目の前のクライエントと一緒に、あなたの作業療法をしてみましょう!

≪小児科ベストプラクティス≫
新分類・新薬でわかる小児けいれん・てんかん診療
Classification and Practice
新規抗てんかん薬の導入と,発作型を重視したILAE分類の改訂により,激変するてんかん診療.抗てんかん薬の単剤・少量・短期療法を基本に,合理的多剤併用療法,無治療,禁忌薬・選択薬の変更を詳細に紹介.
けいれん・てんかんと関わることが多い小児科医に,てんかんのとらえ方・治療法の選び方など新しいスタンダードを専門家が読みやすく紹介.

介護保険の実務 令和6年度版
保険料と介護保険財政
◆保険料と介護保険財政を中心として、介護保険における保険者事務について詳しく解説した実務書です。事例や運用をできる限り記述する一方、介護保険制度の基本的な考え方も説明しています。解説には法令上の根拠を示していますので、知識の整理等にも役立ちます。

臨床雑誌外科 Vol.87 No.9
2025年8月号
高リスク患者に対する周術期管理の要点
高リスク患者に対する周術期管理の要点 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

慢性臓器障害の診かた、考えかた
慢性臓器障害とは,慢性心不全,慢性肺疾患,慢性腎臓病などのCommon diseaseをひとくくりにした呼称であり,本書が初めて提唱する概念です.個々の病態はよくみるものばかりですが,これらを総合診療の現場で臓器群(横軸),進行度(縦軸)ごとに評価することで全く新しい診療スタイルが見えてきます.総合医と専門医の協同を促進する診療フレームワークでもある本概念の実用性と面白さを詳細に解説します.

甲状腺疾患診療実践マニュアル 第4版
甲状腺診療の現場で好評を博している実践書の最新版.甲状腺疾患の診断と治療のエッセンスが簡潔にまとめられており,必要なときに必要なところだけ読んで役立てられるように工夫されている.今回の改訂にあたって内容を最新情報にアップデートし,コンパクトながらさらに充実した内容となった.内科レジデント,一般臨床医におすすめの1冊.

看護学生の勉強と生活まるごとナビ
自律的に過ごすための23のレッスン
看護学生に求められる「勉強」と「生活」を網羅!
看護学生に求められる「勉強」と「生活」について、イラストを交えてわかりやすく紹介するガイドブック。
学生生活をイメージできるよう、「看護とは」「看護師に必要な力」などを整理したうえで、講義・演習・実習それぞれの学びと面白さ、教科書の読み方やノートの取り方、定期テストや国家試験に向けた取り組みなどを具体的に示しています。
対人関係やコミュニケーションのアドバイスも、ぜひご活用ください。

眼科 Vol.61 No.10
2019年9月臨時増刊号
眼科と薬剤
眼科と薬剤 眼科は外科系診療科ですが,日常の外来診療の主役は薬物療法です。
第1部では,よく診る疾患に対する薬物治療を分野別に診療にあたって押さえておくべき内容にトピックスを交えて解説しています。
第2部では,薬物治療の知識と同様に大切な薬物の副作用に関する知識を,クロロキンやエタンブトールという古典的ながら必須の知識から,ヒドロキシクロロキンや各種抗がん剤といった近年眼合併症に遭遇する機会の増えている薬剤まで,11項目ピックアップして解説しています。
現代の眼科臨床医として知っておくべき薬剤に関する知識が一通り網羅できる虎の巻となっています。
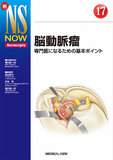
≪新NS NOW 17≫
脳動脈瘤
専門医になるための基本ポイント
No.17では,「脳動脈瘤」を取り上げた。
本書では,専門医を目指す若手医師に向け,脳動脈瘤に対するクリッピング術・外科的治療手技を解説。
経験豊かな執筆陣が,豊富なイラスト・写真とともにPitfall,Essential Techniques,さらにをAdvanced Techniquesを随所に交え,手技ならびにその基本ポイントを丁寧に紐解く書籍となっている。
これから脳神経外科専門医を目指す若手医師には必携の1冊である。
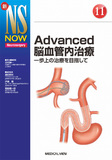
≪新NS NOW 11≫
Advanced脳血管内治療
一歩上の治療を目指して
No.11では脳血管内治療をテーマに取り上げた。カテーテルを用いた脳血管内治療は適応・術式・使用するデバイスなど,現在脳神経外科において最も注目され議論が白熱する話題といって過言ではない。欧米を中心に手術数を増やしている本術式は,今後わが国においてもその数と重要性を増していくであろう。
本書は現在広く血管内治療が行なわれている疾患ごとに章を設け,いかにカテーテルを送り込むか,どのように手術器具を使いこなすかについて仔細に学べる1冊となっている。
