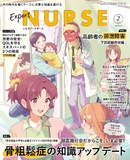
エキスパートナース Vol.42 No.2
2026年2月号
◆超高齢社会だからこそ、いま必要! 骨粗鬆症の知識アップデート
◆高齢者の排泄障害[下部尿路症状編]
◆超高齢社会だからこそ、いま必要! 骨粗鬆症の知識アップデート
◆高齢者の排泄障害[下部尿路症状編]
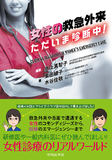
女性の救急外来 ただいま診断中!
救急外来や当直で遭遇する女性のコモンディジーズから,妊婦のエマージェンシーの対応まで,“女性を診る”機会のあるすべての研修医や内科医師に絶対お薦めの書!

日本栄養治療学会JSPEN NST専門療法士認定試験 過去問題集
NST専門療法士認定試験対策本の『一般社団法人日本静脈経腸栄養学会NST専門療法士認定試験過去問題集Ⅰ』待望の改訂新版.近年の出題傾向をふまえて過去問題を精選し,丁寧でわかりやすい解説を付記.「関連する重要事項」も併せて掲載し,試験対策としてはもちろん,NST業務に求められる幅広い知識の習得にも役立つ一冊.
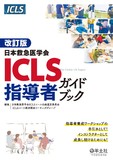
改訂版 日本救急医学会ICLS指導者ガイドブック
ICLSインストラクターの必携書!指導の基礎知識や,ICLSコース特有の指導技能,指導者養成ワークショップの要点がしっかりわかる.さらに指導者として継続的に成長していくためのエッセンスも満載.

職域の健康診断マニュアル
産業医に期待される最も重要な職務が健康診断への関与であり,その対応力が産業医活動の質を左右します。本書では,職域の健康診断ついて,その実施内容~結果の取り扱いに関する168の実務的な質問を取り上げました。経験豊富な専門医が,各分野の専門知識に基づき熟考した回答をコンパクトに掲載しています。
本書の特徴
*職域の健康診断に関するあらゆる疑問・質問を細分化して網羅
*健康診断の企画者,実施者,職場の健康管理担当者,人事担当者それぞれの立場を理解し,的確に対応できるようになる
*労働者への指導方法,受診勧奨の目安など,悩ましい事項を具体的に解説
*総合診療の参考書としてもおすすめ

消化器内視鏡36巻4号増大号
十二指腸・小腸疾患アトラス
十二指腸・小腸疾患アトラス

自己免疫性脳炎・関連疾患ハンドブック
従来原因不明の難病とされてきたが,研究の発展によって救命・予後改善が期待できるようになってきた自己免疫性脳炎と関連疾患の診断と治療について解説.睡眠病,認知症,精神症状の原因も自己免疫性脳炎だった?治療可能な見過ごされている疾患,自己免疫性脳炎の本邦初のハンドブック.自己免疫性脳炎の歴史から抗体の種類,各種疾患群の病理・検査・治療法.各種抗体の特徴を本邦の専門家が執筆・網羅しています.

≪画像診断別冊 KEY BOOKシリーズ≫
肝胆膵の画像診断 ─CT・MRIを中心に─ 改訂第2版
肝胆膵画像診断の決定版!
好評初版より全面改訂し,総論では各臓器の解剖,鑑別診断を画像・シェーマ・表で丁寧にわかりやすく解説.
各論では肝胆膵領域の各種疾患を網羅.
画像所見,鑑別診断のポイントなども整理され,臨床に役立つ内容満載の1冊.

画像診断 Vol.46 No.1(2026年1月号)
【特集】ガイドラインに沿ったMRIのルーチンプロトコール
【特集】ガイドラインに沿ったMRIのルーチンプロトコール 主要領域の各疾患について、ガイドラインが推奨する撮像法を基にした、現場で実際に活用されているルーチンプロトコールを紹介。撮像目的ごとのプロトコール、シーケンス別の意義や工夫、読影ポイントなどを、実践的に解説!

造血細胞移植ポケットマニュアル 第2版
好評頂いた初版を大幅アップデート。移植に携わる全ての医療者に役立つ充実の改訂版。
造血細胞移植について具体的にわかりやすくまとめた実践的マニュアル。移植医、移植スタッフはもちろん、血液内科医にも参考になる書。6年ぶりの大幅改訂になるが、初版同様、基礎知識から臨床の現場で役に立つ細かな注意点までを網羅。さらには移植適応の考え方だけではなく予後予測、移植までの治療、移植前処置、移植後再発対策も含めて解説。移植を成功させて完治へ繋げるために病棟・外来の診療現場で広く役立てて頂きたい。

自己炎症性疾患診療ガイドライン2026
自然免疫の異常によって起こる稀少疾患である自己炎症性疾患は,近年その定義や理解が大きく変化している.従来は小児科領域を中心に扱われてきたが,成人医療でも注目されるようになってきた.本ガイドラインは2017年版の改訂版として,新たな疾患が加わり,最新の知見と推奨される治療を詳細に解説している.小児科医のみならず,成人領域の医師にも幅広く活用できる1冊となった.

救急整形外傷レジデントマニュアル 第2版
整形外科医「以外」のための整形外科当直マニュアル。この本さえあれば、当直中の整形外科疾患の対応には困らない。どの時点で専門医にコンサルトすればよいかも判断できる。診療中に常備しておきたい整形外傷本の決定版! 第2版では、6章「骨折」のX線写真をより典型的なものに更新し、7章「重症軟部組織感染症」を充実。9章「高齢者関連」を新設し、「骨脆弱性骨折」「非定型大腿骨骨折」などに関して追記。*「レジデントマニュアル」は株式会社医学書院の登録商標です

消化器内視鏡2025年37巻増刊号
消化管感染症のすべて2025
消化管感染症のすべて2025

カラー写真で一目でわかる 経食道心エコー 第3版
撮り方、診かたの基本とコツ
入門者に最適の好評書が改訂!豊富なカラー写真で手技を基本から丁寧に解説.人工心臓,SHDインターベンション,3DTEEなど注目の情報もカバー.経食道心エコーを習得するならまず本書から!

しくじり症例から学ぶ精神科の薬
病棟で自信がもてる適切な薬の使い方を精神科エキスパートが教えます
レジデントノートの好評連載が単行本化!入院患者さんが精神症状を発症したとき,起こりうる「しくじり」を防ぎ,病棟トラブルを解決!研修医・非専門医が精神科の薬を使うなら必ず読んでおきたい一冊

救急外来 オススメ処方・ダメ処方
すべての診療科のCommon Senseを一気にアップデート!
各診療科スペシャリストたちによる,現場ですぐに使えるオススメ処方・ダメ処方.“各診療科のあたりまえを全科のあたりまえに”をテーマに,役に立つTips & Pitfallsについて薬剤の処方を中心に簡潔にまとめました.救急・循環器・呼吸器・消化器・感染症・小児科・産婦人科など,20テーマに及ぶ内容を網羅しており,フレッシュな先生にも,ベテランの先生にも有用な,まさにすべての臨床医にご一読いただきたい渾身の一冊です!
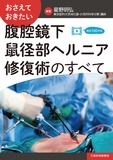
おさえておきたい 腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術のすべて
フルカラーの図と豊富な手術動画で手技への理解が深まる!
腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術における基本手術のすべてを網羅した1冊!
鼠径部ヘルニア(脱腸)は年間約15万件手術が行われており、外科・消化器外科では診る頻度の高い疾患の1つです。
本書では、鼠径部ヘルニアに対する治療の中でも技術の習得が難しいとされる、腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術(TAPP法、TEP法)について、手術の流れや習得すべきポイントをわかりやすく丁寧に解説しました。
外科・消化器外科の若手医師や、内視鏡外科学会技術認定医取得を目指す医師にとって必携の1冊です。
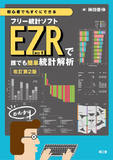
初心者でもすぐにできるフリー統計ソフトEZR(Easy R)で誰でも簡単統計解析 改訂第2版
フリー統計ソフト「EZR」(Easy R)を使って統計解析を始める時に読む“最初の一冊”.インストールから解析機能の使い方,論文作成・学会発表での応用まで,使用シーンごとに実際の画面を見ながら開発者自身がわかりやすく解説.EZRの最新アップデートに対応し、グラフ作成機能などの解説を改訂.統計解析ソフトを使ってみたい,最初の一歩におすすめの一冊.

シンプル生化学 改訂第7版
初版から四半世紀以上にわたり改訂を重ねてきた生化学の好評教科書。成書では詳しすぎる、入門書では物足りないというニーズに応える。単調な知識の羅列ではなく、文章構成に流れがあり、初学者でも無理なく読み進められる。今改訂では新知見の加筆・修正を行ったほか、章・項目の順序を大きく入れ替え、より流れを意識して学べる構成となった。

術後痛ガイドライン
周術期医療において適切な術後の鎮痛管理は,患者の早期的な離床や臓器合併症を予防することが示されている.本ガイドラインは,術中から予防的に開始する術後鎮痛法や術式に応じた鎮痛法に加え,QOLの低下に繋がってしまうような慢性術後痛についても詳述している.また,小児やオピオイド慢性服用患者など特別な配慮を必要とする患者への注意点も解説.周術期にかかわる全医療者必携の指針に仕上がっている.
