
クリニカルガイド小児科
専門医の診断・治療
小児科の外来や病棟で遭遇する主な症候・疾患について,①患児の病態生理を把握し,②症候から鑑別診断を行い,③診断が確定した各疾患の治療を行う際の手順・要点を,診断・治療のステップがわかるフローチャートを提示したうえで,その流れに沿って実践的に解説した.小児科専攻医必携の1冊!

救急整形外傷レジデントマニュアル 第2版
整形外科医「以外」のための整形外科当直マニュアル。この本さえあれば、当直中の整形外科疾患の対応には困らない。どの時点で専門医にコンサルトすればよいかも判断できる。診療中に常備しておきたい整形外傷本の決定版! 第2版では、6章「骨折」のX線写真をより典型的なものに更新し、7章「重症軟部組織感染症」を充実。9章「高齢者関連」を新設し、「骨脆弱性骨折」「非定型大腿骨骨折」などに関して追記。*「レジデントマニュアル」は株式会社医学書院の登録商標です

小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン 2024年12月改訂 第2版
7年ぶりとなる改訂第2版はMinds 2020に準拠、また推奨作成にはエビデンスだけでなく、価値観や容認性、実行可能性など様々な視点における合意形成方法としてGRADEが提唱する「EtD frameworks」を用いた。2017年版で扱った8領域に、肺、耳鼻咽喉・頭頸部、膠原病を加えてパワーアップ。巻頭には各疾患領域の診療アルゴリズムが収載した。
医師、看護師、薬剤師、心理士など多職種に向けた、がん・生殖医療の今を集結させた一冊。

改訂2版 病院前新生児蘇生法テキスト
【新生児蘇生法講習会Pコース公認テキスト】
救急救命士・救急隊・消防士などを対象とした新生児蘇生法(NCPR)講習会(Pコース)公認テキスト。医療施設外での出生を想定し、バッグ・マスクや胸骨圧迫といった標準的な新生児蘇生処置の習得を目指す。出生時の呼吸・循環生理、救急搬送時の留意点などの必須知識も収載。NCPR 2020を反映した改訂2版。講習会予習動画付き。
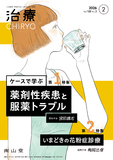
治療 Vol.108 No.3
2026年2月号
【第1特集】ケースで学ぶ薬剤性疾患と服薬トラブル
【第2特集】いまどきの花粉症診療
【第1特集】ケースで学ぶ薬剤性疾患と服薬トラブル
【第2特集】いまどきの花粉症診療 【第1特集】
薬剤性疾患や服薬トラブルは症状が多彩で見逃されやすく,診断や治療に難渋することも少なくありません.「薬が原因かもしれない」と見抜くポイントや処方変更などの対応をケーススタディ形式で学び,実践的対応力を磨きましょう!
【第2特集】
患者数の増加・低年齢化が進み,いまや国民病ともいわれる花粉症.最新の薬物治療に加え,食事・栄養面からのアプローチ,小児や妊娠・授乳中の女性の治療など,プライマリ・ケアで必要となる花粉症診療の知識を整理しました.

ICU頻用薬 使い方のリアル
●「シチュエーション別」に「リアル」なICU頻用薬の使い方を解説!
・薬を使いこなすのに必要なエビデンスを解説します。
・臨床家の経験やコツをこっそりお伝えます。
●集中治療医からon the jobトレーニングを受ける機会の少ない若手医師におすすめ。
中堅以降の医師が読んでも面白いスペシャリストの経験がつめこまれています。
●様々なシチュエーションで,重症患者に「どの薬を選択し,どれくらいの量で使い,どう調整すればいいのか?」というお悩みを解決します!

≪オペナーシング2022年秋季増刊≫
心臓血管外科手術実践マニュアル
【心臓血管外科手術をまるっとやさしく解説!】
MICS・TAVIなど、新しい手術も含む全18術式を解説。基本知識・流れ・オペナースの動きが写真とイラストでやさしくわかる!ほかにも手術の理解に役立つ解剖イラスト、実践に活かせる便利な略語一覧、補助手段の仕組みや麻酔の影響まで網羅した、活用度100%の1冊。

TKA/UKAの匠[Web動画付]
思考と技巧
孤軍奮闘するドクターへ,2人のトップサージャンがTKA,UKAの全テーマを忖度なしに徹底的に解説します.手術の難所を突破するための独自のテクニック・コツを,考え方や裏付けとともにご紹介.2人の匠の技がポイント動画付きで丸ごと味わえて,違いを比較しながら読み進めることもできます.ナビやロボットがなくても自信をもって手術に臨めます.

レジデントノート Vol.24 No.15
2023年1月号
【特集】救急・ERを乗り切る! 整形外科診療
【特集】救急・ERを乗り切る! 整形外科診療 救急で“これだけ”は押さえたい整形外科診療のポイントをシンプル&明確に解説.よくある主訴や受傷機転での的を絞った診察の進め方や画像検査の選び方・読影のコツ,シーネ固定などの手技がやさしく身につきます.

グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン2023
本ガイドラインは,日本骨代謝学会によって2004年に策定された『ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン』の改訂版である.近年,骨粗鬆症薬の開発,本疾患に対する薬剤の評価が精力的に行われ,膨大なエビデンスが蓄積してきた.そこで,本疾患の診療のエキスパートがこれらの科学的根拠を基に合議的会議を経て,現状における最善の診療法,治療法の「推奨」をまとめ,『グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン2023』として発刊することとなった.本ガイドラインは,グルココルチコイド(ステロイド)で治療を行う疾患の担当医全般を対象としており,骨粗鬆症診療が専門ではない一般の医師にもおすすめする.

日本集中治療医学会 専門医テキスト 第4版
日本集中治療医学会による「日本集中治療医学会 専門医テキスト第3版」に続く改訂第4版.
日本の集中治療医学の標準的教科書を作ることを目的に,集中治療専門医を目指す医師が習得すべき基本的な知識から新しい知見を提供するために作成されたテキスト.

言語聴覚士テキスト 第4版
言語聴覚士必読のテキストの最新版!
●言語聴覚士に必要な障害学にかかわる領域を網羅し,重要かつ必要不可欠な知識・情報を,各分野の第一人者がわかりやすく解説.
●新たな知見・情報を取り入れて全体的に見直した定評あるテキストの改訂版.
●言語聴覚士学校養成所指定規則で新規科目として設定された「地域言語聴覚療法学」「言語聴覚療法管理学」の章を新設.

医学のあゆみ296巻5号
第5土曜特集
革新する腎臓病学――臨床と研究の最前線
革新する腎臓病学――臨床と研究の最前線 企画:南学正臣(東京大学大学院医学系研究科腎臓内科学)
稲城玲子(東京大学大学院医学系研究科慢性腎臓病(CKD)病態生理学)
・高齢化の進行,生活習慣の多様化,さらには気候変動や環境汚染といった要因により,腎臓病は世界規模で増加し,国際的な課題となっている.一方で,新規腎保護薬の登場や病態解明の飛躍的進歩により,これまで長らく血圧や血糖,蛋白尿の管理を中心としてきた治療体系から,新たな段階へと踏み出しつつある.
・本特集では,腎臓病の基礎から病態理解と治療のアップデートまで,さらには新規バイオマーカー,オミクス解析,ビッグデータ解析など診断技術の進展や,再生医療,人工腎臓などのフロンティア領域,終末期医療,医療経済,倫理的課題など,腎臓病学の最新動向を豊富に取り上げる.
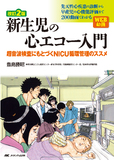
改訂2版 新生児の心エコー入門
【診断・治療に活かす知識・技術を動画で学ぶ】適切な手技で的確な心エコー所見を得て、病態に応じた循環管理を展開することが、新生児を診る医師には求められる。循環管理の基本から、心形態の観察、心機能評価、先天性心疾患の管理まで、スマートフォンですぐアクセスできる超音波動画で解説。心エコーと新生児循環管理の最前線もこの一冊に。心エコー検査の習熟を目指す新生児科医・小児循環器科医必携の書。

リウマチ・膠原病診療ゴールデンハンドブック 改訂第2版
多彩な症状を呈するリウマチ・膠原病の診療について,臨床症状の見極めかたから,各種検査の要点,治療法・治療薬に関して知っておきたい知識,各疾患へのアプローチ,エマージェンシーまで,そのエッセンスを凝縮したポケットブック,待望の改訂版.進歩の著しい薬物療法に関するアップデートを行ったほか,研修医や若手医師が知っておきたいエマージェンシー対応も充実化.最新の分類基準も反映し,リウマチ・膠原病診療の“いま”に沿った内容を提供する.
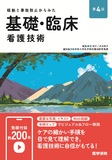
≪からみた看護技術≫
根拠と事故防止からみた
基礎・臨床看護技術 第4版
基礎看護技術のみならず臨床で実践される看護技術の基本を網羅
本書は、基礎教育と臨床現場とのギャップを可能な限り埋めるべく、基礎看護技術はもちろんのこと、臨床で実際に行われている看護技術をも幅広く取り上げ、根拠、コツ、留意点を丁寧に記している。また、写真や動画で看護技術の細かい手順を目で見て理解できる。今回の改訂では、最新情報にアップデートし、一部動画や写真を差し替えている。約200本の動画はインターネット上でいつでも閲覧できる。

脳神経内科クリニカルアップデート Part2
●日本最大級の脳神経内科領域情報サイト「Medixpost」発の好評書籍 第2弾!
●「治療選択肢が増えたが,どれを選ぶべきか迷う」「忙しい診療の合間に最新情報を効率的にキャッチアップしたい」「エビデンスに加えて実際の診療の“勘所”も知りたい」─このような先生方のお悩みにしっかり答える1冊です
●書籍化にあたり,全項再編集。
●本書第一弾とあわせてご覧頂くと,斯界の重要情報を効率よく収集できます。

できる!差がつく!
自信がもてるカルテの書き方
研修医や若手医師向けに,質の高いカルテ作成のための基本的な事項や気を付けるべきポイントなどを解説しました.
様々な文書ごとに「しくじり記載例」と「模範例」で一目瞭然!なかなか教えてもらう機会のない,紹介状を受けたとき・送るときのマナーや礼儀,病状説明や入退院時の書式,患者死亡時の書類,病歴システムで要求される記載のコツなども解説.
外来や病棟,集中治療や救急の現場で,すぐに役立つ必携の書です.

≪Gakken KEYBOOKビギナーズ≫
循環器画像診断 一問一答
心臓CT・MRI・核医学の読影に役立つ基礎知識
循環器診療にかかわるすべての医療職者に向けて,循環器画像診断に必要な基礎知識をQ&A形式でやさしく解説!
解剖を中心とした基本的内容から,心臓CT・心臓MRI・心臓各医学検査の技術や診断について疑問を解決できる一冊.

ブラッシュアップ急性期外科
Brush up Acute Care Surgery
急性虫垂炎に始まり,消化管閉塞・穿孔・虚血・出血から急性膵炎・胆嚢炎,食道破裂に至るまで.中核病院の一般外科医が,非外傷の緊急手術として扱うことが多い疾患・病態について,豊富な手術経験と圧倒的なエビデンスを踏まえ,その歴史と現状を整理し,数々の疑問に答えます.あの『ブラッシュアップ急性腹症』の著者が6年ぶりにおくる珠玉の新作.若手外科医はもちろん,すべてのドクターの必読書です.
