
結核を除外するとはどういうことか教えます
結核の可能性を疑った、疑うべきとき、確実に特定するとき、皆さんはどのように考えていますか? 結核と診断された場合、もしくは結核が疑わしい場合は空気感染対策を行いますが、広めないために具体的に何をすればいいのか、その方法について紹介しています。また、宮崎駿作品で描かれた結核にも触れています。著者オリジナルの味のあるイラストも満載で、難しい病期の進行の変化なども頭にスッと入りやすくしました。肺結核の治療は、抗結核薬を毎日規則的に長期に飲むことで、これを結核の「化学療法」と言います。化学療法ではいろいろな抗結核薬が使われますが、その副作用も様々です。肺結核と肺外結核についてもわかりやすく解説しました。本書で、より詳しく結核のことを知っていきませんか?

世界一わかりやすい心肺運動負荷試験
ATがわかれば運動処方ができる
安全で効果的な心臓リハビリテーション(心リハ)に必要な運動処方,その運動処方のベースとなる心肺運動負荷試験(CPX)について解説した書籍。CPXの基礎知識,具体的な実施方法,結果の評価,運動処方をなるべく平易にわかりやすく説明しており,これから心リハを始める,心リハについて勉強したい方におすすめの1冊。

イラストでわかる神経症候 原書2版
機能・解剖学から診断へのアプローチ
神経系疾患を正しく診断するために必須な解剖学、神経学のエッセンスが学べる一冊。日常診療で遭遇しやすい症候や疾患を取り上げ、ポイントを絞って解説。さらに、1つの図の中で神経系の構造とその異常によって起こる症状がまとめられているため、限られた時間で効率的に解剖学的診断のコツが習得できる。第2版では、理解を深めるためのMRI画像を多数追加。また、「記憶」「ニューラルネットワーク」の2章を追加。

Dr. 下田の論文執筆無双 ストーリーで紡ぐ新たな執筆術
「結局どうやって論文を書けばいいの?」を全て解決する!
「とりあえず1本だけ書ければいい人」/「本格的に書けるようになりたい人」のために,年10本の論文を執筆する著者が「てべ猫」と一緒に誰でも論文を書ける方法を優しく解説します. 「とりあえず1本だけ書ければいい人」には素早くかつ最小限の労力で書き上げるコツを,「本格的に書けるようになりたい人」には今後自分一人で書くことができるようになるためのポイントを,楽しく通読できる形でまとめました.本書の順番通りに書くだけで論文を完成させられる,まさに無双の1冊です.

JASCCがん支持医療ガイドシリーズ
オンコロジーエマージェンシーテキストブック
がん医療が進歩し多様化する昨今、がん治療医、特に腫瘍内科医にとって「オンコロジーエマージェンシー(がん緊急症)」の病態や急性期の対応を含むマネジメントを理解・把握しておく必要性はますます高まっている。
本書では、オンコロジーエマージェンシーの特に重要な病態(計40項目)を取り上げ、各々の病態、特徴、診断、マネジメントについて、豊富な図表やシェーマを用いて、がん診療に精通したエキスパートが平易に解説した。

消化器外科専門医へのminimal requirements 第3版
知識の整理と合格へのチェック
消化器外科専門医への第一歩,“minimal requirements”がついに改訂!
第2版刊行後に発表された各種診療ガイドライン・取扱い規約の改訂に則した内容に大幅アップデート。学会公式テキストで取り上げられているキーワードも解説に盛り込んだ。わかりやすい解説とオリジナルの力試し問題に加え,姉妹本『消化器外科専門医必携問題集 知識のSELF ASSESSMENT』とも紐付けを行い,より体系立てた対策が可能に!
専門医を目指すあなたに“いま”必要な1冊です。

ザ・テキスト 大腸ESD
大圃組の神髄、ここに極まれり。大腸ESD究極の攻略法。
大圃組が全力をあげて完成させた、大腸ESD攻略テキストの決定版。内視鏡のトッププロフェッショナルであるDr.大圃のESD手技を細かなテクニックに分解し、実症例をあげながら解説。基礎・初級・中級・上級の4つのレベルごとの構成で、読者は本書を読みながら確実にステップアップしていくことができる。また、事前にトレーニングすることができない偶発症対策について、対処方法のみならず、その症例を経験した時に入院マネージメントまでどうするかを具体的なフローを詳細に記載。巻末には、大腸ESDを上達させたい内視鏡医必読の、編者らによる特別対談を収録。さらに、著者らのテクニックを余すことなく収録した動画を特設サイトにて公開。

つくる・あそぶを治療にいかす 作業活動実習マニュアル 第2版
●初版から6年,作業活動の好評テキストが待望の改訂!
●作業活動を長年実践・指導してきた作業療法士が,作業技術についてわかりやすく解説した好評テキストの改訂版!
●作業の治療的意味,作業の対象者,即活用できる作業手順,作業療法士としての工夫,補助具,注意事項について解説.
●改訂では,最近の作業活動の方向性やMTDLPの視点,新しく登場した道具や物品を追加.作業分析や治療効果なども刷新.
●養成校の「作業活動学」「作業技術学実習」のテキストに最適.過去13年分の国家試験過去問題も収載!

パーキンソン病診療ガイドライン2018
治療に特化していた前版「パーキンソン病治療ガイドライン2011」から7年、名称を“診療”ガイドラインに変更した改訂版が、満を持して登場! 最新治療はもちろん、新たに国際的な診断基準や画像検査、病因なども網羅した。厳選したクリニカルクエスチョン(CQ)と50のQ&Aで、臨床の課題を徹底解説する。

日本リウマチ学会 リウマチ診療のための関節エコー撮像の手引き 改訂版
日本リウマチ学会が送る公式入門書,関節エコーを用いる多くの方々に愛されてきたあの"青本"が14年ぶりの全面改訂でさらにパワーアップ!観察推奨部位を39項目から大幅追加し58項目に,診療技術・機器の進歩に伴いエコー画像も全て刷新.撮像・評価方法を改めて標準化した新たなスタンダード.検査時の体位・撮像部位は写真とシェーマで,正常/病的画像それぞれの見方は画像中に図示し視覚的にも理解しやすい.関節エコーに活用する全ての方必携の決定版!

心電図7日間最強ブースト マイスターと鍛える1・2級合格へのテーマ別集中対策
心電図検定1・2級に向け短期集中トレーニング! 1日30問×7日間でテーマ別に重点強化.「今日は虚血性心疾患の梗塞パターンを制覇」「明日は起源推定の問題をマスターする」というように分野ごとに極めていき,1週間で総仕上げ.試験ポイントを詰め込んだ問題・解説なので,忙しくて時間がないという方にもおすすめ.姉妹書「心電図完全攻略マニュアル 1・2級合格への最強メソッド」とあわせて勉強すればさらに判読力アップ!
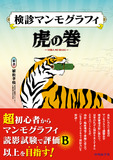
検診マンモグラフィ虎の巻
検診や臨床の現場で役立つ「生きたマンモグラフィ読影力」が身につく
長年にわたってマンモグラフィ講習会や精度管理機構に携わり,乳がん検診を支えてきたエキスパートがこれから検診マンモグラフィに取り組む初学者に向けて執筆した.マンモグラフィの基本的な読影方法,見落としを防ぐための考え方,ピットフォールを具体的に解説.乳癌取り扱い規約第19版で新たに採用された「画像のための肉眼病理」についても言及し,画像所見と病理学的背景を関連付けて学ぶことができるようにした.乳がん検診に関わる医師の読影試験や技師の読影補助に求められる知識と実践力が身につく一冊.

≪jmedmook 101≫
jmedmook101 疑問に答える肥満症診療
◆ 本書では肥満症の診療に際し、患者から聞かれがちな質問とその適切な回答を、わかりやすいQ&A形式にまとめました。
◆ また、アップデートされた肥満症診療の現状から各種の併発症、食事療法、運動療法、認知行動療法など、医療者が知っておきたい知識をそれぞれのエキスパートが解説しています。
◆ さらに医師のみならず、看護師や栄養士、理学療法士の視点からの具体的なメニューや運動例も盛り込み、また減量・代謝改善手術など、患者の関心が高いと思われるトピックも押さえた、医療者の疑問や患者の不安に答えるための1冊です!

統合失調症のみかた,治療のすすめかた
治療によって回復する疾患であるにもかかわらず,適切な「みかた」や「治療のすすめかた」が未だ広く理解されていない統合失調症の診療について解説する書.

みんなの皮膚外用薬 第2版
皮膚科診療に携わるあらゆる職種の読者(「みんな」)に贈る待望の改訂版.Ⅰ章「皮膚外用薬のキホン」,Ⅱ章「皮膚外用薬の上手な使い方」と2章立ての構成で,各薬剤の特徴と使い方から疾患への応用まで網羅.掲載薬剤一覧(写真付き)や参照箇所の表示,重要事項の色字表記や全編にわたる箇条書きなど,利便性を追求しながらも,とにかくどんどん読み進められる.新規薬剤の追加や最新情報へのアップデート,解説やコラムもさらに充実し,ますますわかりやすく!

麻酔への知的アプローチ 第12版
●実践的であること、安全を最優先したものであること、できるだけevidenceに基づくこと、そして情熱をもって麻酔を考えること─。初版刊行以来、この著者の姿勢にブレはありません。
●初版から34年、ロングセラーの全面改訂版。
●本文内の参考文献もさらに充実しました。
●麻酔科をローテートされる研修医の方々はもちろん、麻酔看護師、MEの方々にもおすすめです。全身管理のプロならではの示唆に富む記述が満載。「想定外をいかになくすか」という考え方は医療全体に役立ちます。
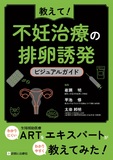
教えて! 不妊治療の排卵誘発 ビジュアルガイド
不妊治療の排卵誘発をイラスト50点超と丁寧な解説でビジュアルに理解できる1冊.
排卵誘発前の基礎知識,薬剤の種類と作用機序,ゴナドトロピン療法を中心とする投与法,卵巣過剰刺激症候群(OHSS)の病因・診断・予防法を紹介し,実際の採卵手技(麻酔・合併症)などを解説し,排卵誘発に関係する保険診療についても掲載している.

TNM悪性腫瘍の分類 第8版 日本語版
がんの病期を記載・分類するための国際標準、7年ぶりの改訂版。
がん診療に携わる医療者必携の1冊!

薬剤師レジデントマニュアル 第4版
困ったときに薬学的ケアのポイントを確認できる心強い相棒!
疾患や治療薬に関する基本的な情報に加え、現場で役立つ「薬剤師による薬学的ケア」「処方提案のポイント」が充実したマニュアル。①現場で役立つ実践的な情報を、②箇条書きで歯切れよく、③ポケットに入るサイズにまとめた。総論は調剤、DI、高齢者、検査、薬剤管理指導の要点を簡潔に記載し、各論は感染症、糖尿病、高血圧など主要54疾患を解説。卒後1,2年目の若手薬剤師はもちろん、実務実習の薬学生にもおすすめ。

浅井塾直伝!できる小児腹部エコー
描出・診断・治療まで「いい塩梅」の活用術
これで小児腹部エコーは完璧!腹痛・嘔吐のよくある原因から尿路・生殖器の疾患,緊急性の高い疾患まで,幅広く描出・診断できるようになる!臨床推論とエコーを融合した新しい「小児臨床超音波」を浅井塾が伝授!
