
生体の科学 Vol.76 No.4
2025年 08月号
特集 味と匂いの脳科学
特集 味と匂いの脳科学 生命科学・生物科学領域における最先端の研究を、毎号特集形式により紹介。神経科学はもとより分子生物学・酵素科学・栄養科学にいたる領域も含め、注目されるトピックテーマの最新情報を提供する。 (ISSN 0370-9531)
隔月刊(偶数月)、増大号を含む年6冊

医学のあゆみ294巻8号
リン代謝研究の最新動向と臨床的意義
リン代謝研究の最新動向と臨床的意義
企画:駒場大峰(東海大学医学部 腎内分泌代謝内科学)
・リンは生命の営みに欠かせない元素である.生物の多様化が起こった“カンブリア爆発”においても,火山活動による海水中のリン濃度上昇が一因とされており,その重要性がうかがえる.
・リン代謝に関する研究は2000年代に大きく進展したが,近年,ふたたび転機を迎えつつある.骨細胞や尿細管細胞によるリン感知機構,テナパノルの登場により注目を集める腸管細胞間リン輸送,ブロスマブ登場により新時代を迎えたくる病・骨軟化症の治療など,新たな知見が相次いでいる.
・本特集ではリン代謝研究の最新知見を紹介し,日々の診療や今後の研究への関心を深める機会としたい.
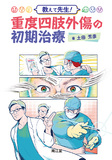
教えて先生! 重度四肢外傷の初期治療
重度四肢外傷患者を救えるかは,初期治療にあたる「あなた」が何を考え,どう行動するかにかかっている! 骨および軟部組織損傷の評価から,洗浄・デブリドマンや抗菌薬の使用,骨の仮固定といった初期治療,専門施設への転送の判断に至るまで,「どうすればよいのか?」の問いに,最前線を切り開いてきた“先生”が答える.重度四肢外傷の「標準的治療」,さらには「奥義」へとつづく第一歩として必読の一冊.

ナビ放射線物理学[電子版付]
診療放射線技師養成課程の学生を主な読者対象とする放射線物理学の教科書.カラーイラストや表を効果的に使用し,初学者にも理解しやすい構成とした.スマートフォンまたはタブレットで閲覧できる電子版を付けたほか,「この章で学ぶこと」「章末問題」で自己学習にも役立つ工夫をしている.関連する科目への橋渡しや,アドバンスな内容はコラムで区別した.

看護教員必携資料集 6版1刷
看護教員に必要な法令、検討会報告書等を厳選し集成。令和6年度改訂版「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」【本文】【資質・能力】をはじめ、近年改訂された各種資料を収録。また、統計資料として、過去約10年の看護師等の教育機関数と入学定員の推移を収録。

やりっぱなしはもう終わり!看護管理者のための研修の極意 1版1刷
学びを現場につなぐ「研修転移」で、人が育ち、看護が変わる!
研修が「受けっぱなし」「教えっぱなし」「送りっぱなし」で終わっていませんか?
せっかくの看護師向け研修を、現場での実践につなげるためには「研修転移」がカギになります。
本書では、受講者・講師・職場の上司という三者それぞれの立場から、研修前・研修中・研修後に何をすべきかを、理論と豊富な事例、ワークシートを交えてわかりやすく解説。
認定看護管理者教育課程の教員や教育担当者、研修を受ける看護師の上司に必携の、実践的な一冊です。
自分の立場に合った章から読むことができ、三者が協力し合う視点も身につきます。

看護師物語
暴力と看護の対話的探求
ありふれた「悲劇」は誰にでも起こり得る。誰でも「その人」という当事者になり得るのだ。
「看護師」はさまざまな矛盾にもがきながら、「その人」を離れず、日常のケアを通じて「その人」を肯定し「その人」を思い続ける。寄り添い続けることで「その人」は生命を脅かす問題と向き合う勇気を得る。その間も「看護師」は「その人」が前向きに行動していけるよう祈り続ける。
本書はそのように「その人」の安寧を願い続ける看護師たちの物語である。

マスターセラピストが語る 家族療法のターニングポイント
インタビューで辿る革新の軌跡
家族療法は、精神分析治療が主流であった1960年代初頭のアメリカに登場し、個人の心理的問題を関係性の変化により解決する新たなアプローチとして注目を集めた。システム思考を臨床に導入し、階層構造やフィードバックを取り入れた家族療法は,70年代にかけて隆盛を極める。
しかし80年代に入ると、この領域は大きな理論的・思想的転換期を迎える。フェミニズムのインパクト、セカンドオーダー・サイバネティクス、社会構成主義の潮流を受け、これまで家族療法を支えてきた前提が問い直され、それに応じて新たな実践形態も現れた。家族を「制御し修正すべきシステム」と見なし介入する視点から、家族を「意味を生成する共同体」と考え関与する視点へ。家族療法家は関係のアセスメントと介入の専門家であるだけでなく、多様な声や物語に耳を傾け、好奇心と協働を通じて家族と関係を築く専門家の役割をも担うようになった。
この変化を生き抜いたマスターセラピストたちへのインタビューは、家族療法の理論的転回と実践の変容を、それぞれの経験と思索を通して照らし出す貴重な証言である。彼らの言葉は、過去の回顧にとどまらず、現在の私たちが家族療法の倫理と可能性を再考するうえで重要な視座を与えてくれる。

社会保険旬報 №2973
2025年8月21日
建設費高騰の中における新病院建設の可能性検証
建設費高騰の中における新病院建設の可能性検証
医療経済フォーラム・ジャパン(会長=中村洋・慶應義塾大学大学院教授)主催の第122回定例研修会が6月26日に都内で開かれ、株式会社プラスPMの木村譲二代表取締役社長が「建設費高騰の中における新病院建設の可能性検証」をテーマに講演した。
病院の建設費がコロナ前の1・5~1・8倍に高騰し、多くの病院が建て替えに踏み切れずにいる。こうした状況下で、コンストラクションマネジメント(CM)の活用が注目されている。病院の基本構想から設計・建設までを一貫して支援し、コストの妥当性を第三者的に評価できる。
木村社長は、地域医療構想の推進などを背景に、機能分化・再編統合の形で建設する場合は、補助金などを活用し、病院のコストを圧縮できる事例を示した。また、新築が難しい場合は「長寿命化」という改修方法があることも提示した。一方で、特に民間病院の建て替えが非常に困難になっている状況に懸念を示した。
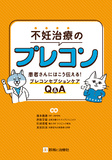
不妊治療のプレコン
―患者さんにはこう伝える!プレコンセプションケアQ&A―
Part1では,プレコンセプションケアの概要や検査方法,保険診療の現状などの基礎知識をわかりやすく解説します.
Part2では,食事,薬・サプリ,ストレス,心理的問題,周囲との関係,生活・仕事・娯楽,疾患,感染症,遺伝など多岐にわたるテーマを取り上げ,実践的な内容を紹介します.
日々の臨床で直面する患者さんからの「ちょっとしたギモン」に自信とエビデンスをもって答える一冊です.

看護 Vol.77 No.10
2025年8月号
特集1:令和7年度 日本看護協会通常総会 全国職能別交流集会 リポート
特集1:令和7年度 日本看護協会通常総会 全国職能別交流集会 リポート
令和7年度 日本看護協会通常総会および全国職能別交流集会は、6月11日(水)・12日(木)に幕張メッセ幕張イベントホールおよびTKP東京ベイ幕張ホールで開催されました。通常総会は、重点政策・重点事業に関する質疑応答を中心にリポート。全国職能別交流集会は、「看護の将来ビジョン2040」をテーマとした三職能合同交流集会のほか、各委員会の昨年度の活動報告および今年度の活動方針、講演、シンポジウム、パネルディスカッションなどから、主な内容についてお伝えします。
特集2:2024年 病院看護実態調査 解説
日本看護協会では、病院看護職員の需給動向や労働状況などを把握するため、毎年「病院看護実態調査」を実施しています。2024年調査では、毎年調査している看護職員の離職率や給与の状況、労働環境の実態のほか、一般病棟における看護職員の夜勤状況と夜勤者の確保策、正規雇用の看護職員の多様な働き方、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者の地域での活動状況、タスク・シフト/シェアの実施状況などについて調査しました。
本特集では調査結果に基づく現状や近年の推移、調査結果のポイントなどについて紹介します。
特集3:外来で行う在宅療養支援
外来では、医療と介護の複合ニーズを有する高齢患者の増加、重症化予防の必要性、医療の高度化等に対応するために多岐にわたる役割が求められるようになってきました。このような中、外来看護師には、外来患者一人ひとりのニーズに気づき、地域の医療機関や介護サービスにつなげる、意思決定支援を行う、セルフケア行動の維持・向上をはかる等の在宅療養支援に取り組むことが期待されています。
本特集では、外来で在宅療養支援が必要とされるようになった背景や外来看護師の役割を解説。さらに、在宅療養支援に積極的に取り組む病院から、外来の仕組みづくりや、外来看護師の人員・時間確保、質向上、情報収集における工夫などを報告します。

訪問看護、介護・福祉施設のケアに携わる人へ
コミュニティケア Vol.27 No.9
2025年9月号
特集:中堅訪問看護師の成長を支える環境づくり
特集:中堅訪問看護師の成長を支える環境づくり
日本訪問看護財団が2025年春に公開した「訪問看護師のための生涯学習ガイド(Ver.1)」では、人口減少・超高齢社会が進展する2040年を見据えて、急速に変化する社会動向に主体的に向き合える中堅層の人材育成を重視しています。
在宅療養者に質の高いケアを提供していくために、さまざまな他職種や社会資源などとの幅広い連携が欠かせない現在の訪問看護では、必要なリソースをケースごとに生かしながら柔軟にリーダーシップを発揮できる中堅訪問看護師の育成がとても重要になっているのです。
そこで本特集では、病棟看護師と比較して成長過程やキャリアとしての定義が曖昧な「中堅訪問看護師」の存在に焦点を当て、訪問看護ステーションにおけるその役割と成長に必要な経験・能力を明らかにした上で、主体的な学びと教育支援を行うための環境づくりに取り組む現場からの報告をご紹介します。

≪ニュートリションケア2025年秋季増刊≫
栄養管理&栄養食事指導に活用できる検査値ガイド
【患者の状態を読みとり、伝える力が身につく】栄養ケアを行ううえで、検査値から患者の状態を読みとる力は重要である。本書では、覚えておきたい検査値の意味、推移の読み解き方や基準値・異常値、関連疾患に加え、栄養食事指導でのわかりやすい伝え方をコンパクトに解説する。ダウンロードしてそのまま渡せる「患者説明シート」つきで、日々の業務に役立つ一冊。

看護管理の達人に学ぶ 人と組織を育てるマネジメント術
【意欲を引き出しやる気にさせる組織を作る】優れた看護管理者たちの行動は、これまでに蓄積された経験や他人からは見えにくい思考によって導き出されている。なぜそう動いたのか、その背景にある思考はなにか。達人のマネジメント術の隠されたコツをわかりやすく解説する。

任命! 看護師長
【任命されたらこの一冊!】役職や立場の変化は、大きな責任への期待と未知への挑戦が入り混じる人生の転機。看護師長に任命され、新たなステージに挑む看護職をサポートするべく、「これだけは知っておきたい」項目をピックアップ。任命する側(看護部長)にもおすすめ!

小児科 Vol.66 No.8
2025年8月号
小児科医が診る泌尿器疾患アップデート―どう診断・治療するか?予後はどうか?
小児科医が診る泌尿器疾患アップデート―どう診断・治療するか?予後はどうか?
小児の泌尿器疾患のうち、子供や保護者の主訴が必ずしも疾患に直結しないケースがある疾患や、救急の現場で小児科医としてのファーストタッチが重要になる疾患を取り上げ、小児科医の立場で診断・治療につなげていくために知っておくべきことをまとめました。
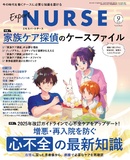
エキスパートナース Vol.41 No.11
2025年9月号
◆増悪・再入院を防ぐ心不全の最新知識
◆「家族ケア探偵」のケースファイル
◆増悪・再入院を防ぐ心不全の最新知識
◆「家族ケア探偵」のケースファイル

整形・災害外科 Vol.68 No.9
2025年8月号
肘関節疾患治療の最近の進歩
肘関節疾患治療の最近の進歩
本特集では,野球選手の代表的な疾患である上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する再生治療や体外衝撃波治療といった先進的治療,肘関節内側側副靱帯損傷に対する再建術,肘部管症候群や変形性肘関節症に対する鏡視下手術など,重要な大関節である肘関節に起こる外傷や慢性疾患に対するより良い治療法・考え方をエキスパートが紹介している。

皮膚科の臨床 Vol.67 No. 9
2025年8月号
細菌感染症
細菌感染症
致死率の高い「劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)」を筆頭に「壊死性軟部組織感染症」など,早期の診断と治療が求められる細菌感染症の症例報告をまとめました。治療方針の選択に役立つポイントが満載です。エッセイ『憧鉄雑感』なども好評連載中!
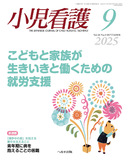
小児看護2025年9月号
こどもと家族が生きいきと働くための就労支援
こどもと家族が生きいきと働くための就労支援 就労は、報酬を得ることはもちろん、自己実現や社会とのつながりを深めることなど、さまざまな意味をもっている。本特集では、病気や障がいをもつこどもだけでなく家族の就労にも焦点をあて、現状の課題や学校・病院・地域での支援状況を紹介する。目の前にいるこどもや家族が今後どのように生きていくのか、 彼らの“働くこと”を支えるヒントを見つけるための1冊。
