
精神療法 第51巻第3号
通巻268号
妊娠・出産という経験
妊娠・出産という経験 周産期における支援や女性セラピストのライフコース、精神疾患と妊娠など多くのテーマで妊娠・出産にまつわる精神医療の現場を記す。

血友病性関節症 ―病態・診断・治療―
私が血友病性関節症を診察するようになった1990年代後半には血友病性関節症の専門書は見当たらず,2000年に発刊された『Musculoskeletal Aspects of Haemophilia』が私の教科書になりました。何度も読み返し得た知識が,私の血友病性関節症をはじめとした血友病患者の整形外科治療の基本となっています。
現在の血友病治療は止血管理だけでなく,患者の健康寿命を延伸するために血友病性関節症治療は以前より重要になっています。しかし臨床の現場で血友病性関節症に遭遇した際に頼りになる専門書はいまだに少なく,とくに和書はありませんでした。
血友病性関節症の病態や評価そして治療だけでなく,整形外科治療時に必要な止血管理や保険制度まで広く最新の情報が,本書には詰まっています。本書が日常診療の教科書としてお役に立つ1冊となれば望外の喜びです。
(竹谷英之「序文」より)

理学療法42巻4号
2025年4月号
図解 バイオメカニクスに基づく部位別理学療法の実際
図解 バイオメカニクスに基づく部位別理学療法の実際 理学療法の臨床場面において、基本動作における動作障害を評価・治療していく上で、力学的要素に基づいて生体の構造や運動・動作のメカニズムを捉えるバイオメカニクス(生体力学:biomechanics)の観点からの臨床推論は非常に重要となります。
本特集では、バイオメカニクスに苦手意識を持つ理学療法士や、測定環境の整っていない職場で勤務する理学療法士にも、バイオメカニクスに基づく理学療法評価・治療の有用性と実際を身近に感じ取ってもらうことを目的とし、写真やイラスト、模式図、シンプルな力学モデルなどを用いて解説していただきます。

腹部の身体診察×エコー超入門
腹部エコーの達人・Dr.森が編集.基本的知識を学べるPart1,2(総論),症例をとおし,身体診察のポイントも交えたエキスパート執筆陣によるPart3(各論),腹部超音波検査のあとのおさえるべき点をまとめた付録からなる.やさしい解説と豊富な画像・動画で「お腹の聴診器」腹部超音波検査を学ぶことができる一冊.
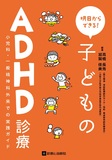
明日からできる!子どものADHD診療
小児科・一般精神科外来での実践ガイド
神経発達症の認知が広まるに伴い「児童精神科の予約半年待ち……」,そんな状況を何とかしたい‼ 一般の小児科,精神科外来で実践可能なリアルなADHD診療戦略をぎゅっと一冊に凝縮! とくに,薬物療法の詳細は従来にない充実ぶりで,処方のコツから薬剤切り替えの注意点,副作用の対応,併存症の治療まで実用情報が満載です.ADHDの子どもたちとその養育者に寄り添い続けてきた編著者陣の,温かなまなざしと臨床知が詰まった,“現場のための”決定版!

糖尿病学2025
わが国の糖尿病領域の最重要課題や基礎・臨床研究の最新トレンドを把握できる珠玉のイヤーブック.
日本を代表する第一線で活躍する医師による論文20編を収録.基礎研究では糖尿病治療の層別化や新薬開発につながるシーズの話題など,臨床・展開研究ではガイドライン解説や新薬・新規デバイスの話題のみならず被災地支援やアドボカシーなど,糖尿病治療の現在がわかる1冊.糖尿病研究者だけでなく一般臨床医にとっても必読の書.

胆と膵 2025年5月号
2025年5月号
特集:胆管細胞をとりまく病態の最新Topics
特集:胆管細胞をとりまく病態の最新Topics

糖尿病UP・DATE賢島セミナー2024(41) 病状・病態に応じたハイブリッド化した管理・治療
ー生活環境と併発合併症に応じた対応ー
● 日本の糖尿病領域をリードするオピニオンリーダー一同が参加する糖尿病UP・DATE賢島セミナーの記録集。
● 第41回のテーマは「病状・病態に応じたハイブリッド化した管理・治療―生活環境と併発合併症に応じた対応―」。
・糖尿病の各種病態(小児糖尿病,妊娠糖尿病,高齢者糖尿病)の管理・治療目標と対応
・2型糖尿病の病態,食事療法,アクティブガイド,薬物療法
・糖尿病性合併症/併発症(認知症,糖尿病性神経障害,サルコペニアとフレイル,骨粗鬆症)
● 清野裕先生,門脇孝先生,植木浩二郎先生による鼎談,若手医師による「困った症例」,糖尿病診療ガイドラインの歴史と役割を解説したトピックス,会場参加型の総合討論も掲載!

ミレニアム精神医学辞典
本書の前身『精神科ポケット辞典』は、1981年に初版が発行されて以来、1989年に補正版、1997年に新版、2006年に新訂版と改訂を重ねてきました。
この度、執筆の中核を担ってきた慶應義塾大学医学部精神・神経科ゆかりの専門家63人が、最新の知見に照らし、項目の選定、校訂、補訂を行い、また、新規に執筆しました。
本辞典の項目は、古典的なものから現代のものまで、長いスパンをカバーしており、それを意味するタイトルとして、「千年紀」を意味する「ミレニアム」に書名変更することになりました。
編集にあたっては、新訂版以降の診断・治療に関する研究・実践の進展を考慮すること、精神医療をめぐる社会の変化に留意すること、本辞典が幅広い読者に利用されてきたことから精神医療に関連した一般用語や歴史的な用語もできるだけ採り上げること、の3点に特に配慮しました。
精神医学、精神医療の最新の動向を十分に踏まえた本辞典は、こころの臨床に携わる医師のみならず、看護師、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士、介護福祉士、薬剤師などコメディカル・スタッフの方々や心理臨床家の日常の臨床に不可欠の信頼できるリファレンスとして、自信を持ってお薦めできる1冊です。またより広くこころの臨床や科学に関心をもたれている方々にもお役に立つものです。
【編者】
三村 將(みむら・まさる)
慶應義塾大学 名誉教授
慶應義塾大学予防医療センター 特任教授
村松太郎(むらまつ・たろう)
慶應義塾大学医学部精神・神経科 司法精神医学研究室 室長
JDC六番町メンタルクリニック 院長
【編集協力者】
内田裕之(うちだ・ひろゆき)
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 教授
遠藤拓郎(えんどう・たくろう)
スタンフォード大学医学部 客員教授
スリープクリニック調布 院長
岸本泰士郎(きしもと・たいしろう)
慶應義塾大学医学部医科学研究連携推進センター 教授
白波瀬丈一郎(しらはせ・じょういちろう)
東京都済生会中央病院健康デザインセンター センター長
武井茂樹(たけい・しげき)
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 非常勤講師
田中謙二(たなか・けんじ)
慶應義塾大学医学部先端医科学研究所脳科学研究部門 教授
田渕 肇(たぶち・はじめ)
医療法人 康生会つつじメンタルホスピタル 理事長
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任准教授
新村秀人(にいむら・ひでひと)
大正大学臨床心理学部臨床心理学科 教授
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任准教授
細金奈奈(ほそがね・なな)
総合母子保健センター 愛育クリニック小児精神保健科 副部長
前田貴記(まえだ・たかき)
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 専任講師

思春期青年期の臨床・学校
治療者は患者との関係をどうかたちづくるのか、各章に描写されるおよそ30の思春期青年期事例は、著者の精神科医40年あまりのごく一部である。
多種多様な治療実践を詳細に語り、治療の現実と実相にせまる。
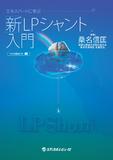
エキスパートに学ぶ新LPシャント入門
医師、看護師のための新LPシャント入門書。
「どこ?」「なに?」「どうして?」LPシャントの疑問を解決!

社会保険旬報 №2965
2025年6月1日
《レコーダ》医療経済フォーラム・ジャパン第121回定例研修会『日本医療機能評価機構の30年の歴史と医学教育河北班について』河北博文
《レコーダ》医療経済フォーラム・ジャパン第121回定例研修会『日本医療機能評価機構の30年の歴史と医学教育河北班について』河北博文
医療経済フォーラム・ジャパン(会長=中村洋・慶應義塾大学大学院教授)主催の第121回定例研修会が4月8日に都内で開かれ、日本医療機能評価機構の河北博文理事長が「日本医療機能評価機構30年の歴史と医学教育河北班について」をテーマに講演した。米国で医療機能評価が確立する経緯に触れつつ、日本医療機能評価機構の設立とこれまでの30年の歴史を振り返った。医療を行う当事者ではなく第三者が医療を評価する意義を強調した。医学教育河北班では、臨床実習の評価と医師国家試験CBT(Computer Based Testing)化を推進している。国会試験はAIやICTを活用した効率的な仕組みとし、医学教育は臨床実習を徹底させる考えが示された。

臨床栄養 146巻6号
臨時増刊号
がんの栄養治療・栄養指導 いま改めて考え,拓く
がんの栄養治療・栄養指導 いま改めて考え,拓く
がんの栄養介入は栄養療法から栄養“治療”へ.
積極的栄養介入のための,進歩するがん治療の栄養治療を学ぶ.
●近年大きく進展したがん治療では,治療開始と同時に栄養介入も進める“攻め”の栄養療法(=栄養治療)が求められている.
●本書では,治療成績をさらに向上させるための栄養治療とそのための栄養指導について解説.前半でがん治療全般に求められる栄養に関するテーマを取り上げ,後半でがん治療領域ごとやがん種別での栄養治療の実際を解説した.

数理でひも解く発がん 確率と進化の視点から腫瘍発生メカニズムに迫る
医学と数学の交差点から発がん現象の本質に迫る
●医学の進歩にもかかわらず,なお人類を脅かし続けるがん.本書では,体細胞の突然変異の蓄積からがん細胞の出現までを数理科学の視点で解説する.
●サイコロやコイン投げといった初等確率論から,発がんのプロセス,薬剤耐性や転移といったがん細胞の振る舞いに至るまで,進化論的な観点から理解できることを示していく.

脊椎脊髄ジャーナル Vol.38 No.6
2025年6月号
■特集
腰椎椎間孔狭窄の診断と治療up to date

作業療法ジャーナル Vol.59 No.6
2025年6月号
■特集
地域で子どもたちを支える―「参加」を支援すること

≪癌治療戦略に活かす病理診断ベストプラクティス≫
下部消化管癌
「病理診断の目的は分類そのものにあるのではなく,治療につながる病理診断こそが重要である」をコンセプトに,好評をいただいた「病理診断プラクティス」シリーズを全面的にリニューアル.単に前シリーズの改訂版ではなく,巻編集からコンテンツ,執筆陣まで,すべて新しく生まれ変わりました.病理医だけでなく,臨床医の皆さんにも必要な病理の知識を簡潔にまとめています.
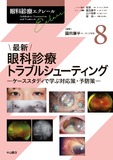
≪眼科診療エクレール 8≫
最新 眼科診療トラブルシューティング
ケーススタディで学ぶ対応策・予防策
眼科日常診療で遭遇するさまざまなトラブルを,救急外来,一般外来,病棟,手術室に分けて取り上げ,トラブルの背景,原因,対応策,そして予防策とフォローアップまでを,各領域のベテラン眼科医がわかりやすく解説.患者対応やレセプト業務に至るまで,280余りのケースについて,陥りやすい落とし穴と回避のポイントを示した珠玉の事例集.いざという時の心強い助けとなる一冊.

看護研究 Vol.58 No.2
2025年 04月号
特集 スコーピングレビュー/レビュースタディの報告ガイドライン
特集 スコーピングレビュー/レビュースタディの報告ガイドライン 研究の充実がますます欠かせない時代。看護とは? 研究とは? という原点を見つめながら、変わらない知を再発見し、変わりゆく知を先取りしながら、すべての研究者に必要な情報をお届けします。誌面を通して、看護学の知と未来をともに築きたいと考えています。 (ISSN 0022-8370)
隔月刊(偶数月)、年6冊

臨床眼科 Vol.79 No.6
2025年 06月号
特集 第78回 日本臨床眼科学会講演集[4]
特集 第78回 日本臨床眼科学会講演集[4] 読者からの厚い信頼に支えられた原著系眼科専門誌。厳選された投稿論文のほか、眼科領域では最大規模の日本臨床眼科学会の学会原著論文を掲載。「今月の話題」では、気鋭の学究や臨床家、斯界のエキスパートに、話題性の高いテーマをじっくり掘り下げていただく。最新知識が網羅された好評の増刊号も例年通り秋に発行。 (ISSN 0370-5579)
月刊、増刊号を含む年13冊
