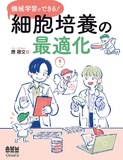
機械学習でできる!細胞培養の最適化
細胞培養(培地最適化)へ機械学習を応用するための基礎やノウハウを解説
本書は細胞培養(培地最適化)へ機械学習を応用するための基礎やノウハウを解説した書籍です.現状,細胞培養に機械学習を応用しようとすると,情報工学や数理統計学のテキストを読む必要がありますが,これらでは情報工学や数理統計学の基本的なカリキュラムを修了していることが前提とされていて,細胞培養のエンジニアや学生が読みこなすのは大変です.
また,情報工学や数理統計学において重要な基本原理の解説と研究事例の紹介がメインであり,必ずしも細胞培養に応用するうえで,「機械学習をどう利用するのか」「どうやってデータサイエンス化するのか」について,詳しく書いてあるわけではありません.
本書では,情報工学や数理統計学のノウハウがなくても,つまり,AIの素養がなくても,読者ご自身の細胞培養の定量性や再現性を高め,予測可能な結果につなげるためのヒントをまとめたものです.著者の経験をもとに,機械学習を応用する大切なポイントを解説しています.
このような方におすすめ
生物学・生命科学・医学・薬学を専攻とする大学生・大学院生
食品、医薬品、再生医療分野の企業の研究者、技術者

2026年版 診療放射線技師国家試験 完全対策問題集 ―精選問題・出題年別―
「診療放射線技師国家試験」対策問題集の最新2026年版!
定番の診療放射線技師国家試験 受験対策問題集!
過去10年分の国家試験問題を、国試対策の初期に有効な精選問題と、まとめの時期に有効な出題年別の2パターンで掲載しているので、読者の準備段階に合わせた使い方ができます。
各問題には読めばそのまま力になる、詳しくていねいな解説を掲載しています。また、索引も付いているので、受験直前にも活用できます
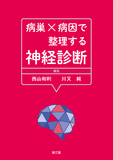
病巣×病因で整理する神経診断
研修医やプライマリ・ケア医を対象とした,脳神経疾患の鑑別診断を体系的に学べる1冊.病歴聴取を元にした「カテゴリー化」と,症候に基づく「病巣推測」を駆使して,診断力を高める.総論と症例編の2部構成で,総論では非特異的な症状の診断法を簡潔に解説.症例編では,鑑別疾患と必要な検査を通じて実践的に学べ,最終的な診断や治療方法も明記.実務に役立つ知識を凝縮した必携書.

おとなの自閉スペクトラム
メンタルヘルスケアガイド
本書では,「自閉スペクトラム症(ASD)」ではなく「自閉スペクトラム(AS)」をキーワードとし,近年拡がりつつある,ASの特性を疾患ではなく多様なヒトの変異のあり方(ニューロダイバーシティ/ニューロトライブ)と捉える価値観に基づいて,成人期のメンタルヘルスの意味を構築していく。
各章では,ASの人達の臨床像の広さや魅力,診断と具体的な支援などについて紹介され,支援者,当事者や家族,当事者と関わりの深い人達など読者のニーズに応じて多様な観点から学べるガイドとなっている。

CKD・透析・腎移植 臨床検査ガイド
本書ではCKD・ESKD診療の場で用いられる臨床検査に焦点を当て,保存期CKD・透析・腎移植患者のそれぞれに対する検査値の読み方をわかりやすく解説.各検査項目の腎機能別の基準値・測定法はもちろん,どんな時にこの検査を行うのか? 患者の腎機能を踏まえて検査所見をどのように解釈するのか? どのように原因診断を進めるのか? そして次にどんな治療・アクションが必要か? その一連の流れをエキスパートが網羅的に解説している.

≪jmedmook 97≫
jmedmook97 プライマリ・ケア医のための腰痛診療
◆ 整形外科以外の一般外来やクリニック等でも診る機会の多い腰痛について、知っておきたい知識を様々な角度からわかりやすく解説。
◆ アップデートされた腰痛に関する知見から鎮痛薬の考え方・使い方、患者に指導する体操などすぐに役立つ実践的な内容に加え、実際の診察法の動画も収載しています。
◆ 労災で一番多い原因・疾患でもある腰痛。本書には腰痛対策のための具体的な職場の改善策など、産業医必読の内容も盛り込まれています。
◆ 患者としても長年腰痛と付き合い、2度の手術も受けている著者ならではの視点で贈る本書は、腰痛の診療に携わるすべての先生に役立つ一冊です。
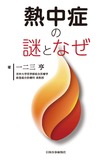
熱中症の謎となぜ
●熱中症の謎となぜを,科学的に,また,ガイドラインの改訂や臨床研究の動向も踏まえて,熱中症診療の最前線で活躍する著者がわかりやすく解説します。
●「熱中症分類がなぜ変更になって,どのように使えば良いか?」といった疑問から,COVID-19の経験を踏まえ,「暑い日にマスクをしたほうが良いのか?」といった気になるトピックスまで,科学的根拠に基づいて著者の考えを記載しています。
●医療現場で疑問に思うことが多い熱中症について,実臨床で役立つ情報を,できるだけ正確にお伝えします。

手外科手術ノートpart2:代表的な骨折・外傷編
・手外科手術ノートシリーズ「part2:代表的な骨折・外傷編」では,特に遭遇頻度の高い20の骨折・外傷を取り上げました。
・各疾患のエキスパートが,現在行っている治療法について丁寧に紹介。豊富な画像やイラストで解剖・手技に関する理解を深めながら,有力な治療法を習得し,選択肢を増やすことができます。
・part1と同様,手技をシーンで切り分けたコンパクトな動画も多く掲載。達人の技と工夫を動画で何度でも見直し,自分のペースで習得できます。
・本書でしか学ぶことのできない,エキスパート独自のアプローチが満載の1冊。手外科を学びたいと考えるすべての医師におすすめの一冊です。
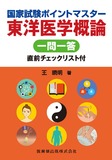
国家試験ポイントマスター 東洋医学概論 一問一答 直前チェックリスト付
新版『東洋医学概論』に完全対応!
大幅改訂された教科書内容を,○×問題でしっかりマスター!
●東洋療法学校協会編教科書『新版 東洋医学概論』が刊行され,国家試験出題基準も改訂されたことにより,令和2年までの13問/140問に対して,令和3年から16問/160問と増加した.
●東洋医学概論の出題傾向は全体的に難易度が上がっているが,他の科目に比べ,得点源となりやすい.東洋医学臨床論とも関連が深く,東洋医学概論をマスターすれば,東洋医学臨床論にも一助となる.
●本書は,東洋療法学校協会編の教科書改訂に対応.重要用語の80%以上を網羅した○×形式で,教科書の理解度と国試対応力を同時に高めるのに最適な一冊.
●巻末には,「ポイントマスター」資料を新たに収録.国試のために覚えなくてはならない最低限の知識の確認に活用できる.限られた時間の中で“最短ルート”を目指す学生さんも効率よく学習できる.

脊椎脊髄手術の出血コントロール[Web動画付]
見てわかる! 手術解剖と止血テクニック
脊椎脊髄手術が上手になる秘訣,それは止血である。本当に手術のうまい脊椎脊髄外科医は,例外なく止血テクニックに優れているといえる。出血マネジメント達人への第一歩は,解剖の教科書には出ていないサージカルアナトミーとよばれる手術を安全かつ確実に行うために必要な個別の血管解剖やその術前評価方法を知ることである。また、そこから得られた出血コントロールや止血のためのテクニックが本書では豊富に解説されている。メジャーな手術から,低侵襲手術における止血のテクニック,近年選択肢が増えた止血剤の種類やその適切な使用法などについてもまとめられており、日頃の手術における出血予防や止血に役立つにちがいない。

不随意運動の診断と治療 改訂第3版
動画で学べる神経疾患
不随意運動は,神経内科をはじめ多くの専門領域の外来でみられる症状です.しかし,的確な診断と治療を行うには実際の運動をみてみないと困難なところがあります.
本書は247本の動画を収載し,そのすべてをオンライン上でみることができます.日常診療で活用することで効果的に診断のコツを習得できます.
初版から19年にわたり,不随意運動のスタンダードな教科書として医療現場で活用されるバイブル的書籍です.

≪健寿ライフBOOKS 1≫
60代から差がつく
健康長寿のためのからだのトリセツ 初版
家族に迷惑をかけずに生き抜くエクササイズ習慣
健康の分岐点、自立か?介護か?
【健康管理は義務】
家族に迷惑をかけずに「ピンピンコロリ」で生き抜く実践書
本書のポイント
理学療法士の専門的な視点から、健康寿命を延ばすために重要な、老化による運動機能の衰えとそのメカニズムを分かりやすく解説。
特に衰えやすい「柔軟性」「筋力」「バランス能力」に焦点を絞り、自分でできる効果的なセルフチェック方法と改善エクササイズを多数紹介。
「キーマッスル」と呼ばれる重要筋肉(大腰筋、大殿筋、大腿四頭筋)を効率的に鍛える方法を解説。
書籍と連動した動画があるので、エクササイズを正確に学ぶことができる。毎日無理なく続けられる、日常生活に取り入れやすいエクササイズのヒントが満載。
毎日5分でできるサーキットトレーニングも紹介。
書籍概要
この書籍は、現代日本において喫緊の課題となっている「健康寿命」をテーマにした一冊です。平均寿命が延びる一方で、健康寿命との間に約10年もの差があり、この期間に多くの人が介護を必要とし、医療費や介護費が国家財政を圧迫している現実を提示します。
著者は、健康管理を個人の問題だけでなく、家族や社会全体に対する「義務」として捉えるべきだと説き、特に60歳以降に顕著になる体の機能の衰えに焦点を当てています。運動機能の衰えは内臓や頭の機能の衰えとも関連しますが、自分自身の意思で最も維持しやすいのが運動機能であり、その維持が全身機能の維持につながると強調します。
本書では、老化によって特に衰えやすい「柔軟性」「筋力」「バランス能力」という3つの運動機能に絞り、そのメカニズムから具体的なセルフチェック方法、そして誰でも無理なく実践できる改善・予防エクササイズを詳しく解説します。体幹、股関節、ひざの柔軟性を高める方法、大腰筋、大 殿筋、大腿四頭筋といった「キーマッスル」を効率的に鍛える方法、荷重の偏りを改善しバランス能力を高める方法などが、写真や動画(動画視聴方法の記載あり)を用いて分かりやすく紹介されています。
さらに、これらのエクササイズを日常生活に無理なく取り入れ、継続するための具体的なヒントも満載です。人生を「ロングゲーム」として捉え、今から体のメンテナンスを始めることの重要性を訴えかけ、一人でも多くの人が健康で、若く、生きがいを持った人生を送るための羅針盤となるでしょう。

実験医学 Vol.43 No.9
2025年6月号
特集1:フェロトーシス 鉄代謝と細胞死 鉄、脂質、レドックスが開くがん・老化の突破口/特集2:フローサイトメトリー革命 スペクトル方式で何が変わるのか?
特集1:フェロトーシス 鉄代謝と細胞死 鉄、脂質、レドックスが開くがん・老化の突破口/特集2:フローサイトメトリー革命 スペクトル方式で何が変わるのか?
特集1:がんや老化,組織傷害など多様な病態にかかわる鉄依存性細胞死「フェロトーシス」.その制御メカニズムの解明と,治療法開発をめざす研究の最前線を徹底解説./特集2:多色化・簡便化を実現した新方式のフローサイトメトリー.活用事例を交えながら、研究の可能性がどのように広がるかをご紹介します.

4つの気質で医療スタッフをラクにする!人間関係メンテナンス術
働きながら「もっとラクになりたい」と思っている人は多いでしょう。でも、ストレスの多くは人間関係によるもの。自分だけがストレスケアを行っても、働く仲間がラクになっていなければ、仲間のストレスが影響してきてしまいます。臨床心理士である著者が、同僚を4つの気質に分け、無理なく楽しく、自分も仲間も、ひいては職場全体もラクにしていくメンテナンス術をお伝えします。
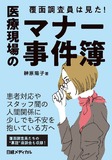
覆面調査員は見た! 医療現場のマナー事件簿
トレーニングを受けた調査員が客を装って医療機関のサービスをチェックする「覆面調査」の報告を通じて、接遇のポイントを分かりやすく解説。事件簿仕立てになっているため、ミステリー小説を読むような気軽さでエッセンスを学ぶことができる。患者対応やスタッフ間の人間関係に少しでも不安を抱いている全ての医療者にお勧めの1冊。

図解 スキンケア
正しいスキンケアから皮膚病治療へ
スキンケアの極意がこの一冊に! 洗い方や保湿など皮膚疾患の治療に重要なスキンケアが,“図解”をコンセプトに写真やイラスト,動画で“見て”わかる.「スキンケアはどうして必要?」「いつ,どうやる?」「何を使ったらいい?」など,あらゆる疑問を解決!部位や症状ごとに適切なケアを学び,満足度の高い治療・患者指導をめざしたい方におすすめ.正しいスキンケアで皮膚をきれいに治しましょう.

臨床画像 Vol.41 No.6
2025年6月号
【特集】CT検査の指示出し:検査依頼に応える撮影プロトコル
【特集】CT検査の指示出し:検査依頼に応える撮影プロトコル

免疫性神経疾患ハンドブック 改訂第2版
多発性硬化症,Guillain-Barre症候群をはじめとした免疫性神経疾患に関する最新の臨床実績と研究成果を,第一人者たちが詳しく解説.幅広い疾患の疫学,病理・病態,神経学的所見,診断,治療を網羅.改訂ではこの間に解明された病態や新薬などの新知見を盛込み,ガイドラインの改訂にも対応.実践に即役立つエッセンス満載で,必読の一冊.

私的高齢者ケア論
リアルな老いから考える、新しいケアのかたち
94歳、看護師。当事者として考える、これからの高齢者ケア
高齢者は同質な老年期集団ではない。当事者として経験する「老い」は、こんなにも多彩で、新鮮な驚きに満ちていた。自らの加齢による変化を辿りながら、長年の看護師としての経験、老年看護学担当教員としての視点を重ねて高齢者ケアを捉え直す、個人的かつ主観的な高齢者ケア論。

フレイル・サルコペニア予防!
在宅でできる生活リハビリテーション・栄養管理のポイント
在宅で行う生活リハビリテーション、栄養管理のポイントをまとめた実践書
フレイル・サルコペニアを予防するために在宅で行う生活リハビリテーション、栄養管理のポイントについて、わかりやすい文章、豊富なイラストを用いて解説した実践書。状態観察、清拭、洗髪、排泄介助、ストーマやウロストミー交換、入浴、食支援など、さまざまな場面における生活リハビリテーションの実践方法がよくわかります。
