
管理栄養士養成のための栄養学教育モデル・コア・カリキュラム準拠 第1巻 管理栄養士論 第2版 専門職として求められる10の基本的な資質・能力
管理栄養士に求められる“10の資質・能力”を解説する,専門職教育の決定版が改訂!
●「管理栄養士養成のための栄養学教育モデル・コア・カリキュラム」準拠.
●管理栄養士として求められる基本的な資質・能力として,「プロフェッショナリズム」「栄養学の知識と課題対応能力」「栄養・食の質と安全の管理」「連携と協働」など10項目を示し,これらを学ぶことで人々の健康と幸福に貢献できる管理栄養士の養成をめざす,新しい専門職教育のテキスト.

切断と義肢 第3版
斯界の第一人者が記す,切断および義手・義足のスタンダードテキスト,待望の改訂第3版
●学生から専門家まで,切断・義手・義足に関わる医療従事者に幅広く役立つ,必読・必携の書.
●学ぶべき古典的内容は残しつつ,統計情報,義肢のパーツ,などの記載を更新.
●義手/義足それぞれのリハビリテーションの内容を学びやすいように章を再構成.
●日本義肢装具学会が作成した,新しい「日本版能動義手適合検査表」に対応.

レーザー医療の基礎と安全 改訂第2版
レーザー医療を安全に行うための注意点を中心に,レーザーの原理,装置の特徴と各疾患での臨床応用までを網羅.基礎研究者,臨床医およびレーザーを取り扱う医療従事者を読者対象とし,豊富な図表で丁寧にわかりやすく解説.

医学のあゆみ292巻13号
第5土曜特集
脳科学研究が推進する うつ病の病態・診断・治療の発展
脳科学研究が推進する うつ病の病態・診断・治療の発展
企画:朴秀賢(熊本大学大学院生命科学研究部神経精神医学講座)
・うつ病は,生物学的要因,心理社会的要因,そして個々の人格や発達の特性が相互作用して発症する複雑な疾患である.働き盛りでの発症が多く,2030年代には社会的損失の最大要因になると推測されている.
・診断は精神科医の主観に頼り,治療は十分な効果を示さない抗うつ薬に依存する現状.いまだ解明されない病態メカニズムという大きな壁が立ちはだかるが,客観的な診断法と確実な治療法の確立は切実な課題である.
・そうしたなかでも,脳科学研究の着実な進歩が新たな光明を投げかけている.『医学のあゆみ』第5土曜特集として14年ぶりにうつ病を大特集.病態・診断・治療の3つの側面から,第一線の研究者らが最先端の知見を余すところなく解説する.
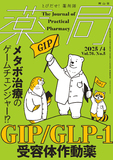
薬局 Vol.76 No.5
2025年4月号
メタボ治療のゲームチェンジャー!?
GIP/GLP-1受容体作動薬
メタボ治療のゲームチェンジャー!?
GIP/GLP-1受容体作動薬 肥満症は糖尿病名に限らず,心血管疾患や腎疾患などのリスクが高まることがわかっています.こうした状況のなか,新たな治療薬としてGIP/GLP-1受容体作動薬(ツインクレチンともよばれる)が注目されています.そこで,本特集では,薬剤師が現場で適正使用を推進するためのポイントや治療効果などをまとめました.また,各診療科の専門医,栄養士,看護師などチーム医療の視点からも本薬剤について解説しています.

事例にまなぶ認知行動療法
子ども×学校の困りごとが解決に向かうマインドセット
舞台は子ども×学校。スクールカウンセラー/開業セラピストとしてデータ分析とケース研究の両輪で悩みをときほぐすユニークな事例集。

臨床放射線 Vol.70 No.2
2025年3・4月号
核医学検査 最近の話題
核医学検査 最近の話題
本号は「核医学検査 最近の話題」と題し、脳アミロイドPETに代表される製剤のラインナップの充実や新たな解析法の登場により、春を迎えた感のある核医学診療の現在と近未来を横断的に渉猟できる特集を企画し、エキスパートの先生方に8本の総説をご寄稿いただきました。また、多彩な診療論文4本と症例報告9本、好評連載「今月の症例」も掲載し、どこから読んでもすぐに役立つ盛り沢山の1冊となっております。是非ご一読ください。

非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)診療ガイド2023

≪実験医学別冊 もっとよくわかる!シリーズ≫
改訂版 もっとよくわかる!幹細胞と再生医療
iPS細胞の誕生から約20年が経ち,幹細胞・再生医療研究はどこまで進んだのか.幹細胞・再生医療を学ぶ最初の1冊として好評のテキストが,オルガノイドやレギュレーション,臨床開発状況などの新項目を追加して10年ぶりの改訂.研究者のリアルが垣間見える充実のコラムもお見逃しなく.

≪新OS NEXUS No.14≫
上肢の関節温存手術[Web動画付]
考え方の基本と実際
「手」と「肩・肘」の2章に分け,関節温存のための骨切り術や靱帯再建術,骨軟骨柱移植術などの関節形成術について解説。また,小児橈骨頭脱臼や胸郭出口症候群についても網羅。

病理と臨床 2025年4月号
肝外胆管癌の日常診療における問題点
肝外胆管癌の日常診療における問題点 特集テーマは「肝外胆管癌の日常診療における問題点」.肝門部領域胆管癌の病理組織学的評価の課題/胆囊腫瘍における診断のポイント/遠位胆管癌/臨床医から病理医へ求めること,問題提起(1)外科医から/【座談会】あえて問い直す胆管癌の諸問題 等を取り上げる.連載記事として[マクロクイズ],[鑑別の森],[病理学基礎研究の最前線],[病理医としてのアドバンテージを体感しよう],[今月の話題] 他を掲載する.
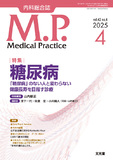
Medical Practice 2025年4月号
糖尿病~「糖尿病」のない人と変わらない健康長寿を目指す診療
糖尿病~「糖尿病」のない人と変わらない健康長寿を目指す診療 特集テーマは「糖尿病~「糖尿病」のない人と変わらない健康長寿を目指す診療」.記事として,[座談会]『糖尿病』のない人と変わらない健康長寿を目指す実地診療,[総説]「糖尿病」のない人と変わらない健康長寿を実現する個別化糖尿病診療の確立を目指して,[セミナー]糖尿病の成因と病態,病期,重症度の診断の実際,[トピックス]糖尿病アドボカシーと病名・呼称検討の背景, 等.連載では,[One Point Advice] 他を掲載.

臨床スポーツ医学 2025年4月号
徒手検査を極める-診断のアートとサイエンス-
徒手検査を極める-診断のアートとサイエンス- 「徒手検査を極める~診断のアートとサイエンス」特集として,[脊椎-骨盤の徒手検査]Kemp徴候,Hoover’s sign-非器質性麻痺の鑑別,Freiberg test/Pace test/Beatty test-梨状筋症候群,[上肢の徒手検査]Empty can test (Jobe test)/Full can test-肩腱板損傷,O’Brien test/Crank test-SLAP損傷,[下肢の徒手検査]FADIR test-FAI ,Lachman test/ADS/pivot shift-前十字靱帯損傷 などを取り上げる.また連載として,「実践!エビデンスに基づくスポーツ医・科学」「スポーツ医学の医療連携・地域連携」他を掲載.

心エコー 2025年4月号
超高齢社会における心エコー─心臓の加齢を知る
超高齢社会における心エコー─心臓の加齢を知る 特集は「超高齢社会における心エコー─心臓の加齢を知る」.心臓,血管系における老化,その機序を知る/加齢によるバイオマーカーの変化を知る/日本人における心エコー図検査の正常値―年齢と性別の影響/加齢と大動脈弁―AS,石灰化,そしてLamble疣贅/高齢者の心筋症―HCM,心アミロイドーシス,そしてDCM/高齢者の負荷テスト―いつ,どのように,何を評価する? 等を取り上げる.連載として,症例問題[Web動画連動企画] 等を掲載.
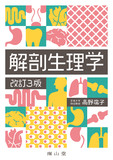
解剖生理学 第3版
本書は,医学をこれから学ぼうとしている方や,すでに医療に携わっている方に寄り添って書かれた「解剖生理学」の教科書です.人体の構造と機能について,カラーの図を多数用いて丁寧に説明しています.関連した疾患についても随所に要点が示されていますので,解剖生理学の勉強を始めたばかりの方にとっては学習の先にあるものが見えてきます.また,学び直しにも最適な一冊です.医療職種全般に役立つ「使える解剖生理学の教科書」です.

開業医のための極上旅スタイル――人生と旅を豊かにするVIP特典活用術
開業医だって働き方改革!
「死ぬまでに必ずしたいこと」というアンケートで最も回答が多いとされる「旅行」.しかし「現場を長く離れられない」「お盆と正月しかまとまった休みが取れない」など,開業医・医師の皆さんにとっては実現が難しいという声も聞きます.そこで本書では,医師があえて職場を離れて旅することの効能と,いざ旅に出るにあたってよりランクの高いVIPな旅行を実現するための裏技をお教えします!
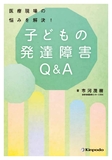
医療現場の悩みを解決! 子どもの発達障害Q&A
若手医師や開業の小児科医,発達障害について実臨床で取り組もうと思っている初心者の医師向けの,子どもの発達障害に関する参考書.かかりつけ医など,発達の問題を専門としない医療者(特に小児科医)が実臨床時に発達障害に興味を持ってもらい,できれば診療に関わってほしいとの思いから本書を企画しました.実臨床時に遭遇する発達障害のギモンを解決できるヒントをまとめた1冊.
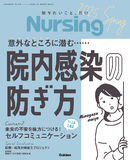
Nursing Vol.45 No.2(2025年春号)
【特集】【1】意外なところに潜む……院内感染の防ぎ方【2】未来の不安を味方につける! ナースのためのセルフコミュニケーション
【特集】【1】意外なところに潜む……院内感染の防ぎ方【2】未来の不安を味方につける! ナースのためのセルフコミュニケーション 臨床現場の疑問や困ったことに、根拠と実践的な視点を織り込んで解説した看護総合雜誌。今日から使える基本・ワザ・コツを網羅!

精神分析とトラウマ
精神分析はどのようにトラウマにアプローチしうるのか。限界と可能性を見極めながらトラウマ臨床の新たな視点を提示する。

看護 Vol.77 No.4
2025年3月臨時増刊号
特集1:看護師長ナビ2025 既卒・中途採用者を戦力に
特集1:看護師長ナビ2025 既卒・中途採用者を戦力に
病院で新規に採用する正規雇用看護職員の約4割は既卒です。「2023年病院看護実態調査」によると、既卒看護職員の離職率(16.6%)は、新卒看護職員の離職率(10.4%)より高くなっています。新卒看護職員の確保が年々難しくなる今後に向けて、既卒看護職員の定着をはかり戦力としていくことは、すべての病院にとって、待ったナシの課題ではないでしょうか。
本号では、既卒・中途採用看護職員の確保・定着のポイントを示すとともに、さまざまな病院の確保・定着戦略や、採用後の定着や教育の要となる看護師長の取り組みの実際を紹介します。
