
医療現場のアンガーマネジメント入門 明日から使えるノウハウを体系的に解説!
職場のスタッフや患者・家族に対する「怒り」の感情をどうコントロールするか。
明日から実践できるよう、体系的かつ具体的に解説。
医療現場では迅速で的確な判断を常に求められる高ストレス環境のため、他のスタッフなどに対する「怒り」が発生しやすいと言われています。そこで重要になるのが、自身の怒りの感情をコントロールする「アンガーマネジメント」です。本書では、院内外で医療従事者向けの研修を多数手がける、日本アンガーマネジメント協会ファシリテーターの大浦裕之氏(岩手県立中央病院副院長)が、医療現場で生じる怒りをどうコントロールし、怒りに起因する被害(パワハラなど)をいかに防ぐか、体系的に解説します。著者が日ごろ活用する院内規程などの関連資料も盛り込んでおり、アンガーマネジメントやパワハラ対策を効果的に実践できる内容です。

≪視能学エキスパート≫
ロービジョンケア
ロービジョンケアの基礎と臨床への応用が幅広く学べる体系的な専門書がついに誕生!
日本視能訓練士協会監修による新時代の視能訓練士向け専門書シリーズの1冊。視能訓練士に必要な学際的関連領域の基礎理論とその臨床への応用を掲載した初学者の教科書であり、かつ充実した症例をもとにした解説によりロービジョンケアの臨床に関わっている方々の日常臨床の疑問に答えられる専門書でもある。視能訓練士・視能訓練学生・眼科医・視覚研究者に役立つ内容。視能訓練士協会推奨の生涯教育プログラム参考テキスト。
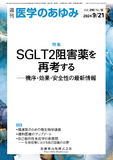
医学のあゆみ290巻12号
SGLT2阻害薬を再考する――機序・効果・安全性の最新情報
SGLT2阻害薬を再考する――機序・効果・安全性の最新情報
企画:金﨑啓造(島根大学医学部内科学講座内科学第一)
・インスリン非依存性の血糖降下薬として登場したSGLT2阻害薬は,近年,心不全や慢性腎臓病への有効性も示され,適応が拡大している.現在では糖尿病以外の治療にも広く使用され,不可欠な治療薬となった.
・SGLT2阻害薬から得られる利益は大きいが,残余リスクについて検討を要し,また,未知の薬効や副反応などに関する課題も多い.そのため,処方にあたっては薬理・薬効の正しい理解が必須である.
・本特集では,SGLT2阻害薬の交感神経制御への影響,尿路感染や膀胱機能障害,腎保護効果,心筋保護効果,肝臓保護,サルコペニアへの影響について解説する.適切な処方を考える一助となることを期待したい.

小児科 Vol.65 No.9
2024年9月号
小児の鉄代謝
小児の鉄代謝
近年、代謝機構の理解が急速に深まった「鉄」が今号のテーマ。鉄が心不全や慢性腎臓病、感染症の治療にどのような影響をもたらすか、また、スポーツをしている児への不適切な鉄剤注射、貧血が経口鉄剤で改善しなかった場合に確認すべきことなどについてまとめました。

社会保険旬報 №2940
2024年9月21日
《レコーダ》 『医療経済フォーラム・ジャパン主催第117回定例研修会から「ポストコロナの医療制度改革~有事の教訓は何か?」』高久玲音
《レコーダ》 『医療経済フォーラム・ジャパン主催第117回定例研修会から「ポストコロナの医療制度改革~有事の教訓は何か?」』高久玲音
医療経済フォーラム・ジャパン(会長=中村洋・慶應義塾大学大学院教授)主催の第117回定例研修会が7月22日に都内で開かれ、一橋大学教授の高久玲音氏が「ポストコロナの医療制度改革~有事の教訓は何か?」をテーマに講演した。
コロナ禍で指摘された課題としては、実績の少ない急性期病床が多いことや高度急性期機能が分散していることをあげた。救急搬送困難事例の研究では年間500万件の搬送事例を解析した上で、救急搬送の応需率を今後の医療改革では重視すべきとし、「救急搬送を断ることを法律で禁止することも一考に値する」と提案。独自の情報公開で病院単位の確保病床数や補助金額の調査結果も報告した。講演の要旨を紹介する。

整形・災害外科 Vol.67 No.10
2024年9月増大号
医療DX
医療DX
超高齢社会による労働人口減少に伴う業務効率化の必要性や医療安全対策などから,医療DXはますます重要性が高まっており,国家戦略にも掲げられている。本特集では医療DXの考え方,病院・クリニックでの取り組みと成功事例,整形外科の各分野における医療DXの現状,各種アプリやメタバースの活用,米国の医療DX事情など,医師に限らず多くの専門家により様々な切り口から医療DXの現状と展望を紹介した。

自立と生活機能を支える
高齢者ケア超実践ガイド
最新の研究、長年の経験・知識・技術が融合した高齢者ケアにかかわる専門職必携のガイドブック。
高齢者ケアの現場で直面する具体的問題とエキスパートならではの解決策がつまった1冊!
超高齢社会の現代日本において、介護予防、健康問題の早期発見・介入が重要です。
医療従事者やケア提供者には、病気を治療するたけでなく、その人らしい生活を支え、尊厳を保つためのケアが求められています。
本書は、高齢者が直面する機能変化、特に老年症候群や認知症、低栄養、筋力低下などに焦点を当て、適切な評価とケアの方向性を解説しています。
さらに後半では、実践的なケア技術にスポットを当て、フィジカルアセスメント、睡眠、排泄、食事、スキンケアといった日常生活の基本から、緩和ケアやエンド・オブ・ライフケアまでを網羅しました。
高齢者ケアにかかわるすべての専門職が活用できるガイドブックです。

エキスパートナース Vol.40 No.12
2024年10月号
◆ねじ子の重症熱傷
◆「どうすればよかったんだろう… 」と悩んでいることを、一緒に考えよう 悩める患者対応、相談のります
◆ねじ子の重症熱傷
◆「どうすればよかったんだろう… 」と悩んでいることを、一緒に考えよう 悩める患者対応、相談のります

産婦人科の実際 Vol.73 No.9
2024年9月号
婦人科がん治療における下肢リンパ浮腫―センチネルリンパ節生検の保険適用はなぜ必要なのか
婦人科がん治療における下肢リンパ浮腫―センチネルリンパ節生検の保険適用はなぜ必要なのか
臨床に役立つ知識や技術をわかりやすく丁寧に紹介する産婦人科医のための専門誌です。面白くてためになる,産婦人科の“実際”をお届けします。2024年度の診療報酬改定において,子宮がんに対するセンチネルリンパ節生検の新規保険収載が見送られました。センチネルリンパ節生検の保険適用化は,患者さんのQOLを著しく低下させる下肢リンパ浮腫の発生を防ぐことにもつながります。本特集では,次期改定で保険適用を掴み取るために,センチネルリンパ節生検,骨盤リンパ節郭清,下肢リンパ浮腫に対する治療法などについて,日本の診療の「現在地」を浮き彫りにしました。

眼科 Vol.66 No.9
2024年9月号
乱視を知ろう!
乱視を知ろう!
どこから読んでもすぐに役立つ、気軽な眼科の専門誌です。今月の特集は「乱視を知ろう!」と題し、快適な視機能を保つためにはその管理が重要となる乱視に関するトピックや問題点を、7名の先生方に論じていただきました。細隙灯顕微鏡と生体染色の重要性を再認識できる綜説や新たな緑内障治療法の開発動向に関する綜説、ドライアイの診断機器「idra」を紹介する連載や投稿論文、学会抄録など盛り沢山な9月号を是非ご一読ください。

産科と婦人科 Vol.91 No.10
2024年10月号
【特集】母児を感染から守る―妊産婦の感染症アップデート―
【特集】母児を感染から守る―妊産婦の感染症アップデート―
妊産婦の感染について最大の課題は,感染による母体死亡の撲滅です.近年,妊産婦死亡の原因として劇症型A群溶血性レンサ球菌感染症が注目されています.また,胎児についても,母体からの感染の影響を考えなければならない場面に多々遭遇しますので,今回は小児科医の先生方にも執筆いただきました.ぜひ臨床でお役立てください!
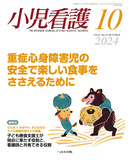
小児看護2024年10月号
重症心身障害児の安全で楽しい食事をささえるために
重症心身障害児の安全で楽しい食事をささえるために 重症心身障害児にとっての食事が単に栄養を摂取するだけの行為となるか、人との社交や文化を感じる機会となるかは支援者のサポートによって左右される。また、子どもの摂食嚥下や消化器官の機能によって、一人ひとりに適した食事形態や方法を選択する必要があり、個別性が高い。本特集では、摂食嚥下障害や胃瘻・腸瘻などの重症心身障害児の食事に関する基礎的な知識に加えて、彼らが“食事を楽しむ”ための支援の実際、家族の思いについて紹介する。

≪実験医学別冊≫
「留学する?」から一歩踏み出す研究留学実践ガイド 人生の選択肢を広げよう
ラボの探し方・応募からその後のキャリア展開まで、57人が語る等身大のアドバイス
進路に悩む学生やポスドクの方に留学という選択肢を示し,その魅力を伝えます.留学先の探し方や応募のしかた,採用試験の準備から留学後のキャリア展開まで,みんなが悩むポイントにつき多くの体験談を交えて解説.

理学療法41巻8号
2024年8月号
理学療法における症例報告書のまとめ方と書き方
理学療法における症例報告書のまとめ方と書き方 レアケースの研究報告である「症例報告」としての位置づけがある一方、理学療法では、担当した患者の、病態や障害構造、生活歴など多様な側面の背景を踏まえ,検査・測定を行い、臨床推論・問題点抽出などを経て理学療法プログラムを立案し、理学療法を実施した結果について考察するという一連の経過を「症例報告書」としてまとめ、カンファレンスでの症例報告や他施設等への申し送りなどに用いられる機会が多い。
症例報告書のまとめ方と書き方については、病院や施設でフォーマットが用意されている場合もありますが、標準化と質の改善に向けた検討が必要とされており、症例報告書に欠かせない項目をリスト化したのもが『CAREガイドライン』です。
本特集では、病院や施設でのカンファレンスなどで、チームのスタッフに患者の情報が正確に伝わる症例報告書のまとめ方と書き方について、CAREガイドラインも参照し、また模式図を用いるなどして解説していただきます。

神経難病の病態・ケア・支援がトータルにわかる
神経難病にはさまざまな種類があり、疾患ごとに経過や起こりうる症状が異なります。
そのため、看護においては、「疾患別」の視点、「症状別」の視点、そして「療養行程」の視点をあわせもつことが重要です。
長い経過のなかで変化していく療養生活課題(困りごと)にどう対応し、個々の生活歴や価値観などをふまえた「その患者さんにとって最善のケア」をどう提供するか、実践に基づいて具体的にわかりやすくまとめました。

関節外科 基礎と臨床 Vol.43 No.10
2024年10月号
【特集】生物学的関節再建の現況と展望
【特集】生物学的関節再建の現況と展望
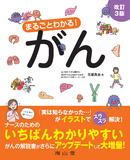
まるごとわかる!がん 第3版
フルカラーの豊富なイラストでがんの基礎知識をわかりやすく解説した好評書の改訂3版.前版から引き継いだ「がんとはどのような疾患か」「がん治療のしくみはどのようなものか」「各がん種の病態や治療」などの解説に最新の治療や新たに8つのがん種についての解説も追加され,大幅にボリュームアップ.がんについて学びたいと考えている初学者に最適な1冊.

臨牀消化器内科 Vol.39 No.11
2024年10月号
急性胆嚢炎・胆管炎を再考する
急性胆嚢炎・胆管炎を再考する
急性胆嚢炎、胆管炎は日常遭遇することが多い疾患であるが、経皮的ドレナージや内視鏡的ドレナージなど、専門性の高い観血的治療が必要で、従来その治療成績は十分なものではなかった.その原因は、どのタイミングにどのような治療を行うえば良いのかというコンセンサスが形成されていなかったことにあり、2007年急性胆道炎ガイドライン(Tokyo Guidelines:TG)が作成されたことは画期的であった.
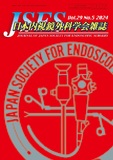
日本内視鏡外科学会雑誌 Vol.29 No.5
2024年 09月号
日本内視鏡外科学会の機関誌。1万5千人を超える学会員から寄せられた投稿論文を、厳正な審査を経て掲載している。2023年より、教育的な症例や独自の手技の工夫、術中合併症への対応症例、困難症例などを動画で紹介することを主眼として、「video articles」欄を新設。 (ISSN 1344-6703)
隔月刊(奇数月)、年6冊、電子版のみ

≪新スタンダード薬学シリーズ 6≫
薬学情報科学Ⅰ. データサイエンス基礎
基礎統計からデータ解析へ
医療人としての薬剤師養成教育に資する標準テキスト
