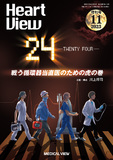
Heart View Vol.29 No.12
2025年11月増刊号
【特集】24 −TWENTY FOUR− 戦う循環器当直医のための虎の巻
【特集】24 −TWENTY FOUR− 戦う循環器当直医のための虎の巻

医師による医師のためのChatGPT入門
臨床・研究を変える究極のプロンプト500選
理想の回答を導く最短ルート!あなたも今日からプロンプトマスターに
好評を得た『医師による医師のためのChatGPT入門』のシリーズ派生作。臨床や研究・教育の医療現場ですぐに使える厳選した500のプロンプト(命令文)を収載。テーマごとにChatGPTの回答例や効果的な活用ポイント、プロンプトアレンジのコツを紹介。すべてのプロンプトはWeb付録からそのままコピペして活用できる。手軽なサイズで生成AIの便利さを身近に感じ、圧倒的な日常業務の効率化へと導く最強ガイド。

ナースビギンズ
看るべきところがよくわかる ドレーン管理
ドレーン管理で必須の手技・知識を1章で,主なドレナージシステムのしくみを2章で押さえたうえで,3章では胸腔・脳室・腹腔など代表的なドレナージの管理・観察のポイントを根拠とともに解説.ビジュアルな紙面でわかりやすく,基本から臨床の実際の手技まで,ドレーン管理のために押さえておきたい内容を無駄なく学べる一冊.

消化器内視鏡2025年37巻増刊号
消化管感染症のすべて2025
消化管感染症のすべて2025

脳波判読オープンキャンパス
誰でも学べる7STEP
病態の多様化が進む中で,より複雑化してきている脳波検査について, 本書は初学者が脳波判読の基礎からしっかりと学ぶことができるよう, 読者の判読スキルに応じて読み進めるべき項目を紹介.また,脳波所見を判定していく手順をデジタル脳波の使い方も含めて丁寧に説明し,最終的な脳波レポートの作成ができるように手順をわかりやすく解説した.臨床脳波に携わる初学者の医師や臨床検査技師にとって必携の一冊.

臨床画像 Vol.42 No.1
2026年1月号
【特集】読影のお作法−連続画像スライスで追う小児の診断:先天性疾患を中心に−
【特集】読影のお作法−連続画像スライスで追う小児の診断:先天性疾患を中心に−

解剖を実践に生かす
図解 泌尿器科手術
著者が20数年かけて積み上げてきた泌尿器科手術の知識・技術を1000枚近いオリジナルイラストに結実! 低侵襲手術を安全かつ手際よく進めるために必要な、剥離の際の指標となる膜構造・層構造を明確に示すとともに、手術のプロセスを仔細に解説。若手からベテランまで、泌尿器科手術のスキルアップに必須となる待望の手術書!
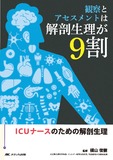
観察とアセスメントは解剖生理が9割
【解剖生理から理解すれば難しくない!】
ICUナースにとって「あれ? おかしいな」とちょっとした変化に気づけることは患者さんを守るうえでとても大切なこと。この気づきに必要な知識の背景として、解剖生理の理解がある。そこで解剖生理の知識をICU看護に結び付けることに特化した1冊として、第一線のエキスパートが観察・アセスメントのポイントを含めて解説!

≪看護学テキストNiCE≫
看護学テキストNiCE
成人看護学 慢性期看護 改訂第4版
病気とともに生活する人を支える
慢性疾患を有する患者の身体・心理・社会的特徴や,その家族の特徴を理解し,患者・家族への援助・支援の基本を学ぶことができる好評テキストの第4版.今改訂では,最新の知見に基づいて全体を見直したほか,疾患別のアセスメント表を大幅にアップデート.治療や療養行動にかかわる概念・理論の項では初学者にもわかりやすい事例を追加し,「災害時における慢性疾患を有する人の看護」の項を新設.一層の内容充実を図った.

術後痛ガイドライン
周術期医療において適切な術後の鎮痛管理は,患者の早期的な離床や臓器合併症を予防することが示されている.本ガイドラインは,術中から予防的に開始する術後鎮痛法や術式に応じた鎮痛法に加え,QOLの低下に繋がってしまうような慢性術後痛についても詳述している.また,小児やオピオイド慢性服用患者など特別な配慮を必要とする患者への注意点も解説.周術期にかかわる全医療者必携の指針に仕上がっている.

「子どもが苦手」な研修医へ 小児救急の極意を伝授
鑑別のポイント,手技のコツ,子どもや保護者と信頼を築くための秘訣などを林先生が伝授します!
子どもとコミュニケーションできる,年齢別で鑑別できる,保護者への対応もわかる…小児救急の魅力が詰まった1冊です!

循環器医・放射線科医のための
ゼロからわかる心臓MRI
本書は,循環器ガイドラインに則しつつ,心臓MRIが実臨床でどのような場面でどう役立つのかを含めて,基本的な撮像法や各疾患の読影の実際をわかりやすく解説した.できるだけ多くの画像を掲載し,実際の症例を取り上げた「症例集」も収録.これからMRIを始めたい循環器医,MRIの中でも心臓には馴染みのない放射線科医が,明日からでもすぐに活用できる一冊となっている.

保存から術後まで
脊椎疾患のリハビリテーション[Web動画付]
脊椎疾患リハの保存から術後まで、療法士が知りたいこと全部。
高齢化社会に伴い、理学療法士が脊椎疾患を担当するケースは今後益々増えるだろう。本書は、脊椎疾患に対して経験の浅い理学療法士をはじめ、臨床実習に臨む学生、また指導的立場にある理学療法士が、安全かつ効率よく、目に見える結果を出せるような脊椎疾患リハビリテーション実施(保存と術後)についてゴールドスタンダードを示す。大事な評価方法、徒手療法、運動療法は実技動画を多数収載。視覚的にもより深く理解できる。

人工呼吸に活かす!呼吸生理がわかる、好きになる
臨床現場でのモヤモヤも解決!
「呼吸生理はイマイチわからない」「臨床で必要なの?」という方,必携!症状・病態と結びつけながら,呼吸管理に必須の考え方をやさしく解説.症状や人工呼吸器設定の本当の意味がわかる!Case Studyで実践力もアップ

整形外科医のための神経学図説 原書第2版
Hoppenfeldの名著『Orthopaedic Neurology』第2版。神経高位診断のわかりやすいガイドブックとして、神経学上の基礎知識から臨床現場に即した診断の進め方までを著者独特のアイデアに基づいた図説を用いて明快に理解できるように工夫されている。今版では、わかりやすい内容はそのままにイラストがフルカラー化され、脊髄損傷患者の診療が追加された。

静がんメソッド 肺癌編 第3版
旧版から400頁超増!! 静がんシリーズ「肺癌編」、待望の改訂版!
新たな免疫チェックポイント阻害薬のほか、新規導入された多数の分子標的薬など、第2版刊行後に保険収載された薬剤を追加し、複雑化するレジメンを整理しました。
本書は、多数の癌患者さんを診療する静がん(静岡がんセンター)での経験則から、治療選択の注意点や有害事象対策のポイントを解説。EBMを根幹としつつ、EBMだけではカバーしきれない、実臨床からの経験的ポイントを解説しています。

介護報酬の解釈 2 指定基準編 令和6年4月版
『指定基準と関係通知を6月実施分も集成した基本書』
『条例制定や事業所・施設運営で大いに活躍』
介護報酬の算定の前提となる事業者・施設の「指定基準」について、国が発出した省令・通知を網羅しています。
各サービスについて、「サービス提供の基本方針」「人員基準」「設備基準」「運営基準」を掲載。指定基準の各条文に解釈通知を配置し、他サービスからの準用規定を読み替えたうえで掲載するなど、実務本位に編集しています。
個別サービス提供についての関係告示・通知も併載しています。
自治体の条例制定に役立つよう従うべき基準や標準とする国の基準をわかりやすく示しています。
令和6年度介護報酬改定では、書面掲示規制の見直しや管理者の兼務範囲の明確化、身体的拘束等の適正化の推進のほか、協力医療機関との連携体制の構築、利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置、福祉用具貸与・販売の選択制の導入など、指定基準が多岐にわたり改正されています。
「介護報酬の解釈 2 指定基準編」では、改正点がわかるように掲載するとともに、指定基準改正のポイントをまとめた資料を掲載しました。
「介護報酬の解釈 1 単位数表編」、「介護報酬の解釈 3 QA・法令編」とあわせてご活用ください。
本書は令和6年9月発刊の第2刷を電子化したものです。

PICCの教科書
失敗しない!挿入から管理までのポイント
診療看護師による医師サイドにたった診療の補助(特定行為)の1つに「PICCの挿入」がある.PICCは安全性面で大きなメリットがあり,適切に管理すればカテーテルを長期間留置可能である.そのため,患者負担も軽減することになる.PICCは海外では広く普及しており,日本でもさらなる普及率増加が見込まれている.本書では、PICCの挿入から管理に至るまでの基本的知識、さらにスキルが身につくよう動画を交えて解説した.診療看護師をはじめ,診療看護師を目指す看護師,PICCを使用していきたいと考える医師にも十分に役立つ内容となっている.
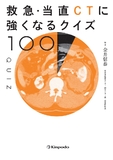
救急・当直CTに強くなるクイズ100
救急外来を受診した実際の100症例について「脳血管障害」「頭頸部」「胸部」「心大血管・他脈管」「腹部・骨盤」「消化管」「泌尿器・婦人科」「外傷」「その他」の9つに分類,クイズを問いていく感覚で,幅広くCTにまつわる知識が得られます.読影はもちろん,読影に至るまでのオーダー(依頼)や撮像プロトコール,読影後どうするか次の一手に関することまで,前後の考え方もわかりやすく記載しています.

ヘンスレー心臓手術の麻酔 第5版
頼れるスタンダード、待望の改訂
心血管・胸部領域の麻酔・周術期管理を包括的に解説したロングセラー臨床テキスト、6 年ぶりの改訂。改訂に際し、初版からの筆頭著者であったDr.Hensleyの名を冠し改題。弁疾患の章を細分化、また体外式膜型人工肺(ECMO)の章が追加されるなど、章立てはよりジェネラルにかつ時代の流れに即し大きく変更。膨大な情報を系統立ててわかりやすくまとめた。心臓血管外科手術に関わる麻酔科医の力強い味方。
