
訪問看護と介護 Vol.30 No.2
2025年 03月号
特集 精神科訪問看護での関わり方をガラリと変えるQ&A集 現場の“困ったケース”で徹底検討!
特集 精神科訪問看護での関わり方をガラリと変えるQ&A集 現場の“困ったケース”で徹底検討! 「在宅」の時代、暮らしを支える訪問看護師に、情報とパワーをお届けします。
ケアに関わる情報はもちろん、「気になるあの人/あのステーションがやっていること」を皆さんに代わって編集室が取材。明日の仕事に活かせるヒントが見つかります。 (ISSN 1341-7045)
隔月刊(奇数月)、年6冊

病院 Vol.84 No.3
2025年 03月号
特集 生き残るための病院財務の基本
特集 生き残るための病院財務の基本 「よい病院はどうあるべきかを研究する」をコンセプトに掲げ、病院運営の指針を提供する。特集では、病院を取り巻く制度改正や社会情勢の読み解き方、変革に対応するための組織づくりなど、病院の今後の姿について考える視点と先駆的な事例を紹介する。 (ISSN 0385-2377)
月刊、年12冊

理学療法ジャーナル Vol.59 No.3
2025年 03月号
特集 科学的介護
特集 科学的介護 理学療法の歴史とともに歩む本誌は、『PTジャーナル』として幅広い世代に親しまれている。特集では日々の臨床に生きるテーマを取り上げ、わかりやすく解説する。「Close-up」欄では実践的内容から最新トピックスまでをコンパクトにお届けし、その他各種連載も充実。ブラッシュアップにもステップアップにも役立つ総合誌。 (ISSN 0915-0552)
月刊、年12冊

臨床眼科 Vol.79 No.3
2025年 03月号
特集 第78回 日本臨床眼科学会講演集[1]
特集 第78回 日本臨床眼科学会講演集[1] 読者からの厚い信頼に支えられた原著系眼科専門誌。厳選された投稿論文のほか、眼科領域では最大規模の日本臨床眼科学会の学会原著論文を掲載。「今月の話題」では、気鋭の学究や臨床家、斯界のエキスパートに、話題性の高いテーマをじっくり掘り下げていただく。最新知識が網羅された好評の増刊号も例年通り秋に発行。 (ISSN 0370-5579)
月刊、増刊号を含む年13冊

シンプル衛生公衆衛生学2025
保健医療福祉分野の専門職を目指す学生に求められる知識を最新の法規・制度・統計数値とともにわかりやすく解説.2025年度版では,フルカラーでビジュアルな紙面はそのままに、最新のトピックスを追加した.衛生学・公衆衛生学の“知識”と“今”をシンプルにわかりやすく伝え,“これから”を考える力を養うために必読の一冊.

がん薬剤師外来マニュアル
がん薬剤師外来(医師の診察前に行う面談)にフォーカスを絞ったマニュアル
がん薬物療法体制充実加算で注目を集めている「がん薬剤師外来」(医師の診察前に行う面談)にフォーカスを絞ったマニュアル。実際にがん薬剤師外来の立ち上げを経験し、外来業務を行っている薬剤師が患者への丁寧な説明、医師への支持療法薬提案、支持療法薬の使い方の説明といったよりきめ細やかな対応を行うためのエビデンスとコツを余すところなく具体的に解説。実際にがん薬剤師外来を始めたい人たちにベストな1冊。

機能形態学[電子版付] 改訂第5版
人体の構造と機能について,薬学部生に必要な情報を簡潔にわかりやすくまとめた教科書.章ごとに箇条書きの「まとめ」を掲載し, おさえるべきポイントを明示することに加え理解度のチェックができる記述式の「練習問題」を掲載.今改訂では理解がよりいっそう進むよう全ページフルカラーを実施、電子版付となった.薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)対応.

カラー図解 人体の正常構造と機能 第4巻 肝・胆・膵 第5版
「黒本」の名前でお馴染み。
解剖学・生理学の高度な内容をやさしく学べる教科書として評判を呼び、シリーズ総発行部数は25万部にのぼります。
最新の知見に基づいて内容を更新するとともに、さらに読みやすく、わかりやすい教科書をめざしました。
図解を中心とした構成 フルカラーの図解を中心に構成したビジュアルな紙面。どの教科書よりも図が豊富でわかりやすいとの評価をいただいています。
見開き完結 ひとつのテーマが見開きで完結するよう編集。重要事項をコンパクトにまとめてあり、読みやすく理解しやすい。
解剖・組織・生理の連携 図解に沿ってマクロ・ミクロの構造を学び、その構造がどのような機能を果たしているのか、その構造や機能を支えている物質は何かを、順を追って学習できるよう構成しました。読み進めていくうちに、各臓器の構造と機能のつながりが実感できます。

カラー図解 人体の正常構造と機能 第3巻 消化管 第5版
「黒本」の名前でお馴染み。
解剖学・生理学の高度な内容をやさしく学べる教科書として評判を呼び、シリーズ総発行部数は25万部にのぼります。
最新の知見に基づいて内容を更新するとともに、さらに読みやすく、わかりやすい教科書をめざしました。
図解を中心とした構成 フルカラーの図解を中心に構成したビジュアルな紙面。どの教科書よりも図が豊富でわかりやすいとの評価をいただいています。
見開き完結 ひとつのテーマが見開きで完結するよう編集。重要事項をコンパクトにまとめてあり、読みやすく理解しやすい。
解剖・組織・生理の連携 図解に沿ってマクロ・ミクロの構造を学び、その構造がどのような機能を果たしているのか、その構造や機能を支えている物質は何かを、順を追って学習できるよう構成しました。読み進めていくうちに、各臓器の構造と機能のつながりが実感できます。

カラー図解 人体の正常構造と機能 第2巻 循環器 第5版
「黒本」の名前でお馴染み。
解剖学・生理学の高度な内容をやさしく学べる教科書として評判を呼び、シリーズ総発行部数は25万部にのぼります。
最新の知見に基づいて内容を更新するとともに、さらに読みやすく、わかりやすい教科書をめざしました。
図解を中心とした構成 フルカラーの図解を中心に構成したビジュアルな紙面。どの教科書よりも図が豊富でわかりやすいとの評価をいただいています。
見開き完結 ひとつのテーマが見開きで完結するよう編集。重要事項をコンパクトにまとめてあり、読みやすく理解しやすい。
解剖・組織・生理の連携 図解に沿ってマクロ・ミクロの構造を学び、その構造がどのような機能を果たしているのか、その構造や機能を支えている物質は何かを、順を追って学習できるよう構成しました。読み進めていくうちに、各臓器の構造と機能のつながりが実感できます。

カラー図解 人体の正常構造と機能 第1巻 呼吸器 第5版
「黒本」の名前でお馴染み。
解剖学・生理学の高度な内容をやさしく学べる教科書として評判を呼び、シリーズ総発行部数は25万部にのぼります。
最新の知見に基づいて内容を更新するとともに、さらに読みやすく、わかりやすい教科書をめざしました。
図解を中心とした構成 フルカラーの図解を中心に構成したビジュアルな紙面。どの教科書よりも図が豊富でわかりやすいとの評価をいただいています。
見開き完結 ひとつのテーマが見開きで完結するよう編集。重要事項をコンパクトにまとめてあり、読みやすく理解しやすい。
解剖・組織・生理の連携 図解に沿ってマクロ・ミクロの構造を学び、その構造がどのような機能を果たしているのか、その構造や機能を支えている物質は何かを、順を追って学習できるよう構成しました。読み進めていくうちに、各臓器の構造と機能のつながりが実感できます。

≪糖尿病ケア+(プラス)2025年春季増刊≫
高齢糖尿病患者の病態・治療・アプローチ
【Q&Aと症例解説で高齢患者のケアがわかる】血糖管理の基準や注意すべき身体症状、低血糖の対策、食事内容、薬剤の選択、認知機能低下による問題など、高齢糖尿病患者のケアにおいて知っておきたいポイントを網羅。症例別のアプローチ解説で実践的な理解も深まる! ダウンロードして患者に渡せる説明シートつき。

≪オペナーシング2025年春季増刊≫
超パワーアップ版! 手術室の薬剤 114
【薬剤への苦手意識を克服できる若手の味方!】手術室で使用する薬剤を網羅し、最新知識・近年の動向も解説。近年話題の術前外来で注意すべき薬剤・術後痛対策での薬剤の使用法の解説も追加。「麻酔科医が何を考えどう選択しているか」がわかる “超パワーアップ版”!※本製品は電子書籍版のみの商品となり、インデックスシールは付属しておりません。

≪看護学テキストNiCE≫
看護学テキストNiCE
病態・治療論 [1] 病態・治療総論 改訂第2版
専門基礎分野において疾病の病態・診断・治療を学ぶためのテキストシリーズ(全14冊)の病態・治療総論編の改訂版.2~14巻で学ぶ病態・診断・治療のベースとなる知識を,豊富な図と平易な文章でわかりやすく解説.看護基礎教育から卒後の臨床までを支える礎となる一冊. 今改訂では,最新情報に基づき情報更新を行ったほか,近年のトピックスを追加した.
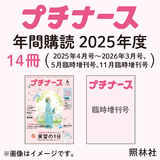
プチナース年間購読2025年度(増刊号あり)
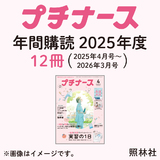
プチナース年間購読2025年度(増刊号なし)

Heart View Vol.29 No.4
2025年4月号
【特集】心不全・心筋症診療 Up to date:診断から治療までの最新動向
【特集】心不全・心筋症診療 Up to date:診断から治療までの最新動向
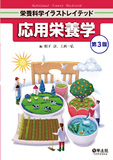
≪栄養科学イラストレイテッド≫
応用栄養学 第3版
ライフステージごとの生理的特徴や栄養ケア・マネジメントが,豊富なカラー図表とポイントを押さえた解説でよくわかる! 第3版では国試出題箇所を中心に下線を引くなどし,さらに学びやすくなりました.「管理栄養士国家試験出題基準」準拠,「日本人の食事摂取基準(2025年版)」対応!

緩和ケア Vol.35 No.1
2025年1月号
【特集】語られてこなかった間欠的鎮静のいま
【特集】語られてこなかった間欠的鎮静のいま
「終末期における鎮静(セデーション)」といえば「持続的な深い鎮静」または「調節型鎮静」をイメージすることが一般的に多い。しかし一方で,おもに夜間にぐっすりと眠ってもらい,昼はしっかりと起きてもらうこと,などを目的とした「間欠的鎮静(レスパイト・セデーション)」の用いるべき場面やその意義については,臨床では多くの場面で用いられることが多いにもかかわらず,あまり語られてこなかったことも事実である。
なぜあえて間欠的鎮静を選択する場面があるのか? その臨床的意義はどこにあるのか? など,あまり特集されることがない間欠的鎮静について,緩和ケア臨床家が知っておくとよい知識や実践をまとめた。

やさしい英語で外来診療 新装版
外国人患者が来てもあせらず正しく鑑別するための診察法と英文例を豊富に掲載.本書1冊で,内科・整形外科・小児科・産婦人科など幅広い症状に対応可能.患者さんにきちんと伝わる口語表現や,日本人が間違えやすい言葉のニュアンス・発音も紹介.診察室の心強いミカタになること間違いなし!
