
産婦人科の実際 Vol.74 No.1
2025年1月号
産婦人科にかかわる医用技術の新たな進歩Ⅰ
産婦人科にかかわる医用技術の新たな進歩Ⅰ
臨床に役立つ知識や技術をわかりやすく丁寧に紹介する産婦人科医のための専門誌です。面白くてためになる,産婦人科の“実際”をお届けします。今回の特集では,日夜進化を遂げる産婦人科領域に関連する最新の技術について紹介します。前半となる1月号では,最新の遺伝子解析技術や感染症に対する新たな取り組み,遠隔医療に用いられる新技術の開発など,臨床医にとって身近で,日常の産婦人科診療に直接かかわるような話題が盛りだくさんです。この特集が,新しく導入される最新の医用技術について理解を深める一歩となることを期待します。

小児科 Vol.66 No.1
2025年1月号
小児・思春期糖尿病アップデート―診断・治療から生活のサポートまで
小児・思春期糖尿病アップデート―診断・治療から生活のサポートまで
ときに急性胃腸炎などのCommon Diseaseにまぎれていることもある小児・思春期の糖尿病を、適切に診断・分類して適切な治療につなげることや、可能な限り患児が不自由なく生活できるようサポートするために必要な情報をまとめました。特集のほか、表皮水疱症の治療、社会的時差、アストロウイルスによる脳症などの話題・症例も掲載しています。

サリン事件
科学者の目でテロの真相に迫る
本書は,サリン事件を中心にオウム真理教が起こしたテロ事件について,科学者の視点から事件の真相を記述したものである.著者は世界的な毒物学者であり,松本サリン事件では,警察からの依頼で,サリン分解物の分析法の情報提供を行った.事件に深くかかわった中川智正死刑囚との4回の面会で直接得られた裏側の情報を盛り込みながら,警察による捜査,医療関係者による救助と治療,教団による兵器開発の実態に科学の側面から光を当てる.
【お詫びと訂正】本書p.126の「菱沼恒夫さん」は,正しくは「高橋一正さん」です.また,p.87,p.88の永岡引行氏のお名前は,正しくは永岡弘行氏です.関係者ならびに読者の皆様にお詫びして訂正いたします.Anthony T. Tu

エキスパートナース Vol.41 No.2
2025年2月号
◆「よくわからない…」を「わかった」に変える! がん薬物療法
◆最新 ナースの資格ガイド2025
◆「よくわからない…」を「わかった」に変える! がん薬物療法
◆最新 ナースの資格ガイド2025
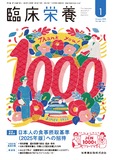
臨床栄養 146巻1号
日本人の食事摂取基準(2025年版)への招待
日本人の食事摂取基準(2025年版)への招待
●新しく改定された「日本人の食事摂取基準」が,2025年春より使用開始となります.日々の栄養管理や給食管理業務を適切に行うには,その根幹となる「日本人の食事摂取基準」についての深い理解が欠かせません.
●本特集では,「日本人の食事摂取基準(2025年版)」を迎えるための準備として,わが国における食事ガイドラインの歴史や策定における各種概念と背景,そして現場で正しく活用するための基本的な考え方について,策定検討会・ワーキンググループの委員の先生方による特別座談会と寄稿記事にてご解説をいただきます.

Medical Technology 53巻1号
きちんとできますか? 脳波検査
きちんとできますか? 脳波検査
●脳波検査に関して,「電極の付け方やアーチファクトの除去法」について知りたいという読者の皆様のお声にお応えし,今月は基礎にフォーカスした脳波検査の特集をお届けします.
●1章では脳波検査のスタートラインに立つための知識,2章では導出法や賦活法に加え,発作時対応やベッドサイドでの検査などを,3章では成人と小児の脳波を読む際のポイントや異常脳波をご紹介いただきます.4章では,チャレンジ編として7つの症例を提示しています.3章までの知識をもとに,ぜひ判読に挑戦してみて下さい.
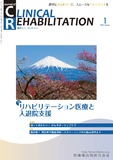
J. of Clinical Rehabilitation 34巻1号
リハビリテーション医療と入退院支援
リハビリテーション医療と入退院支援
●医療機関の機能分化が進展し疾患構造が多様化する中で,多職種による連携が退院支援において不可欠となり,リハビリテーション医療職の関与がますます重要になっている.
●しかし,退院支援の具体的な実践方法やICTを活用した効率的な連携体制の構築には課題が残されており,現場業務の改善や効率化が求められている.
●本特集では,看護管理,院内外の連携,ICT導入,退院後のリハビリ継続,病床管理など各分野の専門家が実践例や成功事例を紹介.入退院支援に関わる現場の改善や業務効率化に役立つ具体的なヒントを提供する.

小児外科56巻12号
Hirschsprung病類縁疾患―診断・治療最前線―
Hirschsprung病類縁疾患―診断・治療最前線―

周産期医学54巻12号
これならわかる骨系統疾患とその周辺
これならわかる骨系統疾患とその周辺

腎と透析97巻6号
CKD患者に望まれる造血・鉄代謝異常の管理
CKD患者に望まれる造血・鉄代謝異常の管理

JOHNS40巻12号
TEES
TEES

手術 Vol.79 No.1
2025年1月号
縫合不全をなくす―漏れ・狭窄を防ぐ消化管吻合の工夫
縫合不全をなくす―漏れ・狭窄を防ぐ消化管吻合の工夫
手術がうまくなりたい消化器・一般外科医のための専門誌。マニアックなほど深堀りした特集内容やビジュアルでわかりやすい手術手技の解説を特長とする。今回の特集テーマは消化器外科手術の泣きどころである「縫合不全」。この厄介で危険な術後合併症を「なくす」消化管吻合の工夫を消化器外科の全領域にわたって取り上げた。ロボット支援手術など,内視鏡外科手術における消化管吻合の工夫も含め,充実の内容となっている。
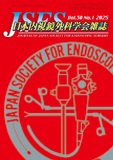
日本内視鏡外科学会雑誌 Vol.30 No.1
2025年 01月号
日本内視鏡外科学会の機関誌。1万5千人を超える学会員から寄せられた投稿論文を、厳正な審査を経て掲載している。2023年より、教育的な症例や独自の手技の工夫、術中合併症への対応症例、困難症例などを動画で紹介することを主眼として、「video articles」欄を新設。(電子版ISSN 2186-6643)
隔月刊(奇数月)、年6冊、電子版のみ

眼科 Vol.67 No.1
2025年1月号
抗VEGF治療の進歩:選択と最適化
抗VEGF治療の進歩:選択と最適化
どの記事もすぐに役立つ、気軽な眼科の専門誌です。2025年1月号の特集は「抗VEGF治療の進歩:選択と最適化」です。着実な進歩がみられる抗VEGF治療について、治療の選択から適応、課題までを疾患ごとにまとめました。デジタル時代の眼科手術教育や薬剤起因性網膜症といった実践的かつ興味深いテーマの綜説、新しいOCT「Glauvas」を紹介する連載や臨床現場から届いた投稿論文も掲載しております。本年も『眼科』誌をよろしくお願いいたします。

臨牀消化器内科 Vol.40 No.2
2025年2月号
ここまで進んだinterventional EUS
ここまで進んだinterventional EUS
今後もinterventional EUSはさらに発展していくことは間違いないが、ERCPなどの既存の内視鏡手技との使い分けなど課題も多く残されている。本特集でも、すでに確立された領域から今後発展が期待される手技まで広く扱ったが、現在の大きな課題である教育システムの確立・標準化を最後に取り上げさせていただいた。

医学のあゆみ292巻3号
肝疾患の早期発見・早期治療の要となる肝機能検査
肝疾患の早期発見・早期治療の要となる肝機能検査
企画:竹原徹郎(大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学)
・肝疾患検査における温故知新! 日常よく測定される肝臓に関わる臨床検査項目 ―ALT,GGT,PT,血小板,FIB-4,アンモニア,肝炎ウイルスマーカー― の最新知見を紹介し,その意味を再考する.
・日本肝臓学会は“奈良宣言2023”を発出した.慢性肝疾患をあらためて“CLD(chronic liver disease)”と位置づけ,かかりつけ医,専門医へと適切につなげていくことの重要性を提言している.
・沈黙の臓器ともいわれる肝臓のSOSを拾い上げ,早期診断から早期治療につなげなければならない.本特集が,日本からCLD に伴う肝疾患を減らす一助となることを期待したい.

看護学テキストNiCE
病態・治療論[4]消化器疾患 改訂第2版
専門基礎分野において疾病の病態・診断・治療を学ぶためのテキストシリーズ(全14冊)の消化器疾患編.医師と看護師の共同編集により,看護学生に必要な知識を網羅.さまざまな症状を理解できる,診断の進め方・考え方がわかる,臨床看護に結びつく知識が得られる,の3点を重視して構成している.今改訂では各種情報を更新したほか,消化器系の機能障害を有する患者の看護の概説を追加した.

看護学テキストNiCE
病態・治療論[13] 産科婦人科疾患 改訂第2版
専門基礎分野において疾病の病態・診断・治療を学ぶためのテキストシリーズ(全14冊)の産科婦人科疾患編.医師と看護師の共同編集により,看護学生に必要な知識を網羅.さまざまな症状を理解できる,診断の進め方・考え方がわかる,臨床看護に結びつく知識が得られる,の3点を重視して構成している.今改訂では各種情報を更新したほか,婦人科疾患の診療を受ける患者への看護および妊産褥婦への看護を概説する項目,遺伝学的検査の項目を追加した.

『手術』年間購読(2025年)
「手術がうまくなりたい」なら必読の雑誌です。食道・胃・肝胆膵・小腸・大腸・肛門など消化器外科治療のうち、「手術手技」に特化した編集方針。売り物の「特集」、プラクティカルな論文「手術手技」「手術症例報告」とも、マニアックなほど深堀りした内容です。

『小児科』年間購読(2025年)
日常診療のコツから、今知るべき他科の知識・時事的課題まで。査読をクリアした信頼度の高い論文が、豊富な話題をやさしく解説。診療の質を上げる、子どもを診るすべての医師のための専門誌です。
