
公衆衛生 Vol.89 No.1
2025年 01月号
特集 超高齢・人口減少社会における災害対策の新たなパラダイム 能登半島地震・観光危機管理・生業再建
特集 超高齢・人口減少社会における災害対策の新たなパラダイム 能登半島地震・観光危機管理・生業再建 地域住民の健康の保持・向上のための活動に携わっている公衆衛生関係者のための専門誌。毎月の特集テーマでは、さまざまな角度から今日的課題をとりあげ、現場に役立つ情報と活動指針について解説する。 (ISSN 0368-5187)
月刊、年12冊

『 Nursing(ナーシング)』年間購読(2025年)
『Nursing』2025年の年間購読(電子版)です。『Nursing(ナーシング)』の内容は下記をご覧ください。 「臨床実践に強くなれるプロの看護総合情報誌」として,タイムリーで,斬新で実践に役立てられるテーマを特集に組み,日々の多忙な業務で見失いがちな看護ケアや技術などの最新情報を深く掘り下げて紹介する.ビジュアルでわかりやすい誌面,明日使えるような切り口,どこにも載っていない情報の噛み砕き方で展開する.好評連載では,最新文献情報など,臨床実践に活かせる情報をお届けする.

はじめての講義
リハビリテーションのための薬理学・臨床薬理学
やさしい記述とわかりやすい図表でリハビリテーション職を目指す学生 や医療従事者に 必要な薬と疾患の知識を解説した教科書.医師と理学療法士による複眼的な視点で編集され, 薬の作用機序から 薬物療法の知識までをコンパクトにまとめ ,初学者でも無理なく学習できる構成となっている.また,リハビリテーションと関連が深い疾患には,実習や臨床の場でも役立つ「リハビリテーション実施上の注意点」を盛り込んだ.

整形外科 Vol.76 No.1
2025年1月号
1950年創刊。整形外科領域でいちばんの伝統と読者を持つ専門誌。読者と常に対話しながら企画・編集していくという編集方針のもと、年間約180篇にのぼる論文を掲載。その内容は、オリジナル論文、教育研修講座、基礎領域の知識、肩の凝らない読み物、学会関連記事まで幅広く、整形外科医の日常に密着したさまざまな情報が、これ1冊で得られる。
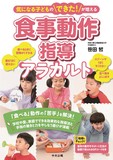
気になる子どものできた!が増える食事動作指導アラカルト
箸がうまく持てない、食べ物をよくこぼす、音を立てて食べる、姿勢が悪いなど、子どもの「食べる動作」の困りごとを解決! 保護者や教員、栄養士、保育者向けに、具体的な動作の指導法、手指の動きを養う遊び、食具の選び方などを紹介する。一部WEB動画付き。

社会保険旬報 №2949
2024年12月21日
《レコーダ》 『医療経済フォーラム・ジャパン第22回公開シンポジウム(下) 災害時の医療のあり方』中田勝己 茂松茂人 小藤幹恵 本間正人 中尾浩一
《レコーダ》 『医療経済フォーラム・ジャパン第22回公開シンポジウム(下) 災害時の医療のあり方』中田勝己 茂松茂人 小藤幹恵 本間正人 中尾浩一
医療経済フォーラム・ジャパン(会長=中村洋・慶応義塾大学大学院教授)は10月17日、都内で第22回公開シンポジウムを開催した。メインテーマは「災害時の医療のあり方」。社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院理事長の神野正博氏の基調講演の後、学習院大学長の遠藤久夫氏の座長によるシンポジウムでは中田勝己氏(厚生労働省医政局地域医療計画課長)、茂松茂人氏(日本医師会副会長)、小藤幹恵氏(石川県看護協会会長)、本間正人氏(日本災害医学会代表理事)、中尾浩一氏(恩賜財団済生会熊本病院院長)の5氏が発言した。
12月1日号では神野氏の基調講演を掲載したが、今号では中田氏、茂松氏、小藤氏、本間氏、中尾氏の発言要旨とディスカッションの模様を紹介する。5氏からは、能登半島地震や熊本地震における災害医療活動や課題などが発表された。

病理と臨床 2025年1月号
消化管Ⅰ―上部消化管―
消化管Ⅰ―上部消化管― 特集テーマは「消化管Ⅰ―上部消化管―」.食道扁平上皮内腫瘍の病理診断/好酸球性食道炎/H. pylori未感染胃腫瘍/自己免疫性胃炎の病理診断/NHPH胃炎の診断/CLDN18/胃癌および食道癌におけるPD-L1評価/非乳頭部十二指腸腫瘍 等を取り上げる.連載記事として[マクロクイズ],[鑑別の森],[病理学基礎研究の最前線],[病理医としてのアドバンテージを体感しよう―海外における病理医活動の紹介―],[今月の話題]他を掲載する.

臨床スポーツ医学 2025年1月号
診察室からのライブ中継~どのようにアスリートに向き合うか
診察室からのライブ中継~どのようにアスリートに向き合うか 「診察室からのライブ中継~どのようにアスリートに向き合うか」特集として,スポーツ診療における診察室の役割/スポーツ総合診療科の診察室/現場と連携したスポーツ診療の構築/アスリート目線の手術適応の判断/エリートアスリートへの対応/外国籍アスリートへの対応/女性アスリートへの対応/障害のあるアスリートへの対応 などを取り上げる.また連載として,実践!エビデンスに基づくスポーツ医・科学]他を掲載.

心エコー 2025年1月号
感染性心内膜炎診療の最前線~Duke診断基準の改訂を受けて
感染性心内膜炎診療の最前線~Duke診断基準の改訂を受けて 特集は「感染性心内膜炎診療の最前線~Duke診断基準の改訂を受けて」.2023年Duke-ISCVID診断基準─改訂点とIE診断の流れ/エコー医・技師が知っておくべきIEの細菌学/人工弁IEの心エコー診断のコツ/ペースメーカリード感染の心エコー診断のコツ/IEの術前経食道心エコー所見と術中所見 を取り上げる.連載として症例問題[Web動画連動企画]両下腿浮腫をきたした12歳女児,[COLUMN]報告記/東京ハートラボ夏休み親子イベントを開催して等を掲載.

皮膚科の臨床 Vol.66 No.13
2024年12月号
悪性上皮系腫瘍
悪性上皮系腫瘍
皮膚腫瘍は多種多様な疾患に分類されますが,そのなかでも今月号は『悪性上皮系腫瘍』として有棘細胞癌,基底細胞癌を中心に貴重な症例報告をまとめました。診断に有用な病理組織所見や各種画像検査所見が豊富に掲載されています。日々の診療に是非お役立てください。エッセイ「憧鉄雑感」などの記事も好評連載中!

整形・災害外科 Vol.67 No.13
2024年12月号
整形外科医の災害対応のあり方―能登半島地震の経験より
整形外科医の災害対応のあり方―能登半島地震の経験より
直近の能登半島地震や各地の豪雨災害,今後発生が懸念される東南海・南海地震など,災害が多発する日本では,整形外科医の迅速かつ適切な対応が求められている。本特集では能登半島地震や過去の震災時に対応にあたった著者の経験を中心に,次の災害に向けて備えるべきことについて幅広い視点から解説している。

ナースの小児科学 改訂7版
小児科の各専門領域をバランスよく学び、エキスパートを目指せるテキスト
初版刊行より30年以上,多くの看護師や教員の方々にご支持をいただいてきた好評のテキスト「ナースの小児科学」が,9年ぶりに待望の改訂.いつの時代も変わらぬ小児看護の基本についての丁寧な解説はそのままに,必須の最新知見を踏まえてアップデートしました.小児内科学,小児外科学,小児診察学,小児治療学,小児保健学など,20以上ある小児科学の各専門領域の全てを網羅した数少ないテキストとして,包括的医療や全人的医療の視点から,これからも小児医療の現場で大いに役立てていただける内容です.

小児看護2025年1月号
外来看護師の技を引き継ぐ
外来看護師の技を引き継ぐ 小児領域の外来看護師は、外来受診という限られた時間のなかで患者・家族に巧みな技を用いて看護を実践している。本特集は、可視化されにくい外来看護師の実際に焦点を当ててたいという思いから、診療所・病院・療育施設などで実施されている専門的な看護ケア・教育プログラムを紹介する。また、こどもの外来看護を基礎教育でどのように学ぶか、学生実習の受け入れが外来で働く看護師に与える影響についても解説する。外来看護師の人材育成を考えるきっかけとなる一冊。

産婦人科の実際 Vol.73 No.13
2024年12月号
動画で学ぶ!次世代へつなぐ婦人科ロボット支援手術
動画で学ぶ!次世代へつなぐ婦人科ロボット支援手術
臨床に役立つ知識や技術をわかりやすく丁寧に紹介する産婦人科医のための専門誌です。面白くてためになる,産婦人科の“実際”をお届けします。今回の特集では,各手術支援ロボットの特徴から実際の手術手技,さらに術者教育に至るまで,いま急速に普及している婦人科ロボット支援手術にまつわる話題を網羅的に紹介します。各疾患の手術手技については,文章だけでは伝わりにくい内容を読者が視覚的に理解し学べるよう,動画付きで解説いただきました。ロボット支援手術がうまくなりたい産婦人科医必読です!

眼科 Vol.66 No.13
2024年12月号
AIによる眼科画像研究の最前線と臨床応用
AIによる眼科画像研究の最前線と臨床応用
どの記事もすぐに役立つ、気軽な眼科の専門誌です。今月の特集は「AIによる眼科画像研究の最前線と臨床応用」です。眼科は多様な装置で様々な画像を取得し分析する機会が多いため、AIの活用が進みつつあります。そこで、眼科におけるAIを用いた研究、なかでも画像にフォーカスを絞って解説をいただきました。その他、スマホ内斜視や緑内障に関する綜説、興味深い内容を記した連載2本や投稿論文ともども、是非、お楽しみください。

身体不活動症候群 Physical Inactivity Syndrome
医療従事者が知っておくべき安静・身体不活動・廃用症候群のすべて
いまなぜDSやPIが問題になっているのかを明らかにするとともに,これらを予防・治療するのに必要なリハビリ・運動療法の実際とその有効性を解説.医療従事者自らが患者に対する安静の加害者にならないように,患者の活動性向上を引き出す技術をきちんと身につける必要があります.医療従事者が「不活動・安静・寝たきり」の危険性を十分に認識し,十分な自信を持ってDSやPIの予防・治療を行うために役立つ一冊.

訪問看護、介護・福祉施設のケアに携わる人へ
コミュニティケア Vol.27 No.1
2025年1月号
特集:現場の実践から学ぶ 経験学習サイクルの視点から
特集:現場の実践から学ぶ 経験学習サイクルの視点から
訪問看護師が研鑽を積んでいくための方策の 1 つである「経験学習」。
それを実践するためには「経験する」「振り返る」「教訓を引き出す」「応用する」という経験学習サイクルの一連の流れを理解するとともに、事例を通して学びを深めることが重要です。
本特集では、経験学習研究の第一人者である松尾睦氏を迎え、まず訪問看護ステーションの管理者が聞き手となり、仕事の経験からの学びや経験学習サイクルの実践などについて、松尾氏がインタビュー形式で解説し、さらに経験学習を習慣化するための第一歩として「5 分間リフレクション・エクササイズ」などを誌上で実践。続いて「経験からの学び」に関する事例として、「家族と医療者の異なる意向をめぐっての学び」「ハラスメント被害を振り返る経験からの学び」「意思決定支援に取り組んだ経験からの学び」「渡辺式家族アセスメント/支援モデルを用いた学び」についてそれぞれ報告します。
2025 年のスタートに当たり、あなたのステーションでもぜひ「経験学習」を取り入れ、スタッフ 1 人ひとりのスキル向上をめざしませんか!

臨牀消化器内科 Vol.40 No.1
2025年1月号
上部消化管内視鏡を見直す-基本から応用まで
上部消化管内視鏡を見直す-基本から応用まで
今回の特集では,上部消化管内視鏡の基本を押さえつつ,新しい機器・技術に柔軟に対応した現代に合った内視鏡観察の最新の知見とポイントについて,quality indicator から臓器別の工夫,そしてAI 診断の役割まで取り上げている.

≪ニュートリションケア2024年冬季増刊≫
栄養評価と栄養療法のキホンQ&A
【ベッドサイド栄養管理の疑問を解消する一冊】令和6年度診療報酬改定における「栄養管理体制の基準」として、「栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること」が明確化された。医療チームの一員である管理栄養士が、栄養管理計画を立案するために迷いがちな栄養状態の評価、栄養補給方法、栄養管理上の課題をわかりやすく解説する。
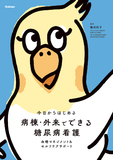
今日からはじめる 病棟・外来でできる 糖尿病看護
血糖マネジメント&セルフケアサポート
図解を中心に展開し,医師,認定看護師,経験の浅いナースを登場人物とした会話形式で展開.
看護師として困ったり,悩んだり,立ち止まったりする場面を想定し,先輩がすぐそばにいたらどうアドバイスするかという視線で一緒に歩いていただけるような内容
