
救急医学2024年12月号
令和6年能登半島地震の現場から
令和6年能登半島地震の現場から 2024年、元日、16時10分。能登半島地震。そのとき、被災地の救護現場で、病院やクリニックで、避難所で、何が起こっていたのか。当事者たちの声を聴こう。いまだ復興の道半ばばからこそ、考えて、そして動こう。

脳腫瘍治療学 腫瘍自然史と治療成績の分析から 第2版
脳腫瘍の増殖・増大様式(腫瘍自然史)を,膨大な数の文献を渉猟し分析.治療目標(戦略)・治療方法(戦術)を考えるにあたり指針となる1冊.WHO脳腫瘍病理分類に沿って,必要な情報を統一した項目で整理し,リファレンスとして使えるようにしている.今改訂では,2021年に5年ぶりに改訂されたWHO脳腫瘍病理分類に対応し,大きく項目立てを変更,新規文献数は800以上.リハビリテーションについての項目も設けた.

プチナース Vol.34 No.1
2025年1月号
◆不安要素を一気に解消! 国試に超でる 解剖生理
◆解きかたのコツ&役立つ知識を伝授! 状況設定問題レッスン
◆不安要素を一気に解消! 国試に超でる 解剖生理
◆解きかたのコツ&役立つ知識を伝授! 状況設定問題レッスン

ICUとCCU 2024年12月号
2024年12月号
特集:日本版敗血症診療ガイドライン 2024(J-SSCG2024)のポイントと将来展望
特集:日本版敗血症診療ガイドライン 2024(J-SSCG2024)のポイントと将来展望
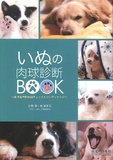
いぬの肉球診断BOOK
東洋医学的体調チェックとツボマッサージ
毎日の肉球体調チェックで、かわいいワンちゃんの病気予防を!
肉球はぷにゅぷにゅかわいいだけではありません。毛が生えていないので皮膚の状態が分かりやすく、体調による変化をつかみやすいのです。
『犬のツボ押しBOOK』(医道の日本社発行)でもおなじみの石野孝獣医師が、手軽に健康状態をチェックできる方法として発案し、実際の診療でも行っているこの肉球診断法。
診察の際に触った肉球の感触や匂いをデータベース化し、それぞれのワンちゃん体調の情報を分析した結果、ワンちゃんの肉球は、東洋医学的体質による8つのパターンに分類でき、その肉球はワンちゃんの体調によって変わっていくことも導き出しました。
本書では、肉球の東洋医学的肉球診断法と、その診断に対応したツボマッサージ法を紹介しています。その他にもワンちゃんの嗅覚のひみつやシッポ、舌のチェックポイントについても簡単に触れています。
犬の寿命は30年前に比べ、2倍以上に延びてきています。今、ワンちゃんの世界はまさに超高齢社会といっても過言ではありません。ワンちゃんも人間同様、ガンや糖尿病など、生活習慣病を患う子が多くなっています。
かわいいワンちゃんを、毎日の肉球チェックとツボマッサージで体調管理してあげましょう!
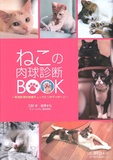
ねこの肉球診断BOOK
東洋医学的体調チェックとツボマッサージ
肉球の東洋医学的診断で猫ちゃんの健康を手軽にチェック!
人間と違い、猫や犬は顔色を診たり、脈を正しく測ることが難しく、健康状態を把握しにくいといわれています。そこで、『犬のツボ押しBOOK』や『ペットのための鍼灸マッサージマニュアル』でおなじみの石野孝獣医師が、手軽に健康状態をチェックできる方法として発案したのが、肉球を使っての診断方法。
肉球は毛が生えていないので皮膚の状態が分かりやすく、体調による変化をつかみやすいからです。
病院に訪れる猫ちゃんたちの肉球専用カルテを作り、その日その日の猫ちゃんの肉球の状態等の情報を収集し、写真を撮影。データベース化し分析した結果、猫ちゃんの肉球は、東洋医学的体質によって8つのパターンに分類でき、その肉球は猫ちゃんの体調によって変わっていくことも導き出しました。
治療により体の調子が変化すると、肉球の状態も変化します。猫ちゃんの肉球は猫好きにとっては究極の癒しです。その肉球には東洋医学的に、猫ちゃんの体調を反映する情報がたくさん詰まっているのです。
本書ではその肉球の東洋医学的診断に基づき、どのツボを押せば猫の症状が改善していくかまでを紹介しています。その他にも、ツボ指圧マッサージや顔つき、爪、毛並からのチェック方法などにも簡単に触れています。
猫ちゃんの体調を東洋医学的に把握して、大事な家族である猫ちゃんの健康管理に役立てることができる1冊です。

もう悩まない! やさしい鍼を打つための本
もう悩まない! やさしい鍼を打つための本
学校を卒業して初めての鍼を打つときや、開業して最初の患者さんに鍼を打つとき。誰でも、最初に一鍼は怖いもの。
そんな不安を解消するべく、経絡治療学会夏期大学で講師を務める中根一先生が、「痛くない、やさしい鍼の打ち方」を伝授します。触診から抜鍼まで、写真でわかりやすく解説。どんなところに気を付ければいいか、ポイントがひと目でわかります。
鍼灸師として生きるための心構えなど、臨床に役立つヒントが満載! これから臨床に出る人に、オススメの1冊です。

≪眼科診療エクレール 6巻≫
最新 網膜循環疾患コンプリートガイド
所見・検査,疾患と診断・治療のすべて
網膜循環疾患の診療は,近年,急速に進歩した眼底画像検査―とくにOCTの普及やOCTAの導入と,新規薬剤―抗VEGF薬の登場により,大きく様変わりした.本書では,経験豊富なエキスパートが,最新のエビデンスに基づいて,網膜循環疾患の所見・検査,疾患と診断・治療を網羅して詳しく解説.眼科のなかで最も“hot”な領域である網膜循環疾患の診療のすべてがここにある.

LiSA Vol.31 No.12 2024
2024年12月号
徹底分析シリーズ:ECPR:麻酔科医も積極的にかかわっていこう!/症例カンファレンス:術中の緊急コンバージョン:方針転換に対する迅速な対応/医学教育お悩み相談室:最近の研修医は出来が悪い!?/2024のシェヘラザードたち:筋弛緩モニターを使おう/こどものことをもっと知ろう:こどもの肺炎/ちょっと拝見 となりのDAMカート:河北総合病院 の巻/diary:栃木県下野市/みんなのプロフィール帳:自分のアブノーマル度もまだまだ/夕ご飯 何にする?:あったかトマトグラタン
徹底分析シリーズ:ECPR:麻酔科医も積極的にかかわっていこう!/症例カンファレンス:術中の緊急コンバージョン:方針転換に対する迅速な対応/医学教育お悩み相談室:最近の研修医は出来が悪い!?/2024のシェヘラザードたち:筋弛緩モニターを使おう/こどものことをもっと知ろう:こどもの肺炎/ちょっと拝見 となりのDAMカート:河北総合病院 の巻/diary:栃木県下野市/みんなのプロフィール帳:自分のアブノーマル度もまだまだ/夕ご飯 何にする?:あったかトマトグラタン

最新理学療法学講座 地域理学療法学 第2版
●令和6年版理学療法士国家試験出題基準に沿って全面改訂!
●地域リハビリテーションの理論を充実させるとともに,令和6年度介護報酬改定をふまえて最新知識を解説.
●介護予防,認知症,呼吸器疾患を新設したほか,国試の頻出内容や重要ポイントがわかる工夫をこらしている.
●地域で求められる知識は何か,理学療法士として何ができるかを考えながら,理解を深められるテキスト.

新装改訂版 現代数理統計学
多くの読者から親しまれてきた定評あるテキストの新装改訂版.
数理統計学の基礎的な概念,標準的な理論を数学的説明だけでなく言葉で丁寧に解説する.さらに,広範にわたる話題を一貫した視点でとらえることにより統一的・俯瞰的な理解へ導く.
このたびの改訂では読者の学習の便宜をはかり,新たに40題の練習問題を追加するとともに,問題解答例をサポートサイトにて公開する.
統計検定®1級試験に向けた学習にも好適.
【統計検定®推薦図書】
※ 本書は,1991年11月に創文社より刊行されたものを新たに組み直し増補改訂した新版です.
※ 統計検定®は一般財団法人統計質保証推進協会の登録商標です.

COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン第6版
COPD(慢性閉塞性肺疾患)は長期間の喫煙に起因する生活習慣病で、本邦には500 万人を超える患者がいると見積もられております。故に本疾患は呼吸器内科のみならず、多くの非専門医がかかりつけ医として診療することになる疾患です。2013 年には「健康日本21(第2次)」において、本疾患が対策を講じるべき生活習慣病として取り上げられ、まずはその認知度の向上を目的とされました。日本呼吸器学会としても本疾患の啓発に力を入れて取り組んでいるところですが、認知度は依然として低く、何らかの対策が求められるところです。今後、人口の高齢化が進むにあたり、多くの高齢者が罹患している本疾患が大きなインパクトをもたらすことが危惧されております。喫煙によって壊された肺は現在の医学では元に戻すことはできません。故にCOPD 患者に禁煙を早期に達成させて少しでも将来リスクを低減して、さらに最善の治療を施すことで現時点の症状を改善することが、呼吸器内科専門医のみならずかかりつけ医の重要な課題であると言えるのではないでしょうか。
この度、『COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン 第6版』が、多くの編集委員、システマティックレビュー委員、査読委員や協力者のもとに作成され、上梓されることになりました。本ガイドラインは、これまでのガイドラインの流れを引き継ぎ、疾患概念、病態、診断、治療について参考となる事項や手順を、新しい知見を加え最新版としたものです。特に本版では、COPD の治療に関するクリニカルクエスチョンを設定し、最新のエビデンスを基に科学的なレビューを行い、クエスチョンに対する現時点でのベストアンサーを模索しております。本疾患の治療・管理に関する記載のみならず、新たに追加・修正された項目もあり、本書を一読することで疾患理解を深めることができると思います。
COPD 患者の生命予後を改善できる治療薬が開発されるなど、近年の治療の開発は目覚ましいものがあり、今後も益々発展するものと思います。また、予防の重要性から、早期発見と早期介入が益々推進されていくことを期待したいと思います。特に禁煙の啓発や施策が進めば、COPD 患者数は減少してくることが期待できます。しかし、今のところ患者が多い状態が当面は続くことが想定されます。本書が呼吸器専門医のみならず、かかりつけ医の皆様にもCOPD の日常臨床のお役に立てると願っております。
最後に、本書の作成に多大なるご尽力をいただいた関係者の皆様ならびにコメントをいただきました学会員の先生方、そして査読にご協力いただきました患者団体代表様に深く感謝いたします。
(日本呼吸器学会COPD ガイドライン第6版作成委員会 委員長 柴田 陽光 「序」より)

咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2019
咳嗽は呼吸器疾患の日常診療においてもっとも高頻度に遭遇する症状の一つであり,とりわけ長引く咳や頑固な咳で医療機関を受診する患者さんは年々増加の一途を辿っています。日本呼吸器学会では,2005年「咳嗽に関するガイドライン」初版に引き続いて,2012年に第2版を発刊しMinds認証も受けました。これまで数多くの診療ガイドラインが刊行されていますが,その大部分はある「疾患」を対象としたものです。よって,ガイドラインを活用するためには疾病の診断が確定していることが前提となっています。しかし,咳嗽のガイドラインは「症候」を冠していることから,症状→検査→診断→治療という通常の診療の流れに則したプラクティカルな構成となっています。
一方,喀痰は咳嗽と並ぶ重要な症状であり,しかも両者は互いに密接に関連しているのにもかかわらず,これまで喀痰に関するガイドラインは存在しませんでした。特に慢性的な気道分泌亢進は,喘息やCOPDをはじめさまざまな気道疾患の病態を修飾し,患者さんのQOLのみならず疾患の急性増悪や予後に重大な影響を与えることもわかっています。このような背景を踏まえ,今回の咳嗽ガイドラインの改訂に伴い,これに喀痰の項目を加えて『咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019』を作成するに至りました。そこで,「咳嗽」のパートは長崎大学 迎 寛 教授,「喀痰」のパートは横浜市立大学 金子 猛 教授を中心に,各々の症候に関するエキスパートの先生方に委員としてご参画いただきました。喀痰に関するガイドラインは国際的にも初めてのものであり,呼吸器診療に大きなインパクトを与えるものと大いに期待されます。
(玉置 淳「序」より)

大気・室内環境関連疾患 予防と対策の手引 2019
「私たちを取り巻く環境と健康」のなかで特に「大気環境と室内環境に関連する疾患」に絞って解説。

薬剤性肺障害の診断・治療の手引き 第2版 2018
最新の知見を反映させるとともに日常診療での参考になるよう平易な記述を心がけて改訂。
薬剤性肺障害は、「薬剤を投与中に起きた呼吸器系の障害のなかで、薬剤と関連するもの」と定義されます。
2002年7月、分子標的治療薬gefitinibが世界に先駆けてわが国で上市されると、同薬による薬剤性肺障害が多発し社会問題となりました。そこで、日本呼吸器学会(JRS)は増加する薬剤性肺障害に対応すべく、2006年4月に「薬剤性肺障害の評価、治療についてのガイドライン」を発刊しました。その後も、新規薬剤の開発が相次ぎ薬剤性肺障害の報告件数が増加するとともに、mTOR阻害薬にみられるような新たな病態も出現してきました。このような経緯から、JRSは「薬剤性肺障害の評価、治療についてのガイドライン」の改訂を試みましたが、薬剤性肺障害は個々の症例が対象で発症の予想が難しく、無作為割り付け試験が存在しないため、ガイドラインの要件を満たすことが困難でした。そこで、ガイドラインから「薬剤性肺障害の診断・治療の手引き」とリニューアルされ、2012年5月に第1版が発刊されました。
現在、わが国では年間100件を超える新薬が承認、上市されています。特に、新たな分子標的治療薬や生物学的製剤などの開発、市場投入が続いています。また、免疫チェックポイント阻害薬の登場など、薬剤性肺障害をめぐる環境も大きく変化しています。このたび、前版から6年の歳月を経て、「薬剤性肺障害の診断・治療の手引き」第2版を発刊することができました。本書では、薬剤性肺障害に関する最新の知見を反映させるとともに、日常診療での参考になるよう平易な記述を心がけました。
薬剤性肺障害の診断に際しては、すべての薬剤は肺障害を起こす可能性があることを念頭に置き、まず疑うことが重要です。多種多様な薬剤を扱う臨床医は薬剤性肺障害に遭遇する可能性が高く、肺に異常陰影の出現をみた場合、必ず鑑別しなければならない病態です。呼吸器内科医のみならず、あらゆる診療科の先生方に「薬剤性肺障害の診断・治療の手引き」をお手元に置いていただき、早期の発見と対応にご活用いただけたら幸いです。
(花岡正幸「はじめに」より一部抜粋)

呼気一酸化窒素(NO)測定ハンドブック
気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease;COPD)などの基礎研究において,気管支鏡を介した気道壁の生検に加え,喀痰の細胞成分や遠心後の上清液の検討は,各疾患の病態の解明および治療法の開発に大きく寄与してきた。特に,気管支喘息においては疾患概念が「気管支の攣縮」から「炎症」へと大転換をきたし,治療も「気管支拡張療法」から「抗炎症療法」へと変わり患者管理効率の飛躍的な向上をみたのは周知の事実である。
臨床運用の面からいえば,喀痰の好酸球数を計測し診断や抗炎症薬の強度(量)の決定の目安としているが,喀痰はすべての患者から採取できるわけではなく,さらに採取したとしても処理に手間を要するという欠点があった。
一酸化窒素(nitric oxide;NO)は,生体で産生され多彩な作用を示すことが1970年代以降盛んに研究され,1998年にはFurchgott,Murad,Ignarroのノーベル医学生理学賞の受賞に至った。NOはNO合成酸素(nitric oxide synthase;NOS)によってつくられる。NOSは神経,血管,気道上皮,炎症細胞に広く分布するが,気管支喘息では炎症性サイトカインにより気道上皮や炎症細胞にNOSの誘導が起こり,大量のNOが生ずる。NOはガス分子であることから呼気で検出することが可能であり,近年喘息の補助診断検査として普及するに至った。
しかし,呼気NO測定検査は保険収載されていまだ数年で,測定の意義や結果の解釈に関し多少混乱がある。こういった状況の下,日本呼吸器学会肺生理専門員会で,呼気NO測定の原理,測定方法,結果の解釈などに関してできるだけわかりやすく解説した本ハンドブックを刊行するに至った。本書が呼吸器診療に携わる少しでも多くの関係者に読まれることを祈念する。
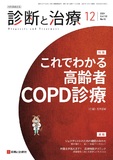
診断と治療 Vol.112 No.12
2024年12月号
【特集】これでわかる高齢者COPD診療
【特集】これでわかる高齢者COPD診療
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者数は増加の一途をたどっていますが,未診断・未治療が多い現状もあります.
基本的な知識から最新の診断・治療法,在宅医療について,さらに併存疾患からCOPDをとらえ,地域医療連携や多職種協働の取り組みについても,診療科や職種の垣根を越えて解説しています.

助産雑誌 Vol.78 No.6
2024年 12月号
特集 「私のからだは私のもの」から始める初期中絶のケア
特集 「私のからだは私のもの」から始める初期中絶のケア かつてない少産化の今、産み育てることに関わる意識や言葉、制度や環境が大きな変革期を迎えています。新しい助産師像を模索する現代の助産師、そして妊娠・出産・育児を考える全ての人と共に、考え、つくる雑誌です。 (ISSN 1347-8168)
隔月刊(偶数月)、年6冊

保健師ジャーナル Vol.80 No.6
2024年 12月号
特集 令和6年能登半島地震の経験を踏まえた今後の備え
特集 令和6年能登半島地震の経験を踏まえた今後の備え 公衆衛生活動の現場で働く保健師に向けた、「保健師」と名の付く唯一の専門誌。 保健活動の現場において「いま」そして「これから」求められる情報や視点を、特集や連載など多様な構成でお届けします。
2022年からは隔月刊化とともに全ページカラーとなり、見やすい資料や豊富な画像によってポイントやイメージをより分かりやすく紹介していきます。 (ISSN 1348-8333)

病院 Vol.83 No.12
2024年 12月号
特集 検証 2024年度診療報酬改定 病院の機能分化と連携の行方
特集 検証 2024年度診療報酬改定 病院の機能分化と連携の行方 「よい病院はどうあるべきかを研究する」をコンセプトに掲げ、病院運営の指針を提供する。特集では、病院を取り巻く制度改正や社会情勢の読み解き方、変革に対応するための組織づくりなど、病院の今後の姿について考える視点と先駆的な事例を紹介する。 (ISSN 0385-2377)
月刊、年12冊
