
≪クリニカル作業療法シリーズ≫
高次脳機能障害領域の作業療法
対象者の生活障害と脳機能の状態に合わせた介入方法を選択して、いかに根拠をもって対処するかを示す。失認、失読・失書、失語、失行、遂行機能障害、半側空間無視など13の障害像に対して評価、利点・問題点、介入方略・目標・方針、プログラム、実施(問題解決)など解説。

看取り死のそのときまで「そのひとである」ことを支える
【暮らしのなかで高齢者を看取るプロセス】苦痛を与えてまで延命するのではなく、死を自然な過程として捉え、苦しみを取り除き、住み慣れた自宅や施設で看取るための考え方と実践のために何をすべきかを伝える一冊。

胸部外科 Vol.77 No.13
2024年12月号
1948年創刊。常に最近の話題を満載した、わが国で最も長い歴史と伝統を持つ専門誌。心、肺、食道3領域の外科を含む商業医学雑誌として好評を得ている。複数の編集委員(主幹)による厳正な査読を経た投稿論文を主体とした構成。巻頭の「胸部外科の指針」は、投稿原稿の中から話題性、あるいは問題性のある論文を選定し、2人の討論者による誌上討論を行っている。胸部外科医にとって必須の特集テーマを年4回設定。また、「まい・てくにっく」、「1枚のシェーマ」、読み物として「胸部外科医の散歩道」を連載。
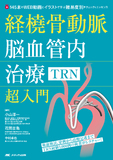
経橈骨動脈脳血管内治療(TRN)超入門
【時代は「手首」へ。さらなる低侵襲治療を】脳血管障害の手術では、低侵襲の血管内治療が急速に普及しているが、最も普及している大腿動脈からの治療では、穿刺部合併症などが問題となる。経橈骨動脈脳血管内治療(TRN)のパイオニアである著者らが、豊富な症例を用いて、安全・確実な治療法を基礎からレクチャーする。
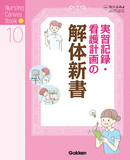
≪Nursing Canvas Book 10≫
実習記録・看護計画の解体新書
NCBシリーズVol.2『看護過程の解体新書』の待望の続編!
看護学生が悩む実習記録・看護計画を書き方基本から1つ1つやさしく・わかりやすく解説しています.
練習問題もついているので,振り返りの学習はもちろん,グループ学習にも最適な1冊!

臨床雑誌外科 Vol.86 No.13
2024年12月号
エキスパートから学ぶ大腸癌に対するロボット支援下手術の実際
エキスパートから学ぶ大腸癌に対するロボット支援下手術の実際 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

多職種で進める糖尿病性腎症重症化予防
糖尿病性腎症重症化予防の全貌と、腎症重症化予防における多職種連携のポイントがわかる!
本書は、2015年6月刊行の『ナースのための糖尿病透析予防支援ガイド』を改訂・改題したものです。
糖尿病性腎症(以下、腎症)は透析療法導入の原因疾患では最大のもので、新規透析導入の約40%を占めています。腎症の重症化を予防するには、多職種連携による早期からの患者支援と治療が重要です。
本書では、各職種の役割を示した上で、患者の状況に合わせた具体的な支援を詳しく述べています。
患者が自分の病状を理解し、セルフケアを続けていけることを目標にした支援が理解できます。
≪本書は第1版第1刷の電子版です。≫

看護 Vol.76 No.14
2024年11月臨時増刊号
特集 「令和6年能登半島地震」から学ぶ
特集 「令和6年能登半島地震」から学ぶ
2024年1月1日、石川県の能登半島を襲ったマグニチュード7.6強の地震。今回の震災では過去の災害と共通する被害が見られた一方で、過疎地域特有の課題が顕在化しました。
次なる災害に備えるためには、こうした課題を深く考察し、対策を検討することが必要不可欠です。
本総特集では、まず、被災地における医療提供体制確保に努めた公益社団法人石川県看護協会や災害支援ナースの活動の実際を紹介した上で、その活動から見えてきた課題を整理。次に、これらの課題を踏まえて今後考えるべき対策について提言するとともに、南海トラフ地震に備えた事前準備などを、県看護協会や医療機関の立場から報告します。最後に、より進んだ海外の事例やインターネット時代ならではのデマ・流言への対策のポイントについて解説します。

社会保険旬報 №2946
2024年11月21日
《レコーダ》 『虎ノ門フォーラム月例社会保障研究会から 公的年金制度の次期制度改正に向けた課題』高橋俊之
《レコーダ》 『虎ノ門フォーラム月例社会保障研究会から 公的年金制度の次期制度改正に向けた課題』高橋俊之
医療介護福祉政策研究フォーラム(虎ノ門フォーラム、中村秀一理事長)による第116回月例社会保障研究会が9月19日に日本記者クラブ(東京都千代田区内幸町)で開催され、日本総合研究所特任研究員で元厚生労働省年金局長の高橋俊之氏が「公的年金制度の次期制度改正に向けた課題」と題して講演した。
公的年金制度では今年、5年に一度の財政検証を実施した。厚生労働省は7月3日、財政検証結果を公表。それをもとに社会保障審議会年金部会では来年の法改正に向けた議論が進められている。講演では、前回2020年改正当時の年金局長だった高橋俊之氏が、2024年財政検証結果を解説、来年に予定されている次期2025年制度改正の課題と方向性について語った。

理学療法41巻10号
2024年10月号
理学療法における技術を科学する―動作支援編【動画付き】
理学療法における技術を科学する―動作支援編【動画付き】 理学療法におけるさまざまな技術を科学的な視点から整理することを目的とする、「技術を科学する」シリーズ第二弾では「動作支援」を取り上げます。
本号では、疾患別の理学療法について、①動作支援の考え方、②動作支援の技術的な要点、③動作支援の技術について、科学としての説明が最もなされているのは、どのような点か、④動作支援の技術について、科学としての説明が最もなされていないのは、どのような点か、⑤動作支援の技術をより科学的に表現していくための課題として、どのような事柄が挙げられるか、に分けて述べていただきます。
また、疾患別、病期別の動作支援の考え方と実際の技術的な要点について、イラスト、写真、動画などを用いて分かりやすく理解していただくことを狙いとしました。

小児科 Vol.65 No.11
2024年11月号
正しく指示する子どもの栄養・病気のときの食事指導Ⅰ
正しく指示する子どもの栄養・病気のときの食事指導Ⅰ
一般論としては知っていても,なかなか個別の病態・疾患ごとに深堀りする機会が少ない「栄養・食事指導」が今回のテーマ。食物アレルギーや肥満・糖尿病をはじめ,腎疾患・肝疾患,心不全,神経筋疾患,鉄欠乏性貧血,口内炎に至るまで。病院勤務の先生にとっても,クリニックの先生にとっても,かゆいところに手がとどく内容を目指しました。

整形・災害外科 Vol.67 No.12
2024年11月号
超高齢社会における手外科疾患の治療
超高齢社会における手外科疾患の治療
人口の高齢化に伴い,手の変性疾患,手外科手術件数が増加している。高齢者が早期に日常生活や仕事に復帰すること,手の健康を維持することは健康寿命の延伸の観点からも重要である。本特集は手の変性疾患,高齢者の手外科疾患の病態と治療について経験豊富な著者が解説しており,日常診療に役立つ内容となっている。

エキスパートナース Vol.40 No.15
2024年12月号
◆精神症状を見分けるコツと対応・ケア
◆インシデントのしくみを学んで インシデントレポートの疑問・不満を解決しよう!
◆精神症状を見分けるコツと対応・ケア
◆インシデントのしくみを学んで インシデントレポートの疑問・不満を解決しよう!

小児看護2024年12月号
こどもとの対話;小児看護におけるコミュニケーションの重要性
こどもとの対話;小児看護におけるコミュニケーションの重要性 こどもにとって、看護師とのコミュニケーションは単なる情報の共有だけでなく、主体性の育成や癒やしにつながるものである。本特集では知っておきたい知識として、こどものことばの発達、母子の対話、コミュニケーションに影響するこどもの心理や遊び、協働意思決定(shared decision-making)に関することを紹介する。また、こどもの発達段階・発達の特性・状況ごとに行われている対話の実際や、障害があるこどもへのICTを活用したコミュニケーション支援についても紹介する。

胆と膵 2024年10月号
2024年10月号
特集:胆膵手術のちょっとしたコツ【動画付】
特集:胆膵手術のちょっとしたコツ【動画付】

臨牀消化器内科 Vol.39 No.13
2024年12月号
良悪性肝門部胆管狭窄への内視鏡的アプローチ
良悪性肝門部胆管狭窄への内視鏡的アプローチ
肝門部胆管狭窄は、良性・悪性を問わず、診断から治療まで高度な専門性が求められる領域である。特集は診断ストラテジーの概説から始まり、経口胆道鏡を用いた進展度診断、そして切除可能性分類と治療戦略へと進んでいく。

≪実験医学別冊≫
疾患研究につながる オルガネラ実験必携プロトコール
各細胞小器官からオルガネラコンタクトまで、実験法のセオリーと熟練のノウハウ
ミトコンドリアをはじめオルガネラの機能解析に着手するにはこの一冊.自らに適した手法を選び実験を成功に導くためのノウハウを,エキスパートが惜しみなく解説.医学系研究者にも細胞生物学研究者にもおすすめ

訪問看護、介護・福祉施設のケアに携わる人へ
コミュニティケア Vol.26 No.12
2024年12月号
特集:被災経験から学ぶ 地域BCPにおける訪問看護ステーションの役割
特集:被災経験から学ぶ 地域BCPにおける訪問看護ステーションの役割
訪問看護ステーションは医療機関と異なり、利用者が地域に点在し、有事の際、職員も必ずステーションにいるとは限りません。そのため、災害時には職員や利用者の安否確認等が必要となりますが、1つのステーションだけでは解決し切れない問題が生じる可能性も高くなります。自ステーションの事業継続に加え、地域全体の医療・ケアの提供を継続するという視点からも、平時からの地域BCPへの参画、ステーション同士での連携体制の構築が重要です。
本特集では、〈インタビュー〉〈特別報告〉において、令和6年能登半島地震発災時から訪問看護師として活動し続ける中村悦子さん、後方支援として役割を発揮した石川県訪問看護ステーション連絡会が、当時から今に至る状況について報告します。また、〈論考〉で地域BCPの重要性について述べた上で、〈報告〉はさまざまな被災経験を踏まえた、訪問看護ステーションや訪問看護ステーション連絡協議会から地域における災害への備えを紹介します。
あなたのステーションのBCP、この機会にあらためて見直してみませんか?

手術 Vol.78 No.12
2024年11月号
誌上ディベート ロボット支援肝胆膵外科手術のpros and cons—近未来のスタンダードとなり得るか
誌上ディベート ロボット支援肝胆膵外科手術のpros and cons—近未来のスタンダードとなり得るか
ロボット支援手術の適応拡大が進み,その施行症例数が着実に増加してきた現在,ロボット支援手術が「スタンダードとなり得るか」は,外科医にとっての大きな関心事であろう。向こう10年ほどの「近未来」において,「ロボット」という新たな選択肢を手にした肝胆膵外科手術がどう変わっていくのか,あるいはさほど変わらないのか……。現時点におけるエキスパートの考えを,それぞれの立場からディベート形式で論じた特集となる。
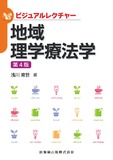
ビジュアルレクチャー 地域理学療法学 第4版
好評の地域理学療法学テキスト,改訂第4版!
●自立とは? ノーマライゼーションとは? 地域リハビリテーションとは?
●本書では,初学者にもご活用いただけるよう120点を超える図表を掲載しつつ地域理学療法学の要点を解説している.
●第4版では,感染予防対策,災害時のリハビリテーション,SDGsなどについて解説を追加したほか,関連制度・法律・統計データのアップデート,令和6年版理学療法士国家試験出題基準への対応を図った.
