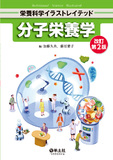
≪栄養科学イラストレイテッド≫
分子栄養学 改訂第2版
これからの栄養学に分子生物学の知識は必須!各栄養素の細胞・遺伝子レベルでのはたらきや,疾患との関連についてわかりやすく解説.次世代のプレシジョン栄養学に向けて栄養指導に役立つ内容も必読!

肝臓クリニカルアップデート 2024年10月号
2024年10月号
特集:薬物療法の進歩における肝細胞癌の診断と治療Update
特集:薬物療法の進歩における肝細胞癌の診断と治療Update

胆と膵 2024年9月号
2024年9月号
特集:膵胆道周囲の後腹膜腫瘤性病変の診断と治療
特集:膵胆道周囲の後腹膜腫瘤性病変の診断と治療

臨牀透析 Vol.40 No.12
2024年11月号
いざ実践! 透析患者の栄養管理
いざ実践! 透析患者の栄養管理
今回の透析食については各栄養素毎の充足方法が中心に「制限食」から「補充」「調整」といった表現で取り入れました。経口栄養から静脈栄養に至るまでの工夫点にも触れています。
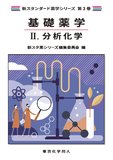
≪新スタンダード薬学シリーズ 3≫
基礎薬学Ⅱ. 分析化学
医療人としての薬剤師養成教育に資する標準テキスト

ねころんで読める緩和ケア
【経験を元にした緩和アプローチのヒント】緩和ケアに自信がもてない医師のため、身体的な症状緩和(痛み、呼吸困難、せん妄、嘔気)、患者のQOLを良好に保つための症状マネジメント(便秘、食欲不振、不眠)、精神症状(気持ちのつらさ・不安)、鎮静について、すぐに役立つポイントを中心に解説した。患者のニーズに合わせた緩和ケアが提供できる知識や説明のコツがわかる書籍。

≪眼科ケア2024年秋季増刊≫
眼科の検査機器・手術器具パーフェクトブック
【一冊で使い方をマスターできる!】眼科の検査機器と手術器具を網羅し、前編は「検査」、後編は「処置・手術」という構成で、場面ごとの機器や器具の使用目的や使用手順、取り扱いのポイントや注意すべき点、トラブル対処法をわかりやすく解説。日々忙しく働くスタッフが全員で読める便利な一冊です。

認知症のみかた,考えかた
認知症診療に必要な知識の整理とアップデートを1冊で!
日本にはすでに400万人を超える認知症者がいるとされ,認知症は稀少疾患ではなくコモンディシーズとなり,認知症を正しく理解することは必須のいま,日常診療ですぐに役立つ実践的マニュアル!
診察のコツや,早期発見・正しい判断のための検査,認知症を来す疾患それぞれについての解説から,レカネマブなど最新の抗体療法を含む具体的な治療,法律・社会制度まで,体系的にすべてをまとめた必読書

診断と治療 Vol.112 No.11
2024年11月号
【特集】外来で見逃さない危険な疾患,相談すべき症例―気づくコツ,つなぐヒント―
【特集】外来で見逃さない危険な疾患,相談すべき症例―気づくコツ,つなぐヒント―
外来で見逃すと重大な病態に進む“隠れた”危険なサインや“最初の”サイン,すぐに専門医に相談すべき訴えを取り上げ,救急分野での最新の方法論も紹介し,“気づくコツ,つなぐヒント”を考えます.
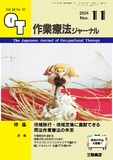
作業療法ジャーナル Vol.58 No.12
2024年11月号
■特集
地域移行・地域定着に貢献できる司法作業療法の未来
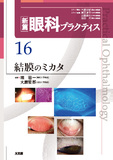
≪新篇眼科プラクティス 16≫
結膜のミカタ
結膜の正しい「診かた」を学び,日常診療の「味方」となる,若手からベテランまで必携の一冊.豊富な写真で視覚的にもわかりやすく,基本知識から診断・治療,最新の話題まで体系的に理解できる.【シリーズ概要】「日常臨床にすぐ役立つ」をコンセプトとした「眼科プラクティス」の最新シリーズ.今シリーズでは図版をより効果的に示すことで,さらにビジュアル面を大幅強化.直感的に理解できる「視る教科書」を目指した.

眼科診療ガイド 第2版
日常診療で必要な時にすぐ活用できるをコンセプトに,長年診療現場を支えた眼科診療ガイドの第2版がついに登場.専門医試験基準に準拠した疾患に加え,稀少疾患,新しい概念の疾患,不定愁訴への対応やリスクマネジメントまで盛り込んだ最新版.診療ガイドラインにアクセスできる二次元コードも掲載し利便性もアップ.眼科診療に携わるすべての医療者が使いやすい新たな実践書のスタンダード.

薬局 Vol.75 No.13
2024年11月号
適剤適処!Bz(ベンゾジアゼピン)受容体作動薬
リスク/ベネフィット比を最適化する
適剤適処!Bz(ベンゾジアゼピン)受容体作動薬
リスク/ベネフィット比を最適化する ベンゾジアゼピン(Bz)受容体作動薬は,優れた効果をもっていますが,一方で依存性が問題視されています.さらに新たな睡眠薬も登場し,Bz受容体作動薬は処方すべきでない不適切な薬のように扱われる場面も見られるようになりました.しかし臨床現場では,有効性と安全性のバランスを最適化した適正使用が求められています.また,最近報告されたリスクなどもあり,エビデンスのアップデートも重要です.そこで11月号では,Bz受容体作動薬のリスク/ベネフィット比の最適化をテーマとしました.臨床で役立つ薬学的視点を養う特集です.

地域リハビリテーション論 Ver.9
地域リハにかかわる各職種必携の書
2024年度のトリプル改定(診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬)についての最新情報を加えてバージョンアップ !
地域リハの全体像を学べると好評をいただく本書。
「Ver.9」(=第9版)は、2024年に行われた6年ぶりの診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬のトリプル改定に伴う情報を反映させてバージョンアップ。
「2025年問題」を目前に、全国の各市町村で地域包括ケアシステムの構築に向けたさまざまな取り組みが行われるとともに、地域リハビリテーションへの関心が高まっています。地域リハのありかたを理解し、自身の視点を持つことは、医療・介護従事者だけでなく、地域包括ケアに取り組む市町村職員にとっても必須です。
本書では、地域リハ活動の歴史や介護保険との関わりを網羅し、支援の体制づくりや今後の地域リハについても言及。リハ職を目指す学生、および高齢者や障害者を地域で支える職種の方に必携の教科書です。

精神医学テキスト 改訂第5版
精神障害の理解と治療のために
理学療法士・作業療法士養成過程を中心とした学生向けテキスト.現場で扱う精神疾患の解説を詳しくし,記述に軽重をつけ,また主要な疾患・症候は簡潔な「症例(ケース)」にて典型例を紹介することで具体的な理解を容易にしている.今改訂では,好評の「症例」を充実させたほか,「心理検査と統計」「ゲーム障害」「漢方薬」の項目を追加し,採用者の要望に応えて全体を充実させた.

リハビリテーション医学テキスト 改訂第5版
リハビリテーション医学を平易かつ網羅的に解説しており,確かな知識がつく教科書.総論部分では全体を概観し,各論部分ではリハビリテーションに関わる各疾患について,概念,評価,治療などを簡潔に解説している.今改訂では,「がん・悪性腫瘍」の章を新設したほか,学問領域の進展にともなう情報更新を行い ,より充実した教科書となった.

麻酔 Vol.73 No.9
2024年9月号
周術期急性腎障害up-to-date
周術期急性腎障害up-to-date 大侵襲手術の合併症として急性腎障害の頻度が高いことは周知の事実であり、周術期腎障害を如何に予防するか、重症化を回避するかは、依然として重要な課題である。本特集ではKDIGOバンドルの各項目にいくつかのトピックを追加し、それぞれ解説していただく企画とした。

形成外科 Vol.67 No.9
2024年9月号
総合病院における美容医療の実践
総合病院における美容医療の実践 すでに総合病院で本格的な美容医療を提供している全国の施設の先生に,総合病院での美容医療の運営にまつわる困難や苦渋,あるいは知恵や利点を執筆頂いた。施設で美容医療を始めた経緯や,難しい問題をどう乗り切ったか,あるいは乗り越えることができなかったかなど,様々なハードルが存在する総合病院での美容医療を赤裸々に記載した1冊。
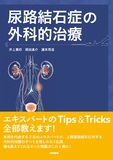
尿路結石症の外科的治療
エキスパートが伝授する、上部尿路結石症外科的治療のTips&Tricks
URSおよびPCNL/ECIRSを中心に、上部尿路結石症の積極的治療の基礎知識から実際までを解説した実践書。日本を代表するエキスパートである3名の著者が、豊富な経験から得た知識や技術を惜しげもなく披露した。後半のCase Discussionでは、具体的な症例に沿って達人の考えかたや技が学べる。誰も教えてくれなかったTips&Tricksが満載の一冊!

Evidence Based で考える認知症リハビリテーション2 BPSDの評価と介入戦略[Web動画付]
認知症新時代に求められるエビデンスベースのBPSDリハビリテーション・ケア
好評を得た『Evidence Basedで考える認知症リハビリテーション』の第2弾。前作同様、「臨床と研究をつなぐ」「エビデンスベースド」をコンセプトに、認知症者の行動・心理症状である「BPSD」を深く掘り下げる。症状ごとの出現要因や適切な解釈、最新の知見をもとにした妥当な介入戦略の数々を紹介。各項目収載のレクチャー動画も理解の助けとなる。認知症リハビリテーション・ケア分野の医療従事者必携の1冊。
