
眼科 Vol.66 No.11
2024年11月臨時増刊号
眼科外来診療 ―クリニックでの対応と紹介のタイミング―
眼科外来診療 ―クリニックでの対応と紹介のタイミング―
どこから読んでもすぐに役立つ、気軽な眼科の専門誌です。本年の臨時増刊号は「眼科外来診療―クリニックでの対応と紹介のタイミング―」と題し、日常臨床の場で診断や治療を進めていく際のポイントと、ある一線を越えた場合や初診時既に一線を越えている病態に対し、より高度で適切な医療を提供するために紹介するタイミングに焦点を当て、専門家の先生方にご執筆をいただきました。秋の夜長に是非お楽しみいただければ幸いです。
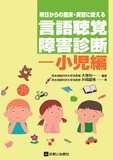
明日からの臨床・実習に使える言語聴覚障害診断―小児編
本書は言語発達に問題がある子どもへの初期評価の方法を解説した書籍です.診断が未確定の子どもに対し,どのような評価が有効かを具体的に紹介しており,特定の障害に限定しない点が特徴です.また,保護者支援の重要性にも言及し,面談や心理的配慮のポイントも詳述.言語聴覚士の実務や教育現場で役立つ一冊です.

明日からの臨床・実習に使える言語聴覚障害診断―成人編 改訂第2版
初学者や若手臨床家向けに,初期スクリーニングと診断の基礎力を養うために2016年に刊行された書籍の第2版.診断が難しい障害の注目症状や評価項目の解説を比較方式で追加し,実習用スライドも導入.見出しデザインと内容の再構成でわかりやすさが向上しました.『小児編』と併せて幅広い年代に対応.養成校の講義のみならず臨床の現場で役立つ一冊です.

ICUとCCU 2024年11月号
2024年11月号
特集:臓器不全におけるフェノタイプ解析
特集:臓器不全におけるフェノタイプ解析

Prostate Journal 2024年10月号
2024年10月号
特集:良性前立腺疾患のアップデート
特集:良性前立腺疾患のアップデート

理想のリーダーになる! チームがまとまる! マンガでわかる看護管理 リーダー編
マンガでわかりやすい! 共感できる! ナースが直面する、リーダー業務の現場あるあるをカヨ先生が解決に導く!
看護師なら避けて通れないリーダー業務について、現場でよく起こる問題や悩みを軸に、明快にわかりやすく解説する

介護保険の実務 令和6年度版
保険料と介護保険財政
◆保険料と介護保険財政を中心として、介護保険における保険者事務について詳しく解説した実務書です。事例や運用をできる限り記述する一方、介護保険制度の基本的な考え方も説明しています。解説には法令上の根拠を示していますので、知識の整理等にも役立ちます。

介護保険制度の解説 [解説編] 令和6年度版
改正後の介護保険制度を理解し、考えるための「わかりやすい」決定版!
◆介護保険は,高齢者の介護を社会全体で支えあうしくみです。どのような人が,どのような手続を経て,どのようなサービスをうけられるのか,そしてその費用はどのようにまかなわれ,どのように制度が運営されるのかについて,全体像を見通しつつ,詳細に解説しています。
◆解説編では、法令・資料にもとづいて、介護保険の内容を丁寧に解説しています。図表を豊富に掲載することにより、理解しやすい構成になっています。
※法令編はついていません。

社会保険旬報 №2945
2024年11月11日
《インタビュー》 『社会の変化に対応した協会けんぽの運営を 財政運営「中長期的なスタンスで」』全国健康保険協会理事長 北川博康
《インタビュー》 『社会の変化に対応した協会けんぽの運営を 財政運営「中長期的なスタンスで」』全国健康保険協会理事長 北川博康
昨年10月1日に就任して1年が経った全国健康保険協会(協会けんぽ)の北川博康理事長から、これまでの取組みと今後の目指すべき方向性について話を聞いた。北川理事長は、戦略キーワードとして「DX」「SDGs」「国際化」、運営テーマとして「全員参加型運営」「マーケティング思考」の5つを掲げて取り組んでいることを紹介した。協会けんぽの財政運営については、「いかに長い期間、現状の平均保険料率のもと、今の医療保険制度を維持させていくことができるかという中長期的なスタンスで考えたい」との認識を表明した。
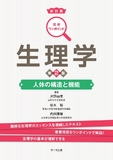
新訂版 図解ワンポイント生理学 第2版
全面改訂。最新の国家試験問題から関連問題を掲載。生理学の項目を見やすい見開き2ページ構成で解説。左ページに図版、右ページにその解説。図版を見ながら難解な生理学を理解するテキスト。

ぶっつけ本番 解剖生理学試験初級編 第1版
間近に迫った解剖生理の試験。今からでは間に合わない。そんなときに、明日からすぐに役立つ、すぐに使える、やさしい解剖生理問題集。
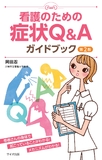
看護のための症状Q&Aガイドブック 第2版
臨地実習や臨床の場でよく出合う40の症状を取り上げ、読みやすいQ&A形式で解説している。第2版では、新たに「意識障害」の項目を追加した。読み進めるうちに、症状が起こるメカニズムから観察の方法や看護まで、自然にマスターできる1冊。患者さんの身体で何が起こっているのかがよくわかる。患者さんの身体で起こっていることがわかる! メカニズムがわかる!
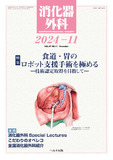
消化器外科2024年11月号
食道・胃のロボット支援手術を極める;技術認定取得を目指して
食道・胃のロボット支援手術を極める;技術認定取得を目指して 2023年度より日本内視鏡外科学会技術認定においてビデオ申請が認められるようになった、胃・食道領域のロボット支援手術。その認定審査のポイントと、具体的手技を豊富な術中写真を通して学び、技術認定合格を目指そう。

救急医学2024年11月号
激変・急増する高齢者外傷を診る
激変・急増する高齢者外傷を診る 現代の救急医なら避けては通れない、高齢患者の外傷。遭遇する機会が多いからこそ、適切に、スムーズに対応できるよう、高齢患者特有の背景・併存疾患・注意点を復習し、とくに重要な損傷・骨折の初期対応を整理しておこう。

社会保険旬報 №2950
2025年1月1日
《新春鼎談》 『審査支払機関の役割と未来~医療DXの推進に向けて~』神田裕二 原勝則 榊原毅
《新春鼎談》 『審査支払機関の役割と未来~医療DXの推進に向けて~』神田裕二 原勝則 榊原毅
質の高い医療の効率的な提供や医療機関等の業務の効率化などを目指し、医療DXに関する業務が進められている。こうしたなか、国はさらなる医療DXの推進に向けて、医療DXの実施主体として社会保険診療報酬支払基金(支払基金)の抜本改組などを盛り込んだ改正法案を今通常国会に提出する方針を示している。
新春鼎談では、「審査支払機関の役割と未来~医療DXの推進に向けて~」をテーマに、支払基金理事長の神田裕二氏、国保中央会理事長の原勝則氏、厚労省大臣官房審議官の榊原毅氏の3氏で、医療DXの推進や「近未来健康活躍社会戦略」、保険者・自治体の支援、今後の審査支払機関の展望について語り合ってもらった。
」看板+_Thumbnail.jpg)
社会保険旬報[電子版]年間購読(2025年1月1日号~2025年12月21日号:計36冊)
医療提供に関わるすべての皆様へ、事業経営に役立つ情報を提供する“オピニオンジャーナル”
1941年創刊の医療・社会保障の専門誌「社会保険旬報」です。紙の冊子版は毎月1日・11日・21日の年36回発行

整形外科学テキスト 改訂第5版
理学療法士・作業療法士養成課程の学生にとって重要科目である整形外科学をこの一冊で網羅できる充実した内容の教科書.頻度が高く,重要な疾患については典型例の写真を充実させ,丁寧に解説している.今改訂では,各章末に「学習のまとめ」の理解を確認できる練習問題を掲載し,国家試験対策により役立つ内容とした.

放射線安全管理学 [電子版付]
診療放射線技師に欠かすことのできない放射線管理の知識や技術,事故の予防・対策はもちろん事故が発生してしまった際の対応について解説する教科書.一般的な放射線安全管理の知識に加え,臨床現場での実例を取扱うことで,学生が現場をイメージしながら学ぶことができるように工夫した.巻末付録として第1種放射線取扱主任者試験問題と解説を掲載し,読者の知識の定着を確認することができる.

LiSA Vol.31 No.11
2024年11月号
徹底分析シリーズ:脊髄くも膜下麻酔さいこう/症例カンファレンス:進行性骨化性線維異形成症の整形外科手術/快人快説:肺動脈カテーテル再考/医学教育お悩み相談室:自分の希望を主張するばかりの専攻医に困っています/ぶらり研究室探訪記:大阪公立大学大学院医学研究科 麻酔科学講座/こどものことをもっと知ろう:小児のルート確保のコツ/ちょっと拝見 となりのDAMカート:兵庫医科大学病院の巻/紹介:機械翻訳事始/diary:兵庫県豊岡市/みんなのプロフィール帳:人生は冒険である/夕ご飯 何にする?:森の恵みのオムレツ
徹底分析シリーズ:脊髄くも膜下麻酔さいこう/症例カンファレンス:進行性骨化性線維異形成症の整形外科手術/快人快説:肺動脈カテーテル再考/医学教育お悩み相談室:自分の希望を主張するばかりの専攻医に困っています/ぶらり研究室探訪記:大阪公立大学大学院医学研究科 麻酔科学講座/こどものことをもっと知ろう:小児のルート確保のコツ/ちょっと拝見 となりのDAMカート:兵庫医科大学病院の巻/紹介:機械翻訳事始/diary:兵庫県豊岡市/みんなのプロフィール帳:人生は冒険である/夕ご飯 何にする?:森の恵みのオムレツ

「育てにくさ」に寄り添う支援マニュアル
子どもの育てにくさに困った親をどうサポートするべきか
子どもの育ちに関するさまざまな疑問・問題を保護者から相談された場合,小児医療・保健にたずさわる専門職者はどう対応すべきかを一冊にまとめた.年齢別,ケース別に98の問題項目を挙げ,実際の対応パターンと,さらに詳しく相談するよう促すことを目的にとした専門機関受診のタイミングを呈示した.
