
小児内科56巻9号
思春期医療に向き合う~苦手意識からの脱却
思春期医療に向き合う~苦手意識からの脱却

小児外科56巻9号
必携小児外科レジデントマニュアル2
必携小児外科レジデントマニュアル2

JOHNS40巻9号増大号
てこずった症例・難治症例にどう対応するか
てこずった症例・難治症例にどう対応するか

周産期医学54巻9号
新生児のケア,検査,治療の工夫―筆者はこうしている
新生児のケア,検査,治療の工夫―筆者はこうしている

理学療法ジャーナル Vol.58 No.11
2024年 11月号
特集 Multimorbidity and Multiple Disabilities(MMD) 多疾患重複時代がやってきた!
特集 Multimorbidity and Multiple Disabilities(MMD) 多疾患重複時代がやってきた! 理学療法の歴史とともに歩む本誌は、『PTジャーナル』として幅広い世代に親しまれている。特集では日々の臨床に生きるテーマを取り上げ、わかりやすく解説する。「Close-up」欄では実践的内容から最新トピックスまでをコンパクトにお届けし、その他各種連載も充実。ブラッシュアップにもステップアップにも役立つ総合誌。 (ISSN 0915-0552)
月刊、年12冊

臨床眼科 Vol.78 No.11
2024年 10月号(増刊号)
特集 6年前の常識は現在の非常識! AI時代へ向かう今日の眼科医へ
特集 6年前の常識は現在の非常識! AI時代へ向かう今日の眼科医へ 読者からの厚い信頼に支えられた原著系眼科専門誌。厳選された投稿論文のほか、眼科領域では最大規模の日本臨床眼科学会の学会原著論文を掲載。「今月の話題」では、気鋭の学究や臨床家、斯界のエキスパートに、話題性の高いテーマをじっくり掘り下げていただく。最新知識が網羅された好評の増刊号も例年通り秋に発行。 (ISSN 0370-5579)
月刊、増刊号を含む年13冊

臨床婦人科産科 Vol.78 No.11
2024年 11月号
今月の臨床 生殖医療の最新潮流とその一歩先
今月の臨床 生殖医療の最新潮流とその一歩先 産婦人科臨床のハイレベルな知識を、わかりやすく読みやすい誌面でお届けする。最新ガイドラインの要点やいま注目の診断・治療手技など、すぐに診療に役立つ知識をまとめた特集、もう一歩踏み込んで詳しく解説する「FOCUS」欄、Web動画を用いて解説する記事もある。毎春に刊行する増刊号は必携の臨床マニュアルとして好評。 (ISSN 0386-9865)
月刊、合併増大号と増刊号を含む年12冊

循環器ジャーナル Vol.72 No.4
2024年 10月号
特集 循環器診断マスター 「ロジック」と「暗黙知」で診断の真髄に迫る
特集 循環器診断マスター 「ロジック」と「暗黙知」で診断の真髄に迫る 循環器専門医を目指す若手の呼吸器内科医・研修医を主な対象とした季刊誌。 臨床に役立つ最新の知見を、第一線で活躍する経験豊かな執筆陣が解説する。 (ISSN 2432-3284)
年4冊刊(1月・4月・7月・10月)

総合診療 Vol.34 No.11
2024年 11月号
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る! 患者情報の「言語化」への挑戦
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る! 患者情報の「言語化」への挑戦 ①独自の切り口が好評の「特集」と、②第一線の執筆者による幅広いテーマの「連載」、そして③お得な年間定期購読が魅力! 実症例に基づく症候からのアプローチを中心に、診断から治療まで、ジェネラルな日常診療に真に役立つ知識とスキルを選りすぐる。「総合診療専門医」関連企画も。 (ISSN 2188-8051)
月刊、年12冊
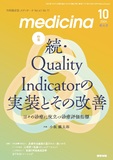
medicina Vol.61 No.11
2024年 10月号(増大号)
特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善 日々の診療に役立つ診療評価指標
特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善 日々の診療に役立つ診療評価指標 内科診療に不可欠な情報をわかりやすくお届けする総合臨床誌。通常号では内科領域のさまざまなテーマを特集形式で取り上げるとともに、連載では注目のトピックスを掘り下げる。また、領域横断的なテーマの増刊号、増大号も発行。知識のアップデートと、技術のブラッシュアップに! (ISSN 0025-7699)
月刊、増刊号と増大号を含む年13冊

公衆衛生 Vol.88 No.11
2024年 11月号
特集 「こどもまんなか社会」を目指して 成育基本法・こども基本法・こども家庭庁
特集 「こどもまんなか社会」を目指して 成育基本法・こども基本法・こども家庭庁 地域住民の健康の保持・向上のための活動に携わっている公衆衛生関係者のための専門誌。毎月の特集テーマでは、さまざまな角度から今日的課題をとりあげ、現場に役立つ情報と活動指針について解説する。 (ISSN 0368-5187)
月刊、年12冊

便失禁診療ガイドライン2024年版 改訂第2版
初版以降の新たなエビデンスと日本の医療状況に立脚した実践的なガイドライン改訂版.便失禁の定義や病態,診断・評価法,初期治療から専門的治療にいたるまで基本的知識をアップデートし,新たに失禁関連皮膚炎や出産後患者に関する記載を拡充.また治療法選択や専門施設との連携のタイミングなど,判断に迷うテーマについてはCQとして推奨を示した.患者像により多様な病態を示す便失禁の診療とケアに携わる,すべての医療職にとって指針となる一冊である.

新版 心疾患の診断と手術
1974年の初版より改訂を重ねてきた名著を継承し,東京女子医科大学心臓血管外科の総力をあげて全面的に刷新.小児(先天性)・成人心疾患および各部位の主要な疾患が網羅され,低侵襲心臓手術や体外循環法を含む心臓血管外科領域の全容を解説している.実践に裏打ちされた診療指針を学ぶ教科書として,心臓血管外科を志す若手外科医に最適の一冊.

保険医療機関のための 診療報酬とカルテ記載 令和6年版
『診療報酬請求にカルテ記載が求められている「医科」に関係する項目をすべて収載』
『個別指導の状況,チェックリスト,カルテの記載例を掲載』
◆本書は,算定するためには「診療録(等)に記載(又は添付)しなければならない」と規定されている内容を抜粋し,チェックリスト,カルテ例などの付加情報を加えて編集しました。
◆点数表の項目順に,項目の解説,規定,チェックリストとカルテの記載例を掲載しています。
◆新しく追加・改定された項目がわかるようにマーク「新」「改」で表示しています。

社会保険旬報 №2944
2024年11月1日
《論評》 『医療と介護の連携―令和6年度介護報酬改定を中心に』古元重和
《論評》 『医療と介護の連携―令和6年度介護報酬改定を中心に』古元重和
医療と介護の提供体制が転換期を迎えている。
我が国では、今後、国内ほぼすべての地域で生産年齢人口の減少が見込まれる中、2040年までに医療と介護の両方のニーズを有する85歳以上の方の救急搬送や在宅医療需要が大きく増加し、同時に認知症の方や高齢者単独世帯も増加する。
こうした将来を見据え、現在行われている「新たな地域医療構想等に関する検討会」では、従来の地域医療構想が「病床の機能分化・連携」に着目したものであったのに対し、「入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等も含む、医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ」との方向性が示されている。
これに先立ち、令和6年度は診療報酬と介護報酬の同時改定が行われ、医療と介護のさらなる連携に向けて大幅な制度の見直しが行われた。
本稿では、今後の医療・介護政策を検討するにあたり、関係者の共通認識となるよう、筆者が老健局老人保健課長としてかかわった、令和6年度介護報酬改定の内容や考え方などについて解説したい。また、この改定による医療・介護連携に向けた効果や、今後の展望についても考察したい。

イムス葛飾ハートセンター
心臓血管外科手術[Web動画付]
高画質動画 約7時間 × 精細な静止画像でわかる
イムス葛飾ハートセンターのすべてをここに。
若手心臓外科医が習得すべき手技を41の項目に細分化し,できる限り丁寧に解説。精緻な高解像度の画像をコマ送りで掲載し,「どのように考えてどう行うべきか」を“リアルタイム”で詳述。全項目に高解像度の動画が付帯しているので,書籍で手術の全体像を頭の中に入れたら,動画で流れを確認できる。さらなる上達を目指すのためのアドバイスも充実。
知りたかったところがここまでみえる! わかる! 実践に特化した,専門医を目指す若手必携の一冊。

≪クリニカル作業療法シリーズ≫
福祉用具・住環境整備の作業療法
障害者の自立・自律を支援する福祉用具。本書は、ベッド・床上動作、移動・移乗、コミュニケーションなど、ADLごとに福祉用具を選択する流れを解説。高齢者、脳血管疾患、脊髄損傷、神経筋疾患などの疾患・障害別に、福祉用具選定・導入の「どうやって?」がわかる!
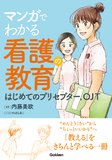
マンガでわかる看護の教育
はじめてのプリセプター,OJT
看護の教育がマンガでわかる!
初めてプリセプターを任されることになった花咲の1年~春夏秋冬奮闘記.
現場で直面する悩みや困りごとの「現場あるある」を,教育学の理論に基づき丁寧に解説.
考え方や対処法を伝授.後輩指導をきちんと学びたい人,必読の書!

Clinical Engineering Vol.35 No.11(2024年11月号)
臨床工学ジャーナル[クリニカルエンジニアリング]
【特集】植込み型心臓デバイス治療のニューノーマル
【特集】植込み型心臓デバイス治療のニューノーマル ペースメーカ等の植込み型心臓デバイスは飛躍的な進化を遂げている。教科書にも加えるべき植込み型心臓デバイスの新たな機能等を紹介した、臨床工学技士から臨床工学を学ぶ学生まで幅広く読んでいただきたい特集!
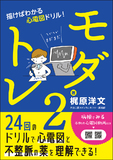
モダトレ2
描けばわかる心電図ドリル!
●24回のドリルで心電図と不整脈の薬を理解できる!
●心電図、電気生理学、薬理学の知識を連動する考え方を学ぶための1冊目!
不整脈の薬物治療の学習でよく陥るピットフォールとして、心電図のパターン暗記があります。しかし、不整脈の薬物治療には、どのような刺激伝導異常が生じるかを知ったうえで理論的に心電図を解析し、かつその異常を是正する薬理作用をもつ薬剤を選択することが必要です。こう聞くと非常に難しく感じますが、実はこの思考過程を学ぶためのコツをつかめば、この分野の理解は大きく前進します。前作の「モダトレ」(2019年7月刊)で紹介しきれなかったそのコツを紹介する機会を、今回ついに得ることができました。
本書は、総合的な薬物治療評価のために心電図、電気生理学、薬理学の知識を連動する考え方を学べる問題形式となっていますが、答えがわからない場合には無理する必要はありません。答えをみて理解できれば十分です。この点は通常の問題集とは異なるため、誤解のないようお願いします。また、詳細に解説すると難しくなる内容は成書に譲って、理解を優先するために省略し、簡易的な表現としている点もご了承ください。
