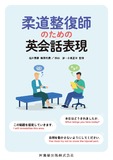
柔道整復師のための英会話表現
これからの柔道整復師に必要な「使える英語」を学べるテキスト!
●日本語を話すことができない外国人患者に対して柔道整復術を行えるよう,接骨院でのコミュニケーションに必要な英語表現を収載した,これからの柔道整復師に必読の「使える英語」を学べる一冊.
●受付から医療面接,身体観察,施術,会計にいたるまで,すべて実際の施術の場面に即した代表的な例文を紹介し,多様な英語表現を覚えたり,使ったりできるよう配慮.
●施術についても,施術開始時や施術中の汎用表現のほか,整復・固定・物理療法・運動療法・手技療法など,各施術における表現まで広く掲載.
●巻末には,身体部位・筋・骨の英語名,事前質問票や登録用紙(施術申込書)の英文見本,各章の用語一覧を付録として収載.

入門 運動器の超音波観察法 実技編 プローブ走査を中心に
超音波観察をこれから始めようと考える柔道整復師にオススメ!
『入門 運動器の超音波観察法』の実技編が刊行!
●柔道整復師のための超音波観察法の実践的解説書.プローブワークを中心として,柔道整復師に求められる具体的な超音波検査テクニックを解説.
●肩関節や手指部など部位別にプローブの当てかたと実際の超音波画像例,その読み取りかたを豊富な写真と図によって基本的な事項を一つ一つわかりやすく解説.本書を読めば,正しいプローブワークが身につき,日常施術のレベルアップにつながります!

ひとりでも確実にできる!
スタートラインの整形外科基本手技[Web動画付]
手術器具の基本から術野の準備,麻酔法,各種の縫合法から手術別の基本手技まで,整形外科を経験するうえで必要となる超基本的手技を網羅し,盛りだくさんの画像やイラスト,動画を駆使してビジュアル解説! さらに失敗しやすいポイントや上級医からのアドバイスも満載。
整形外科専攻医はもちろん,初期研修医にも役立つ一冊!

≪運動と医学の出版社 実用書 園部式改善メソッド≫
園部式脚の痛み・しびれ改善メソッド
腰だけが原因じゃない!—知られざる脚の痛みの真実とは?
医者任せにしない!年齢のせいにしない!
手術を考える前にあなた自身で痛みの原因を見つける方法を人気治療家がわかりやすく解説。
手術をするしかない、と
あきらめていたのに・・・・・・
セルフケアで
痛みとしびれが
消えた!
本当の原因をセルフチェックで探る
本当の原因を突き止めて、セルフケアで改善する
再発予防のデイリーケア
痛みもしびれもさようなら
わかりやすい解説QR動画21本付き

感染対策ICTジャーナル Vol.19 No.4 2024
見極めて強化する 流行期の感染対策
見極めて強化する 流行期の感染対策

≪眼科診療エクレール 5巻≫
最新 神経眼科エッセンスマスター
診察の基本と疾患別の診療の実際
神経眼科診療の①疑問が直ぐ参照できる,②診療に即した内容で役立つ,③患者に説明できる,の3点をコンセプトとして神経眼科のエキスパートが最新の内容で分かりやすく解説した極めて良質な参考書.
神経眼科診療に必要な機能解剖の知識と診察法を解説したうえで,さまざまな神経眼科疾患の背景,病態生理,典型的所見,実際の治療法を具体的に解説.神経眼科への興味と理解が深まる絶好の書.

がん看護 Vol.29 No.6
2024年11-12月号
がん患者の療養の場の移行支援 ~アセスメント&社会資源の活用例~
がん患者の療養の場の移行支援 ~アセスメント&社会資源の活用例~ がんの医学・医療的知識から経過別看護、症状別看護、検査・治療・処置別看護、さらにはサイコオンコロジーにいたるまで、臨床に役立つさまざまなテーマをわかりやすく解説し、最新の知見を提供。施設内看護から訪問・在宅・地域看護まで、看護の場と領域に特有な問題をとりあげ、検討・解説。告知、インフォームド・コンセント、生命倫理、グリーフワークといった、患者・家族をとりまく今日の諸課題についても積極的にアプローチし、問題の深化をはかるべく、意見交流の場としての役割も果たす。

医学のあゆみ291巻4号
生体信号を活用した医療AIの臨床応用に向けて
生体信号を活用した医療AIの臨床応用に向けて
企画:藤原幸一(名古屋大学大学院工学研究科物質プロセス工学専攻先進プロセス工学)
・わが国の医療機器開発は諸外国に遅れているが,政府主導の「医療機器基本計画」の策定や,AIプログラム医療機器(SaMD)の実用化支援など,最先端技術で世界をリードするための環境づくりが進められている.
・医療分野での機械学習・AI技術の活用は,CTやMRIの画像診断で成熟しつつある.一方,心電図や脳波などの生体信号の活用は始まったばかりである.しかしそこには,複雑で非定常的なパターン,稀少な発生頻度,アーチファクトやノイズの混入,個人差など,機械学習の真価が問われる難題が立ちはだかる.
・本特集では,第一線の医師と工学研究者らが,生体信号を用いた医療AI開発の現状,課題,そして倫理的問題まで多角的に解説する.

≪看護管理まなびラボBOOKS≫
6ステップで実現する
看護マネジメント・質改善につなげるデータ分析入門
現場を知る強みを活かした6ステップの分析が、未来を拓く!
看護をデータで示すことを求められ、悩んだ経験はありませんか?本書は、病棟レベルの質改善や業務改善につながる、正しい数字の読み方・示し方や、データの基礎的な分析方法を身につけるための入門書。データ分析に取りかかる段階から改善活動までの流れを6ステップ(①思考の整理、②分析計画の立案、③分析の実施、④分析結果の解釈、⑤改善策の提案、⑥改善活動評価のための継続的なモニタリング方法の検討)で解説します。

臨床画像 Vol.40 No.11
2024年11月号
【特集】特集1:絶対苦手分野にしない 消化管の画像診断/特集2:専門医試験体験談:勉強法やお薦めの本/サイト
【特集】特集1:絶対苦手分野にしない 消化管の画像診断/特集2:専門医試験体験談:勉強法やお薦めの本/サイト

胸部外科 Vol.77 No.12
2024年11月号
1948年創刊。常に最近の話題を満載した、わが国で最も長い歴史と伝統を持つ専門誌。心、肺、食道3領域の外科を含む商業医学雑誌として好評を得ている。複数の編集委員(主幹)による厳正な査読を経た投稿論文を主体とした構成。巻頭の「胸部外科の指針」は、投稿原稿の中から話題性、あるいは問題性のある論文を選定し、2人の討論者による誌上討論を行っている。胸部外科医にとって必須の特集テーマを年4回設定。また、「まい・てくにっく」、「1枚のシェーマ」、読み物として「胸部外科医の散歩道」を連載。
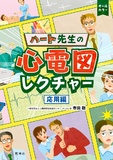
ハート先生の心電図レクチャー 応用編
心電図を正しく学習するためには、まず12誘導心電図の意味を理解する必要があります。
しかし、ここが大きなハードルであり、波形が12個も並んでいる記録を見ただけで混乱し、前に進めなくなってしまう人が多いようです。
心電図は見えない心臓の現象を波形にしたものです。
狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患では、ST変化や異常Q波出現など、特有の波形変化が生じます。
12誘導心電図を克服する近道は、こういった波形の変化は“なぜ起こるのか”という本質を知ることです。
現象の意味を正しく理解すると、波形の判断力が高まり、心電図の波形をよく眺めてみようという気持ちも生まれます。
判読する力がさらに向上していきます。
基礎編に続く「応用編」でも、心臓の状態と心電図波形の変化が連動したハート先生オリジナルのイラストを中心に、
目で見えない現象をできるだけ目で見て理解できるよう工夫しています。
【こんな本です】
・苦手意識の強い「12誘導心電図」を中心に、心臓の動きと波形の成り立ち、波形のとらえ方まで、正しく学べます。
・病棟を舞台に物語を読み進めながら、心電図にともなう臨床場面を体感できます。
・心電図の知識だけでなく、心筋虚血の病態についての理解も深まります。

図解理学療法技術ガイド 第5版
理学療法臨床の場で必ず役立つ実践のすべて
「評価」「運動療法」「物理療法」「義肢装具」「補助具」「各種疾患別理学療法」「地域リハビリテーション」「理学療法管理」の章立てで,理学療法を行ううえで重要なこと,臨床で役立つことを網羅.ネット検索よりも本書で調べることで正しい情報に辿り着けることを目指した.また,臨床での工夫等を「クリニカルヒント」として多数加えた.学生の臨床実習や,入職後のPTが知りたいことをすぐに調べることができるガイドブック.

整形外科 Vol.75 No.12
2024年11月号
1950年創刊。整形外科領域でいちばんの伝統と読者を持つ専門誌。読者と常に対話しながら企画・編集していくという編集方針のもと、年間約180篇にのぼる論文を掲載。その内容は、オリジナル論文、教育研修講座、基礎領域の知識、肩の凝らない読み物、学会関連記事まで幅広く、整形外科医の日常に密着したさまざまな情報が、これ1冊で得られる。

臨床雑誌外科 Vol.86 No.12
2024年11月号
肝胆膵外科領域のロボット支援下・腹腔鏡下手術
肝胆膵外科領域のロボット支援下・腹腔鏡下手術 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

理学療法41巻9号
2024年9月号
エビデンスも活用した下肢運動器疾患患者に対する理学療法ケーススタディ
エビデンスも活用した下肢運動器疾患患者に対する理学療法ケーススタディ 安全で効果的な理学療法を実践していくためには、
「①理学療法士の臨床能力」、「②施設の設備や環境」に,「③質の高い臨床研究の検証結果であるエビデンス」“も”加えて基本的な方針を立案し、「④対象者の意向や価値観」との折り合いを取りながら臨床的な方針を判断していくという根拠に基づく実践(evidence-based practice:EBP)の概念と手法を展開していくことが重要となります。
2020年の理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正により、実習生が診療チームの一員として加わり、臨床実習指導者の指導・監督の下で「診療参加型臨床実習」を行うというスタイルの推奨・導入が始まっています。これにより、改正前のように同じ対象者を同じ実習生がサポートを続け全体像を捉えるという経験、つまり理学療法を展開する思考過程を学ぶ機会が少なくなり、他職種とのカンファレンスなどにおける対象者を中心としたゴール設定に難渋する若手理学療法士も多いのではないかと感じます。
そこで本特集では、上記の「診療参加型臨床実習」で不足しがちな視点を学ぶ機会を提供するという観点も含めて、症例の状況を総合的に勘案した上でのEBPの具体的な進め方についてケーススタディを通して学ぶ機会を提供することを目的として解説していただきます。
また、対象者が享受できる期間に関する制限(期間制限)と、理学療法士が提供できる週あたりの単位に関する制限(単位制限)についても触れ、上記の「ステップ1からステップ5まで」のEBPのプロセスに基づいて述べていただきます。

看護学生のための臨地実習
スイスイのりきりガイド
いざ実習で行うケア,患者さんへの対応,患者さんの観察方法,記録の書き方などがシンプルにわかる!
実習への不安に寄り添い,あたたかく具体的に解説.実習前はもちろん,実習後,ナースになってからも役立つ1冊です!

STARTUP! 乳がん診療入門
エキスパートが教える最新知識と実践テクニック
乳がん診療をはじめよう!
一見複雑な乳がん診療も,確固たる土台を築くことができれば,その後はスイスイ理解できる.
乳がん診療の概観を短期間に習得し,しっかりとした土台を築くための入門書.疫学~診断~治療~再発予防を過不足なく網羅しながらも,一人の著者による整合性ある記述だから臨床での思考過程を理解できる.エキスパートがやさしく教える最新知識と実践テクニック.
成書を読む前の1冊としてご活用ください!!

すべての臨床医が知っておきたいリウマチ・膠原病の診かた
これならわかる!主要徴候から導く鑑別診断のポイント
多彩な症状を呈すために難しいイメージのあるリウマチ・膠原病.なかでも特に多い関節炎については7つのグループに分けて診断の流れをとことん解説.主要徴候から鑑別診断にアプローチする新しい入門書!

実験医学 Vol.42 No.18
2024年11月号
【特集】栄養分子と生体の相互作用 食理学
【特集】栄養分子と生体の相互作用 食理学 私たちの体は食関連分子に対してどのように振る舞うのか? 摂取した栄養素の生体中での反応を,分子,細胞,組織,個体レベルで解明すれば,栄養の機序が見えてくる.「食の理」を解き明かす最新の知見を特集!
