
実験医学増刊 Vol.42 No.17
【特集】マイクロバイオームと医療応用 全身の微生物叢が生理機能と病態をいかに制御するか?
【特集】マイクロバイオームと医療応用 全身の微生物叢が生理機能と病態をいかに制御するか? 全身を覆う常在微生物は,宿主の代謝,神経内分泌,免疫機能をも制御します.本書は,細菌・真菌・ウイルスの,ヒトの健康・疾患における役割から,便微生物移植を筆頭とした治療法開発の最前線までを紹介します!

実験医学 Vol.42 No.18
2024年11月号
【特集】栄養分子と生体の相互作用 食理学
【特集】栄養分子と生体の相互作用 食理学 私たちの体は食関連分子に対してどのように振る舞うのか? 摂取した栄養素の生体中での反応を,分子,細胞,組織,個体レベルで解明すれば,栄養の機序が見えてくる.「食の理」を解き明かす最新の知見を特集!

放射線技術学シリーズ MR撮像技術学(改訂4版)
最新のシラバス・カリキュラムの内容に則った、充実の改訂4版
2017年に発行した「放射線技術学シリーズ MR撮像技術学(改訂3版)」の改訂版です。
全国の大学・専門学校など、診療放射線技師の養成校における必修科目である「診療画像技術学」「磁気共鳴技術学」で扱われるMR撮像技術学の教科書です。
そこで本書は、全国の技師養成校のシラバス・カリキュラムに沿った形で内容構成を見直し、MRIの基礎原理から効果的な撮像法、アーチファクトへの対策、各部位の撮像のコツなどをわかりやすくまとめた書籍です。

これならわかる 医療被ばく説明・相談の実務
カウンセリングの観点も交えて、医療被ばく説明・相談をやさしく解説
各種放射線機器を用いて検査・治療などを行う際、患者、またその同伴者、医療従事者、周辺環境への被ばくについて安全性をもって行われていることを説明すること、またこれらに関する相談に請け負うことは非常に重要なことです。また、安全性の基準となる関連法令・ガイドラインなども時を経て移り変わるため、診療放射線技師をはじめとした医療従事者がその時期・世相などに応じた理解をもって説明・相談することもまた重要です。
本書は、医療被ばく説明・相談の各場面における実際的な対処について、最新の関連法令・ガイドラインを踏まえつつ、カウンセリングのコツも交えながら、実際の現場で役立つよう、わかりやすくまとめた書籍です。
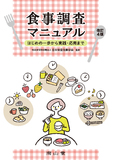
食事調査マニュアル 第4版
はじめの一歩から実践・応用まで
第Ⅰ編には食事調査に必要な基礎知識をまとめ,第Ⅱ編には実際の方法と手順についてくわしく解説し,第Ⅲ編に実施で必要となる資料を掲載.今改訂では,日本食品標準成分表2020年版(八訂),情報学領域における画像認識,自動化された24時間思い出し法などの新しい知見や話題を追加し,内容の充実を図りました.管理栄養士を目指す学生のみならず,すでに実務として食事調査を行っている方々にもおすすめの一冊です.

ここからの精神医学入門
精神科医はどう診ているの?
●問診のコツ、患者との接し方を知る
●患者・家族のケアがわかる
●疾患のリアルなイメージを掴む
本書は、こころの病気のありよう、患者さんの実像、そして診療の流れをベテラン精神科医がわかりやすく解説したものです。読者は、精神科医療に関わったことがないか経験の少ない医療者を念頭に置いていますが、医療系の学生はもちろん、精神疾患に関心のある一般の方でも十分に読むことができます。精神疾患や診療の全体像について、具体的なイメージをつかむのに最適な入門書です。

≪非腫瘍性疾患病理アトラス≫
骨関節
病理総論的な本態とその病態プロセスの理解なくして,病理診断は行えない―.非腫瘍性骨関節疾患の組織形態を読み解くためには,病態の時間経過を踏まえ,類推,検証していくプロセスが必須となる.本書では長年,骨関節の病理診断に携わってきた著者が,目の前にある標本の組織形態をいかに読み解くか,その診断思考プロセスを惜しげもなく披瀝する.『非腫瘍性骨関節疾患の病理』(2003年)をベースに,200枚以上の精選写真を追加.

社会保険旬報 №2943
2024年10月21日
《対談》 『生活習慣病の重症化予防に向けて―保険者の保健活動とかかりつけ医の連携を考える』尾﨑治夫 柴田潤一郎
《対談》 『生活習慣病の重症化予防に向けて―保険者の保健活動とかかりつけ医の連携を考える』尾﨑治夫 柴田潤一郎
高血圧、脂質異常症、糖尿病の生活習慣病は、国民の疾病のなかで大きなウエイトを占め、重症化すれば半身不随、失明、人工透析などQOLの低下につながる。このため、医療機関のみならず、協会けんぽをはじめ保険者は、高齢者医療確保法に基づき、特定健診・特定保健指導を通じて生活習慣病の重症化予防に取り組んでいるが、十分な成果をあげるには医療機関との連携が不可欠だ。
そこで、「生活習慣病の重症化予防」をテーマに東京都医師会の尾﨑治夫会長と全国健康保険協会東京支部の柴田潤一郎支部長に話し合ってもらった。話題は、働き方改革を通じた職場の環境づくりやヘルスリテラシーの大切さなど多岐に及んだ。
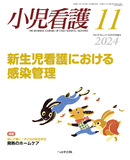
小児看護2024年11月号
新生児看護における感染管理
新生児看護における感染管理 新生児看護において、感染管理は重要な課題である。新生児の免疫能は未成熟であり、在胎週数や出生後の日齢によって患者の感染リスクは刻々と変化する。また、侵襲的な医療器具の使用や手術などの処置に伴う感染リスクは、年々複雑かつ高度化している。本特集では、新生児における感染管理の基本的な知識や原則、ガイドラインなどで推奨されている感染防止技術、サーベイランスによる評価といった実践に必須の知識と、新生児集中治療室(NICU)や産科新生児室における感染対策についての臨床の取り組みを紹介する。
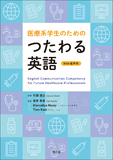
医療系学生のためのつたわる英語[web音声付]
English Communication Competency for Future Healthcare Professionals
医療関連職に必要とされる英語と 医療倫理 (心構え) の基礎を同時に学べる教科書.医療現場で日常的にみられる15の場面を取り上げ,実際に使えるコミュニケーション・スキルが習得できるよう工夫.英語教育者と国内外で活躍する現役医師・医療専門家がタッグを組み,初学者でも無理なく学べる構成・難易度を設定した.

≪シンプル作業療法学≫
シンプル作業療法学シリーズ
作業療法学概論テキスト
初学者が作業療法・作業療法士の全体像を理解できるよう平易かつ簡潔に解説した教科書.作業療法の成り立ちや役割,対象領域や各種制度,支援方法など,基本となる考え方から実践的な内容まで,学生に必要な知識を幅広く提供する.「作業療法とはなにか」を理解しながら学べるよう,豊富なイラストと具体例を用いながら丁寧に解説した.

シンプル理学療法学シリーズ
運動器障害理学療法学テキスト 改訂第3版
障害と疾患の基本的理解と,根拠に基づく介入法とその実践に必要な整形外科学などの基礎学問を解説した教科書の改訂版.今改訂では本文をフルカラーとし,運動療法・検査などを分かりやすいイラストで多数掲載.視覚的な理解にも優れた紙面となった.さらに運動器障害理学療法学分野,またその理解の基礎となる整形外科学分野の過去10年分の国家試験問題へのリンクも収載した充実の改訂版.

シンプル理学療法学シリーズ
物理療法学テキスト 改訂第3版
今改訂では各種物理療法の生物学的効果、生理学的効果、臨床効果を踏まえたうえでクリニカルリーズニングを行う力を養えるように構成を見直した。エネルギーの種類(国際物理療法学会の分類に準拠)、使用するデバイス、運用方法、効果、エビデンスなどの情報を階層的な枠組みで整理し、系統的な理解を促す。紙面のフルカラー化、最新の知見を取り込んで全体をアップデート。

≪シンプル理学療法学・作業療法学≫
シンプル理学療法学・作業療法学シリーズ
生活環境学テキスト 改訂第2版
理学療法士・作業療法士養成課程の学生に必要な「生活環境整備」の知識をコンパクトにまとめた教科書。高齢者や障害者のための住環境整備を中心に、現在の住宅事情から住宅改修の方法、福祉政策を解説。医学的視点で生活機能障害を分析し、他職種と連携しながら生活環境整備を行うことを目指した内容構成が特徴。今改訂では「まちづくり」の章を新設し、さらに広い視点で学習できる構成とした。

実践クリティカルケアリハビリテーション
効果的なICUリハビリテーションを迅速に行うための必須知識を1冊で体得
現場からのニーズで必要に迫られている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が,明日から実践できる知識を短時間で身につけられる1冊!
ICUナース,集中治療科医師,リハビリテーション科医師,ICUチームすべてに役立つ内容をわかりやすくまとめました.
1. リハビリテーション前の情報収集
2. ICU入室時のチェックポイント
3. リハビリテーションの実際
4. リハビリテーション中のリスク管理
5. リハビリテーション終了時に考えること
を具体的にエキスパートが伝授します!
単なる知識紹介本ではなく臨床スキルが上がる実践書として,役立つこと間違いなし.

≪Visual栄養学テキスト≫
臨床栄養学Ⅱ 各論 第2版
「臨床栄養学Ⅰ 総論」の続編となる本書は,栄養食事療法が重要となる疾患を網羅的に抽出し,疾患別の栄養ケアを解説.
患者への適切な栄養管理を目的として,疾患の知識(概要,診断,治療),栄養食事療法について(栄養生理〈病態栄養〉,意義,基本方針,栄養アセスメント・モニタリング,栄養食事管理目標と実際)という構成で,わかりやすく説明をしている.
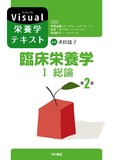
≪Visual栄養学テキスト≫
臨床栄養学Ⅰ 総論 第2版
栄養学と医学・医療を融合し,疾病の治療や予防を担う「臨床栄養学」を学び・実践するため,臨床で役立つ内容を簡潔に解説.
第1部では,臨床栄養学の意義,医療や福祉・介護における臨床栄養,栄養アセスメントや栄養ケアプランなどの知識を,第2部では,発熱などの症候への栄養ケア,新生児・乳幼児期,術前術後や化学療法・放射線療法下,また終末期の栄養ケアなどを学習できる.

グングン上達する 認知症のみかた
診断の‘手掛かり’はココにあり!
厳選された51症例をピットフォールごとに10パートに分類して提示・解説。各症例を通して、診断に至るまでの思考過程と病歴や症候の見逃し・見誤りやすいポイントがわかり、自ずと診療のコツが身につく。各症例は3~5頁の読み切りサイズで、気になるトピックから読み進めることができる。25点の動画コンテンツ付き。専門・非専門問わず、認知症診療」に携わる臨床医はこれ一冊でグングン上達する!

診療放射線技術 下巻 改訂第15版
診療放射線技師養成課程教科書の定本として高い評価を得ているテキスト.上巻・下巻の2冊で養成課程に必要な知識を体系立てて学ぶことができる.今改訂では,項目の見直し,新知見,法律への対応を行った.

診療放射線学概論
診療放射線技師に必要な放射線とそれを用いた医療,医療現場における診療放射線技師の役割,かかわる法律など,学生が今後学ぶ専門科目の全体像を把握できるよう過不足なくまとめた教科書.各章の冒頭に学習目標と事前学習の項目を,章末には学習到達度自己評価問題を設けた.
