
総合診療 Vol.34 No.10
2024年 10月号
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ! よくある騙され方のゲシュタルト
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ! よくある騙され方のゲシュタルト ①独自の切り口が好評の「特集」と、②第一線の執筆者による幅広いテーマの「連載」、そして③お得な年間定期購読が魅力! 実症例に基づく症候からのアプローチを中心に、診断から治療まで、ジェネラルな日常診療に真に役立つ知識とスキルを選りすぐる。「総合診療専門医」関連企画も。 (ISSN 2188-8051)
月刊、年12冊

公衆衛生 Vol.88 No.10
2024年 10月号
特集 その政策にエビデンスはあるんか!? 根拠に基づく健康政策(EBHP)を進めるために
特集 その政策にエビデンスはあるんか!? 根拠に基づく健康政策(EBHP)を進めるために 地域住民の健康の保持・向上のための活動に携わっている公衆衛生関係者のための専門誌。毎月の特集テーマでは、さまざまな角度から今日的課題をとりあげ、現場に役立つ情報と活動指針について解説する。 (ISSN 0368-5187)
月刊、年12冊
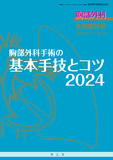
胸部外科 Vol.77 No.10
2024年9月増刊号
胸部外科手術の基本手技とコツ2024
胸部外科手術の基本手技とコツ2024 1948年創刊。常に最近の話題を満載した、わが国で最も長い歴史と伝統を持つ専門誌。心、肺、食道3領域の外科を含む商業医学雑誌として好評を得ている。複数の編集委員(主幹)による厳正な査読を経た投稿論文を主体とした構成。巻頭の「胸部外科の指針」は、投稿原稿の中から話題性、あるいは問題性のある論文を選定し、2人の討論者による誌上討論を行っている。胸部外科医にとって必須の特集テーマを年4回設定。また、「まい・てくにっく」、「1枚のシェーマ」、読み物として「胸部外科医の散歩道」を連載。

薬局 Vol.75 No.11
2024年9月増刊号
西洋医学×東洋医学
解剖生理で学ぶ くすりの効きどころ
西洋医学×東洋医学
解剖生理で学ぶ くすりの効きどころ 漢方薬は身近にさまざまな診療科で処方され,西洋薬とあわせて処方される場合も少なくありません.しかし漢方薬は西洋薬と比べて,基礎薬学的な解説に馴染みがなく,作用のしくみを理解するのが難しいという印象をもっている方も多いのではないでしょうか.くすりの効果は,もともと身体が持ち合わせている生理的な作用に基づき,各病態で過剰になっているはたらきや不足しているはたらきを,抑えたり補ったりすることで発揮されています.そのコンセプトは,西洋医学でも東洋医学でも基本的には同じはずです.つまり,漢方薬でも西洋薬でも,キホンとなる解剖生理・病態生理や生命活動のとらえかたの概要をつかめば,くすりの利きどころ(標的,効果,副作用)が見えてくるということです.また,解剖生理・病態生理からくすりの作用を捉えることは,医療者がくすりの作用を具体的にイメージし,それを患者さんに伝えやすくなることにもつながるはずです.そこで本書では,西洋医学と東洋医学における身体の各部位の機能を,薬物療法と絡めてやさしくおさらいします.図やイラストも豊富で,解剖生理とくすりの作用を簡潔に理解できる内容となっています.西洋医学と東洋医学の垣根を越えて,より深く患者さんの薬物療法を支える一助となれば幸いです.

眼でみる実践心臓リハビリテーション 改訂5版
大好評書籍が全面アップデート!心リハ実践マニュアル決定版
最も効果的で安全な,施設で行う包括的な心臓リハビリテーションを具体的・体系的に学べる必読書が,約90ページ増の充実内容でますます役立つ1冊になりました!離床訓練だけではない運動療法や、患者教育・生活習慣の改善などによって心臓病からの回復と再発予防をかなえる包括的心臓リハビリテーションが心疾患の治療そのものであり,心疾患治療・管理の中心の1つになっています. 遠隔心臓リハビリテーションやクリニックでのリハビリ,外来・入院それぞれの方法など必須知識をわかりやすくまとめた,間違いない1冊です.

臨床スポーツ医学 2024年10月号
スポーツ現場・臨床で使える!トレーニングやエクササイズのための器具と機器
スポーツ現場・臨床で使える!トレーニングやエクササイズのための器具と機器 「スポーツ現場・臨床で使える!トレーニングやエクササイズのための器具と機器」特集として,スポーツパフォーマンスに必要な基礎身体能力/パワー・協調性トレーニングに有用な器具/アジリティ・スピードトレーニングに有用な器具や環境/バランス・協調性トレーニングに有用な器具/持久力トレーニングに有用な機器-エルゴメータ などを取り上げる.また連載として,[スポーツ関連脳振盪-アムステルダム声明-]他を掲載.

心エコー 2024年10月号
心膜疾患を語り尽くす
心膜疾患を語り尽くす 特集は「心膜疾患を語り尽くす」.心外膜脂肪の意義と計測法/急性心膜炎・心タンポナーデの診断/収縮性心膜炎の身体所見を見直す/収縮性心膜炎の診断─Mayo Clinicの診断基準を中心に/滲出性収縮性心膜炎の診断/癌性心膜炎・心臓腫瘍の診断/先天性心膜欠損症の診断/コアグラタンポナーデの診断/収縮性心膜炎の外科治療 を取り上げる.連載として症例問題[Web動画連動企画]声帯麻痺の原因は?,[COLUMN]Something new, Something special等を掲載.

ナイチンゲール助産論
Introductory Notes on Lying-in Institutions
本書は、ナイチンゲールの膨大な印刷文献の中で、これまでほとんど知られていなかった『産院覚え書・序説』(Introductory Notes on Lying-in Institutions)の翻訳書です。
ナイチンゲールは、1862年に英国で始めて助産師訓練学校を開設し、助産師を女性の専門職のひとつとして誕生させました。しかし産科病棟に産褥熱が蔓延したため、病棟も学校も閉鎖を余儀なくされてしまいました。長年の夢が打ち砕かれたナイチンゲールは、産褥熱発生の実態調査に乗り出しました。健康な産婦がなぜ産院で死ななければならなかったのか? 彼女はヨーロッパ中の産院の現状をつぶさに把握し、その死亡率は自宅で分娩する産婦の死亡率よりも高いという事実を知りました。
そこでナイチンゲールは、理想的な産院構造を示すとともに、産院における設備のあり方やその管理の仕方に至るまで、細かな指摘をしています。さらに新たに助産師訓練学校を開設するとすれば、いったいどのような教育が理想なのかについても熱っぽく語っています。
本論文からは、ナイチンゲールが描く理想的な助産師像を読みとることができます。その理想は、現代の助産師界にとっても新鮮で、消えることのない本質的なものです。
それは助産所で自立して働く助産師に希望と方向性を与えてくれるものであり、日本の助産師界の今後の方向性を思考するうえで限りなく参考になるものと推察されます。
さらに、ナイチンゲールが看護師訓練学校とは切り離して助産師訓練学校を開設したことで、その後、世界の助産師教育の潮流は、英国を筆頭に、看護師教育とは分離して行われているという事実にも、関心を寄せる必要があります。
翻訳文の前に、訳者・金井一薫による「訳者・論考」が記されています。本書を読む方々は、論文の時代背景や当時の英国の助産事情など、詳しい解説を読むことで、本書への理解が進み、ナイチンゲールの意図がよりスッキリと頭の中に入ってくるでしょう。
ナイチンゲールの言葉
「助産師とは、科学的かつ実践的な訓練を受けて、必要時には相談・助言を受けながら、正常・異常を問わず、あらゆる分娩事例を、産科医と同様に取り扱うことができる女性のことを指します。このような訓練は、2年以内に終わらせることはできません。」

泌尿器外科 2024年9月号
2024年9月号
特集:Real Worldにおける上部尿路結石の診断と治療─恐れながら素人がエキスパートに質問させて頂きます─
特集:Real Worldにおける上部尿路結石の診断と治療─恐れながら素人がエキスパートに質問させて頂きます─

胆と膵 2024年8月号
2024年8月号
特集:膵・胆道癌の発生・進展メカニズムを探る
特集:膵・胆道癌の発生・進展メカニズムを探る

実験医学 Vol.42 No.16
2024年10月号
【特集】神経から免疫で炎症性疾患を治す!
【特集】神経から免疫で炎症性疾患を治す! 「病は気から」のその先へ!これまで多く研究されてきた免疫から神経への影響とは反対に,神経が免疫を制御する分子機構が明らかに.神経刺激による疾患治療法の開発へ/DORAなど「研究評価」の世界動向丸わかり

≪Crosslink basic リハビリテーションテキスト≫
心理学・臨床心理学
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士の養成校の専門基礎科目に対応したテキストシリーズ。学習内容と国家試験を結びつける[学習の要点],実習や臨床現場にリンクする[臨床に役立つアドバイス]など,「なぜそれを勉強するのか」「将来にどのようにつながるのか」をイメージしやすい知識を補足し,用語解説なども適宜追加。項目末の[まとめ]では,学習の理解度を確認するために簡単な問題を掲載。噛み砕いた表現と多数の図表で,評価・治療方法について視覚的にも理解しやすい紙面に加え,各見出しごとの[POINT]で,どこに重点を置いて学習すべきかが一目でわかる構成となっている。本巻では,専門基礎科目である「臨床心理学」およびその基盤となる心理学の理論をわかりやすくまとめ,さらにシリーズのコンセプトである「専門科目や臨床とのつながり」を重点解説。もちろん国試対策もしっかり押さえた充実のテキスト。

訪問看護、介護・福祉施設のケアに携わる人へ
コミュニティケア Vol.26 No.10
2024年10月号
特集:地域の暮らしを知る「地域・在宅看護論」実習
特集:地域の暮らしを知る「地域・在宅看護論」実習
第5次カリキュラム改正において、「在宅看護論」は「地域・在宅看護論」と改称され、同時に単位数の増加や実習要件の緩和等が行われました。
これは、国として病院完結型から地域完結型の医療に移行するため、地域で活躍できる看護職を育成することがねらいです。
また現在、看護学生を取り巻く環境も変化し、暮らしの中で地域住民と触れ合う機会は以前よりも減っています。
教育機関はそのような社会情勢等の下、学生が地域で活躍できる看護職となるにはどのような学習や実習が必要かを模索しています。
では、実際に教育機関はどのような考えの下でこれらに取り組んでいるのでしょうか。
本特集においては、「地域・在宅看護論」実習のねらい等をあらためて示した上で、地域の人々の暮らしを知ることを学習や実習の一環として取り入れた学校の多種多彩な取り組みを報告します。またコラムでは、訪問看護ステーションの管理者の立場から、実習生を受け入れる意義等を述べます。
今の看護学生、実はこんなことを学んでいます!

臨床雑誌外科 Vol.86 No.11
2024年10月号
外科臨床研究・臨床試験―どう計画し,どう取り組むか
外科臨床研究・臨床試験―どう計画し,どう取り組むか 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

根拠からわかる!実習で実践できる!
vol.3 フィジカルアセスメント
わかるできる看護技術シリーズは、「わかる」→「できる」をキーワードに、看護学生が看護技術をビジュアルで視覚的に理解できるように、カラー写真・イラスト・図表を中心にして、技術の理解や実践に欠かせない根拠や注意点などを踏まえて、くわしく解説しています。
フィジカルアセスメントでは、体温・脈拍・呼吸・血圧などの基本のバイタルサインとともに、呼吸器系・循環器系などの系統別、状態・疾患・経過別のフィジカルアセスメントを掲載しています。
<本書の特徴>
1 看護技術の基礎知識や手順がビジュアルでわかる
2 技術の理解や実践に欠かせない根拠や注意点がわかりやすい
3 項目別・系統別に主要な項目を網羅し、1冊で広く・深い知識が得られる
4 実習で役立つ疾患別のアセスメントも身につけられる
5 コピーして実習メモに貼れる手順表・ポイント表つき!

がん患者診療のための栄養治療ガイドライン 2024年版 総論編
がん患者の多くは、侵襲的な治療による栄養障害や、がんそのものの炎症や異化亢進などによる栄養障害を経験する。栄養障害は合併症の増加やQOL低下などさまざまな影響を及ぼすが、がん種やステージなどによって必要となる栄養治療は多様であり標準化に課題がある。
本診療ガイドラインではMindsの方式に準拠し、4件の臨床疑問(CQ)についてエビデンスに基づく推奨を提示した。
また、「背景知識」の章ではがん患者に対する栄養治療の基礎知識から最新の知見までを解説し、患者・家族向けのQ&Aもコラムとして収載している。
本診療ガイドラインは、それぞれのがん種ではなく、さまざまながん種を広く対象とし、栄養治療に関する推奨、知識、情報を提供する。

臨床放射線 Vol.69 No.5
2024年9・10月号
即時適応放射線治療 Surface-guided radiotherapyの実際
即時適応放射線治療 Surface-guided radiotherapyの実際
本号は特集を「即時適応放射線治療」と「Surface-guided radiotherapyの実際」の2本立てとし、近年導入が進んでいる最先端の放射線治療技術を、読者の先生方に紹介する趣向となっております。いずれもコンピュータや人工知能の発展により実現した、治療側・患者側双方の負担を軽減可能な最新技術・機器です。日々の診療や患者への説明・話題提供の参考になること請け合いです。14本の症例報告論文や好評連載「今月の症例」ともども、是非ご一読ください。

臨床画像 Vol.40 No.10
2024年10月号
【特集】特集1:絶対苦手分野にしない 小児の画像診断/特集2:小児領域の核医学検査・PET検査の読影と管理上の注意点
【特集】特集1:絶対苦手分野にしない 小児の画像診断/特集2:小児領域の核医学検査・PET検査の読影と管理上の注意点
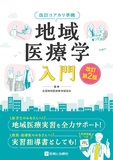
改訂コアカリ準拠
地域医療学入門 改訂第2版
全国地域医療教育協議会監修の,地域医療の必携書!
令和4年度改訂版のコアカリに対応し情報もアップデート.へき地医療,多職種連携,地域包括ケアシステムなど基本的要素を網羅し,現在・未来の日本医療に欠かせない地域医療を体系的に学べます.医学・医療系学生の皆さんの学習や,教員・指導医の皆さんの実習指導など幅広く活用いただけます.
問題文も豊富に収録し、医学部を目指す受験生にも面接・小論文対策としておすすめです.

≪クリニカル作業療法シリーズ≫
高齢期領域の作業療法 第2版
臨床・実習で役立つシリーズ。疾患・障害・場面別に病院と地域をつなげるために必要な視点と展開方法を提示。認知症、慢性疾患、閉じこもり、健常、生活行為向上マネ、通所・訪問リハ、在宅終末期など16の事例を用いて解説する。活動・参加のリハの知識を加えて改訂した。
